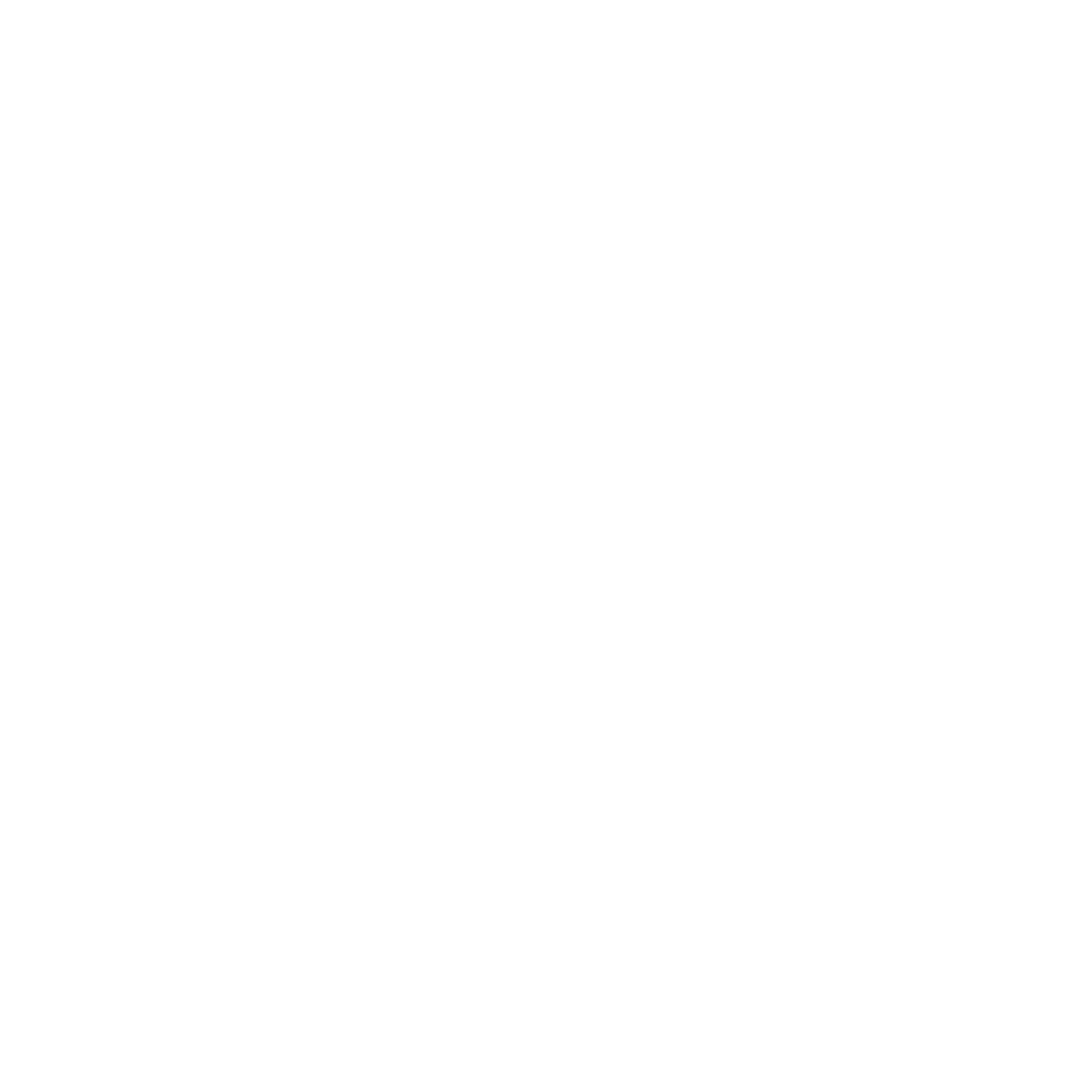第拾捌話 誰がモノ
東京少年鑑別所。
そこは非行または犯罪を行ったとされる少年少女が、沙汰が下されるまで収容される法務省所管の施設だ。収容者にはそれぞれ僅か三畳ほどの部屋が与えられ、収容期間中は規律に基づいた生活を強いられることになる。
「昼食だ。いい加減ちゃんと食えよ」
そして今日もまた、可もなく不可もない味の昼飯が、部屋の中へ運び入れられた。
「……」
香ばしい匂いを放つ山盛りの唐揚げには目もくれず、万次郎は壁にもたれ掛かり、ひたすら歪な空を眺め続ける。
鉄格子に阻まれたぶつ切りの青空が、ここから見える外界のすべてだった。ここにぶち込まれて二週間。何の気力も湧かず、万次郎はこれまでの苛烈さが嘘のように、大人しく檻の中に閉じ込められている。
(タケミっち……)
心に大きな爪痕を残すこととなったあの出来事は、夜な夜な万次郎を苛んだ。
突然武道が刺された瞬間の映像がフラッシュバックしては、発狂して飛び起きる。起きている時でさえ、彼を失うかも知れないことへの猛烈な恐怖と不安に駆られ、身体の震えが止まらなくなった。
トスッというやけに軽い音。徐々に広がってゆく血溜まり。鼻につく鉄の匂い。
全部覚えている。忘れられるはずがない。面会に来た真一郎から、武道が意識を取り戻したという話は聞いている。けれど、心の奥深くに根付いた不安の芽が摘まれることはなかった。
「……っ」
息が、苦しい。
『この手、オレ……大好きだから……汚さない、で……。ね、おねがい』
黒い衝動に呑まれた己の手を掴む、弱々しい指先の感触が、今もずっとこびりついて離れない。今が檻の中で良かった。もし外で野放しにされていたら、何が何でも彼を攫いに行っていただろうから。
彼への想いはすべて、捨てると決めたはずなのに。
――コン、コン。
「おい佐野、郵便物だ」
部屋の隅で静かに丸まっていれば、唐突にノックの音が響く。万次郎がここへ入れられてからというもの、偶にチームの仲間たちから手紙が届くことがあった。今回もそうなのだろう。小窓から滑り込んできた白い封筒を手に取って、万次郎は無気力に封を切る。
「え……」
ざっと中身に目を通して、慌てて封筒の差出人名を確認した。
《花垣武道》
そこに記されていたのは、気が触れそうなほどに会いたくて堪らない人の名前で。驚愕から目を見開くと同時に、身体中の血液が沸騰するような高揚感が込み上げた。
佐野万次郎様
前略 お元気ですか? 俺は昨日ようやく退院できました。
今のところ経過は順調で、幸いにも後遺症は残らないとのことです。あまりにも治るのが早いから、担当医の人に驚かれたくらいでした。よくわからないけど、普通はもうちょい時間が掛かるらしい。
多分俺は生まれつき身体が丈夫な方なのでしょう。母からも「アンタの耐久性はダイヤモンド級」とお墨付きを頂きました。なんかちょっとカッコいいよな、ダイヤモンド級って響き。ただそのことを学校のダチに話したら、ダイヤモンド・武道とか渾名つけやがったのはマジで許せねぇ。
だって売れない芸人みたいでダサくね?
普通に悪口だわ、アレ。
真一郎君から、万次郎が鑑別所に入れられたと聞きました。
鑑別所は少年院と比べると緩いってイザナ君が言ってたけど、万次郎からすれば、かなり窮屈なところなんじゃないかな。監視員さんたちのこと、ウゼェからって殴ったらダメですよ。それから、他の入所者さんたちに喧嘩を売らないように。君は喧嘩っ早いし気紛れな人だから、皆さんに迷惑を掛けていないか心配です。
君が出所したら、いっぱい話したいことがある。俺たちは言葉が足りなかった。君と会えなくなって、そのことを痛感しています。もっと面と向かって話せば良かった。殴り合いになったって、いっぱい喧嘩したって、俺が思っていることをちゃんと君に伝えればよかった。
次に外で会う日はいつ頃だろう。春なら花見に行きたいし、夏なら海までツーリングしたい。秋はちょっと遠出して、食い倒れツアーとかしても楽しそう。冬は寒いの無理なんで、いっそ沖縄旅行とかどうでしょう?
たとえ一ヶ月だろうと、一年だろうと、それよりもっと長くても、俺は万次郎が帰ってくるのをずっと待ってます。万作さんも、真一郎君も、エマちゃんも、イザナ君も、東卍のみんなだって君の帰りを待ってる。
大丈夫、万次郎の居場所はちゃんと此処にある。
早く君に会いたいです。
草々
2005年11月14日
花垣武道
読み終える頃には、黒いインクがところどころ滲んでいた。誰に見られているわけでもないのに、顔を隠すべく膝を抱えて蹲る。胸が痛い。心臓がぎゅうぎゅう締め付けられて、目頭が燃えるように熱かった。武道だ。本当に、武道が生きている。ようやくまともに息ができたような心地だった。
真一郎から武道が意識を取り戻したと聞いた時、万次郎はその知らせをどこか他人事のように受け取った。
真一郎の言葉を疑っていたわけじゃない。ただ単に現実味が湧かなかったのだ。周りからいくら言葉をかけられようと、己の中の武道はあの美しい双眸を閉ざしたまま、力なく血溜まりに身を浸している。ぐったりとした肢体を引き上げようとすればするほど、万次郎の両の手は赤黒く染まり、深みに嵌まっていくばかりであった。
いつ彼を失うとも知れぬ恐怖に苛まれる日々。身の内で今にも暴れ回りそうな狂気を、必死になって抑え込んだ。
「……っタケミ、っち」
声が裏返り、嗚咽が漏れる。
最悪だ。彼に向けるありとあらゆる感情を削ぎ落としたつもりであったのに、こうして少し彼の断片に触れただけで、堰き止めていた想いが溢れ出てくる。
「……っ」
衝動に突き動かされ、傍らに放置された昼餉を喰らう。
冷めきった飯が喉元を通る度に酷くえずいた。吐きそうになりながらも、皿の上に積み上げられた肉の塊を、口一杯に詰め込んでゆく。
無気力に弛緩した手足と、そこら中に蔓延る退廃的な空気、虚空を映すガラス玉。監視員たちにすら哀れみを向けられていた、魂の抜けた屍はもうどこにもない。
在るのは放棄していた生に再びしがみつかんと躍起になる、一人の男の姿であった。
*
二〇〇五年十一月十九日
周囲を威嚇するような爆音が、其処彼処で轟く深夜未明。好き勝手に改造された族車の群れが、静寂を保つ海辺の景色に雪崩れ込む。次いで白、黒、赤といった、各チームカラーを背負った男たちが、続々と白い砂浜を踏み荒らしていった。
「おい、テメェんとこの頭はまだか」
苛立ちを露わにした東卍隊員が噛み付く。
「元凶が遅刻とかナメてんのか。ア?」
「一番偉い立場の人間が最後に来るのは当然のことだ」
対して黒龍隊員が飄々と返せば、男は顔を真っ赤にして怒鳴り散らした。
「ぁ゙あ゙⁉ んだとゴラ!」
「おい、うるせぇぞソコ! 勝手に喧嘩売ってんじゃねぇよ!」
ゴッと鈍い殴打音と共に男は回収されていき、その場は無理矢理収められる。
まさに一触即発。関東トップスリーの暴走族が勢揃いとあれば、自ずと空気はピリついたものとなる。特に黒龍は東京卍會の元隊員に総長を傷つけられたとあって、まさに手負いの獣状態であった。現にその恨みの根深さを表すように、白い特服姿の男たちは東卍隊員へガンを飛ばしている。
なけなしの理性で踏み留まる彼らは、一度許可が下りれば喜び勇んで殴りかかることだろう。獲物を前にお預けを食らわされている猟犬たち。そんな物騒な比喩に相応しい、暗雲めいた気配が、彼らの間に立ち込めていた。
――バブー!
「……来たか」
それまで沈黙していた天竺の王が、人知れず呟く。
ドドドド、と腹の底に響く重低音と共に姿を現したのは、小柄な一人の少年だった。
月光を浴びて輝く金糸雀色の髪に、蒼穹を閉じ込めた澄んだ双眸。儚げな色彩の少年はしかし、圧すら感じるほどの強い存在感を放ち、片っ端から周囲の目を奪っていく。
「おいテメェら、総長のお通りだ! 道を空けろ!」
肩から羽織った黒の特攻服が風に煽られ、背に刻まれた龍が夜を舞う。晦冥を統べる龍の長の降臨に、それまで荒んでいた白雲たちは一斉に頭を垂れた。
「お疲れ様です! 花垣総長!」
愛機から降り、側近たちを侍らせた少年が、申し訳なさそうに眉尻を下げる。
「皆さんもお疲れ様です。遅くなってすみません」
「途中サツに追われてな。撒くのに時間かかっちまった」
「ご無事で何よりです」
隊員たちの先頭に立っていた銀髪の青年が、慣れたように荷物を受け取る。厳つい容姿の男たちが、年季の入った黒いアタッシュケースを幾つも抱えて歩く姿は、何とも異様な光景であった。
また、その近寄り難い雰囲気に当てられたのか。それまで殺気立っていた者はみるみるうちに勢いを失い、淡々と情報を共有する黒龍の隊員たちを、遠巻きに伺っている。
「武道」
その時、狂犬たちの威嚇などものともせず、天竺の王が平然と龍の懐へ近づいた。
「怪我の具合は」
冴え冴えとしたアメジストの瞳に滲むは親愛の色。それまでの眼光の鋭さは鳴りを潜め、身内の前でのみ見せる和らいだ表情を晒している。排他的な美しさを覗かせる怜悧な美貌には、はっきりと『心配』の二文字が書かれていた。
「もう大丈夫。傷口も塞がってるし痛みもないよ。心配かけてすいません、イザナ君……」
そう武道が答えると、イザナはホッと息を吐く。
「そうか。ならいい」
褐色の掌が武道の頭に乗せられた。そのままくしゃくしゃと金髪を撫で回し、手の主が小さく「弟が悪かったな」と謝罪の言葉を口にする。直後、動揺の漣が広がっていった。あの天上天下唯我独尊で知られる天竺の王が、頭こそ下げぬものの謝っただなんて。天竺のメンバーたちでさえも、目を剥きながら王の後ろ姿を凝視した。
一方謝罪を受けた武道は、特段驚くそぶりも見せず、軽く一度だけ頷いてみせる。
「イザナ、そろそろ……」
「あぁ」
次の瞬間、イザナの表情が変わった。
それまで柔らかな光を湛えていたアメジストが冷たさを帯び、逆らう者は皆殺しと言わんばかりの重圧が放たれる。そんな彼に倣うように、武道もまた表情を引き締め、天色の瞳をゆるりと細めた。
「では、これより『血のハロウィン』の精算を始める」
此度の合同集会の目的は、先日起こった血のハロウィンの後始末をすることであった。天竺と東卍の抗争に割り込んだ黒龍、並びに元隊員の凶行とはいえ、黒龍の総長を刺すという不祥事を起こした東卍の処遇。そして天竺、東卍、黒龍の乱戦状態となった抗争の勝敗について。
諸々決めなくてはならないことは多い。
恐らく抗争をぶち壊した黒龍には、何らかの制裁が下されることになるだろう。だが、黒龍の面々の表情に、憂いはひとつも浮かんでいなかった。皆、そうなるとわかった上で、総長についていくことを決めたからだ。たとえ行き先が地獄でも、隊員たちは道連れになる覚悟ができていた。
「まずは黒龍。如何なる理由があろうと、審判を立てた喧嘩をぶち壊したからには、それなりのペナルティが与えられることになる」
「はい」
今回の抗争にて審判役を務めていた阪泉が、粛々と黒龍の処遇について告げていく。
「よって、黒龍は天竺へシマの一部を譲渡すること。また、どの地区を譲渡するのかは、天竺が決定権を有するものとする。依存はないな?」
「はい、ありません」
「次に東卍」
あくまで事務的な態度を崩さぬ阪泉が、東卍隊員たちの方へ向き直る。武道は龍宮寺たちの表情に、さっと緊張がよぎったのを見た。万次郎のカリスマ性でチームを纏めていた東卍にとって、総長不在の今が一番の耐え時であろう。東卍の本当の力量が試されるのはここからだ。
「黒龍総長を刺したのは、お前たちの元隊員だと聞いている。それは本当か?」
「はい。間違いありません」
阪泉の問い掛けに、龍宮寺が神妙に頷く。
「既に追放されているとはいえ、あの事件はお前らの不始末が原因で起こったことだ。東卍にも何か罰を……と言いたいところだが、既にマイキーが責任取ってサツにしょっ引かれてる。後は黒龍に頭下げて、きっちりケジメつけるこった」
「はい! ……花垣、」
渾名で呼ばれぬことに一抹の寂しさを覚えるも、顔には出さない。今の自分たちの関係性を思えば、それは仕方のないことであったからだ。
今生において武道は、極力東卍メンバーとの接触を避けていた。黒龍総長としての立場が障壁となったのも勿論あるが、何より『自分と関わることでまた彼らを不幸にしてしまうかも知れない』、という深奥にこびりついた強迫観念が、彼らとの交流を断たせた一番の要因であった。
未だ武道の記憶には、彼らの死に際の姿が鮮明に刻み込まれている。だから、最悪な未来へ繋がる可能性を少しでも減らすために、武道は己の存在を彼らの中から剪定する道を選んだ。
「本当に、すみませんでした」
「すいませんでした!」
その選択に後悔はしていない。
してはいないけれど……やはり、寂しいものは寂しい。
「……確かに、謝罪を受け取りました」
頭を上げてください。
東卍隊員たちが全員姿勢を正したタイミングで、阪泉がイザナの方へ視線を向けた。彼らが目を合わせたのは一瞬のことで、阪泉は許可を得たとばかりに言葉を続ける。
「最後に、『血のハロウィン』の勝敗について……」
*
結論から言うと、勝者は天竺に決まった。
また、抗争の敗者は勝者に吸収されるのが一般的であるのだが、今回はイザナが東卍の傘下入りを望まないということで、吸収合併には至らなかった。
口では東卍が目障りだの、完膚なきまでにぶっ潰すだの、物騒なことを言っていたイザナであったが。真一郎の言っていた通り、兄として万次郎に灸を据えるためだけに、この抗争を仕掛けたようだ。なんやかんやで家族想いなのである、あの孤高ぶった王様は。本人は決して認めやしないだろうけど。
「ったくよ。港区と品川区を寄越せだなんて、強欲な奴らだぜ」
――ところ変わって黒龍新宿総本部。
慈悲のない天竺の罰により、黒龍は港区と品川区という超優良なシマを泣く泣く手放すこととなった。港区は何店舗か飲食店を経営していたし、品川には二番目に規模の大きな拠点を置いていたので、この二つのエリアを失ったのは正直かなりの痛手である。
「六本木だけは見逃してやってたのによ、結局港区ごとぶん奪られるとは……金で解決しようとしても取り付く島もねぇし」
「まぁまぁ、完全撤退にならなくてよかったじゃないスか。飲食店も不動産も、権利絡みは黒龍が所有したままで良いって言ってくれてるし」
「その代わり何割かショバ代払えって言われたけどな……。何だよショバ代って。ヤクザかあいつら」
ぐったりとソファにもたれかかった九井が愚痴る。相当キているのだろう。沈痛な面持ちのまま、ひたすらに天を仰いでいた。
「今日は泊まり込み決定だな。新しい拠点の場所考えねぇと……」
「あんまり根を詰めないでくださいね」
「だいじょーぶ、だいじょーぶ」
「信用できねぇなぁ……」
「とりあえず風呂入ってくる。ボスも疲れてんだろ。早く寝ろよ」
重い足取りで九井が浴室へ向かうのを、無言で見送る。大寿は合同集会後に八戒を連れて帰宅しており、生憎この場にはいなかった。他の幹部たちも同様に、その場で解散済みであったため、今この場にいるのは武道と九井、それから……。
「イヌピー君、眠いならベッドで寝たほうがいいっすよ」
「ん……」
武道の膝の上で眠る乾の三人だけであった。
「首、痛くなっちゃいますって」
「はな、がき……」
「もう」
嫌々とむずがりながら、乾は武道の腹に顔を埋める。武道が退院してからというもの、彼は見事なひっつき虫と化してしまった。
「ブランケットどこだっけな……」
どうやら武道が目の前で刺されたのが、余程堪えたらしい。元々過保護なきらいはあったが、ここ数日でその度合いがさらに悪化している。事例を挙げればきりがなかった。室内では危険だからと包丁や鋏といった刃物類を遠ざけられ、外に出る時は事あるごとに護衛として傍に侍り、無関係な一般人まで威嚇しまくる。
しかも東卍の特攻服を見掛ければ、反射的に殴りかからん勢いで突っ込んでいくため、外出先では一秒たりとも彼から目を離せなかった。
『いい加減にしろ犬ッコロ!』
そして、ついに我慢の限界になった大寿が、盛大な雷を落としたのが三日前。かなりどぎつい教育的指導を施されたことで、ようやく乾の暴走は鎮火することと相成った。
「まだ……このまま、で……」
要は、今の状態は乾の不安が違う形で発露した結果なのである。そう考えるとどうにも彼を引き剥がす気にはなれず、結局こうして甘やかしてしまうのだった。
「……ごめんね、イヌピー君」
「ん、……?」
「オレが油断したから、あの時……不安にさせてごめん」
もっと武道が器用に立ち回っていれば、あんな惨劇は起こらなかった。万次郎が捕まることも、皆んなにあれほどの心配をかけてしまうことも。すべては己の要領の悪さが招いたことだ。
「そんな……ッ花垣は悪くない! 悪いのは喧嘩に刃物持ち込んだアイツで……!」
「イヌピー君は、どうしたら安心してくれる?」
「……っ」
「オレに反感を持ってた先代派の人たちは除名した。キヨマサに情報を横流ししてた裏切り者だって、君たちが処分してくれている」
全部後から知ったことだ。
キヨマサが武道を刺すに至った経緯について、九井は黒龍内に潜んでいた先代派の者たちが、裏で糸を引いていたのだと教えてくれた。
組織が大きくなればなるほど、それだけ統率を取ることは難しくなっていく。まして、佐野兄弟のようなカリスマ性があるならまだしも、武道は言ってはなんだが平凡だ。喧嘩は弱いしビビリで泣き虫。そんな自分が総長なんてやれているのは、ひとえに部下たちに恵まれているからに他ならなかった。
「不安要素は取り除いたはずだ。でも君はまだ不安がってる……それはどうして?」
最近になって纏まりの出てきた黒龍ではあれど、先代総長とは真逆のタイプの武道に、未だ燻った思いを抱えている者は少なくない。しかし、そういったチームの事情を把握していても、敢えてそのまま放置してきた。己に不満を持つ者がいるのであれば、彼らに認めてもらえるまで努力すればいい。そうすれば、いつか彼らとの間の蟠りも解けるはず。そんな青臭い理想論を馬鹿みたいに信じ、黒龍を束ねてきたのだ。
「ねぇ、イヌピー君。君はオレに何をして欲しい?」
今となっては、それはただの驕りであったのだと理解している。今までが順調に行き過ぎて、心の何処かで油断していたのだ。限界まで膨れ上がった悪意の芽は、やがてとんでもない狂気を孕み、ある日突然牙を剥く。その結果の凄惨さを己はよく知っていたのに。
「時には切り捨てる残酷さも必要なんだって、この一件で学んだ。もうオレは間違えない。皆が危険にならないように、不穏分子は極力遠ざけていくつもりだよ。ねぇ、他にどうしたらイヌピー君は安心できる? オレに何かできることはある?」
「花垣……」
「遠慮は無しだよ。何でも言って。オレは君にちゃんと応えてみせるから……」
抱き締めてくれ、と彼は掠れた声で言った。
ただ自分を抱き締めて、傍にいて欲しい。それだけでいいのだと。
「本音を言えば、もうあんな無茶な真似はさせたくない。今すぐ何処かに攫って閉じ込めて、オレだけのモノにしちまいたい」
でもそれだと、乾の愛した花垣武道ではなくなってしまうから。だから、我慢する。我慢が一番嫌いな男が、己の性分を捻じ曲げてまで、武道の意志を尊重すると言っている。眩いほどの思慕を捧げられ、身体の芯からボッと熱が込み上げた。
「……色々と、隠さなくなったよね」
「ふっ……あぁ。これからも隠すつもりはねぇから、そのつもりで」
「末恐ろしいな、まったく」
すり、と太腿に頬擦りする男の髪を撫でつけ、頭を抱き込む。途端に、ぶんぶんと勢い良く振り回される尻尾が見えた。可愛いひとだ。
ちゅ。
ボサボサになった旋毛へ、そっと口づける。いつになく甘い戯れに、されど乾からの反応はなかった。触れたのが一瞬であったため、彼は武道からキスされたことに気づいていないようだ。それならそれで都合がいい。相手が知らないのをいいことに、滑らかに流れる金糸へと再び唇を寄せていく。
あと少し。吐息が伝わりそうなほどの距離まで近づいた時、しかし測ったようなタイミングで、乾が武道の名を呼んだ。
「花垣、」
「ん?」
「佐野のこと、どうすんだ」
男の髪を梳く手を止める。
「……マイキー君が出所したら、ちゃんと話すよ」
「それで、お前はアイツのモノになるのか?」
「いや……それはない」
武道が万次郎のモノになるのは、どうしようもなくなってからだ。彼が道を踏み外し、後戻りの利かない場所へ行ってしまった時。置いていかれるくらいならば、自分はまた性懲りも無く、彼に己のすべてを捧げて共に修羅の道を歩むのだろう。血に塗れた世界の片隅で、息を潜めて生きていく。そんな歪な生き方をしている武道と万次郎の姿は、残念なことに容易に想像がついた。
「オレがあの人のモノになったら、また苦しめると思う。だからそれは最終手段かな」
「そうか」
「離れた方がいいんだろうね」
「……」
「このままじゃいけないのはわかってる。いい加減、あの人を解放してあげないと……」
「それはやめた方がいい」
いやに真剣な声だった。何となく顔を下へ向けると、予想外に強い眼差しに射抜かれ困惑する。
「お前が手を離したらアイツ、死ぬぞ」
ヒュッと喉が鳴った。彼にはタイムリープの詳しい話を聞かせていない。だというのに何故、さも未来を見てきたかの如く、はっきりと断言できるのか。鮮烈な光を宿した水浅葱の瞳は、己の抱える罪をすべて見透かしているようで、武道は咄嗟に視線を逸らした。
「……なんで、」
「俺ならそうするから」
「っ!」
「俺とあいつは、多分同類だ」
恐る恐る覗いた双眸の中に、隠しきれぬ嫉妬と劣情の炎が渦巻いている。思わず息を呑んだ。それは奇しくも、万次郎の目に浮かぶそれと同じであったから。
まさか、ここまでとは。
率直に思ったことはそれだった。乾から好意を向けられている自覚はある。万次郎との情事の後、身体を清めてもらう時に一線を越えかけたこともあったし、実際告白だってされた。自覚するなという方が無理な話だ。だが、あくまで彼から向けられるものは、飴玉みたいに甘く、太陽に翳せば爛々と輝く宝石のようなソレであり、己と万次郎が抱える苦味を伴うモノとは違うと思っていた。
「お前がいないと息もまともにできねぇ」
なのに、何だその目は。そんな目で見られては、嫌でも伝わってきてしまう。彼もまた、自分たちと同じなのだと。口にするのも憚れる感情を持て余し、身の内でのたうち回る本能と理性の狭間で、みっともなく足掻いている最中なのだと。
「……っ」
ごくり。
生唾を飲み込んだ。手が届かないと思っていた綺麗な存在が、翼をもがれ目の前に落ちてきた。そんな仄暗い期待と狂喜が、腹の底で首を擡げたのがわかった。
「欲がないんだな、花垣は」
ぽつり、と。思いがけずといった体で零れ落ちた言葉に、我に返る。欲がない、とは。全員の運命を変えて、全員を救う。最早神仏の領分すら踏み越えて、それでも尚、手を伸ばし続ける浅ましさ。その咎の重さを武道は嫌というほど理解している。そんな己に向かって、よりにもよって欲がないとは。
「佐野のことが欲しいなら、首輪をつけちまえばいいだろ。それが一番簡単なはずだ」
「首輪……」
「それを思いつかない時点で、お前は『欲がない』んだ」
目から鱗、とはこのことか。万次郎に首輪をつける。そんなこと今まで考えたこともなかった。
「怖いのか?」
「え……」
「アイツを飼い慣らす自信がないのか?」
声が出ない。あれだけ熱かった身体が、急激に冷えていく。さっと血の気が失せて、目の奥がチカチカと明滅した。まるで警告するみたいに。は、は、と短い吐息が漏れ、頭の中がぐちゃぐちゃに掻き回される。やめろ、やめてくれ。そんな、希望を持たせるようなこと、言わないでくれ。
「そんな、こと……」
これ以上何を望む?
救いたい人たちを救い、己の理想とする未来へのレールは、今のところ順当に真っ直ぐ伸びている。この後に及んでまだ欲するというのか。
強欲だ、と名も知らぬ誰かが叱責した。これ以上を求めれば今度こそバチが当たる。もたらされる幸福が大きければ大きいほど、その代償もまた大きくなる。誰かが幸せになるのなら、誰かがその分不幸になる。それこそがこの世の摂理だろう。
元より人ひとりが手に入れられる幸せなど限られている。いいじゃないか、もう。みんな生きている。限りなくハッピーエンドに近い未来に向かって、順調に進んでいるのだから。この辺りで妥協すべきだ。
「佐野が欲しいか?」
「……」
「お前がアイツの傍を離れれば、佐野は堕ちるぞ」
「でも、」
「言い訳はいらねぇ。欲しいか、欲しくないかだ」
どっちだ?
頭は依然として混乱したままだ。渇いた喉を引き絞り、声にもならぬ気泡を吐く。死にかけの虫の如く惨めな仕草を、目の前の男は揶揄するでもなく、じっと見つめていた。
「オレは、――」
ドロリと濁った欲を吐き出した。途方もない時間をかけて熟したそれは、甘ったるい腐臭を撒き散らし、薄桃色の唇を汚す。
「大丈夫だ、花垣」
脳髄を蕩けさせる甘言で以てして、縛る。
「お前ならできる。きっとアイツも、お前に首輪をつけられるなら本望だろう」
鎖の擦れる音が響いた。
枷を嵌められたのは、果たしてどちらか。
「もっと欲張ってくれ、花垣。アイツだけじゃない。俺のことも、もっともっと欲しがってくれ」
哀れに震える愛し子を抱き締め、青年は微笑む。
舌舐めずりする狡猾な獣の顔を、その美しい仮面の裏に隠して。
*
「ボスはもう寝たのか?」
「あぁ」
ずっと気を張っていて疲れたのだろう。乾の腕の中で寝落ちした武道を仮眠室へ運び、シャワールームに向かう途中。ソファで寛いでいた九井が、意味深な笑みを浮かべながら声を掛けてきた。
「やるなイヌピー。これでボスを佐野万次郎に奪られる心配はなくなったってワケだ」
「さて、何のことだか」
九井が武道とのやり取りを聞いていたことについて、わざわざ怒りはしない。しかしまんまとしてやられるのは癪に障るので、平静を貫きしらばっくれてみせるも、流石は長い付き合いの幼馴染みである。乾の突き放した物言いに怯むこともなく、尚もズケズケと無遠慮に踏み込んできた。
「花垣があいつのもんになっちまったら、どうせガッチガチに束縛されちまうだろ? それにあんだけ花垣に執着してんだ。花垣を手に入れた佐野万次郎が、イヌピーのことを許容するとは思えねぇ」
「……」
「なら簡単な話だ。花垣が佐野万次郎よりも優位な立場になっちまえばいい。ボスはお優しいからなァ……イヌピーのことだけ手放して、佐野万次郎だけ掬い上げる、なんてことできねぇだろうよ」
乾の愛する人は、きっと色んな地獄を見てきたのだろう。
タイムリープを繰り返す中で、沢山の人を失って、救って、また失って。人よりも多くの死を目の当たりにしてきたからこそ、大切なモノはある日突然、容赦なく奪われることを知っている。
幸せになることを極端に恐れる彼を焚きつけたのは、誰かのために傷つき続けている優しい男が、我が儘一つ許されない現状に苛立ったからだ。アイツこそ誰よりも幸せになるべきなのに。世界はいつだって武道に厳しい。
――花垣武道を幸せにしたい。
乾の行動原理は昔から何一つ変わらない。
武道を必ずこの手で幸せにしてやる。ただそれだけだ。だから可能な限り、乾は武道にとっての『庇護すべき存在』であろうとした。彼は一度懐に入れた人間の手を、無碍に振り払うようなことはしない。その点、何かあった時に手を差し伸べやすい『花垣武道の飼い犬』という乾の立場は、実に都合が良かった。
「にしても意外だったぜ。イヌピーのことだから、ボスを独占したがるかと思ってた」
「……悔しいが、流石に佐野相手じゃ分が悪い。こうする以外花垣の傍にいられる方法を思いつかなかった」
「あー……確かに。拗らせてるもんなアイツら」
我らが愛するボスは、残酷なまでに優しく臆病で、いつでも自分は救う側でありたいと考える傲慢な男である。しかも素直に人の好意を受け入れられない性分なので、彼が納得できるだけの理由がなければ、こちらがいくら手を差し伸べても拒まれてしまうのだ。
故にこうするしかなかった。たとえ他の男と彼を共有することになったって、自分が彼と共に在り続けるための抜け道はこれしかなかった。
武道が万次郎のモノになってしまったら、乾は確実に佐野万次郎の手によって排除されることになる。万次郎に弱い武道も、その判断に思うところはあれど、恐らく異を唱えることはしないだろう。ならば武道には、手遅れになる前にさっさと万次郎の手綱を握ってもらう必要があった。
「それに清水将貴の一件で、佐野はかなり参ってるはずだからな。あの猛獣に首輪つけんなら今しかねぇだろ」
「……恐ろしいねぇ。お前のこと、天然で純粋培養なワンちゃんだと思って可愛がってるボスには、ちと刺激が強かったかもな」
「そうか?」
「堂々と二股推奨しといてすっ惚けてんじゃねぇよ」
ゴスッと脇腹を小突かれる。別に惚けたつもりはないのだが。同情的な言葉とは裏腹に、楽しそうな顔をしている幼馴染みが、歌うように言葉を続ける。
「従順な子犬の皮を剥いだら、中身は立派な狂犬か。あーあ、可哀想になァ。一生離してもらえねぇとも知らずに」
彼の人の良さに漬け込んだ自覚はある。
罪悪感なんて欠片も持っていないし、反省もするつもりはないけれど。ただここまでしたからには、二度と彼にあんな顔はさせないつもりだ。自分は幸せになる資格はないとでも言うような、何もかも諦めきったあの顔だけは……。
「それにしてもあのお人好しに、こんな暴れ馬を二頭も御し切れるかね」
「できるさ」
反射的に答える。
いつも飄々としている幼馴染みが、珍しく面食らった顔をしたのが面白かった。
「当たり前だろ。俺が選んだ男だぞ?」
「……ヒュー。お熱いこって」
苦く笑った九井が、スッとソファから立ち上がる。
「確かにもう何匹も怪物を手懐けてたわな。今更な話か」
おやすみ、と短く挨拶を交わして、九井はそのまま部屋を後にした。
あの様子ではこれから仕事をするに違いない。いい加減、大量に備蓄されたエナドリを一掃してやるか。そしたら諦めもつくだろう。九井からしたら堪ったもんじゃないことを考えながら、乾もまた踵を返す。
部屋を出る際、煌々とついていた明かりを消す。
ガラス張りの壁越しに、地上のスターダストが眼下に広がった。明滅する数多の散光を眺めて、ほう、と息を漏らす。
花垣武道の愛した世界は、確かに美しかった。
「……ちっ」
だが同時に、彼を散々追い詰めたそれが忌々しく思えて。小さな舌打ちと共に、乾は煌びやかな虚構の空から視線を剥がす。
『にしても意外だったぜ。イヌピーのことだから、花垣を独占したがるかと思ってた』
腹の底で死に損ないの邪欲が蠢く。耐えるように下唇を噛んだ。
「んなもん、できるもんなら……」
苦し紛れに吐いた独白は、やがて星雲に呑まれ輪郭を失い、無数に散らばる夜光の一つとなった。
人々はあの幻想的な輝きを前に、ありきたりな美辞麗句でもってして、その眺望の素晴らしさを語るのだろう。
されど自分だけは、決してあの輝きに惹かれてはならない。
そう本能的に理解していた。
何故ならあの麗しき妖光の正体は、花垣武道を犠牲にして輝く、生き血を啜る凶星なのだから。