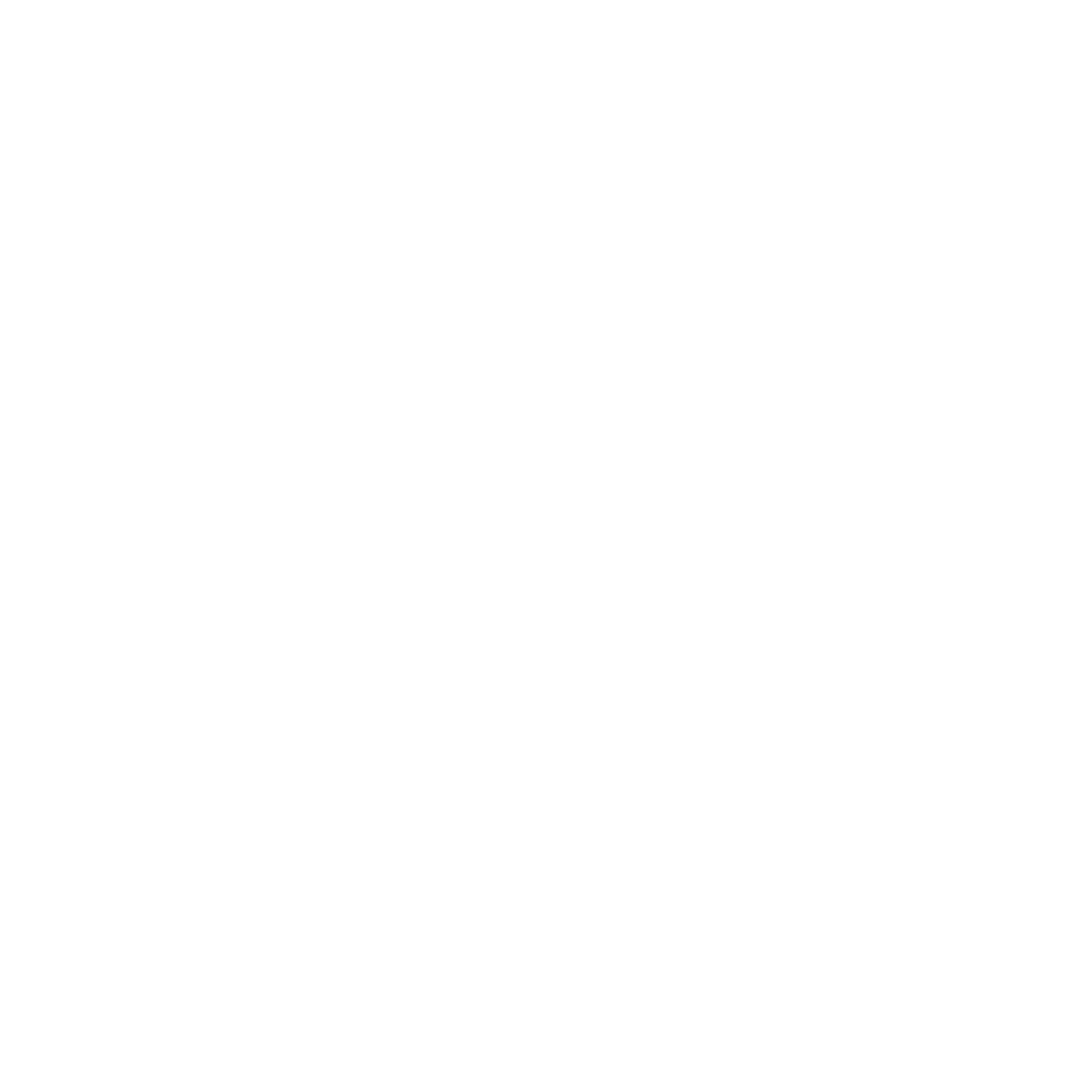第九話 化け物の定義
布擦れの音が響く。意識朦朧とした状態で、断続的になり続ける水音と、ぱちゅぱちゅという肉のぶつかり合う音を聴きながら、国広は喘いだ。
「ぁ、はぁ……っ」
気持ちいい。いつもよりもずっと、昂りが収まらない。快楽から頭がぼうっとして、正常な判断が出来ない。少しでも快感を拾うべく、首を擡げた自身をシーツへ擦り寄せようとすると、そんな国広の動きを見た男が、嗜めるように最奥を貫いた。さらには腰を大きく使って穴をぐずぐずに掻き回されてしまい、あられもない嬌声が上がる。
「ァアッ! やま、ばぎり……っ! そこ、ダメ! ダメ!」
「何がダメなのかな? こんなにヨガって締め付けてくるのに」
パンッパンッと腰を打ち付けられる度、尻たぶに長義の恥骨が当たる。あまりに激しい律動に、腰が逃げを打とうとしたところを無理矢理引き寄せられ、ぐりぐりと前立腺を抉られた。何度も達した身体には過ぎた快感に、国広はシーツへしがみつき悶絶する。もう限界だ。ヒューヒューと空気を漏らす喉は焼けつくような痛みを訴えているし、幾度となく精を吐き出した半身はとっくに空っぽである。だというのに小刻みに痙攣する内腿と、男の精を貪欲に求めんとする尻穴の締め付けが、再び訪れるであろう絶頂を予感させ、国広を絶望に叩き落とした。
「ん、もう、無理だからァ! やめ、抜け、抜いて……っ!」
「お前から誘ったんだろう。俺を煽った責任は最後まで取ってほしいな」
乱暴な手つきで尻たぶを揉まれる。反射的にきゅうっとナカを締め付けてしまい、長義の形を生々しく感じ取った。後ろから覆い被さり、国広の懇願を聞き入れずに好き勝手腰を振る男は、明らかに理性が飛んでいる。
何故、こんなことになったのだろう。
激しく身体を揺さぶられながら、考える。こうなる少し前まで、国広は二晩徹夜で近侍部屋に閉じ籠り、書類仕事にあたっていた。政府からの依頼である護衛任務を終え、本丸へ帰還してからというもの、膨大な量の《刀霊守本堂》絡みの事後処理に追われてしまって。ましてや扱っている情報が機密とされているものが多かったため、どうしても処理に時間がかかってしまったのである。そして、ようやく資料を纏め上げたのが、本丸に帰還して二日後の夜。出来上がった資料を片手に、審神者と国広以外で唯一事情を知る長谷部へ引き継ぎをして、晴れて国広は案件から解放されたのだった。
長義に会ったのは、疲れた身体を引き摺って部屋へ帰ろうとしていた時だった。廊下で鉢合わせた彼と一言二言言葉を交わした後、国広の方から長義の部屋へ行っても良いかと持ち掛けて、それから――。
「それで、偽物くんはあんなに待望していた本歌に抱かれて、満足したのかな?」
はん、と勝ち誇った笑みで見下ろされて腹が立つ。確かに、あの時寝不足でぼうっとした頭のまま何事か口走ってしまった気がするが。だからといって待望していたというのは大袈裟である。大体、国広は長義のことを知りたい一心で、彼と話をしたいがためにこの部屋に来たいと言ったのに。それを『抱かれたかったから』と曲解されるとは思ってもみなかった。とんだ誤解である。
「ちがう……っ! だから、俺はあんたと話を、したい、と……っ」
「下のお口で? はしたない子だね」
「あ、ンッ」
こいつ、絶対わかってやっているな。
ずちゅ、と淫らな水音と共に、また奥を突かれ身悶える。溜まりに溜まっていた疲労も相まって、もう気をやりそうだ。このまま貪られ続けたら冗談抜きで折れる。
「は、……やま、ばぎり」
「ん?」
右腕を掴まれ、ぐいっと上半身を起こされる。体勢が変わったせいで挿入の角度が変わり、先端がイイところを掠めた。再びきゅんきゅんと物欲しげに内側を締め付けた瞬間、捻じ込まれたままの欲望が膨張し、男も限界が近いのだと悟る。
「は、ぁ……きもちいい……いい、から……も、限界……だ……」
「……っ」
「も、イッて……俺でイッて……? 本歌……っ」
「お前……、」
ずるり。
それまで己を翻弄し尽くした欲が、一度抜き出される。入り口に擦れる感触にすら感じてしまい、程よく筋肉のついた下腹部が波打った。一方、長義は未だ身を震わせていた国広の腰を掴むと、それまで組み敷いていた身体を上向きにひっくり返す。気づけば国広は、がばりと両足を割り開かれ、あられもない場所を男に曝け出していた。だが、既に理性をドロドロに溶かされた状態では、羞恥心など覚えるはずもなく。それどころか男にすべてを委ねている現状に、酷く興奮する。
「ほんか……」
最早抵抗する気力も失せ、成すがままとなった国広を、長義が見下ろす。潔癖なまでに整えられた髪はぐしゃぐしゃに乱れているし、垂れ下がった前髪からは汗が滴っている。何かを耐えるように唇を引き結んだ姿からは、普段の余裕など皆無で。ただひたすらに目の前の獲物を骨の髄まで貪らんとする獣が、そこにいた。
「はぁ……っ」
悩ましげに息を吐き、自らの意思で膝を掴んで、さらに足を割り開く。挙句もどかしげに腰を揺すって、雄を誘った。それでも動こうとしない男に焦れて、その怖いくらいに整った顔へ手を伸ばせば、獣は気持ち良さげに目を細めるだけで、大人しく国広の掌を甘受する。手の甲で頬を撫で、指先で唇を辿り、陰を落とす長い睫毛の縁を撫でてから、垂れ下がった銀髪を耳に掛けてやる。その後、何の気なしに男の首に腕を回して、顔を一気に引き寄せた。
ちゅ、ちゅ。
触れるだけの口吸いを交わす。二度、三度と、啄ばむように。だが、頑なに閉じたそこは一向に開く気配を見せない。そんな男の反応に不満気に眉根を顰めた国広は、唇をくっつけたまま割れ目を舌先でつつき、先を促した。
「本歌……口吸いがしたい。舌を絡める、深いやつを……」
吐息がそのまま肌に伝わるくらいの至近距離で、強請る。
「……お前、本当に今日はどうしたんだ」
「……ダメか?」
「ダメではないが……、」
珍しい。あの高慢で、自信満々で、滅多に揺らがない長義が目を彷徨わせている。
愛しい、と思った。愛しい、可愛い、綺麗だ。もっと彼の表情が変わるところを見たい。彼を知りたい。同じくらい、自分を知って欲しい。
『人は臆病な生き物だからね。相手を想えば思うほど、わからないことを恐ろしいと思ってしまうのさ』
不意に、審神者の言葉を思い出す。人は未知を恐れるのだと言っていた。まぐわいを確認行為だとも。だとしたら人の器を得た今の自分は、長義の一番近いところで、彼と何かを確かめ合っているのか。そのことがこんなにも嬉しい。確かめているものが愛なのか、それとも別の何かなのか、それはわからない。わからないが、そんなことは国広にとっては瑣末事だった。ただ彼から向けられる感情の一つ一つを、純粋に余すことなく受け取りたいと思う。それだけ。
「本歌、口吸いを……」
どうか、どうか。与えてくれ。お前の全部を。
口吸いをして、優しく抱き締めてくれ。あの美しい本霊のように微笑みながら、お前のことを教えてくれ。何を見て、何を思い、何を考え……何を好み、何を厭い、何を欲するのか。全部、全部教えて欲しい。知りたいのだ。山姥切長義という刀のことを。そして、同じくらい俺のことも知って欲しい。俺が何を誇りとし、何を生き甲斐とし、何を大切にしているか。その大切な物の中には彼の存在も、ちゃんと入っている。
――俺はかの名刀工・堀川国広が作刀した『山姥切国広』が俺の写しであることを、とても誇りに思っているよ。
別れ際に本霊から与えられたあの言葉が、胸の奥にじんわりと染み入っていく。小さな灯火がゆっくりと時間を掛けて広がってゆき、やがて大きな青い炎になった。身体が熱い、熱い。呼吸を堰き止めてしまいそうなくらいに大きな想いが、喉元に込み上げてきて、息苦しさを助長する。
だが、不思議なことにその苦しさは、彼と出会った頃に感じていたそれと比べ物にならぬほど、温かで優しかった。
「なぁ、山姥切」
「……なんだ」
「俺もな、あんたが本歌であることを誇りに思っている」
もっと知って、知ってくれ。俺のことを。
「あんたが俺を写しとして不出来だと思っていても、俺は……ん、!」
「もう黙ってくれ」
――頼むから。
それは懇願だった。常にない長義の様子に驚く暇もなく、呼吸を奪われる。性急に交わされた口吸いは乱雑で、歯が当たって口端が切れたし、血の味がするしで散々なものだったけれど、それ以上に満たされるものがあった。くちゅくちゅと熱い口内で舌を擦り合わせ、戯れに上顎を舐め上げられる。国広は長義の口端から溢れた唾液に、じゅっと吸い付いて、また角度を変えて唇を重ねた。もっと、もっと、と求めて、与えて、際限無く溺れていく。
「……ふ、あんたとの口吸い、好きだ」
「……っ黙れと言っているだろう!」
あ、まただ。また、温かな何かが心に溢れた。それは例えば、秋の木漏れ日のような。傍を吹き抜ける春風のような。ふとした瞬間に気づく程度の、小さな温もり。そこでやっと理解した。今日のまぐわいが、いつもよりもずっと気持ちいいと感じた理由を。今自分は長義に心を委ね、己を曝け出している。山姥切長義という刀を、この自分が一番近くで見ている。山姥切国広という刀が何たるかを、一番近くで彼に見てもらえている。それを自覚するだけで、こんなにも変わるなんて。
「……人の身は奇怪だな」
「……俺にはお前の方が意味がわからないよ」
悔しげに呟かれた言葉に首を傾げる。呆れたようにため息を吐いた彼は、もう一度唇へ軽い口づけを落とし、すり、と腰をくねらせて下半身を擦り寄せた。天を仰ぎ、熱り勃った剛直を尻に擦り付けられ、その大きさと硬さに少しだけ怯む。
「お前、急にどうした」
「どう……とは?」
いよいよ挿れられる、となった時。焦らすように動きを止められムッと唇を突き出した。だが、そんな国広の無言の催促など華麗に無視して、長義が言う。
「俺に会いたかった、だとか、夜に俺の部屋に来てもいいか、とか。普段は俺が呼びつけて渋々来るくせに。それに、最中の反応も……変だ」
「……だから、変とは何がだ」
ここまですべて曝け出しているのに、まだわからないのか。わからないなら、答えるまで。そう内心意気込んでいると、そんな国広の鼓舞も虚しく、長義は気まずげに顔を背けた。
むず痒そうな顔をした男が、もごもごと口の中で言葉を転がしている。あまりに小さな声だったので、何と言ったかまでは聞き取れない。つくづくこの男にしては珍しい。人のことをとやかく言う前に、長義の方が余程変ではないか。国広は訝し気にしながらも、じっと男から答えが返るまで待った。そして、ややあって腹が決まったのか。苦虫を噛み潰したような顔をした長義が、ぐっと顔を近づけてくる。冷たい色をした瞳はドロリと欲望に蕩けており、その目を見るだけで下腹の奥が淫らに疼いた。
「……いつもより可愛い」
「は、……?」
ずぶり。
言うが早いか、ズンッと一息に貫かれて星が飛んだ。
「ぅ! な、……そんな、きゅうに……っ!」
一瞬意識が遠のきそうになったのを寸でのところで引き留めて、何とか戻ってくる。可愛い、といったのか、今。もう一度何と言ったのか問おうとするも、それから長義はひたすらに国広の肢体を貪るばかりで、一向に口を開くことはなく。国広も国広で口から零れる嬌声を押し殺すのに必死で、到底尋ねられる状態ではなくなった。
「っ、」
「んァ……ッ、は、うぅ」
ゴリゴリと前立腺を突かれ、さらに奥まった場所を先端でこじ開けられる。息が止まった。あんまり気持ちよくて。加えてナカの快感だけでも凄まじいのに、長義の手が悪戯に前を弄り始め、気が狂いそうになる。
「声、聴かせて」
「い、やだ……ァ!」
半狂乱で髪を振り乱しながら頭を横に振ると、宥めるようにそっと金糸を撫で付けられる。
「おねがい」
ヌメヌメと滑る先端部分を親指で擦られ、もう何も出ないというのに射精感ばかりが積もっていく。もう出ない、からっぽだ、無理だ、やめてくれ。そんな切実な国広の制止の声など聞こえていないかのように、長義は行為を激しくさせていく。
「……くにひろ。きもちいい? 俺はきもちいい」
ずるい。こんな時にその名で呼ぶなんて。涙で濡れた翡翠がうろうろと長義を映し出すと、ふ、と柔らかく微笑まれた。そんな顔、初めて見る。
「……わらった」
「……ん?」
「うれしい……」
ほにゃり、と国広の表情が緩められる。嬉しい、嬉しい。あの氷の神様のような男が、人らしく笑っている。あの柔らかな笑みを、他でもない己に向けている。これ以上ない幸福感が溢れた。真綿で包まれたようなふわふわとした、軽くて温かい、浮足立つような喜び。
「あ、……きもちい、やまんばぎり、そこ、きもちいい……っ」
「……っ、ほんと、今日のお前はどうかしてる」
「うぁっ! ぁああ、あ!」
「ぐっ……」
どくどくと己のナカで脈打つ長義の熱を感じて、国広も絶頂に達する。倒れ込んできた身体を受け止め、舌を絡める深い口づけを交わせば、注ぎ込まれた霊力も相まって、完全に一つになったような錯覚を抱いた。
(一つに?)
そこで、ハッと気づいた。気づいて、しまった。本当に一つになったなら。互いに互いのことを理解し、すべてわかり合う日が来たならば。この行為に意味はなくなってしまう。この、甘やかな時を彼と共有することは無くなってしまう。本歌と写しという縁を持っただけの、赤の他刃として、付かず離れずのありきたりな関係に収まってしまうかも知れない。
それはとても寂しいことだと思った。失いかけてようやく、国広は長義にそこまで入れ込んでいるのだと知った。
「ほんか、ほんか」
「ん、なにかな、国広の」
長義の首筋に頬を擦り寄せると、クスクスと笑い声を漏らした長義が、上機嫌に国広の髪を撫でつける。俺をもっと知って。頭のてっぺんからつま先まで、全部。でも、知らないで。まだ、終わりたくないから。
「……ふ、」
「何を笑っている。気でも触れたか」
投げられた言葉は鋭いが、その声色が今までのそれの比ではなく、何処までも優しい。
我ながら愚かだと思った。こんなの本末転倒だろう。わかって欲しいのに、わかって欲しくないなんて。矛盾にもほどがある。こんなことでは長義だって戸惑う筈だ。あれだけきらきらと輝いていた景色が、途端に色褪せていく。心臓が鼓動を止め、身体の芯から冷えていく。まるで崖のどん底に突き落とされた心境だ。あんなにも、嬉しくて堪らなかったのに。己を暴かれるかと思うと、先へ進むのがどんどん怖くなる。あぁ、本当に今日の俺はどうかしている。
「やまんばぎり、俺は、なんだとおもう」
うぞうぞと名残惜しそうに国広の肌の上を這っていた手が、動きを止める。
「お前は俺の写しだよ。それ以下でもそれ以上でもない」
恍惚とした表情でこちらを見る男に、胸中で舌を出す。
俺は堀川国広の最高傑作。今は主の刀。それから、この山姥切長義の写し。この男が知っているのは、俺のごく一部だけ。彼が俺の全部を知ることがなければ、この甘やかな生き地獄は続いてくれる。涙が零れた。生理的なそれではない。正真正銘の、感情が溢れた涙だった。
「何故泣く?」
「……さぁ、なんでだろうな」
骨ばった指先が、頬を伝う涙を拭い去る。自ら彼の掌に擦り寄ると、長義は一瞬だけ身体を強張らせはしたが、恐る恐るといった手つきで国広の頬を撫でてくれた。いつもは強引なくらいにしたいことをするくせに、こちらから行動を起こすと戸惑うらしい。
「……おれは、どうかしてしまったのだろうか」
「お前は年中わけがわからんからな。今更だろう。なに、不良品となった時はこの本歌が直々に手折ってやるさ。それくらいの慈悲は見せてやる」
疲労が頂点に達し、うとうとと微睡み始めた国広の隣に、長義が寝転がった。頭の下に腕を差し入れられ、ぐっと強く腰を抱き寄せられる。ゴソゴソと身動いで、収まりのいい場所を探した。そして程よく筋肉のついた胸板に顔を埋め、ぴたりと肌を重ねたまま目を瞑り、自ずと眠りへと誘われていく。
「……それは、頼もしいな」
「あぁ。だからしっかりとおやすみ」
頭上から降ってきた就寝の挨拶に、言葉を返せたのか。返せなかったのか。ぐちゃぐちゃに散らばった緩慢な思考回路では、判断がつかない。何もわからぬ間に、国広は深い眠りに落ちていった。
*
ザクッとふかふかの土に鍬を突き立て、両側の畝にかけていく。斬った山姥の呪いなのかなんなのか。長義は畑の土に触れると肌がかぶれてしまうため、膝まである長靴に、厚手の軍手を二重に嵌めるという重装備で、畑仕事にあたっていた。これは審神者から特別に支給されたもので、初めこそそんなものに頼るものかと強がってみせたものだが、今では有り難く使わせて貰っている。長義が受け入れた理由としては、畑当番を終える度に、手入れ資材を無意味に減らしたくはなかったというのと、何より無駄に資材を使ったせいで、あの主命の鬼から雷を落とされたくなかった、というのが大きい。
ザクッザクッ。
肥料を撒いて肥やした土は、新たな命の芽生える苗床となる。審神者の霊力で満たされた本丸内の畑では、種を蒔いてから僅か半日程で収穫の時を迎えた。よって、畑当番は肉体労働であり、畑を耕すところから収穫に至るまで、そのすべてを半日の間に終えなければならないという、スピード勝負の作業でもある。それこそ二振り体制でなければ回らないくらいには、それなりにきつい。だから、目の前の男のようにサボられると、そのツケが丸々自分に跳ね返ってくるわけで……。
「おい、遊んでないで手を動かしてくれないかな」
畑の片隅でせっせと何かを植えている太鼓鐘へ、長義が声を掛ける。先程から何かの種を植えているようだが、手に持ったパッケージを見るに、あれは指定された野菜のものではなかった。何をしているのかな、まったく。
何を植えているのか問うたところで、「ヒミツ!」の一点張り。ニヤリと不穏な笑みを見せるだけ。行程的には、まだ種植えと水やり、収穫が残っているので、このまま作業を放棄されては長義の負担が大きくなる。さて、どうしたものかな……。なんて内心頭を抱えていたら、ようやく《ヒミツの作業》とやらを終えたらしい太鼓鐘が、野菜用の種を持って戻ってきた。
「待たせたな! ちょ〜っちみっちゃんを驚かせてやろうと思って!」
「……君は鶴丸殿の影響を受け過ぎじゃないか」
「んなことねーよ? 俺は俺のやり方で皆をド派手に驚かせるからな!」
そういうところだ。などと指摘しても、どうせ聞く耳など持ちやしないのだろう。他の刀たちもそうだが、各々個性が強くて困る。
「ていうか、影響受け過ぎってんならあんたのことだろ。山姥切、隊長の影響受け過ぎ〜」
「はぁ?」
揶揄うように言われて頬が引き攣る。なんだそれは。この本歌たる俺が、偽物くんの影響を受けているだと? 冗談じゃない、と憤った。
「いや、なんつーか……雰囲気? が柔らかくなったってか、話し掛けやすくなったというか」
「へぇ、前までの俺は取っ付きにくかったのかい」
「ま、気安く話し掛けていい感じの空気じゃあなかったな。外面は良いんだけどよ。触れたらぶった斬る! ってのが透けて見えてたぜ」
そこまで攻撃的になったつもりはないんたが。何となくモヤモヤとしたものを抱えながらも、作業に戻る。彼と話していても時間の無駄でしかない。この数時間で学んだ。
そもそも影響を受けた、というのなら、それは国広の方だろう。あの男は長義と再会してから、みるみるうちに変わっていった。まず、綺麗になった。外見も内面も。これは日頃の長義の努力の賜物である。身体を重ねるようになってからというもの、長義と国広は共に風呂へ入る機会が増えたため、国広の身体のメンテナンスは長義が手ずから行うようになった。その成果あって、最近の国広の毛艶や肌の調子はすこぶる絶好調である。赤子同然の柔肌は、いくら撫でても飽きない。纏う服も、長義の部屋の中だけではあるが、長義の誂えた一級品の服を着るようになった(自分の服よりも、写しの服の量の方が多くなってきたのは完全に余談である)。内面に関しても教育は抜かりなく、彼が卑屈を発揮しようとする度に、「俺の写しなのだからしゃんとしろ!」と叱咤し、度が過ぎれば夜に仕置をしてやったおかげで、今では滅多に、写しであることに引け目を感じているような、後ろ向きな発言はしない。まぁ、これは長義の前でだけかも知れないが。
そして何より、最近の彼は可愛くなった。これに関してだけは、未だに長義の中で心に整理がつけられないでいる。あの山姥切として顔を売っていた偽物くんだ。号を喰いかけた相手を、可愛いだなどと考えるようになるなど……いつから己は、そんなに甘くなったというのか。
「山姥切……!」
あぁ、噂をすれば何とやらだ。無粋な足音を立てて長義の方へ駆けてくる国広を見て、緩みそうになる表情筋を引き締め直す。「そんなに足音を立てるな」と嗜めると、すぐにハッとした顔をして、あたふたと足音を立てぬよう気をつけながら走り出すものだから、堪らなかった。
「それで、何の用かな。そんなに慌てて」
「あ……畑仕事を終えたら、共に菓子でも食おうかと思って……」
鶯丸がくれたんだ。
と、控え目に包みに入った茶菓子を見せてくる国広に、長義は苦笑する。これではまるで親と子だ。まだまだ未熟で不出来な写しと、その生まれる所以となった本歌。成り立ちを考えるならば親子に近いものはあるが、それでも厳密に言えば違う物。これは本歌たる山姥切のために生まれ、本歌を引き立て、本歌の存在を後世まで伝えるという役目を背負った写しだ。親子というより、寧ろ自分の手足、一部といった方が相応しい。
「後でいただこう。昼餉前には畑当番も終わるだろうから、その頃に茶室で用意をして待っているといい。ついでだ。昼餉もそこで共に食べよう」
「……っあぁ!」
またドタドタと去っていく写しを見送り、小さく笑う。あれは、さっき言ったことなどすっかり頭から抜け落ちてしまっているな。また、ちゃんと言って聞かせなければ。この山姥切の写しとして然るべき振る舞いを……。
「なぁ、やっぱあんたら変わったわ」
「……?」
「そんなんじゃ、隊長が修行に行った時とかやべぇんじゃねえの? 早く写し離れしろよ、本歌サマ!」
へへん、と得意げに笑ってみせる太鼓鐘に対し、長義は閉口する。修行……修行か。演練相手で見かけた、やたらと堂々とした面構えをした己の写しの姿を思い出す。何度か話し掛けられたこともあり、極めた写しがどのような変化を遂げるのかについては、大方知っている。知っているからこそ、国広が修行に行くなんてことは、到底許せそうもなかった。あんなふてぶてしく、薄情な物に成り下がるくらいならば、修行なんて行かせぬ方がマシだ。それに、打刀の極化は弱体化が著しいとも聞く。尚更今のままでいいではないか、という気持ちの方が強かった。
「あれは修行なんて行かせないよ」
極めた後のことを考えて、ゾッとする。写しとしての自覚がますます無くなり、万一この縁が途絶えてしまったら。主人の刀としての意識が強まり、己の管理下から完全に外れてしまったら。長義は何をするか自分でもわからない。
「あー……こりゃ隊長も大変だな」
そんな会話を最後に、二振りは畑作業に集中していく。ペースが格段に上がったのは、余計なことを考えたくなかったが故に、作業に没頭したからだ。
全ての工程を終え、後は収穫……となったタイミングで、長義は太鼓鐘が嬉しそうな声を上げたのを聞いた。結構大きな声だったので、何事かと思い彼の方を見てみると、なんと見たことが無いほどの馬鹿でかい花が咲いている。何だあれは。食虫植物か何かか。人の器の太鼓鐘が、縦に二振り並べても尚余りあるくらいに大きなそれは、圧倒的な存在感でもってして、畑の一角を占領している。
「なんだそれはっ」
思わず声を荒らげてしまった長義は悪くない筈だ。しかし、大笑いしながら花を眺めていた太鼓鐘はというと、何ら悪びれた顔一つ見せずに、「ちょっとみっちゃん呼んでくるわ!」と言ったきり、厨の方へ走っていってしまう。必然的にぽつん、と収穫籠を持ったまま、畑に置き去りにされる形となった長義は、あまりに一瞬の出来事に、唖然とその場で突っ立つことしか出来なくて。やがて太鼓鐘の姿が完全に見えなくなってから、時間差で込み上げてきた怒りのままに、その場で地団駄を踏んだのだった。
あの男、俺に畑仕事の大半をやらせておいて、収穫作業まで!
「クソックソッ! 今度はちゃんと真面目な刀と組ませてもらえないかな⁉」
これは後で燭台切を引き連れて戻ってきた太鼓鐘から聞いた話なのだが。
あのやたらと大きな花の名前は《スマトラオオコンニャク》といい、世界で一番大きな花とされているらしい。また、日本ではその形状から《ショクダイオオコンニャク》とも呼ばれているようで、太鼓鐘はそれを演練相手の同位体から聞かされたことで、今回の計画を実行したのだとか。
ちなみに、花を見た燭台切の一言目の感想は、
「うーん……世界一っていうフレーズは惹かれるものがあるけど、あんまりカッコ良くない見た目だね……」
という、微妙なものであったことを、ここに記しておく。
*
カタリ、と音を立てて、襖を開く。分厚い雲が星々を覆い隠した、月の見えない夜。手元に持った簡易ランプの明かりを頼りに、国広は人気の無い廊下へ踏み出した。
「……兄弟?」
すると、うん、と眠い目を擦りながら起き上がった堀川が、今にも部屋から出て行こうとしていた国広を呼び止める。そんな彼に「起こしたか」とだけ返してから、国広は未だいびきをかいて眠る山伏まで起こしてしまわぬよう、慌てて手元の明かりを消した。
「こんな時間に……何処に行くの?」
訝しげにする兄弟刀へ、安心させるよう秘めやかに笑む。
「……散歩に。修行が近いから、少し考えたいことがあってな」
「そっかぁ。ついに兄弟も極修行か……散歩、僕も一緒に行ってもいい?」
「……あぁ」
床冷えせぬよう厚手の靴下を履いてから、堀川が国広の後についてくる。こんな時間にすまない、と謝れば、気にしないで、と微笑まれ二振り揃って苦笑した。行く場所は決めていない。せっかく誰もいないのだ。少し遠くまで足を運んでみるのも一興かと、西の離れから少し離れたところにある南庭へ向かう。あそこの池で泳ぐ鯉たちには、気紛れに餌をやりに行っていた。あの場所なら、きっと静かに物思いに耽ることが出来るだろう。
「修行はいつからだっけ?」
足元に散らばる小石を蹴飛ばしながら、堀川が聞く。
「……明後日の予定だ」
「そっか。旅道具や身支度は僕に任せて! 自分の経験も踏まえて、必要な物を揃えておくから」
「兄弟にそう言われると、頼もしいな」
「うんうん、頼ってくれていいんだよ。僕は割と初期の頃に極修行に行ったからね」
それからは色々なことを話した。この本丸に顕現されてからのこと、人の器を得て初めて挑んだ出陣について、それから一介の刀であった時分の話、親父たる刀工・堀川国広のこと。特に、堀川が修行中に見たという、親父が旅の中で出会った蕎麦屋の娘に入れ込んで、一週間連続で三食を蕎麦だけで過ごした、という話は傑作で。そこまで行動しても想いを告げられなかったあたりが親父らしいな、と腹がよじれるぐらい笑った。親父は職人気質で、弟子たちには厳しく檄を飛ばしたものだが、女子ども相手だと照れ性で口下手を発揮する性分だったのだ。
「……修行とは、何百年、何千年という己の生き様をこの目で見て、己と向き合うために在るのだと聞いた。それを聞いた時、俺は修行に行くのはまだ早いのではないか、と思ったんだ」
そして、次第に話の内容は、国広の修行のことへと移り変わる。
「俺は俺と向き合う決心がつかなかった。俺が歩んできた歴史は、決して良いものばかりではない。寧ろ嫌な思いをしたことの方が多かった。写しだからと侮られ、国広の最高傑作であるにも関わらず、不当な評価を下され……また、あれを見せられるのかと思うと、正直少しだけ怖気づいた」
情けないよな、俺は親父の最高傑作なのに。
そう続ければ、堀川は真剣な顔をして、首を横に振る。
「兄弟。嫌な記憶は、誰しもが持ってることだよ。それを見たくないという気持ちだって、僕にも痛いほどわかる。それは当たり前のことなんだ。兄弟だけじゃない」
「……兄弟、」
「兄弟は、間違いなく父さんの……僕らの自慢さ。だから、胸を張って、堂々と自分の過去と向き合ってくればいい。時には心ない言葉を見聞きしてしまうこともあるかも知れない。写しに厳しい評価を下す時代は、確かにあったから。それでも、その出来事があってこそ、僕らはここにいる。『今』がある。こうして真っ当な評価をしてくれて、僕らを使ってくれる主さんにも出会えたんだ。それに、僕ら兄弟が顔を合わせることだって……」
堀川が、徐に本体を呼び出す。国広もまたその意図を察し、本体を呼び出した。二振り揃ったところで刀をゆっくりと前へ差し出し、互いに鯉口を切る。
カチッ。
「……兄弟」
「うん」
生き生きとした光を湛えた二振りの刀が、鞘から少しだけ顔を覗かせた。その瞬間きらり、と。雲の切れ間から差し込む月光を反射して、剥き出しの銀色が鋭く輝く。手入れの行き届いた、刃こぼれひとつない名刀同士。互いの命に等しいそれを、絶対の信頼を寄せた相手へと、無防備に曝け出す。
「どうか、兄弟が立派になって帰ってきますように」
堀川が、想いを込めて願う。
「国広の名に恥じぬ、刀となってみせよう。主の、そして兄弟や親父たちが誇る、国広の最高傑作の称号に相応しい刀に」
国広も、己の心の臓に刻みつけるように、言の葉を紡いだ。
――金打。
キィンッと軽い金属音が辺りに響き、刃を交わせた二振りは刀身を鞘へと収める。迷いは晴れた。俺はもっと強くなる。強くなれるんだ。皆が誇る刀となれるように、国広が誇る一振りの刀として、すべてを背負って俺は旅に出る。そして、山姥切国広という刀が歩んだ物語を、一つ一つこの目で見てこよう。例え、それが苦い思いをした歴史であったとしても。
もう、目を背けない。背けてはいけない。俺はそれだけのものを、既に背負っているのだから。
「それにしても、そんなに修行に行くことを迷ってたのに、よく決心がついたね」
何かを思い出したかのように、堀川が言う。
「きっと、兄弟が変わりたいと思うきっかけになってくれた人が、いるんだね」
優しく微笑む堀川は、多分それが誰なのか見当がついていた。そしてその男は、たった今国広が思い浮かべた男と同じに違いない。
「……堂々と並び立ちたいと思ったんだ」
兄弟だからこそ、打ち明けられた本音。彼と出会って始めの頃は、彼の隣に並び立つだなどと恐れ多いことは、思いつきもしなかっただろう。しかし、あの男との関係の変化と共に、国広の気持ちにも徐々に変化が生じてきて、そしてようやく腹を決めることが出来たのだ。
「……兄弟、今日は」
「夜遅いし、迷惑にならないようにね。でも、修行の前に、ちゃんと話しておいた方がいいから……行ってきな」
「すまない。山伏の兄弟とも、明日ちゃんと話をする」
「うん、それがいいよ。……おやすみ」
「おやすみ」
――西の離れと東の離れの境界で、国広と堀川は別れた。
ひたひたと歩く国広の足取りに、迷いはない。目指す場所は一つ。通い慣れたあの男の部屋だ。例え彼が眠っていようと叩き起こしてやる、くらいの勢いで、国広は部屋まで辿り着くと、三度ほど扉を叩く。
「……山姥切、入ってもいいか」
扉の向こうから、ゴソゴソ、と布擦れの音がする。もしかしたら眠っていたのかも知れない。彼が割と遅くまで本を読んでいることを知っていた国広は、来るタイミングを間違えたか、と苦い顔をした。
「……どうぞ」
しかし、予想外にも入室の許可は得られた。帰ろうか迷っていたが、結局彼の言葉に甘えることにして、そうっとドアノブを回す。ギィ……と軋む音を立てて扉を開くと、やはり眠っていたらしい長義が、寝台の上で眠たげに宙を眺めていた。
国広が長義の下へ歩み寄るまでの間、二振りに会話はなかった。一歩、また一歩と近づいていくごとに、嗅ぎ慣れた柑橘系の香りが鼻腔を擽る。心臓が高鳴った。長義が目の前にいる。その事実だけで、ド、ド、と刻まれる鼓動は速度を上げていき、それに伴って緊張も張り詰めていく。これ以上進むと、心臓が壊れてしまうかも知れない。そんなありえないことを考えて、国広はあと少しというところで足を止めた。
「……?」
すると、なかなか傍に寄ろうとしない国広に焦れたのだろう。今にも瞼を閉じてしまいそうな顔をした長義が、棒立ちになっている国広の方を一瞥する。
「……夜遅くに、すまない」
何とか声を絞り出し、詫びる。
「本当にね。寝ていたというのに」
「それは、本当にすまなかった」
「いいよ。そら、早くこちらに来い」
手を引かれ、寝台に倒れこんだ。ぎゅうっと抱き締められたまま横倒しにされ、突飛な彼の行動に戸惑う。
「……足、冷たい。手も冷えているな。お前、結構な時間外にいただろう」
「……すまん。今離れるから、」
「こら、離れるな。俺があっためてやるから……」
寝惚けているのか。
足を絡め、手を繋ぎ、より身体が密着させれる。こっそり長義の胸に耳をあてがうと、とくとくと緩やかな鼓動が聞こえてきて、その音を聞いているだけで心が満たされていくのを感じた。あぁ、温かい。足も、手も、心も。やはり、彼の近くは心地良い。
「……あんたと話がしたくて、ここに来たんだ」
「……下の口で?」
「またそれか。違うと言っているだろう」
「ふふ、冗談だよ」
目を閉じたままの長義が、夢現にいるからか、いつもよりもふわふわとした声で言う。普段こんな軽口を叩いたことなどなかったので、今こうして彼と普通に会話が出来ているということに、とても嬉しくなった。
修行に行くという話は、主の計らいでごく限られた者にしか伝えていない。自分がいないことで確実に業務に支障をきたすであろう、近侍率の高い刀である長谷部。同室で、兄弟刀である堀川と山伏。それから、暫くの間第一部隊の隊長代理を務めてもらうことになった、副隊長の三日月。また、修行に行くことを明かしている者たちにも、明確にいつ行くのかという日取りは前日に告げるという徹底ぶりだった。彼らを口が軽いとは思っていないが、何かの拍子に噂が広まって大ごとになっても困る。大仰な見送りはせずに、内々だけの見送りで。それが、国広たっての希望だった。
「なぁ、聞いてくれ……」
山姥切には、ずっと伝えるか迷っていた。言えば最後、この関係が破綻してしまうように感じて、なかなか言い出せなかったのである。だが、先程の堀川との会話の中で、心が決まった。
「明後日、修行に行くんだ」
「……」
返事はない。目を瞑ったまま微動だにしない長義を前に、国広は言葉を続ける。
「今まで俺が歩んできた歴史を、見つめ直してくる。こちらの時間軸では四日ほどだが、あちらでは俺は数百年という時をかけてを旅するんだそうだ。だから、その前に――」
「俺に、別れの挨拶をしに来たって?」
え、と小さく声を上げたと同時、長義の目が開かれた。
ついさっきまでうつらうつらとしていたとは思えないほど、澄んだ青瑠璃は剣呑とした光を湛えていて。その瞳の奥に、苛烈な色が過ったのを目の当たりにする。なんで、どうして、そんな目をする? 理解が追いつかず、ただひたすら己を射抜く双眸を見つめていると、桜色に色づいた薄い唇が、酷薄な笑みを形作った。
「……また性懲りもなく断ち切るつもりなんだ?」
断ち切る? 何のことを言っているのだ。
「いいよ。出来るものならやってみるといい。逃げられるものなら逃げてみろ」
「……っ」
掴まれた手首の骨が、ギリ、と軋む。折れてしまうのではないか。そんな本能的な恐怖から、思わず身体が彼から離れようと動いた。
恐らく、それが決定打だった。
「何度だって、結び直してやる。何度だって、……」
「山姥切……? いっ!」
がぶり。
首筋に噛み付かれて強い痛みが走る。噛まれた場所に手で触れると、案の定そこからは血が出ていた。突然豹変した長義の様に混乱を極めていれば、そうしている間にも布を剥がされ、夜着を乱されていく。この空気は、知っている。初めて国広が長義に犯されたあの夜。無理矢理事に及ぼうとして、手酷く抱かれた日の彼と、まったく同じだ。
「山姥切……っ、待ってくれ、まだ話が」
「修行の話か? そんなくだらない話など聞く価値もないな」
くだらない?
くだらないと言ったのか、今。国広が一大決心をして、前へ進もうとしたことを、くだらないと切り捨てたのか。他でもない、己に踏み出すきっかけをくれた、この男が。
「くだらなくなどない!」
声を張り上げる。あまりの国広の剣幕に、長義は軽く目を見張った。まさか国広が言い返すなど、思ってもみなかったのだろう。長義が強引に進めようとした時、今までの国広は文句こそ言うけれど、最終的には大人しく従っていたから。
「俺は修行に行って、強くなりたいんだ……っ! お前の隣に堂々と立ちたい……!」
「写しが身の程を弁えろ! 本歌と並び立つだなどと、よくもそのようなことが……っ」
「お前の傍にいたいんだ!」
国広を暴こうとしていた手が止まる。己に覆い被さった身体が強張り、長義の顔に至っては凍りついていた。
「本歌と写しとしてじゃない、一振りの刀同士として、傍にいたい。対等でありたい。もう、今のままでは……嫌なんだ……」
強欲な写しだと嘲笑うか。笑うなら笑え。俺は本歌という次元を超えて、山姥切長義という刀そのものに惚れている。
そう、惚れているのだ。薄々心の何処かで気づいていた。ずっと見ないふりをしていた。だって、自覚したところであまりにも不毛過ぎる。俺はこんなにも長義を想っているのに、こいつの意識の範疇に入る俺は、あくまで一介の写しでしかない。本歌たる彼より格下で、己を引き立てる物で、常に管理下に置くべき物。それが、彼の中の山姥切国広という刀の存在意義だ。そんなの、ずるい。俺ばかりが、この刀を求めている。求めているのに、俺のすべてをやってもいいとすら思っているのに、こいつはそんな国広の気持ちなど知らずに、また残酷にも上っ面だけの仮初の慈悲を与えてくるのだ。それが本歌の役目だからと。
「お前は、自分が極めた後にどのような刀となるのか知っているのか?」
信じられないものを見るような目で国広を見ながら、長義が問う。
「極めた後のお前は主の刀としての意識が強くなり、山姥切の号を切り捨てる」
「そんなことは、」
「ない、と言い切れるか、お前に。他でもない、極める前でさえ何度も、何度も山姥切の呪縛から、逃れたいと思っていたお前に……っ!」
胸倉を掴まれ、ぐらぐらと揺さぶられる。
ひゅ、と喉が鳴った。何も言い返せない。俺を通して本歌を見る人の子たちの目。写しというだけでベタベタと貼り付けられる偽物のレッテル。不当に歪められた己への評価。そのすべてから逃れたくて、いつからか汚らしい薄布を纏い外界を遮断した。己が写しではなかったらと、ただの堀川国広の最高傑作として生きることが出来たならと、考えては虚しくなって。向けられる好奇や悪意から心を守るため、自分の殻に閉じ籠った。
それは事実だ。今更覆りようのない、紛れもない事実。確かに国広は、嘗て長義との縁を拒絶した。
「ほらな……何も言い返せない。随分と薄っぺらい言葉だ。お前の言う『傍にいたい』だなんて」
「……それ、は」
「お前が離れようとする度に、途切れかけた縁を結い直していたのは誰だと思う……? お前はそんなことも知らずに、いつだって俺から離れていこうとする」
つ、と首筋を撫でる指先。そこで気づいた。この場所にはきっと、目に見えぬ彼と己の間に結ばれた縁の糸が在るのだと。
「……写しとは、本歌のために在るものだろう? そもそもが傍にいたいだとか、そんな希望論の話ではないんだ。お前は初めから俺の傍に在る『べき』物なのだから。なのに何故、わざわざ遠くへ行こうとする。やっと、やっとこうして手の届く場所に、置くことが出来たと思ったのに……」
どうしたら、伝わるのだろう。きっと、言葉で伝えても無駄だ。俺はあまりにも、彼の中で《写し》であり過ぎたのだ。千年近く掛けて凝り固まったその概念を紐解いていくのは、きっととても難しい。
「……俺を抱け、本歌」
ならば、全部曝け出そう。自然と言葉が滑り落ちてきた。もう何も恐れない。すべて理解し合った先で、彼が俺への関心を失ったのなら、何度だって振り向いてもらえるように努力する。俺に出来るのはそれだけだ。何と言っても堀川国広の最高傑作。本歌たる刀の気を引くことなど、造作もない筈だ。
「なにを、」
「全部やる。俺の持っているものをぜんぶ。お前にやるから」
国広の帯に手を掛けたままだった長義の掌を、そっと掴む。ぴくりとも動かないそれを己の頬へ近づけて、すり、と擦り寄った。潤んだ瞳で長義を見れば、目が合った瞬間にぱっと彼の顔色が紅潮する。口を半開きにして固まった顔は、未だ惚けたままで。そんないつにない間の抜けた表情を晒す男に、少しだけ胸がすっとした。
「おい、」
長義の纏う夜着の合わせ目を、ゆっくりと寛げる。合わせ目から覗く、芯を持っていない逸物は、黒いボクサーパンツの上からやわやわと揉み込んでやった。ふ、と思い立ち、徐々に首を擡げ始めたそれに顔を近づけ、すんっと匂いを嗅ぐ。すると、蒸れた雄の匂いがして、より一層興奮を煽られた。己の昂りを逃すように、ふ、と悩ましげな吐息を漏らし、国広はついに下着へと手を掛ける。
先端に引っかからないよう気をつけながら、慎重にそれを取り去る。その瞬間、顔を出した肉棒を口いっぱいに頬張って、挿入さながらの締め付けを与えながら、頭を上下に動かした。
「く、……なにして、」
長義が、息を呑んでこちらを見つめている。驚きに見開かれた双眸には、仄かな欲が灯っており、時折良いところを国広の舌先が這う度に、腰がビクンッと跳ねた。
目は口ほどにものを言う。口ではやめろ、と制しているくせに、荒くなった息が、真っ赤に熟れた頬が、突き刺さるような視線が、彼の興奮状態を如実に表していた。気持ちいいのか。少しでもこの身体で感じてくれているならば、嬉しい。そんなことを思いつつ、裏筋を下から上へねっとりと舐め上げ、くびれを舌先で刺激する。同じ男だ。どこをどう攻めれば気持ちよくなるかなど、手に取るようにわかった。
(そろそろか)
ここまで勃起していれば、中に入れるのに支障はあるまい。そう判断したところで、最後にじゅるりと音を立てて先走りを吸い取る。その際、ちゅ、ちゅ、と音を立てて、割れ目に口づけを落とせば、そそり勃った剛直は切なげにふるふると震えた。
「……はは、勃ったな」
すっかり固くなったそれに頬擦りしながら言えば、羞恥から長義の顔がさらに赤くなる。クソッ! と悔しげに小さく舌打ちをしていた彼であるが、満更でもなさそうだ。国広はこの先へと進むべく、今度は自らの夜着をさらに寛げ、下着を取り去った。
一糸纏わぬ姿になった後、とん、と男の肩を押して、腹の上に跨る。上から見下ろした状態でするのは初めてだ。緊張と共に、今からこの男と一つになることを思うと、仄暗い悦びが腹の底に湧き上がる。
「ふ……」
ずぷっ。
軽くいきみ、尻穴を緩めながら腰を下へ下へと沈めていく。慣らしていないそこは閉じていた。しかも潤滑油を使っていないため、ところどころで引っかかる。これでは最後まで入らないし、何より長義が痛かろう。そこまで思い至ってから、国広は一度途中まで入っていた逸物を抜き去り、己の指を丹念に舐め始めた。次から次へと溢れ出る唾液を指先に絡め、それを自らの穴に塗りつけていく。
「待て、そのままではお前が傷つく……っ、」
一本、二本、三本。乱暴に慣らしたそこはまだ固い。
「ぐ……っ」
「やめろ、国広!」
「はぁ、ぐ……ぅ……!」
ずぶりっ!
おざなりに慣らしただけの状態で、一息に腰を沈めた。痛い。きっと入り口は裂けて、血が出てしまっている。だが、痛いくらいで丁度良かった。この痛みは、愚かにも男の寵愛を求めた己への罰も同然なのだから。
「ほん、か……」
「……チッ。この、ばか」
ぐっと腹筋を使って上体を起こした長義が、馴染むまで国広を抱き締めて待っていてくれる。滅多に見せない優しい触れ方に、じわじわと涙が滲んだ。何故そんなに性急にことを進めた、だとか、自分の身体を粗末に扱うな、だとか色々と言われた気がするけれど。そんな小言など気にもならないくらいに、心が痛くて、痛くて。
「どうか、……」
「……?」
「『俺』を見てくれ……長義」
想いのカケラが、一雫。頬を伝って落ちる。痛みのせいじゃない。ままならぬ現状に押し潰されそうで、耐えかねて零れた涙だった。
「俺は写しだが『山姥切国広』だ……あの新刀の祖・堀川国広が作刀した最高傑作……。なぁ、頼む。俺をただの写しとしてみるんじゃなくて、俺を、俺として見てくれ……」
認めて欲しい。写しとしてではなく。一振りの刀として。他でもないこの男に認められたなら、それ以上の幸福はない。
ぽすり、と長義の肩に額を押し付けて、ぐりぐりと擦り寄る。好きなんだ。こんなにも、痛みだって捩じ伏せてしまえるくらいに、己の身を顧みることを忘れるくらいに、心底惚れている。この感情の一部には、写しであるが故の本能から芽生えたものも、少しは混ざっているのかも知れない。それでも、彼を愛しく思うこの気持ちは、彼に愛されたいと、認められたいと乞う気持ちは、紛れもなくこの『俺』だけのもの。それだけは、信じて欲しかった。
「……なぜ、そこまで、」
唖然と、長義が呟く。
「……わからないか?」
ちゅう。
国広は目の前の白い首筋に、強く吸いついた。赤い花が咲いた。鮮やかで毒々しくて、醜い執着が刻み込まれた、痕が。ここから先の言葉は、叶うなら修行から帰ってきてから伝えたい。だから、また何事かを問おうとしたその口を、己のそれで塞ぐ。舌を絡めることもない、触れるだけの口吸いに込められた意味を、この聡い刀はどう受け止めてくれるだろう。
「……これだけは、わかってくれ。俺が修行へ行きたいと思ったのは、お前の傍にいたいからだ。今だけじゃない。これからもずっと、お前と一緒にいたいから……お前に、『俺』を認めて欲しいからだ……」
「……くにひ、ろ」
「……この先は……極めたその時に、伝えたい。返事も、今は要らない」
震える指先で、その銀色の髪を撫でる。涙で顔はぐちゃぐちゃだし、色んな場所は痛いしで散々な独白だ。でも、これくらいしないと、お前は俺の話を聞こうとしないだろ? 俺を見ようともしなかっただろう。だから、これは必要なことだった。後悔はしていない。
「……動いてくれ」
「……っだが、」
「……痛くしてくれていい。お前の好きなように動いてくれ」
きゅうっとナカを締め付けた。硬度を保ったままのそれがピクリと反応し、生々しく脈打つ。臆することはない。これに貫かれながら揺さぶられる時の快感を、国広は知っている。
「長義を、くれ……欲しい」
――お前が、欲しい。
「っ! お前というやつは、」
もつれ合いながら背中から押し倒され、あっという間に形勢は逆転された。ギシギシと軋むベッドフレームの音が、その行為の激しさを物語り、視線を彷徨わせたその先では、己の両足がゆらゆらと揺れている。やがて痛みが快感に変わる頃。一度果てた長義は、ほぼ同時に達した国広の精液を潤滑油代わりにして、再び国広を貪った。
「ちょ……ぅぎ、」
「はぁ……、くにひろ……っ」
「……すまない」
――好きになって、すまない。
もっと、息が楽になる関係は、確かに自分たちに残されていた筈なのに。
「……っあや、まるな!」
ガツガツと腰を打ち付けられ、中に出された長義のものが溢れ出し、入り口が泡立つ。苦しそうに眉根を顰めながら、それでも動くことをやめない男に縋って、引き寄せて、そっと彼の頭を抱き込んだ。
「長義」
本歌でも、山姥切でもない。ただの一振りの刀。何の因果も持たぬ刀同士であったならば、こんな不安に苛まれることはなかったのだろうか。現に自分は、彼と歪な関係性を築いてしまったせいで、彼に疎まれることを心底恐れている。挙句恋い慕っているからこそ、不出来な刀だと関心を失われるその時が、厚顔無恥な写しだと忌み嫌われるその日が来ることを、酷く恐れているのだ。
(あぁ、)
本霊に答えたあの言葉。訂正しなくてはならない。本歌が理解出来なくて、偶に恐ろしいと思いこそすれ、彼を化け物だなどと思ったことはないと言った、あの言葉を。
主が言っていたように、未知なる恐れを化け物と定義するのなら。彼は確かに国広にとって、《化け物》と呼ぶに相応しかった。恐ろしいものなど、全部斬ってしまえばいいだけだと思っていた国広を、こんなにも震え上がらせる存在が、目の前で平然と息をしている。
「……っは、」
刀が刀を恐れるなんて、お笑い種もいいところだ。こんなことでは、失望されて当然か。
(好きだ、長義)
今はまだ、言えないけれど。何百年、何千年と途方もない時間を見つめ返して。胸を張って彼の前に立てたなら、その時は。
一振りの山姥切国広としての言の葉を、どうか受け取ってくれ。