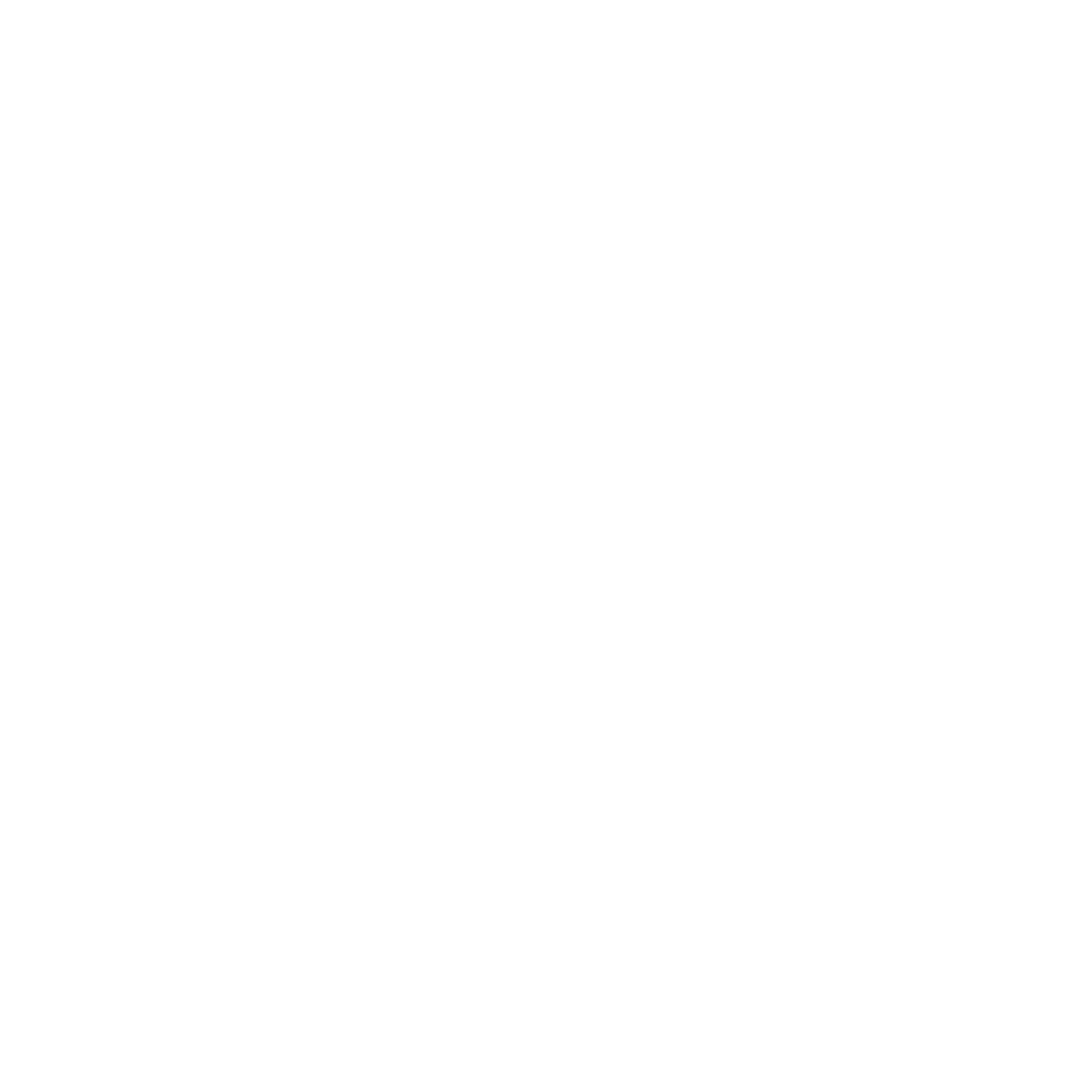最終話 縁のかたち
南庭の片隅に、白い山茶花が咲いている。
この一帯だけ季節が一定に保たれていることを、一体どれほどの刀が知っていることだろう。橋を渡ったその奥の、生垣の向こう側。そこに、隠れるようにして咲いている花の存在自体、知っている者はごく僅かに違いない。
「おや、こんなところにいましたか」
「江雪……」
膝ほどある白藍の髪を揺らしながら、旧知の仲である男――江雪左文字が生い茂る葉を掻き分けてやってくる。畑仕事の帰りだろうか。紺の甚平姿に長靴という、普段の戦装束姿と比べると一気に砕けた印象の装いに、彼が着替える前にわざわざ長義を探して、ここまでやってきたことを悟った。
「国広は……」
あぁ、あれのことを心配してきたのか。それもそうか、と納得する。彼は国広が幼かった頃のことを知っているせいか、何処かあれのことを気にしていた気来があったから。
「まだ寝ている。あと半刻ほどで手入れが終わるらしい」
「そうですか……」
長義の話を聞いて、江雪が頷く。昨晩無理なまぐわいをしたせいで、国広は軽傷となり手入れ部屋に入っていた。だが、まさかそんな夜の事情をあけっぴろげに言い触らすわけにもいかず、周りにはいつもの口喧嘩が殴り合いに発展して、結果国広が軽傷を負ったということにしている。国広は長義が悪者になるのでは、と不満げな顔をしていたけれど、流石にあれだけ無体を強いたのだ。これは俺が負って然るべき責だと強く言い聞かせれば、渋々納得した。
「暴力は感心しませんね」
昔から変わらぬ、江雪らしい言葉に苦笑する。
「俺も反省している。あれ相手に大人げなかったと」
「……和睦の道を、」
「あれが俺の言うことに素直に耳を傾けるようになったらね」
はぁ、と呆れたようにため息を吐き、江雪は目の前の山茶花へ手を伸ばす。そして、そうっと白い花弁をひと撫でして、長義の方へ向き直り、言った。
「あなたの国広への執着は、些か度が過ぎているように思います……」
それは自分でも自覚している。長義はあの写しを、己のために作られた刀を、どんな手を使ってでも手元に置いておきたくて仕方がなかった。己の誉れを証明し、己の姿を後世まで残す役目を背負った写し刀。しかもそれはただの写しではなく、本歌たる己と伯仲の出来と言われるほどのもので。あの刀が打たれた当時、長義は己の写しが打たれたという事実と、その打たれた写しが大層美しく、出来が素晴らしかったことに、とても誇らしくなったのを覚えている。
「彼の首……あれほど縁の糸が絡まっていては、碌に息も出来ないでしょうに」
国広の首に何重にも巻きつけられた縁の糸は、長義の執着の証だ。相手の急所に刃をあてがい、いざとなればこの手で手折ることも辞さぬ無慈悲さと執念の表れ。
「あれが写しの本分も忘れて、縁を絶とうとするからだ」
「彼は元より独立した一振りの刀です。縛り付けられ、傍に置かれておくことを良しとするような、そんな柔な物ではありませんよ」
ぴしゃり、と言い切った江雪を、長義が睨みつける。
「独立した一振りの刀……? 何を言う。あれは俺の一部だろう。本歌と写しとはそういうものだ」
「普通の写し刀ならば、そうでしょうね。ですが彼はこの本丸の初期刀であり、自他共に認める『刀工国広の最高傑作』です」
また、それだ。何かにつけて国広の最高傑作だなんだと。そもそもあれが生まれた理由は、俺があってのことではないか。写しとは、本来そういうものだろうに。それもこの山姥切と伯仲の出来とも言われた写し刀だぞ。それ以上の誉れなどあるものか。ここまでの栄誉を賜っておいて何故、わざわざ他の存在理由を見つけようとするのか。長義には理解出来なかった。
そう、理解出来なかったのだ。昨晩、国広を抱くまでは。
――『俺』を見てくれ……長義。
情事の真っ最中。国広から言われた言葉を思い出す。あんなに必死になって彼から何かを乞われたのは初めてだった。
(俺を見ろだと……あいつは俺の写し。それ以上でも以下でもない)
常ならば、その一言で切り捨てられた。だというのに一体なんだ、この喉元にしこりが残ったような違和感は。何かが引っかかる。彼が何を必死になって己に訴えたかったのか、あと少しでわかりそうな気がした。されどその解は酷く遠い場所にあり、伸ばした掌は空を切る。今己が掴もうとしているものは、とても大切なもの。それだけは理解していて、昨晩からずっと考え続けている。
「長義の。何を恐れているのです。あなたらしくもない。あなたは山姥を斬った刀……霊剣・山姥切でしょう。あなたの価値もまた、皆は認めているのですよ」
そもそも俺は、何故こんなにもあれを俺の傍に置きたがるようになったのだったか。
「恐れてなど、」
「彼は彼。あなたはあなたでしょう。確かに本歌と写し、その縁は変わりません。ですが、あなたたちの縁はもう、それだけではない筈です。もっと太く、強く、それでいてしなやかな……違う縁が、その手に結ばれているではありませんか」
左手を上げる。ふ、と視線を下げた先には、今にも途切れてしまいそうなほどにか細く、春の景趣に溶け込んでしまいそうなくらいに淡い、薄紅色の糸が括り付けられていた。
――この想いを、人の子はなんと言ったか。
戦の気配があちらこちらに色濃くあった、あの頃。足利の城に二振り揃って在った、千年近くも昔の話。当時の主であった足利城主・長尾顕長は、あれほど栄華を誇った北条家が傾いてゆく様を見て、当時足利にいた堀川国広へ写しの作刀と、長義の磨り上げを依頼した。
その理由は明らかだった。己が刀を持ち、戦場へ出る覚悟を示すため。二振り揃って持って行くつもりだったのか、それとも長義と国広のうち一振りを、信の置ける家臣の誰かに下賜するつもりであったのか。今となっては誰にもわからない。ただ、彼が不利な戦況の中、死を覚悟して戦さ場へ赴こうとしていたのは確かで。当時大太刀であった長義が実戦向きな大きさへと姿を変えたのも、長義の写しとして国広が作刀されたのも、つまりはそういうことだった。
『じきに足利も戦さ場と化すだろう。恐らく、かなり厳しい戦になる……八王子の城は、男だけでなく女子どもまでもが、悲惨な末路を辿ったと聞いた。……お前だけでも逃げろ』
主の傍らに置かれた長義が、その会話を聞いたのは偶然だった。
水無月の下旬。間者より入る報告によれば、小田原の様子は日に日に不穏なものとなっている。主の顔も曇り始めていた。そんなある日の夜、寝室にて共寝をしていた奥方へ、顕長が言った。
『何をおっしゃいます』
それを聞いた奥方は、普段の穏やかさから打って変わって刺々しい声を出した。次いで、すぐにその長い黒髪を揺らし、首を横に振る。
『私はあなた様の正室、添い遂げる契りを交わした妻にございます。絶対に、あなた様のお傍を離れは致しませぬ』
その後、いくら顕長が説得しようとも、奥方は頑として首を縦に振らなかった。こうしている間にも、着々と戦況は悪化している。このままいけば、恐らくは……。多くの戦を経験してきた武将たる主には、この戦の勝敗は既に見えていたのだろう。だからこそ、奥方へ逃げろといったのだ。しかし、それを奥方は聞き入れなかった。
傍にいたいと言ったのだ。妻とはそうあるべきなのだと、ひたすらに繰り返して。
『あなた様がここで戦うのなら、私もお供致します。伊達に何十年と武将の妻をしておりませぬ。ここであなた様と共に腹を切るくらいの覚悟は、とうに決めております』
『何故そこまで……』
『何故とは、野暮なことをお聞きになるのですね。だって、私は……』
傍に、ずっと。
行く先に死が待っていると理解していても尚、共にいる。その死への恐怖を凌駕するほどの強い想いに、長義は惹かれた。とても美しい在り方だと思ったのだ。
(××していると、奥方はおっしゃった。なら、俺はあれの傍に……いや、俺たちの場合は本歌と写しなのだから、あれが俺の傍に在るべきなのか)
雷に打たれたような衝撃を伴って、思い立つ。本歌たる己のために生まれた写し。あの子が俺の傍にあることは、当然のことなのだと。
だって、俺はあの子を××しているのだから。
『国広の、ずっと俺の傍にいるのだぞ』
生まれたばかりの赤子同然。無垢で幼く、実に哀れな俺の写し刀。彼の世界のすべてが俺だけで構成されていた、あの頃。それをいいことに、長義は国広を言霊で縛った。
『ほんかのおそばに? なぜ?』
『写しとは、そういうものだからだ』
『……ほんかがそういうのなら。おれはあんたのうつしだからな』
しかし、あれから何百年と、千年近い時を生き永らえて、あの時抱いていた想いの形は変わってしまった。甘やかな情は怒りに染まり、巫女の編んだ組紐の如き清く美しい縁の形は、醜く姿を変え、果ては血のように赤黒く変色した。途切れそうになる度に結び直し、離れていこうとする度に男の首を締め上げる、怒りに塗れた日々。そんなことを繰り返すうちに、あれだけ美しいと思った心の在り方は、どんどんどす黒いものに侵食されていった。
救いは無かった。長義と国広は、長い間ずっと離れ離れになったが故に、関係を清算する機会が与えられなかったのだ。その結果が、今だ。
(あぁ、そうか)
「江雪」
思い出した、気がする。すべての始まりを。俺の原点を。
「……はい」
「最近、あいつが俺の写しでなかったら……なんて考える」
空を見上げる。曇り空だ。今にも一雨きそうな分厚い雲が、蒼を覆い隠してしまっている。燕が足元を飛び去り、湿った風が銀糸を攫った。
身体を重ねている時、唐突に溢れそうになる温かな何か。無性に触れたくなって、あの吸い付くような白い肌を掌でなぞった。吐息を零す桜色の唇を塞ぎ、己の息を吹き込んでやりたい。呼吸も、思考も、五感も、あの刀を構成するすべてを、この俺で満たしたい。そんな衝動に突き動かされて、己の痕を全身に刻み込んだ。
「あの刀を……不本意だが、時折恐ろしいと感じる」
何を考えているのかわからないあの翡翠に、静かに見つめられると、それだけで心が落ち着かなくなる。首に巻き付けた縁の糸が途切れていないことを確認しては、ほっと胸を撫で下ろす自分が滑稽で。偶に怒りに任せ何もかもを壊したくなった。
「無性にあれを見ていると苛立って、一つになってしまえばいいと思ったんだ。あまりにも、あれが俺を否定するから」
己の霊気を注ぎ込んだ男の様を見て、二振りで一つになったように錯覚を覚えては、充足感に浸る。その瞬間のなんと甘美なことか。一方で、混じり合うことを本能的に嫌忌する己もいて、せめぎ合う二つの感情に挟まれ、内側をズタズタに切り刻まれるような苦痛を伴った。
「……そうか。俺は忘れてしまったのか」
大事なものを、忘れてしまっていた。
南泉に言われた、お前は心が化け物になってしまったという、あの言葉。まったく言い得て妙である。あの日、あの瞬間、主に教えてもらった人の子としての感情を、いつしか長義は思い出せなくなっていた。何かを慈しむ心を失い、怒りに支配された物など、化け物意外の何者でもない。
「……長義の。雨が降ってきました」
「……」
「戻りましょうか」
ひたり、と頬に当たる水滴を、指先で拭い去る。硬く結ばれた赤黒い縁の結び目が次々と解かれていき、それらは数本の細い糸となった。そして、解かれた糸の先から、山藍摺、青瑠璃、金糸雀、白銅……といった、長義と国広の髪や瞳を思わせる色に始まり、薄紅や臙脂といった温かみのある色が増えてゆく。複雑に絡み合いながら、結われ、解かれ、また結われ。やがて太く美しい一本の組紐となった縁の形は、千年ほど前にみたあの姿と同じだった。
(お前は……)
あいつは既に、応えていたのか。俺の心の在り様だけで、こんなにも糸の形が太く、美しく変わるなど……。見えていなかっただけで、ずっと傍にあったというのか。そんな簡単なことにも気づかず、己はなんと滑稽なことをしていたのだろう。
「……俺は、」
あの子のことが――……、
*
夕餉を済ませた後、翌朝には修行に出ることなど塵とも悟らせぬ顔をして過ごしていた国広を、長義は部屋へ誘った。堀川や山伏と話すのであれば構わないと、念のため気遣うと、彼らとは昼に話をしたから問題ないと返され、内心安堵する。今までよりも彼を誘うのが緊張したのは、きっと彼に対する感情を明確に意識したからだ。
そう考えると何だか落ち着かぬ心地になって、緩みそうになる口元を叱咤する。
「寛いでいてくれ。茶を淹れる」
「俺がやろう」
「いい。お前はそこに座っていろ」
いつもと勝手が違うからか。落ち着かなそうにそわそわと腰を下ろす国広を尻目に、長義は部屋の奥の戸棚から湯呑みを取り出す。手早く湯を沸かし、二振り分の茶を淹れたところで、適当な茶菓子と共に国広の前に出してやった。
「明日だな」
「……あ、あぁ」
うろうろと視線を彷徨わせている国広に、長義は首を傾げる。
「なんだ、どうした?」
「その……この茶菓子は、」
「芋羊羹だ。お前、それが好きだったろう」
「……っうん」
こくり、と一度頷いてから、緩々と口角を上げた写しの顔を、長義は見つめる。頬が少しだけ紅潮し、嬉しそうに顔を綻ばせる彼は、今まで以上に綺麗に映って。見ているこちらが何だか照れ臭くなってしまった。
「……何だ、その顔は」
「いや……覚えていてくれたんだな」
嬉しい。
そう言って微笑む彼の表情は、心の底から嬉しいのだという感情を長義に伝えてくる。
「……っ」
堪らなかった。今すぐ抱いてしまいたい。こんなにも愛らしい生き物を傍で見ていて、何故今まで気持ちを自覚しなかったのか。否、純粋にこの男を愛していたというだけならば、きっと早々に気づいていた筈だった。だが、長い年月をかけて色んな想いが複雑に絡まり合っていって、元の形がわからなくなるくらい拗れてしまったばかりに、こんなにも自覚するのが遅くなってしまった。
「お前のことを、俺が忘れるはずがなかろうに。……国広、」
――励めよ。
少しだけ、笑う。国広は目を大きく見開いて、呆気に取られていた。
「お前がさらに立派になって帰ってくるのを、ここで待っている」
「……ちょ、……山姥切」
「長義でいい」
「……っ!」
「長義でいい。国広の」
かたん。
湯呑みを机に置き、背筋を伸ばす。真剣な顔でもう一度繰り返せば、彼はゴクリと喉を鳴らし、長義と同じように居住まいを正した。
本歌と写し。この関係が変わる日は、自分たちが山姥切長義と山姥切国広という二振りの刀である限り、絶対に訪れない。離れて過ごした年月分、二振りはずっと苦しみながら日々を過ごしてきた。人の言葉に捻じ曲げられ、在り方そのものを歪められ、時には相手を疎み、それでも断ち切ることの出来なかった縁。正直、今でも国広が山姥切としてこの本丸で過ごしていたことには、思うところはある。写しとしての本分を放棄し、長義から離れていこうとしたことも。しかし、それ以上にこの刀を愛おしいと思う気持ちの方が強くて。叶うならば、あんな互いに傷つけあうような形ではなく、互いに認め合い、寄り添い合うように……それこそ、足利で見た嘗ての主たちのように、共に在れたらと思った。
そう、思えるようになったのだ。
「返事は要らないと言ったな」
びくり、と。国広の肩が小さく揺れる。
「……あぁ」
「では、お前が修行から帰ってきた時、話をしよう」
話をしよう。自分たちには言葉が足りなかった。いや、国広は何度も訴えてきてくれていた。長義が、それを聞かぬふりをしていたのだ。話をすれば最後、国広が己の前から消えてしまうことを、血反吐を吐くような思いをして繋ぎ止めた縁を、断ち切られてしまうことを、無意識のうちに恐れていたから。
「……俺も、あんたに伝えたいことがあるんだ」
「……」
「修行から帰ったら……聞いてはもらえないだろうか」
これだけ濃密な関係を築いておいて、そんな自信なさげに言うか。まぁ、今までが今までだったので致し方ないかとは思うのだけれど。それでも、そこまであからさまに遠慮されてしまうと、悲しいものがある。
「いいだろう。だから、あんまり本歌を待たせるんじゃないよ」
「……感謝する」
そこから二振りは、少しだけ昔のことを話した。
足利に在った頃の、遠い思い出。国広は存在が不安定であったせいか、当時の記憶がほぼ残っていないらしく。それを残念に思いながらも、長義は己が覚えている限りの思い出を、国広へ語ってやった。
身体が小さく、歩くのが遅かった国広は、どうしても長義と歩くと小走りになってしまって。それに痺れを切らした長義が、国広の小さな身体を抱えて、城内の至る所を歩き回るようになるまでは、そう時間はかからなかった。途中、城に棲む様々な精霊や付喪神と出くわすと、国広は必ずちょっかいをかけられて泣いた。それも大泣きだ。わんわん泣き喚いて鼓膜が破れそうなくらい叫ぶし、なまじ元気がいいものだから、一度癇癪を起こしたが最後、それはもう暴れまくる。いくら女神が優しくあやしてもダメで、国広に懐かれていた屏風の男神でもダメで……完全にお手上げとなった時。必然的に国広をあやすのは、長義の役目になった。理由としては、長義が抱いてあやすと、すぐにコロコロと笑い出し、国広の機嫌が直ったというのが大きかった(それに少しだけ優越感を抱いていたのは、一生の秘密である)。
足利の城の庭に植わっていた、蜜柑の木。真冬に開花し実をつけて、三月頃までは共に庭先まで出向いては、何度かその実をもいで食べた。四月には満開となった桜を見に山へ降り、木の幹に躓いて転んだ国広を抱き起こし、泣きべそをかく彼をあやすまでが恒例だった。だが、五月には身体の動かし方を学んで転ばなくなったので、それを長義が褒めてやれば、桜に負けず劣らずの満面の笑顔を咲かせた。
「俺は……あんたに凄く世話になっていたんだな」
気恥ずかしそうに布を引き下ろしながら、国広が言う。
「そうだね。お前のおしめを取り替えてやったこともあったね」
「流石にそれは嘘だとわかるぞ……。俺たちは排泄なんてしないだろ」
むぅ、と唇を突き出した国広に、クスクスと笑った。おいで、と一言告げて己の膝を叩けば、彼は手に持っていた湯呑みを置き、大人しく長義の膝の上に向かい合って座る。
「大きくなったな」
「……あんたは小さくなった」
「おや、磨り上げ前の姿を覚えてるのかい」
「ぼんやりとだが……」
銀色に輝く髪を、国広の白い指が撫でる。何処か惜しむような手つきで、上から下へと指を滑らせる様に、そういえば昔は髪が長かったことを思い出した。
「長い方が良かったのかな?」
ふるふる、と。国広が頭を横に振る。
「どちらでも。今の長義も……綺麗だ」
「あぁ、そう」
触れるだけの口吸いをした。一度軽く触れて、顔を離し、至近距離で見つめ合う。互いの瞳の奥には欲が燻っていて、肌にかかる吐息がやけに熱かった。
くちゅ……。
箍が外れた。次は貪るような口づけを交わし、何度も角度を変えながら舌を割り入れる。舌先で口内を愛撫すれば、時折唇の隙間から国広の喘ぎが漏れ、その淫靡な響きがみるみるうちに、長義の腰を重たくさせていった。
「なぁ、長義……」
悪戯に国広の手を取り、一本一本の指を焦らすように絡ませると、ぎゅっと握り返される。
「ん?」
「……早く言いたい」
「なら、早く帰ってこい」
ぽすり、と長義の肩に頭を乗せて、国広が笑う。
「……ふ、簡単に言ってくれる」
「俺の写しが、たかが数百年の旅もこなせなくてどうする」
国広が修行から帰るのは、この本丸の時間軸で計算すると、たった四日程度。しかし、彼がこれから体感するのは、自らが打たれたその瞬間から現在に至るまでの、千年近くの時の流れだ。その間、この刀はひたすらに己の刃生を見つめ直し、己と向き合うことになる。長義への想いを胸にしまい込んだまま。
「それとも、自信がないのかな?」
「……別にそうとは言ってない」
「心変わりしたら、ぶった斬るよ」
襤褸布を剥ぎ取る。中から現れたのは、何度見ても綺麗な、俺の写し刀。今国広が纏っている薄手の夜着は、以前長義が贈った紺の着流しで、その合わせ目から遠慮なく掌を滑り込ませる。乱れた襟ぐりから肩が覗き、そのままストン、と滑り落とした。露わになった目に眩しいほどの白い肌は、艶かしく長義を誘い、引き寄せられるように顔を近づける。
左胸の飾りを爪で引っ掛ける。何度か弾き、くりくりと捏ねくり回す、ということを繰り返しているうちに、慎ましい頂はピンとそそり立った。反対側の方も唇で愛撫してやれば、唾液まみれになっててらてらと光るそこが、明確に形を変える。もっともっととはしたなく強請るように、顔を上げた薄ピンクのそこを、長義は心ゆくまで堪能した。
「ん……っ、ぁ……はぁ、」
「……ん、」
無意識の行動なのだろう。夢中になって、じゅるじゅると音を立てて乳首へ吸いつく長義の頭が、国広の両手に抱えられ、さらに胸の方へと押し当てられる。
「……足りない?」
「……うん」
「何が欲しいか言ってごらん」
涙目で息を乱す国広の頬に、口づけを贈った。幼子をあやすようなそれだ。すると、蕩けた翡翠が長義を捉え、淡く色づいた唇が花開く。
「……下、さわって、くれ」
同時に下半身を擦り付けられ、鈍い快感が腰に広がる。言うだけ言った後、国広はすっかり照れてしまって、長義の肩に顔を埋めて隠れてしまった。国広の恥ずかしがっている顔が見えないのは残念だが、彼自らが長義に擦り寄ってくる形となったので、それはそれで良しとする。それより目下の問題はというと……この完全に勃ち上がってしまった己の欲望だ。
(……挿れたい)
ここは我慢だ。何度も己に言い聞かせ、自我を保つ。あの熱くうねるナカへと一刻も早く突き入れたい、という気持ちは山々だけれど、まだ彼の入り口を解していなかった。国広に与えるダメージのことを考えれば、到底彼に挿れようとは思えない。それに、明日彼は修行に旅立つ。この前と同じ轍を踏むわけにはいかないのだ。
「国広、触ってやるから下着を脱いでくれないか」
その時、国広の身体が大仰に跳ね、ピシリと固まる。
「国広?」
「……」
不思議に思って問えば、気まずそうにそろそろと目線を逸らした彼が、顔を俯けた。そんな不審極まりない彼の様子に、訝しげに目を細めた長義は、じっと彼からもたらされるであろう言葉を待つ。
「……履いていない」
「は?」
長義は胃がひっくり返りそうになった。今こいつは何と言った。下着を履いてないと? ということは、だ。夕餉のあの時から、こいつはずっと下着を履いていなかったということで……あの時も、その時も、全部無防備な状態を周囲に晒していた、と。
「……っお前、なんてことを!」
「は、早く……抱いて欲しくて」
悲鳴に近い声を上げれば、慌てて国広が言い募る。そしてまた、予想を遥か斜めにいく方向から爆弾を投下され、長義は今度こそ胃が完全にひっくり返ったと思った。精神的要因で手入れ部屋行きなんて笑えない。
「もう……、暫くお前に触ってもらえないと思ったら……つい、」
不意に国広が膝立ちになった。長義と真正面から向き合う顔は、林檎や梅なんか目じゃないほどに真っ赤である。一体何を、と突拍子も無い彼の行動に呆気に取られていると、国広は徐に半分脱げかけた着流しを完全に取り去り、生まれたままの姿になった。下半身には己より些か控えめな大きさの彼の分身が、切なげに涙をこぼしながら天を見上げている。正直にいうと、視覚の暴力以外の何者でもなかった。
「……ほ、解してきた」
「えっ」
耳を疑った。間の抜けた声が出て、されどそんなことを気にする余裕もなく、国広の顔を凝視する。
「潤滑油の仕込みまでは流石に……夕餉もあったから。でも、もう解してあるから……っ!」
反射的に国広の手を掴んでいた。無言で戸惑う彼を引っ張り上げ、寝室まで連れて行く。ドンッと乱暴な音を立ててドアを開き、寝室へ雪崩れ込むようにして押し入った長義たちは、灯りもつけずに部屋の奥にある寝台の前まで進むと、そこでようやく立ち止まった。そして、長義が有無を言わさず、投げ飛ばす勢いで国広をシーツの上に転がし、その上から覆い被さる。
「……お前、責任取れよ」
腹の底から這い出たような低い声に、国広の身体がぶるりと震える。
「煽ったのはお前だからね」
「……わかってる」
サイドテーブルから、銚子油の入ったボトルを取り出した。性急な手つきで掌にそれを塗り広げると、人肌ほどの温度になってから、それを四つん這いにさせた国広の蕾へと、丹念に塗りつけていく。国広の言った通り、そこは既に十分解れていて、入り口とナカに潤滑油を塗りつけただけで、長義のものを収めるには十分なくらいに緩まった。
人差し指と中指、それに薬指入れて、三本の指をバラバラに動かす。とろとろに蕩けた内側は熱く、長義の指を拒絶するどころか、さらに奥へ奥へと誘うようにうねり始めて。もどかしそうにきゅうっと締め付けてくる様が、可愛くて可愛くて仕方なかった。食べてしまいたい。骨の髄まで余すことなく、全部。頭から足の先まで、食らってしまいたい。暴力的なまでの衝動に耐えながら、ナカの凝り固まったしこりを探り当て、そこをぐっと強めに押してやる。すると、国広の腰が電流が走ったかの如く、ビクンビクンと跳ね上がった。
「ぁあ! あぅ……っ」
「こら、手を噛むな。傷つくだろ」
咄嗟に声を抑えようと、国広が自身の腕に歯を立てる。それをやんわりと窘めて、長義はさらに前立腺を攻めた。
「ひ、ぅ……っ! あ、ちょうぎ……、も、やぁ……!」
ひっきりなしに嬌声を上げる中で、やだやだと国広が頭を振る。
「何が嫌なんだい? こんなに気持ち良さそうにしてるのに」
「……っちょうぎのがいい!」
意地悪く笑んで問うてやれば、理性が吹っ飛んだ彼は長義を求めた。
(あー……可愛い)
可愛い、可愛い。本当に可愛い。長義の名を呼ばれる度に、首を一周する縁の糸が、甘やかに締め上げてくる。胸の高鳴りが止まらない。心の臓がぎゅうっと収縮して、腹の底から形容し難い感情が溢れてくる。だけど、まだ口には出してやらない。それは彼が、修行から戻ってからだ。彼が俺の写しとして立派になって帰ってきたなら、ご褒美に告げてやるのだ。
――『お前を愛している』と。
「俺の何が欲しいのかな?」
「あ、ん……いえな、」
「言ってみせて。国広、そら、」
ちゅ、ちゅ、と涙を零し続ける瞼に口づけてやって、愛撫しているのとは逆の手で、国広の頭を撫でる。もっと俺を求めろ。脇目も振らず俺だけを見ていろ。刀工国広の最高傑作という部分が、彼を彼たらしめる軸であることは知っている。しかし、どうにかしてこちらに振り向かせたかった。俺がお前の本歌なのだ、と心が叫んでいる。千年近くもの間、ぽっかり空いた心の虚が、己を満たす何かを探して、慟哭を上げている。
そら、俺を求めろ。与えてやるから。俺が欲しいと、縋れ、啼け、叫べ。全部与えてやる。
「ちょ、うぎぃ……いえないっ」
「言って。おねがい」
「あぅ……ぁ、ちょうぎの……」
きゅ、とナカが締まった。興奮しているのか。
「ちょうぎの、まらが……欲しい」
「よくできました」
お前には特別に優を与えてあげよう。
軽く唇を重ね合わせて、長義は指を引き抜いた。ずっと下着の中で窮屈そうにしていた半身を取り出し、下着はそのまま脱ぎ捨てる。着ていたものをすべて、乱雑に床へと投げ捨てれば、ばさりと布擦れの音が響いた。
「はやく、」
ドロドロに涎を滴らせて、ぱくぱくと収縮を繰り返す口元へと先端をあてがう。暫く滑りを良くするために擦り付けていると、嬉々として穴が魔羅に吸い付いてきた。
「……っ」
「そんな顔をするな……」
期待に揺れる瞳を向けられると堪らない。
「いじめたくなるだろ」
「ンアッ! ああ!」
ズズ、と腰を進めた瞬間、掴んでいた内腿がビクビクと痙攣し出した。その反応に、挿れただけで達したのか、と察すれば、驚愕に見開かれた瞳がうろうろと長義を捉える。何をそんなに驚くことがあるのか疑問に思いつつ、彼の半身へ視線を落とし……そこでようやく、長義は国広の驚愕の意味を悟った。
「……空でイッたのか」
国広の半身は射精していなかった。まだ天を仰いだままで、到底白濁が吐き出されたようには見えない。しかし、長義が掴んでいる柔らかな内腿の痙攣と、凄まじいナカの締め付けが、彼が確かに達したということを証明していて。おなごのように空で国広がイッたということに思い至り、長義の興奮は最高潮に達した。
「そんなに俺のが気に入ったのかなっ!」
ばつんっ!
汗で湿った肌がぶつかる音が、断続的に部屋へ響く。恥骨が尻に当たるまで深く貫くと、内側の収縮はさらにキツイものとなった。
「アッ! だめ! 今はダメ……! ちょ、ぅぎ……っ! んぅ、う……っ!」
「はぁ……は、」
何度も、何度も、大きく腰をグラインドさせて最奥を叩けば、あまりの快感に国広が身悶える。眉根を寄せ、固く目を瞑り、ぎゅうっと長義の首へしがみつく写し刀が、愛しくて、愛しくて、頭がどうにかなりそうだと思った。
「くにひろ、そろそろ……っ」
「ん……っ、イッて、長義……ナカ、出して……ぇっ! ひ、あ、ァアッ!」
ガツガツと貪り、国広が幾度目かの絶頂を迎えた頃。同時に長義もまた国広の中で吐精し、凄まじい快感から視界が真っ白に染まる。乱れた息を整えている時、ふ、と目に入ったのは、左手の薬指から伸びる縁の糸で。江雪と話した時よりも、より太くなっているそれを見て、長義は幸せのあまり微笑んだ。
「なんで、泣いてるんだ……?」
不意に、国広の手が長義の方へ伸びてきて、親指で頬を拭われる。そこで初めて、己が泣いていることに気がついた。
「……なんでだろうね」
いつぞやの国広のようにはぐらかしてやると、その意図に気づいたのか。む、と唇を突き出し、国広が顔を顰める。その幼げな唇へ口づけて、続けて真白のまろい頬へ、瞼へ、額へ、余すことなく唇で辿りながら、気持ちが満たされていくのを感じていた。
「……早く帰ってこい。国広」
「……ん、」
「偽物くんがいなきゃ、張り合いがないだろ」
「写しは偽物とは違う。……ふ、素直じゃないな、お前は」
「お前は本当に可愛くない写しだ」
嘘だ。可愛いよ。こんなに腹が立つほど可愛くて、綺麗で、とびきり俺好みの刀なんて見たことない。何百年の時の流れを見てきたら、俺がとびきり甘やかしてあげるから。だから早く、早く、立派になって帰っておいで。
お前はいつまでも、何があっても、この俺の自慢の写し刀で……、
――唯一無二の想い刀だ。
*
まだ日の出る前の、夜明け時。
旅装束の留紐を結んで、被り笠を身につける。長年連れ添ってきた襤褸布は、散々迷った挙句旅装束の下に纏った。流石に脱いではどうかと兄弟からは言われたが、仕方ない。これは俺の分身のようなものなのだから。この布無くして、俺は俺では在りえない。
見送りは事前に伝えていた刀たちと、主である審神者だけだった。堀川と山伏に連れられてゲートとなる鳥居へ向かえば、既に三日月と長谷部、審神者が待っていて。そこに彼の姿は無い。昨晩見送りには行かないと言われたので、わかってはいたのだが……。やはり少しだけ寂しく思った。
(思えば、あれからもう半年か)
すべての始まりの時を、思い出す。
逢魔が時。茜色に染まる世界の真ん中で、頭まですっぽり白布を被った男は立っていた。あの鳥居の柱のところだ。忘れることはない。庭先の紅葉が丁度見頃で、朱と金の絨毯が敷き詰められた、賑やかな色彩の秋の景趣。はらはらと落ち葉の舞う中、圧倒的な存在感を放ちながら、冷涼な空気を纏った男は、凛と背筋を伸ばして待っていた。
監査官と名乗る男から突如与えられた、聚楽第特命調査任務。国広の存在を揺るがす大事件へと発展した件の任務は、後の本霊たちの在り方まで変えてしまった。そして、任務が終わって満身創痍で本丸へ帰還すれば、かの本歌がどうしてか顕現されていて……あの時は驚きと動揺で、暫く生きた心地がしなかった。
(懐かしい)
無理矢理抱かれた、あの日。
屈辱と悔しさのあまり、嘗てなく怒り狂ったのを覚えている。同時にあの男のことが恨めしくて、でも恨みきれなくて。複雑な心境を抱きながら、なし崩しに長義との関係が始まった。今思えば、あんな始まりだったのに、何故あの男を好きになったのか。甚だ疑問である。まぁ、惚れた方が負けとも言うし、もう後には引き返せないくらいに好きになってしまったのだから、こればかりは諦めるしかないか。こんなことを思っていると長義に知られれば、怒られてしまうかも知れないが。
本霊に会った。話をした。
あの本霊のおかげで、自らの気持ちに気づけた。清らかな神域から帰還して、己の本歌に心を委ねた途端、止めどなく溢れてきた好きの気持ち。温かく優しい感情の泉は、じわじわと巨大な湖を形作って、国広の想いをさらに深く深く水底へと沈めた。溺れるように息をしながら、彼へ本音を吐露した夜。鳩が豆鉄砲を食ったような顔をして、国広の独白を聞いていた長義の姿は、何度思い出しても傑作だ。
(……千年、か)
こんなに穏やかな気持ちで彼に接する日がくるとは、夢にも思っていなかった。きっと、互いに恨み、恨まれ、永遠に変わらぬ関係性に雁字搦めにされながら、苦しむものだとばかり……。
「……すまない、皆」
口を突いて出たのは、この場へ見送りに来てくれた皆への謝罪の言葉。
「一つ、忘れ物をしてしまった。すぐに取ってくる!」
「え、忘れ物? 僕が取ってくるよ、って……あ、兄弟!」
走る、走る。整えた装束が乱れようと気にならない。忘れ物があった。大切な、大切なもの。絶対に忘れてはならないもの。
「山姥切国広だ! 長義はいるか……っ!」
ドンッドンッと乱暴にドアを叩き、部屋の住人の名を呼ぶ。眠っているなら起こすまで。彼に会わなければ意味がない。迷惑だろうがなんだろうが知ったことか。修行に出る前に、どうしても彼に一目会いたかった。
「騒々しい! 何時だと思ってるのかな⁉ 近所迷惑だ!」
思っていたよりも早く、住人はドアから顔を覗かせた。寝起きにしては整っている服と、綺麗にセットされた銀髪。国広が修行に行くと知っていたからこそ、朝早くから起きていてくれたのだと察して、思わず国広は男に抱きつく。軽々と国広の身体を受け止めた男は、はぁ、と小さくため息を吐くと、未だ長義にがっちりとしがみついたままの国広の頭を撫でた。
「……どうかしたかな。もう旅に出る時刻だろう」
「……忘れ物をした」
「はぁ?」
「長義、」
ちゃり、と音を立てて長義の掌に握らせたのは、国広がいつも首から提げていた刀紋だ。堀川国広の打った刀として、山姥切長義の写しである山姥切国広として、己を己足らしめる大切な物。それを、国広は本丸に置いていく想い刀へと手渡した。すると、それを見た長義の顔色が、明らかに変わる。
「お前、これは」
「……俺の心を、お前に預ける」
常に心の臓の近くに在ったそれ。今までの国広の葛藤も、辛酸も、愛も、痛みも、全部を知っている物だ。これを、旅立つ前にどうしても長義に渡しておきたかった。複雑に絡み合っていた、国広の心を綺麗に紐解き、根こそぎ奪い去っていった彼に。
「ここに誓う。俺は、千年経とうとこの気持ちは変わらないと。そして、お前が誇る写し刀として、立派になって帰ってくると」
身体を離し、凛と背筋を伸ばす。千年近くの時を超えて再会した、あの日の彼のように。
「……行ってくる」
秘めやかに笑み、長義へ言う。
どちらからともなく近づいて、一度だけ口吸いをした。戯れに指を絡め合ってから、名残惜し気に解く。踵を返して歩き出す。後ろは振り返らなかった。もし、この背を彼が見送ってくれているのならば、情けない姿は見せたくなかったから。
「あ、兄弟! 忘れ物は大丈夫だった?」
ゲートの前へ行けば、堀川が慌てて駆け寄ってくる。
「すまん、待たせた。もう大丈夫だ」
前にお前は俺に、何もわかっちゃいないと言った。あぁ、そうさ。俺は何もわかっていない。だって、今まで現実から目を逸らすばかりで、知ろうともしてこなかったのだ。だから、旅に出る。お前を理解し、俺を理解するために。山を越え、谷を越え、麓を流れる川で夜を明かし、人の子たちの伝承を一つ一つ拾い集めて……それはきっと、途方もない時間が掛かるだろう。真実を知り、傷つくこともあるのだろう。だが、それらと全部向き合って、そして、大きく成長して戻ることが出来たなら、その時は。
「国広、達者でな」
「主のためにも研鑽に励めよ。近侍はこの俺が任された」
「はっはっは、野垂れ死んでくれるなよ」
「兄弟、修行に励むのである! 迷ったらいつでも拙僧に助言を求めよ」
「兄弟、気をつけて行ってくるんだよ」
「あぁ……」
では、行ってくる。遠くへ。
――未来永劫、俺は山姥切長義を愛していると、胸を張って伝えたい。