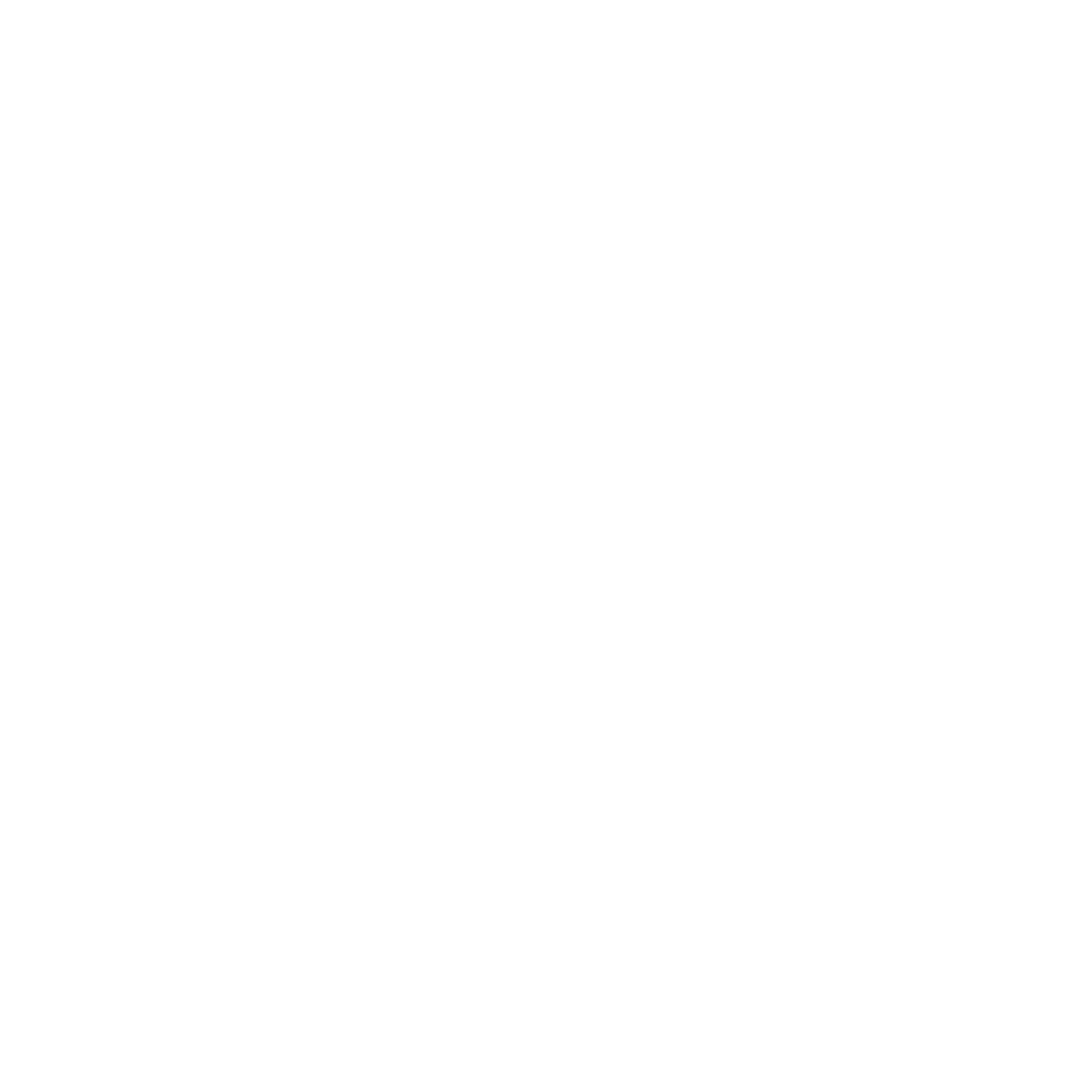後日談 数万分の一の物語
天を飛び回る鷹が鳴いた。
今日も空は蒼い。雲一つない晴れ空は、今日という日の訪れを祝福しているかのようで、長義は今なら億劫な馬当番も、鼻歌交じりに終わらせられるような気がした。
本丸内の空気はどこか落ち着かない。皆そわそわと何かを気にしている素振りを見せ、出陣に出る予定の刀たちも、頻りに戦装束を確認したり、時間を気にしたりといつもより忙しない。それもそのはずだ。何故なら今日は、彼が帰ってくる日。この本丸を初期から支え、審神者から絶対的な信頼を置かれているあの刀が、数百年に渡る修行を終え、本丸に帰還する日なのだから。
――カンッカンッ!
その時、本丸中に帰還を告げる鐘の音が響いた。すると、それまで作業をしていたありとあらゆる刀たちが一斉に手を止め、同じ方向へ走り出す。一番乗りはやはり、彼に懐いていたすばしっこい短刀たちだった。その後を脇差、打刀たちが続き、太刀や大太刀の一部がバタバタと駆けていく。一方で、源氏兄弟や三日月といった、普段からマイペースな刀たちは、その後をのんびりと歩いていて。その中に長義も混ざり、努めて平静を保ったまま、悠々とゲートの方へ向かった。
(ようやくか)
帰ってきた。あの子が。俺に心を預けていった、俺の特別で可愛い写し刀が。
「お帰りなさい! 隊長!」
「国広さーん!」
長義たちがゲートに到着すると同時に、わぁっと周りを取り囲んでいた刀たちが湧いた。馴染みの打刀たちの頭上から覗く、ひょこりと跳ねた金色のアホ毛は、紛れもなくあの刀のものだ。早く顔を見たいと思う気持ちを封殺して、長義は一歩離れた場所から様子を見守る。「何で何も言わずに行ったんだ!」とか「修行はどうだった?」などという興奮しきった皆からの絡みに、堂々と応対してみせる姿は、うじうじと卑屈の殻に閉じ籠り、世辞にも愛想がいいとは言えなかった以前のあれを思うと、確かに立派に成長していた。
(あれが極か……)
これでは長義の出る幕はないな、と苦笑しつつ。ぼそり、と小さく迎えの言葉を呟く。
「……おかえり」
だがその瞬間、タイミングを見計ったかの如く、男がこちらを向いた。
軽く見開かれた翡翠が燦然と輝き、額に巻かれた朱色の鉢巻が風にたなびく。途端に緩められた表情を遮る襤褸布は無く、見る者を魅了する美しい微笑みが、無防備に日の下に晒された。それを目の当たりにした刀たちは、ほうっとため息を吐き、次いで彼の視線の先に立つ長義へと視線を移す。
「ちょう……山姥切」
国広が長義の名を呼んだ途端、周囲の空気に緊張が走る。
周りの目があるところで、二振りは積極的に言葉を交わしてはこなかった。関係を悟らせぬよう、会う時は夜だけと決めていて、昼に顔を合わせても素知らぬふりをして……。加えて、長義の国広に対する冷たい態度のこともあり、周りから二振りは仲が悪いと思われていた。それほど、二振りの態度は徹底していたのだ。よって、そういった事情もあって、長義が国広に対して何と返すのか、皆固唾を飲んで見守っているというわけである。
「へぇ、あの襤褸布は卒業したのか。ちょっとはマシな身なりになったじゃないか」
は、と鼻で笑いながら、長義が言う。
「完全に手放したわけではないがな。でも、お前にそう言ってもらえるのは嬉しい」
「……白々しいことで」
遠回しな嫌味にも動じず、笑みを浮かべたままの国広は、文句無しに綺麗だ。
(可愛げがなくなったな。まぁ、でもあれもなかなか)
手なづけ甲斐がある。未だ長義と国広の様子を、恐る恐る伺っている刀たちに背を向け、長義は歩き出す。どうせ夜には会うことになるのだ。ここで下手に関わって、関係を悟らせるわけにはいかなかった。何より、あれは嘘が吐けない。今だって、あんなにも好意があからさまな笑顔を晒して……バレたらどうしてくれる。
(後で仕置きだな)
とにかく、無事な姿が見れただけで安心した。チャリ、とポケットの中にある国広の刀紋を、指先で弄ぶ。一番最初の出迎えは、古参の連中に譲ってやったが、それ以外の時間に関してはそうはいかない。今夜執り行われる手筈となっている酒宴の後、国広を自分の部屋へ誘おうと心に決めて、長義は馬小屋へと向かった。尚、その日の馬当番はいつもより一時間ほど早く終わったというのは、完全な余談である。
「こっちの酒無くなっちまったよ!」
「おう、こっちはまだあるぜー」
わいわい、がやがや。
国広の修行帰還を祝う宴は、案の定無礼講のどんちゃん騒ぎとなった。大広間のあちこちに空になった酒瓶が転がり、やれ呑み足りないだの野球拳をしようだなどと、部屋の一角は大騒ぎになっている。短刀たちも見た目はあれだが、中身はかなりの年寄りばかりということで、皆それぞれ呑んで食べてと騒がしくしていた。そんな中、主役の国広はというと、兄弟刀たちと共にちびちびと酒を呑みながら、親しげに何かを話し込んでいて。お陰でなかなか長義が話し掛けに行くタイミングが訪れず、先ほどからずっとやきもきさせられていた。
酒の席ではまず本歌に酌をしに来いと、あれほど言って聞かせたというのに。そんなところはまるで成長していないらしい写し刀に、長義の機嫌は急降下していく。
「すげぇ顔……にゃ」
「うるさいよ、猫殺しくん」
右手に持った猪口に並々注がれた酒を、一息に煽る。ピッチが早いことは重々自覚しているが、呑まなければやってられなかった。何が嬉しくて、結ばれるとわかりきっている想い刀を前に、生殺しを食らわなければならないんだ。今までが今までなので、今夜はとびっきり甘やかしてやろうと思ったのに。あの兄弟刀たちが邪魔でなかなか割り込めない。
「許してやれよ。久しぶりの本丸なんだから、そりゃ家族水入らずってやつの方を優先すんだろ、にゃ」
「本歌より兄弟刀の方が大事だと……?」
「お前……その無駄にある自信の根拠はなんなんだよ……にゃ」
モヤモヤとしたものを内に抱きながら、ひたすらに酒を煽る。一杯、二杯、三杯……もう何杯目か数えるのも億劫になった頃。そっと隣に誰かが座る気配がして、長義はそちらを振り向いた。
「……遅い」
ギロリと気配の主を睨み付けると、男は申し訳なさそうに眉を下げ、言う。
「すまない……兄弟たちと話し込んでしまって……」
ん、と差し出されたのは酒の入った徳利だった。酌をさせろ、ということらしい。無言で猪口を前に出すと、その中にとぷとぷと酒を注がれる。ゆらゆらと揺れる水面と眺めているうちに、ぐらりと景色が傾く。そこでようやく、己が大分酔っていることを自覚した。
「……それで、今更何の用かな」
鈍った頭で、思いついたことをそのまま口から吐き出す。久方ぶりの会話なのに、嫌味っぽい言い方になってしまったのは、少しくらい不貞腐れても許してくれるだろう、という甘えからだった。宴はもう終盤に差し掛かっている。野球拳を始めた連中は、もう脱ぐものがないくらいに服を脱ぎ散らかしていた(千子村正は、勝ち負け関係なく服を脱いでいたが)。粟田口の刀たちはとっくに自室に戻っており、保護者の一期一振共々会場から姿を消している。
こんなに放置されたのだ。せいぜい困りきって無様な姿を晒してしまえ。この澄ました顔を歪めてやりたい、という気持ちが、酒で理性を溶かされたことによって、歯止めが効かないくらいに大きくなっていた。
「あ……皆も大分酒が回ってきて、誰も俺たちのことなど気にしてる奴はいないだろ……?」
長義の不機嫌を察した国広が、うろうろと視線を彷徨わせながら、話し出す。彼を囲んでいた兄弟刀たちの姿は近くにない。堀川は新撰組の刀たちと飲み直しているし、山伏は青江派や三条派の霊刀たちと何やら盛り上がっている。そういえば、と右隣を見やって、南泉もいつの間にか鯰尾や物吉といった、馴染みの面々のところへ移動していたことに気づいた。
酒に酔うとここまで気配に鈍感になれるとは。新たな発見である。
「ん、主は」
「長谷部と執務室へ戻った。まだ仕事が残っているらしい」
長義たちの周りには誰もいない。少し声を潜めれば、誰の耳にもその声は聞こえやしないだろう。この時、酒の後押しもあって、長義の気は大きくなっていた。
「ふぅん。それで、偽物くんはこの本歌にただ酌をしに来ただけなのかな?」
本当は、長義の方から誘おうと思っていた。しかし彼が帰ってきてからと言うもの、ひっきりなしに誰かしらが彼の周りにいて。国広には自分以外にも頼るものや、気を許しているものがいると、そう思えば思うほどにどす黒いものが腹の底で渦巻いた。まるで振り出しに戻ってしまったみたいに、素直になれなくなっていく。久しぶりに会うのにこんなことでは興ざめだとわかってはいても、どうにも嫌味を吐いてしまう口を、閉じることが出来なかった。
「偽物くんは俺よりも大事な刀がいるんだろう? そっちへ酌しに回ってやったらどうかな?」
「確かに皆大切な仲間たちだが……お前は別だろう……」
きゅ、と。袖を掴まれる。彼からの久しぶりの接触に、気持ちがふわふわした。地に足が着いてないような、不安定な感情。怒涛の勢いで流れ込んでくる愛しさだとか、憎らしさだとかが、それまで燻らせていた苛立ちをすべて洗い流してしまう。
「……今夜、部屋に行っても?」
耳元へ唇を寄せられ、囁かれる。
「……兄弟たちは」
「あれだけ酔ってるんだ。どうせ俺が朝帰りしたところで気づかない。なぁ、久しぶりに……その、ダメか……?」
袖を握るばかりで、手に触れてこようとしないのが、この刀のいじましいところだった。
変わってしまったものは沢山ある。あの襤褸布で自らを隠そうとしなくなり、口を開くと以前の彼からは考えられないような、自信に満ちた言葉を吐くようになった。だが、変わっていない部分も、当然のことながらあるわけで……。その一つ一つをこうして目の当たりにする度に、長義は堪らない気持ちにさせられた。
「……まずは俺がここを出る。お前も機を見て抜けてこい。そのまま風呂へ行こう。……身を清めてから、俺の部屋に行くぞ」
「……っあぁ」
言うが早いか、長義はすくり、と立ち上がる。見下ろした先の己を見る翡翠には、隠しきれぬ熱が籠められていた。目が合ったその瞬間、酒で火照った身体がさらに燃え上がる。抱きたい。ぐちゃぐちゃに溶かしてやりたい。その澄ました顔を快楽で歪めたい。次々と首を擡げる欲は膨らんでいく一方で、それらのすべてを断ち切るよう、長義は未だ己を見つめる国広に背中を向けた。
(我ながら何と余裕のない……)
乱暴な手つきで襖を開けて廊下に出れば、外の澄んだ空気が肺に流れ込んでくる。桜は散り、新緑が目立ち始めたこの頃。夜の庭からは虫の音が聞こえてきて、断続的に鳴り響く穏やかな歌声に、次第に昂ぶった心は凪いでいった。
ひたひたと、廊下を歩く。部屋に辿り着き、早急な手つきで下着やらタオルやらを風呂敷に詰め込むと、長義はすぐに湯殿へ向かった。彼が上手く抜け出しているなら、そろそろ到着している頃だろう。湯殿は長義の部屋のある東の離れよりも、堀川部屋のある西の離れからの方が近い。
(やっと話せる)
この時間だ。もし湯殿に国広と長義だけしかいなかったのなら、ゆっくりと湯船に肩まで浸かりながら、彼の旅の話でも聞いてやろう。冷静さを取り戻した頭で、そんなことを考えていれば、自ずと歩く速度は速くなった。
「……長義、」
ガララ、とドアを開けて湯殿へ入ると、そこには予想通り国広が待っていた。
「皆は?」
「酒で潰れている。風呂には俺たち以外は誰も……あいつらは、今晩はそのまま大広間に泊まると言って、……っん、」
「……はぁ、」
ちゅう、ちゅ……。
耐えに耐えていたものが限界に達する。誰もいないという言葉を聞くや否や、長義は国広を引き寄せて唇を奪った。何度も角度を変え、貪るような深い口吸いを仕掛けて、国広の舌を絡め取る。歯の裏側を舌でなぞり、上顎を舐め上げると、それだけで久しぶりの快感を得た身体は容易く根を上げた。
「あ……っ、長義、まっ」
「待たない」
国広の口端から、受け止めきれなかった唾液が伝う。てらてらと濡れた唇が、息をしようと薄く開かれ、その隙間から熱い吐息が漏れた。顔を真っ赤にして恥じらう様が、修行に出る前の彼の姿と被る。彼が修行に出ている間、長義のいた本丸に流れていた時間はたったの四日。されど、数千年は待たされたような心地だった。
「国広、」
すぐ手の届く場所に、彼がいる。俺に心を預けたまま、数百年の旅路に出てしまった想い刀が。やっと、ようやく俺の手の中に帰ってきた。
「……おかえり」
ぎゅうっと抱き締め、まろい頬へ口づけを落とす。腕の中の身体が、ひくりと身動ぎした。
「……ただいま」
そっと控え目に腕を回されて、二振りは抱き合った。幸せだ。天にも昇りそうなほどに、今が幸せだと思った。
それから服を脱いで風呂へと入った長義たちは、国広の修行中に起きた出来事の話や、長義が本丸でどう過ごしていたかといった話をして、互いに背中を流し合った。時折悪戯心が湧いて国広の感じる場所を擽ってやると、彼はあっという間にぐずぐずに溶けてしまって。涙目で「やめてくれ」なんて乞われた時は、このまま襲いかかってやりたい煩悩と理性の間で、それはもう醜い死闘を繰り広げた。
互いに隅々まで身体を清め終わった後、屋外に設置された露天風呂へと、国広の手を取り歩き出す。ざぶんっと音を立てて柚子の浮かんだ湯船に浸かれば、ふわりと柚子の香りが鼻腔に広がり、湯気が立ち昇った。
「満月か」
ぼんやりと空を見上げて、言う。視界を遮る雲一つない、宝石箱をひっくり返したような星空。周りを煌びやかな星々に囲まれる中で、黄金色に輝く満ちた月が堂々と鎮座している。
「……綺麗な景色を見る度に、お前と見たならもっと美しく思えるだろうに、と思った」
疲れた身体に、本丸の風呂はさぞ染み入るのだろう。何処か気の抜けた声で、国広が語り出した。
「隣に長義がいないことが寂しくて……足利でお前の本霊を見た時は嬉しかったが、すぐにあれは違うと思ってしまって……」
「俺も寂しかったよ」
ハッとした顔で、国広が長義を見る。
その驚愕しきった表情に苦笑を漏らして、長義は続けた。
「夜に眠っていると、酷く寒くなって目が覚めた。お前が隣にいないからだと知ったのは、お前が修行に出たその日の夜だ」
ふ、とした瞬間に、本丸で国広の姿を探してしまう。国広のいない己の部屋が、酷く閑散としているように見えて、彼に預けられた刀紋を眺めては、落ち着かない気持ちを宥めていた。ある日には気を紛らわせるために戦場へ赴いて、却って昂ぶってしまった身体を、一人で慰めた。その時想像したのは、あられもない姿で喘ぐ国広の痴態だった。
虚しくて、寂しくて、どうにかなるかと思った。
「笑うか?」
「まさか。でも、そうか。お互い同じだったのか……俺はてっきり、お前は何ら変わらず待っていたのかと……」
嬉しいものだな。
そう呟いて、微かに笑った国広のこめかみを、雫が伝う。今まで何度も暴いた真白の肌は、湯に浸かっているせいか赤く上気していて、やけに美味しそうに映った。そっと首筋へ顔を近づけ、今にも流れ落ちそうになっていた水滴を舐めとる。汗の味がしたそれは、されど舌先を甘く痺れさせ、長義の興奮を煽った。
「な、なんだ急に」
大仰に肩を跳ねさせて仰け反った国広が、また悪戯を仕掛けようとしていた長義の口を押さえる。
「そろそろ限界だ。触れさせろ」
「な、おま……いっ!」
べろり。
ぎゅうぎゅうと押し付けられた掌を舐め、それに驚いた国広が手を離した隙に、衝動的に彼の肩へ噛みついた。かなり強い力で噛んだため、吸い付くような柔肌には薄っすらと血が滲んでしまっている。まるで獣のマーキングだ。これは俺のだと頻りに主張する痕が、この醜い独占欲と支配欲を満たしてくれる。このまま完全に己だけのモノに出来たなら。そんなことを考えては、独り善がりな本能に理性が削られていった。
「……ふ、」
くっきりと歯形の残った噛み痕を、丹念に舐め上げつつ、さらに国広の身体をまさぐっていく。脇腹を撫で、尻たぶを揉み、すっかり閉じてしまった尻穴を戯れにノックした。目の前では、声を抑えようと自分の腕を噛む想い刀が、物欲しげに自分を見ている。なけなしの理性なんてものは早々に匙を投げた。ありとあらゆるストッパーは見事に弾け飛び、長義の手つきは次第に大胆なものになってゆく。
「おい、そこは……っ」
「ここ、俺がいない間に使った?」
「ぅ……そんなわけないだろ!」
はー、可愛い。色々と限界になってきて、長義は国広の肩に軽く凭れ掛かる。一方、好き勝手されるがままだった国広はというと、己の肩に乗った銀色の頭を撫でながら、拗ねたように唇を尖らせてぼやいた。
「……痛かったんだが」
「だろうね。あー、血の味がする……」
「お前は吸血鬼か何かか」
酒と興奮のせいで、頭がぼうっとしてうまく働かない。思うがままにかぷかぷと甘噛みし、舌先で歯形をなぞり、また甘噛みをする、ということを繰り返していると、頭上からクスクスと笑い声が降ってきた。何となくそれが気に入らなかった長義は、不満気に眉根を潜めて顔を上げる。
「お前に甘えられるのは擽ったいな」
「俺が写しに甘えるわけがないだろ」
「お前がやってるのはそういうことだ。少し猟奇的だがな」
「うるさいな。減らず口を叩くのはここかな?」
軽口を叩き合いながら、口吸いをする。徐々に深まっていくそれは互いの息を奪い、酸素の回らなくなった頭は行為をエスカレートさせた。このままでは逆上せてしまうな。そう思い至り、流石に暑くなってきたので湯から上がる。そして、湯船の縁に腰掛けた長義は、くたりと力の抜けた国広の身体を持ち上げ、己の膝の上に座らせた。
ぴったりと肌を重ね合わせて、ぎゅっと腕の中に閉じ込める。細い腰は変わらず抱き心地が良く、腿の上に置かれた柔らかな尻の感触が、己の下半身事情に直撃した。そんな中、修行前と比べると厚みの増した胸板が眼前に迫れば、悪戯心の一つや二つ湧いてくるというもので。弾力のあるそれに手を伸ばすと、すかさずやわやわと揉み込んだ。
「ん……っ」
時折胸の飾りを引っ掛け、抓る。時間を置いてしまったため、感度が低くなっているかもという懸念は、あっさり覆された。
「なに、感じてるの?」
「……、ちがっ」
「へぇ……?」
否定するなら、認めさせるまで。ぷっくりと膨らんだそこに触れるのを止め、焦らすようにその周りを撫でるだけにとどめる。すると、国広がもどかしげに腰を揺すりながら、自らの胸を長義の掌に押し付けてきて。期待に濡れた瞳を向けられてようやく、褒美とばかりに強く抓ってやった。
「ンンッ……!」
ビクッと大きく身体が跳ね、国広が長義の頭を抱え込む。突如としてやってきた快感を逃すためか。長義の頭上からは、ふー、ふー、という深く息を吐き出す音が聞こえていて、それを聞いているだけでズクズクと下半身が疼いた。本音を言えば今すぐにでも挿れたい。あの熱くうねるナカを思い切り突き上げ、とろとろに蕩けたそこを掻き回したい。だが、今はその時ではないということだけは、理性の飛んだ頭でも理解していた。国広としては修行の疲れもあるし、既に満身創痍だろう。本来なら、ここで行為を切り上げるべきなのかも知れない。
だが……、
「……悪いが、もう少しだけ付き合え」
「……ぅん、」
このままでは互いに苦しいし、何より痛いくらいに昂ぶった半身を鎮めぬことには、外に出られない。
目の前で上下する国広の胸の頂きを、ぱくっと唇で咥え込み歯を立てた。その瞬間、また艶やかな嬌声が耳元で上がって、すりすりと甘えるように旋毛へ額を擦り付けられる。まるで修行前の彼そのものだ。感じる場所も、反応も、最中の甘え方に至るまでまったく同じ。あれから数百年経ったとは思えぬその感じ方に、長義はとある一つの結論へと辿り着いた。
「お前、一人の時にもここを弄ってたのか?」
「なっ……! そんなわけ、」
ぴんっと頂を弾くと、ヒゥ、という甘い声が漏れる。その直後、耳まで真っ赤に熟れた顔を晒した国広は、居た堪れないと言わんばかりに俯き、長義の方に倒れ込んできた。そして、「長義を想ってシた」とくぐもった声で言われてしまえば、長義の下半身とて無事では済まず……。
というか、まずい。少しだけ漏れた。
「ァアッ⁉」
ブチッと何かが切れる音がした。
猛ったそれを国広のものと重ね合わせ、両手で二本同時に扱き始める。これは長丁場になればなるほど自分が不利になる。そう悟り、一刻も早く決着をつけるべく行為を急いた。写しに負けるなんて、折れても御免だ。これはさっさと白黒つけねば……。
「ァッ……ちょうぎ、それ……ダメ……ッ」
「……っ、何が、ダメなのかな?」
ぐりっと先端を親指で押し、また竿の部分を扱き上げる。
「ひあっ! ぁあ、きもちい……からぁ、」
いやいや、と頭を振る国広の反応は、どこかおぼこくていやらしい。幼気な子どもを弄んでいるような背徳感に見舞われて、不謹慎だが長義の興奮はさらに昂ぶった。あぁ、ナカへ挿れられないのが実に惜しい。もし今挿れることが叶ったなら、この子が気絶するまで貪ってやったというのに。
「……国広、こちらを向け」
「は、……長義、ぃ……んむ、」
「……ん、国広……好きだ」
「……っ!」
好きだ、好き。大好きだ。愛してる。本当は、久しぶりに一つになった時に言おうと思っていた。もっと優しく丁寧に、それこそ焦れるくらいにゆっくりと、彼の身体を解きほぐしてから。だが、耐えきれなかったのだ。だって、身の内から溢れる想いが、こんなにもこの愛らしい写し刀を好きだと叫んでいる。これ以上我慢することなど、もう出来そうにない。
「俺も……、俺もだ、長義……っ、好き、はぁ……すき……!」
そんな長義の叫びに、国広もまた応えた。先走りが剛直を濡らし、ぐちゅぐちゅと下品な水音が響く。限界は近い。互いに堪らず口づけ合って、さらなる愛を求めた。どこまでも貪欲に、真っ直ぐで純粋なその心を。
「もっと言ってくれ……っ」
「ちょう、ぎ……あ、すき、すきっ!」
ぴゅる、と勢い良く白濁が吐き出される。掌の中の欲望たちは小刻みに震え、暫しの間、互いに凭れ掛かりながら絶頂の余韻に浸った。
じんじんと腰から広がり、頭を突き抜けていく快楽の波が思考を奪い去る。頭がふわふわした。酒による酩酊では到底得難い感覚だ。想いを交わした後の行為が、こんなにも気持ちいいことを初めて知った。挿れずにこれなのだ。もし挿入したとすれば、一体どうなってしまうのだろう……ダメだ、考えるな。その期待感だけで再び逸物が首を擡げる気配を感じ取り、咄嗟に雑念を振り払う。ここで本番なんてことになったら、多分一生後悔することになる。それだけは絶対にダメだ。
「……すまん。無理をさせたな。お前は帰ってきたばかりだったのに」
荒い呼吸を繰り返しながら、ぐったりと長義へ身体を預けている国広の頭を、優しく撫でてやる。
「……ん、大丈夫だ……それより、長義に触ってもらえて嬉しかった」
「……お前ね、」
本当、どうしてくれようか。この罪作りな写し刀は。思わず天を仰いで長義は遠い目になった。もしかしたら自分は、とんでもない刀に惚れてしまったのかも知れない。そう密かに長義が頭を抱えていると、何やら国広の掌が、ペタペタと二振りの下腹部を撫で始める。
「……?」
「ふ、……なぁ、見てくれ。俺たちの……混ざってる」
挑発的に笑いながら、目の前に翳されたのは、爪の先まで整った白い掌。その手は先ほど吐き出した白濁に塗れていて、近づけられるとつん、と精の匂いが鼻を突く。まさかの国広の行動と、思わぬところから食らわされた爆撃に、自ずと長義は石のように固まった。
「……お前、わかってやってるだろ」
「バレたか」
「修行に行って、随分と強かになって帰ってきたもんだ」
はぁー、と深くため息を吐く。なんだこの生き物。前より数百倍タチが悪くなって帰ってくるなんて、そんなの聞いてないぞ。極めた個体というのは、もっとふてぶてしくて図太くて、可愛げのない奴だったと記憶しているが。これも惚れた欲目なのかな?
「そんな俺も嫌いじゃないだろ」
「今日は見逃してやるけど……明日は泣かすからな。覚えておけよ」
最後に、ちゅっと唇を重ねて、身体を離す。
まずは身体を洗い直さねば。何となく手離すのが惜しくて、膝の上に乗せたままの国広を横抱きにすれば、女扱いするな! と怒られた。女扱いも何も、この俺がここまで世話を焼いてやってる時点で、恋刀扱い以外の何者でもなかろうに。そういうところが鈍感なままなのだから、やっぱりこの写しは生意気でいけない。
まぁ、そんなところに惚れたのだけれど。
*
しとしとと雨が降っている。
桜は散り、深緑が目立ち始め、夏を思わせる花々の開花の兆しが、あちらこちらに散りばめられている今日この頃。庭先の紫陽花がついに花をつけ、閑散とした景観に涼しげな彩りを添えた。国広が修行から戻ってきてから、早いもので一ヶ月になる。夏を目前に控えてやって来た梅雨入りは三日目を迎え、ここ最近はずっと湿った空気が本丸中に流れていた。
しとしと、ぴちゃぴちゃ。
水溜りに雫が落ち、跳ねる。生い茂る葉を伝い、大地へと還る、循環の輪。
「やぁ、猫殺しくん」
「げっ……また来たのかよ、にゃ」
西の離れの片隅の縁側。中庭が一望出来るその場所は、この猫の呪いを受けた打刀の絶好の昼寝スポットだった。だが、最近は天気も悪く、日によっては些か肌寒い時もあるため、彼が眠っている姿は暫く見ていない。そして、ぼうっと景色を眺めては、気怠げに欠伸を漏らすその刀を揶揄いに行くのが、ここ数日の長義の日課になりつつあった。
「またとは、そんな暇人みたいに。これでも忙しい身でね。時間を見つけてこうやって足を運んでやってるんだよ」
「いや、忙しいならどうぞお気になさらず、お仕事してください……にゃ」
またそんなに可愛げのないことを言って。照れ隠しかな? まぁ、こんなに美しく自他共に認める名刀が隣にいたら、並みの刀では気後れしてしまうだろうが。いや、猫殺しくんが並みの刀とかそういうことではなく、斬ったものの格の差的に……山姥と猫では、ね?
息をするように失礼なことを考えながら、長義は問答無用で南泉の隣に腰掛ける。本当にお前って人の話を聞かねぇよな、だの何だのとぶつぶつ文句を言われたが、そんなものには無視をした。
「んで、何の用だよ。大体予想はついてるけどよ」
嫌そうな顔をした南泉が、渋々話し掛けてくる。
「うん、流石は猫殺しくんだ。飼い主の話はちゃんと覚えているんだね」
「誰が飼い主だ! にゃ!」
「はい、これ今日の分の手土産」
「……チッ!」
下町で五時間は並ばなければ買えない、と言われている評判の店の和菓子を渡すと、忌々しそうにそれをぶんどって、南泉は引き下がった。ちなみにこの店の芋羊羹が国広の気に入りで、南泉の分は国広のための菓子を仕入れるついでに買ったものである。でなければこんなにいいものをこの男にやる筈がない。
「……んで、いつものあれか、にゃ」
「そうなんだ……俺も困っていてね」
「あっそーですか」
バリバリと包装紙を破きながら、南泉が投げやり気味に相槌を打つ。
その開け方はいただけないな。なんて片眉を上げるも、特に口を出すこともなく、長義は目下の問題へと意識を戻した。そう、これはちょっとやそっとの無礼なんか気にもならないほどの、深刻な問題なのだ……。
「国広が最近可愛くて可愛くて仕方ないんだ……」
「……」
ぽたぽた、と雨粒の音が響き、沈黙が降りてくる。
はぁ……と物憂げにため息を吐く男の姿は、もの寂し気な梅雨の景趣も相まって、大層様になっていた。しかし、この男は初めて知った恋に浮かれる、只の《浮かれポンチ》であることを、南泉は知っている。そう簡単には騙されないぞ、と白けた目を向けるも、当の本刃はどこ吹く風。毎度のことで既に諦めていることとはいえ、もう何日と同じやり取りを繰り返していれば、いい加減嫌気が刺してくるというもので……。
しかし、賄賂を受け取ってしまったからには逃げ場もなく。そもそもこの男から逃げるというのも癪に触るという理由から、南泉は毎回いいようにこの男から、相談という名の惚気を聞かされていたのだった。
「今度は何をしたんだあいつ……にゃ」
「いや実はね、昨日の夜にあれを抱いていた時……」
「下の話はやめろって何度も言わすな馬鹿! にゃ!」
ぶっと口の中に入っていた和菓子を噴き出した南泉に、思わず長義が眉根を寄せる。「汚いなぁ」と長義が咎めれば、「誰のせいだ!」と南泉が怒鳴り返し、収集がつかなくなった。相変わらずこの野生の猫は、初心でいけない。ごそごそと胸の内ポケットを漁り、ピンとのりの効いたハンカチーフを取り出した長義が、そっとそれを南泉へと渡す。
「そら、これで拭きなよ。あ、返さなくていいからね。汚いし」
「いいぜ、売られた喧嘩は三倍にして買ってやるよ! にゃ!」
表出ろにゃあ! と怒り立った南泉は、まさしく威嚇してフシャーッと毛を逆立てる猫そのものだ。あぁ、はいはい。可愛い可愛い。国広には負けるけど。そんなに威嚇したところで、語尾がそれだと全部無意味だな、なんて内心で小馬鹿にしつつ。長義はマイペースに話を続けた。南泉からしたらたまったものではないが、これが二振りの常通りである。
「それで、話を戻すが……最近の国広のことなのだけどね……」
「ちったぁ人の話を聞け! にゃーっ!」
時は少し巻き戻る。
先日、新たな戦場が開かれた。《青野原の記憶》と呼ばれるその時代は、時間遡行軍の動きが最近活発化していると判断され、開放されて間もない合戦場であった。未踏の地となるその時代へ向かうこととなったのは、未だ弱体化が著しい国広を除く第一部隊の面々と、国広の代わりに部隊入りした長義の計六振り。練度が上限に達したために隠居生活を送っていた長義としては、久しぶりの戦さ場である。部隊入りは素直に喜ばしいことであった。何より刀としての本能が、常に戦場を求めているが故に、血が騒いだのだ。だからこそ、長義は意気揚々と顔合わせを済ませた後、第一部隊の面々と共に、延元三年の阿弥陀ヶ峰へと出陣したのだが……。
「……先に行っておくが、任務は完璧に遂行したよ。俺がいるからね。当たり前の話さ」
「そうだなー」
「ただ……その後のことが、問題だったんだ……」
丁度その頃、修行から帰り一週間の暇を与えられていた国広が、練度上げのために頻繁に出陣するようになった。厚樫山に、夜戦が中心の京の都、途中開放された大阪城……などなど。その場所と時間帯は見事にバラバラで、そうなると必然的に、長義と国広の生活サイクルはすれ違ってしまう。国広が夜戦続きの週なんかは酷いもので、五日連続彼の姿を見ない、なんて日もあった。
「だが、可愛い恋刀がいるのに一人で抜く、なんて虚しいことはしたくないじゃないか。我慢したよ……この二週間ほど」
「……もう俺は何もツッコまねぇぞ、にゃ」
「禁欲って身体に悪いんだね。今回のことで学んだよ。恋刀のいない刀たちには、もう少し優しくしてやろうと思った、かな……」
「マジで腹立つなこいつ」
そしてやっとのことで会う時間が取れたのが、昨日の夜。周りに関係を隠している二振りは、例え非番が被ろうとも日中は共にいられない。夜の僅かな時間だけで、愛を深めるしかなかった。だからこそ、夜の逢瀬は今まで会えなかった分を取り戻すかの如く、濃密な時間となって……昨晩も御察しの通り、お楽しみだったというわけだけれど。長義が頭を抱えている問題というのが、その情事の時の国広についてであった。
「あいつが積極的なんだ。極めてからというもの、本当にお強請り上手になってね……昨日なんて俺の上に乗ったんだよ……。俺の上で、あられもない姿で腰を振って……っ。今までの俺は馬鹿だった。絶対あれに主導権を握らせて堪るかって意地になって、頑なに上に乗せることがなかったからな……」
「ほーぅ。で、感想は?」
「絶景だった。いや、間違えた。最高だった」
「何で言い直したんだよ。どっちでも変わんねぇっての……にゃ」
この猫刀には伝わらないかも知れないが、もう本当に、それはそれは夜の国広は愛らしいのだ。そしてえろい。俗な言い方になってしまったが、とにかく極めてからのあれは本当にえろくなった。まず積極的になった。あの潤んだ翡翠に見つめられながら強請られると、何だって与えてやりたくなる。元来より付喪神としての性質に強く影響を受けているからか、与えたがりの性分である長義だけれど、国広へのそれは明らかに他のものたちへのそれと、一線を画していた。
次に、夜伽が上手くなった。これは長義の教育の賜物である。長義が感じるところを的確に攻め、尚且つ自らも快感を得ようと腰を振る様は、傾国の美女も裸足で逃げ出す妖艶さだ。あれに勝てる生き物はいるのか? いや、いない。この世もあの世も何処を探したって、あれほど完璧で美しく、俺好みの子なんているわけがない。
「はぁ……あれが俺の恋刀なんだぞ。どうだ、羨ましいだろ?」
「あー、はいはい。羨ましいにゃあ……」
「は? 何だ、まさか国広に気があるんじゃなかろうね?」
「なぁ、お前わざとやってんの? え、いや……本気なのか? にゃ……」
マジでドン引きだわ……。
なんて呟いた南泉の声は、一人ヒートアップしていく長義には聞こえていない。というより、聞く気がなかった。あくまで長義はこの溜まりに溜まった想いの捌け口として、止むを得ず一番口が固そうで話しやすい南泉に話をしているのであって、そこに対話など求めていない。寧ろ国広の良さを共感されたらキレる自信がある。南泉からしたら、とばっちりもいいところの超理論だった。
「お前、そんだけ溜め込んでんなら、もうオープンにしちまえば? そうすりゃ堂々と、国広のことを俺のものだって言えんだろ。なんでわざわざ関係を隠すのか、俺にはさっぱり理解出来ねぇな……にゃ」
「君はわかっていないな。あれだけ美しくて出来た写し刀が、実は心も身体も俺のものなんだと、あれに絆された刀たちを見ながら優越感に浸るのが、また一興なんじゃないか」
「お前の潔いくらいの性格の悪さは、一周回って尊敬するわ。いや、やっぱ天地がひっくり返っても尊敬出来ねぇわ、にゃ」
猫殺しくんに尊敬されても、ねぇ……?
と微妙な顔をすれば、こめかみに青筋を立てた南泉に睨みつけられる。しかし、ふ、と何かを思い出したような顔をした彼は、途端にニヤァ……と意地の悪い笑みを浮かべて、訝しげにその様子を見ていた長義へ耳打ちをしてきた。
「そんだけ魅力的な写し刀だ。あんまり余裕ぶっこいてっと、他の刀にペロッと頂かれちまうかもしんねぇぞ?」
突拍子も無い脅し文句に、長義はハンッと鼻で笑い飛ばしてみせる。
「あれが俺以外に? ありえないな。俺以上に器量のある刀などいるはずがない。いくらこの本丸に集う刀たちが名の知れた名剣名刀でもね」
「どうだかなぁ。とりあえず古参の連中には気をつけろよ。あいつら、国広がすっげぇ懐いてるからよ」
「へぇ?」
古参の刀たちが国広と仲が良いのは知っている。しかし、それはあくまで仲間としての範疇内だ。惚れた腫れただのとそんな関係に発展する気配は皆無である。確かに、彼らに対して国広は随分と気を許しているように見えるが、それにいちいち嫉妬するような狭量な器でもなし。何を今更、と内心ほくそ笑む。それに、あれが俺に心底惚れ込んでいるのだ。余所見をする暇などあるわけがなかろうに。
「特に歌仙なんかは、昔国広と同室だったらしいからな〜」
「……なに?」
だが、南泉がそう言い放った瞬間、二人を取り巻く空気が凍った。
同室……? 堀川部屋が良いと、頑なに長義の誘いを断ったあの国広が? あぁ、思い出しただけではらわたが煮えくり返ってくる。一体いつの頃の話なのかは知らないが、この本歌を差し置いて写しと同室だなどと、そんな話を聞かされては流石に冷静でいられない。
「堀川派がまだあいつしかいなかった頃の話だとよ。ま、だからそうやって現状に胡座をかいてちゃあ、掻っ攫われちまうかもって話よ……色々と噂もあったみたいだし? ……にゃ」
「おい、それはどういう……っ」
――ヴーッ! カンッカンッカンッカンッ!
意味深な言葉を発しておきながら、そのまま立ち去ろうとした南泉を呼び止めた、その時。けたたましいサイレン音が、本丸中に鳴り響いた。
「この音……、重傷帰還か!」
「今出陣に出ているのは、遠征部隊と……国広のいる第二部隊だ……っ」
そんな、まさか。最悪の予想が胸を過ぎる。確か、今日国広が出陣したのは厚樫山だ。あそこは検非違使も出る要注意の戦場。メンバーはほぼ練度が上限に達したものたちばかりで、あの中では国広の練度が一番低かった。もし検非違使が出現したのだとしたら、一番重傷になる確率の高い者は……。
「何ぼけっとしてんだ、行くぞ山姥切!」
ぐらぐらと肩を揺さぶられ、ハッと我に返る。
「……っ言われなくとも!」
長義と南泉がゲートに到着した頃には、既に審神者と複数の刀たちが担架を用意して待っていた。その中には医術に長けた薬研の姿もある。ゲートの周りに立つ者たちは、皆険しい表情をしていて、それだけで今から帰還する部隊が、どれだけ危険な状態なのかが伺い知れた。もし、国広が折れてしまったら、なんて縁起でもないことを考えては、ドクドクと心臓が嫌な音を立てる。いつも彼を想う時の胸の高鳴りとは違う、忌々しい響き。元の白い顔をさらに真っ青にして、その場で待機していると、やがて鳥居の下にある空間が歪み、第二部隊の面々が姿を現した。
「……っ」
むわり。血の匂いが辺りに漂う。戦の匂いだ。焼けた肉と硝煙の入り混じった、澱みきった不穏な匂い。
「みっちゃん!」
耐えきれんとばかりに、門の前に立っていた太鼓鐘が、見るからに満身創痍な状態の燭台切へ駆け寄る。
「検非違使が出てね……。すまない、無様なところを見せてしまった……僕はいいから、あの子を……」
「主……っ! 国広がやべぇ……! 最優先で手入れ部屋に……!」
「国広……っ」
血塗れでぐったりと燭台切の背に抱えられた国広が、担架の上に乗せられた。だらんと担架の上から垂れ下がった腕に、頭の芯がひやりと冷える。
一瞬だけ目が合った。駆け寄ろうとして、出来なかった。長義を捉えた翡翠は、されどすぐに逸らされてしまって、あたかも長義との無関係を装う写しの態度に、ガツンと頭を殴られたような衝撃を受けたからだ。そこでようやく思い出す。自分たちの立場を。長義と国広は、皆の前では犬猿の仲にも等しい、本歌と写しというだけの間柄でしかないという事実を。
「歌仙くん、薬研くん。後は頼んだよ……」
雨に濡れ、頭から流れ落ちてくる血を拭いながら、燭台切が担架を持つ歌仙たちへ言う。
「あぁ、任せてくれ。とはいえ君も酷い怪我だ。もう一台担架を持って来させるから、ちゃんと手入れ部屋に入るように」
「大将の手入れだ。安心しな、燭台切の旦那。……大将、手伝い札は精霊に渡してあるぜ。準備万端だ」
「すまないね。では、行こうか」
国広が、よりにもよってあの男の手で運ばれていく。それを黙って見ていることしか出来ない自分。
改めて自覚した。自分たちの関係の在り方が、どれほど危うい均衡の上に成り立っているのかということを。恋刀の窮地に駆けつけることも出来ない。彼の身に何かあったとして、そのことを一番に伝えられるのは、長義ではなく彼の兄弟刀たちや、彼と親しい古参組。いざという時の長義の優先度は、皆の中ではあまりにも低かった。そのことを、むざむざと思い知らされた。
「おい、大丈夫か。しっかりしろ」
「……猫殺しくんに心配されるまでもないよ」
俺は一体、何をやっているのか。
本当なら、いち早く駆けつけて、あいつを運ぶのも、手入れに立ち会うのも、全部俺が任されるべきだというのに。弱ったあれに気まで使わせて、対面を作ろうことの愚かさよ。惨めで仕方なかった。
「……クソッ」
頬にへばりついた髪を乱雑に掻き上げ、拳を握る。この期に及んで夜に見舞いに行かねばと考えてしまう自分が、何より許せなかった。
*
丑の刻を回った深夜。
静まり返った本丸内を抜け出し、長義は国広のいる医療棟へと向かった。手伝い札を使ったおかげで、彼の手入れは既に終わっている。しかし、かなりの深傷を負っていたということもあって、本来なら自室で療養することになっていた筈の彼は、今は長期治療用の入院室で絶対安静を言い渡されていた。
「国広……俺だ。入るぞ」
どうせ起きてはいないだろうから返事を待つこともなく、部屋へ滑り入る。寝台の上に横たえられた国広は、案の定すやすやと穏やかな寝息を立てており、深く眠っているようだった。また、そのすぐ傍には彼の本体が置かれていて、手入れしたばかりのそれを、長義はそっと持ち上げる。鞘、鍔、柄……見たところ異常はなし。徐に鞘から刀身を抜き出してみれば、鋭い輝きを放つ刃が顔を覗かせる。刀身にもひびや刃こぼれはなし。すべて元通りだ。そこまで確認してから、ようやく長義はひと心地ついた。
「よかった……」
未だ眠り続ける国広の頬を撫でる。本当に良かった。もし、あのまま折れてしまっていたらと思うと、ゾッとしたものが背筋を走る。今彼を失ったら、俺は正真正銘の化け物と成り果ててしまうだろう。世を恨み、彼の死を嘆きながら、怒りに囚われ心を失う。そんな無様を晒すことにならなくて、よかった。
「今更お前を手放すなんて……俺には出来そうにないな」
「ん……、」
さらさらと流れる金糸を指先に絡め、そっと梳いてやる。すると、国広がむずがゆそうに顔を顰めて、布団の中で身動いだ。覚醒の予感から彼に触れていた掌を離し、暫くその様子を見守っていると、ややあって薄目を開けた彼が、うろうろと視線を彷徨せる。やがてゆっくりと焦点を合わせていった翡翠の瞳が、長義の姿を捉えた時。堪らず長義はそれまで引っ込めていた手を、再び彼の方へと伸ばした。
「……ちょう、ぎ?」
掠れた声が、長義の名を呼ぶ。
「あぁ、見舞いに来たぞ」
それに蜂蜜を垂らしたような甘ったるい声で応えて、その柔らかな頬を撫で上げた。気持ちよさそうに目を細め、自らの手に擦り寄ってくる彼が、愛おしい。
「今は何時で……」
「もう丑の刻を回っている。誰もいやしないよ」
「そうか……」
ほっと息を吐く国広を見て、胸が痛む。それほど周りに知られるのが嫌か。今までの自分のことは棚に上げておいて、そう思ってしまう自分に嘲笑が漏れた。なんて都合のいい話だ。彼がこうなるまで、この秘めやかな関係から得られる蜜を、散々啜っていたくせに。今ではこの関係に焦燥すら抱いている。緩やかに崩壊へ近づいているような、そんな恐怖にも似た焦りを。
「……なんて顔をしてるんだ」
そっと前髪を撫でつけられ、ハッとする。そんなに酷い顔をしていたのだろうか。病み上がりなのは国広の方だというのに、余程彼の方が心配そうな顔をしていた。
「どうもしないよ」
「嘘だ。あんたがそんな顔をする時は、決まって何かを隠してる時だ」
「……随分と、わかったような口を利いてくれるじゃないか」
あんたのことだからな、なんてゆるりと微笑む彼が恨めしい。いっそ本当に恨めたらいいのに。惚れた方が負け、なんて言葉はよく言ったものである。確かに今の自分は、到底この美しい男に勝てる気がしなかった。
「……俺たちのこと、皆に正式に公表しないか」
そう言った途端、銀糸を弄んでいた掌の動きが止まる。国広の表情からは、何を考えているのか読み取れなかった。ただただじっと、彼は長義の言葉に耳を傾けている。
「こうしてお前が傷ついている時に、一番に駆けつけてやれないのが……なかなかキツいものがあってね」
そう長義が言うと同時に、きゅ、と桜色の唇が引き結ばれる。大方己の力不足を嘆いているに違いない。血が出るほど噛み締められたそこを指先でなぞると、少しだけ力が緩められた。慰めの言葉をかけることはしなかった。お前のせいじゃないよ、と告げてやるのは簡単だ。だがそれでは、彼のためにならない。本当に彼のことを思うのならば、もう二度とこんなことがないように、早く強くなれと叱咤しなければならないのだ。どれだけ彼から疎まれようと、憎まれようと、彼が危険に陥らないように。時には自らが手ほどきをし、少しでも彼を強くする方を、長義は選ぶ。だから、長義は彼に何も言葉をかけなかった。
――この悔しさをバネに、また力をつけておいで。
そんな気持ちを乗せながら、国広の唇へ口づけを落とす。触れるだけの軽い口づけを。
「俺は、あんたとの関係を公にするつもりは、ない」
だが、離された唇から漏れたのは、期待外れの否定の言葉で。
「……何故」
「とにかく、ダメだ」
「俺が恋刀だと知られるのに、何か不満でも?」
暫しの間、睨み合う。彼がどうしてそこまで頑なになるのか、長義にはわからなかった。せめて理由を教えてくれたら、と思えど、国広は首を横に振るばかりで、一向に答えようとしない。そんな彼に痺れを切らして、威圧的な声で詰めってみようとも、終ぞ彼の口を割ることは叶わなかった。
「恥じているのか、この関係を」
どうして、なぜ。
どんどん考えが悪い方へと向かっていく。不意に、昼に聞いた南泉の言葉を思い出した。歌仙と国広が昔同室だったという、この本丸の過去にまつわる話。それに加えて何やら二振りにまつわる噂があったとも、あの男は言っていた。
もし、嘗て国広と歌仙が想い合っていたとしたら。長義よりも歌仙の方が、特別だと思われていたとしたら。そもそも、国広が長義のことを好いている理由が、本歌と写しという関係故の、ただの擬似的な恋情だとしたら。それが事実だったなら、長義は迷いなくこの刀を折るだろう。次に惨めな己自身を、この場で怒りに任せ叩き折るだろう。例え想像だとしても許し難い……そんな屈辱、認めてなるものか。
長義を取り巻く空気が、みるみるうちに不穏なものになっていく。それを国広とて察しているであろうに、それでも弁明しようとしないことが、また癇に障った。
「そんなわけがないだろう」
「だが、お前が言っているのはそういうことだ!」
バン!
力いっぱい叩いた寝台が、派手な音を立てる。衝撃で国広の身体も軽く跳ね上がり、そこでようやく長義が本気で怒っていることを悟ったのか。慌てて上体を起こした彼が、長義の顔を覗き込んできた。
「違う。俺がお前とのことを恥じるわけがない。お前らしくないぞ。いつものあの自信はどうした?」
「そんなもの、お前を前にすれば一気に失せる」
ごくり、と白い喉が鳴る。構わず長義は国広を睨みつけ、言った。
「何を躊躇うことがある。事実、お前は俺の恋刀じゃないのか……?」
「それは、そうだが……」
はくはくと何か言いたげに開閉した口は、結局また閉ざされる。落胆した。何も言わないということは、それが俺に言えない理由だから。それ以外に何がある?
「あぁ、それとも……俺との仲を、知られたくない誰かでもいるのかな?」
ある日、歌仙の部屋で花を習っていた国広を迎えに行くと、二人で穏やかに笑っている姿を見た。あの頑固で卑屈な刀が、珍しく他刃に心を開いていたものだから、少しだけ驚いたのを覚えている。国広が生けた花を、詠んだ歌を、我が事のように誇らしそうにしながら、長義へと説明するあの男はまるで、国広の身内のようで。お前たちは兄弟刀のようだね、と言えば、二振りは顔を見合わせて苦笑した。
そういえば、こんなこともあった。国広が見覚えのない羽織を手にしていたから、それは何かと長義が問うた。すると、あいつは照れ臭そうな顔をして、こう答えたのだ。「歌仙から貰った」と。国広の髪色に映える、紅葉柄の刺繍が施された白い羽織。それは、彼のことを思って誂えられたことが一目瞭然な代物で。あの時の嬉しそうに羽織を抱えて歩いていた国広の姿を思い出し、形容し難い黒い靄のようなものが、心の奥底で渦巻いていく。
「……っ」
あの頃には何とも思わなかった記憶が、チクチクと心に突き刺さる。割れた心の破片が内側を傷つけ、切り刻み、細切れにしていく。急速に冷えていく思考が苛烈な怒りをも押さえつけて、その代わりに、静かに青い炎が燃え上がったのを感じた。熱い。内側が燃えるように、ありとあらゆる感情が煮えくり立つように。熱い、熱い、熱い。
「長義……?」
「……い、なら、」
「おい、どうしたんだ?」
――奪われるくらいなら、いっそ。
「い……っ! 長義⁉」
ゆらりと顔を上げた長義は、目の前の肢体を押し倒すと、手近に置いてあった青いネクタイで、無抵抗な両手を縛り上げた。そして、国広が咄嗟のことで反応出来ないでいるのをいいことに、すらりと伸びた両足を割り開き、その間に自らの身体を滑り込ませる。流石にまずいと感じたのだろう。途端にジタバタと暴れ出した足は、力任せに無理矢理上から押さえ込んだ。今の国広は極修行の影響で弱体化している。よって、練度が上限に達している長義ならば、彼を力づくで組み伏せることなど実に容易い――。
「何をするつもりだ……、おい、早くこのネクタイを外せ!」
焦った顔で国広が吠えるのを、冷え冷えとした青瑠璃が無機質に見下ろす。
「何だその目は……気に入らないね」
「は、……な、長義、やめろ!」
そんな目で見るな。そんな、化け物を見るような目で。お前は俺の恋刀だろ。だというのに、なんで俺を拒絶する。とにかく彼の一挙一動が癪に触って、今度はいつも彼が身につけているハチマキで、その視界をも奪う。すべての抵抗が敢え無く無効化されてしまった男を、上から下まで舌舐めずりして眺めた。いいザマだ。あれだけ生意気な口を叩いていたのが嘘のように、視界を塞がれた男は大人しく己の下に転がっている。
「いい眺めだな」
「……っ冗談にしてもタチが悪いぞ」
「へぇ、ここまで来てもまだこれが冗談だと?」
「……まさか、」
手入れ後ということで、彼の纏っている衣類は最低限のものだけだった。薄手の紺の着流しを手際よく脱がし、白い肌を露わにする。いつもならこの時点で可愛らしく首を擡げている筈のそこは、まだ兆しておらず。下着の中で縮こまったままだった。
緩やかに盛り上がったそこへそっと手をあてがうと、それだけで掌の中がびくりと反応する。
「う、そだろ……」
「いつもより敏感になってないか?」
「そんなわけ、ん……っ」
つ、と脇腹を撫で上げる。声が漏れた。甘い余韻を残す声が。
「……ほら、やっぱり」
「……ぐ、ぅ」
くにくに、と玉の部分を優しく揉み込む。二つの玉が袋の中でこりこりと動き、もどかしそうに国広が身体を捩った。まだ柔らかい状態の竿を下着越しに扱けば、男の身体は現金なもので、徐々に芯を持ってくる。
「ん……ぁ、あ、」
長義の手の動きに合わせ、国広の腰がビクビクと数度にわたって跳ねる。焦れったい愛撫を始めてから、数分ほど経った頃。はぁ、はぁ、という荒い息が響き始めて、長義はうっそりと微笑んだ。
(残念だったね)
もう抵抗の声はない。あるのは、いつもより鋭敏になった神経が拾い上げる快感を、どうにかしてやり過ごそうとする、哀れな写し刀の喘ぎだけ。多分に吐息を含んだそれは、明らかにいつもより興奮していて、そのことに少しだけ沈みきっていた気分が浮上した。
「ちょ、ぅぎ……これ、解け……っ」
「やだ」
「ア……、はぁ、」
くちゃくちゃと水音が聞こえ出す。先走りが卑猥なシミを作り、窮屈そうに逸物が下着を押し上げた。身体はこんなに正直なのに、素直じゃない上の口が忌々しい。あぁ、可愛くない口を叩くくらいなら、上も塞いでしまおうか。だらしなく開かれた唇の隙間から、ちらちらと覗く赤い舌を見て、ふ、と思い立つ。
「んぅっ……ぁ、うん……っ!」
下を弄る手の動きはそのままに、何の前触れもなく深い口吸いを仕掛けた。不意を突かれた国広は拒む余裕もなくされるがままで、長義が何度も舌を絡め、吸って、甘噛みして、と繰り返していくうちに、やがておずおずと自ら舌を絡めてくるようになった。
愛らしい。
いっそ憎らしいほどに。こちらがいくら愛しても、与えても、まったく気づかない鈍感のくせして、快楽を追う時ばかり潔く手中に落ちてくるとは。これが可愛さ余って憎さ百倍、というやつか。まさか身をもって体感することになるとは思わなかった。
「は……、随分としおらしくなったな」
舌が絡み合う度に、ぴちゃぴちゃと水音が響く。偶に派手な音が鳴ると国広の身体がひくりと震え、手の中の魔羅が脈打った。
「……音にも感じるんだ?」
「それ、は……ぐっ」
「この淫乱」
「ぁうっ……む、」
反論は許さない。そう言わんばかりに、ぐりぐりと先端を親指で押し潰した瞬間、国広の口からくぐもった声が漏れて、長義の口内へと呑み込まれていく。動きがおざなりになった舌を絡め取り、吐息も、声も、唾液も、何もかも全部を喰らい尽くすと、ぽっかり空いた虚が満たされていくような錯覚を覚えた。気分が良かった。とても。この頑なで清廉な気を纏う男を、自分の好きなように乱している。その事実が、長義の中に芽生えた仄暗い支配欲を満たしてくれて、得も言われぬ安心感を抱いた。
「いつもより感じちゃった?」
「は、ぅ……」
「そら、また泣いた」
「ひど……ぃ……っん、」
次から次へと涙を零す魔羅が、新たな快感を求めてふるふると震える。既に彼の下着の中はぐちゃぐちゃだった。最早身に着けている意味を為していない。国広は頻りに限界を訴えていたけれど、尚も長義は仕置きとばかりに、国広の感じる場所ばかりを攻め立てていく。玉袋を優しく揉み込み、欲望の裏筋を撫で上げ、時折気まぐれに亀頭をいじめ倒す。それだけにはとどまらず、先ほどから仄かに存在を主張している胸の飾りも啄んで、快楽を強制的に引き摺り出した。
「長義……、も、やだ……っ」
何が?
なんて惚けてみせて、あやふやにはぐらかす。そんな、と絶望した声で嘆かれるも、そう簡単に言うことを聞いてやるつもりはさらさらなかった。これは仕置きなのだ。ただの情交ではない。この写しには俺しかいないのだと心身共に刷り込むための、謂わば躾。甘やかしてつけ上らせては元も子もない。
「見えない……っ、長義、頼む。外してくれ……これ、外して……!」
勢いよく頭が振られ、ばらばらとシーツの上に金髪が散らばる。
いよいよ形振り構わなくなってきたな。限界が近そうだ。いやに冷静な頭でそんなことを考えつつ、容赦なく胸にじゅっと吸い付いた。口の中でピンとそそり立った乳首を転がすと、一層甲高い嬌声が上がり、ついに手の中の熱が弾ける。
「んぁ……っ!」
「イッちゃったね」
「〰〰っ! ッやめろ……! イッてる! イッてるからぁ! 吸うな、ァア……っ!」
じゅるじゅるっ。
幾度となく跳ね上がる腰を無理矢理押さえつけ、唾液塗れとなった桃色の突起を、さらにキツく吸い上げる。ひゃうっと可愛らしい声を上げ、あっさり二度目の絶頂に達した国広は、過ぎた快感を逃がそうと息絶え絶えになり……頭上で縛られた両腕をバタバタと暴れさせた。
「はずして、ぇ! ああっ!」
みしみしと軋むネクタイは、されど緩まることなく依然として国広の自由を奪い、身の内に熱を燻らせていく。二度達したことで過敏になっているおかげか。今の彼はどこを触っても感じてしまうようで。精液の飛び散った下腹やへそといった際どい部分に指先を這わせれば、それだけで大仰に腰を跳ねさせた。
「はは、そんなに喘いで……まるでおなごのようじゃないか」
「んぅ……っ!」
苦しそうだね。可哀想に。でも、許してなんてやらない。長義はそれまでいじめていた胸から唇を離し、そのまま下へ下へと顔を降下させていく。そして、ぬるついて滑り始めた下着を乱雑に取り去ると、元気良く顔を出した国広のそれを、かぷりと奥まで咥え込んだ。
「いや、ァアアッ!」
ここまでいくと、まるで拷問だな。どうやら自分で思っていたよりも、長義の怒りは根深かったらしい。行き過ぎた快楽に善がり狂う国広を尻目に、長義は己の口で執拗に国広の魔羅を可愛がった。
根元から括れにかけて舐め上げれば、悲鳴に近い声で写しが喘ぐ。数度精を吐き出した鈴口の割れ目を舌先で抉ると、薄くなった精液がまたとぷとぷと溢れ出した。苦い。だがそれ以上に甘い。とめどなく溢れてくる白濁を、ズルズルッとわざと大仰に音を立てて啜ってやる。
「ひ、ッア、それだめ、……!」
ちらりと国広の顔を見れば、目を覆ったハチマキが、涙で濡れていた。だらしなく開いた口からは唾液が溢れ、顔も下半身もぐちゃぐちゃになった様に、いつになく興奮する。何て倒錯的な光景だろう。眼下に広がる絶景を恍惚と眺めて、長義は熱い息を吐く。
そろそろ、俺も限界だ。
「またイッちゃったね?」
「ぅ……うう……っ」
ほろほろと上気した頬を流れる涙を舐めとり、そっと頭を撫でてやる。
「ほら、泣くな。可哀想になってくるから」
「なら、もう解け……」
「それはダメ」
ちゅっ。
クスクスと笑い、口づけを一つ、落とした。続けて額、頬、こめかみ、と順番に唇を押し付けていき、最後にフッと息を吹きかけてから、耳たぶを甘噛みする。ぐずる幼子を宥めるような接触はしかし、濃密な精と汗の匂いのせいですべてが台無しだった。二振りを取り囲む淫靡な空気は、例え窓を開け放ち換気をしようとも、到底晴れそうもない。
「なぁ、そろそろ俺も気持ちよくさせてくれないか」
すっかり昂ぶってしまった己のものを擦り付けて、長義が囁く。
「……っも、むり」
「国広の」
「ぅ……あ、」
疲労困憊といった様子の国広をひっくり返せば、自ずと発情期の雌猫のような格好で、濡れそぼった尻たぶが眼前に現れた。くぱくぱと痙攣して開閉する穴が、長義をはしたなく誘っている。ここは長義専用の穴だ。他の誰にも見せることはおろか、触れさせることなど絶対に許さない。はっきりと所有者がわかるように、この柔らかな内腿にでも銘入れしてやろうか、なんて物騒なことを考えながら、先ほど吐き出された彼の精液を掬い取った。
「ちゃんと慣らさないと……痛いのはいやだろう?」
指先で絡め取ったそれを、ぬるぬると勿体付けるように蕾の周りに塗りつけて、焦らす。
「ちょうぎ、……も、いいから……っちょうだい」
「何が欲しいのかな? ちゃんと言わなきゃわからない」
ずぶずぶ、と人差し指を突き入れ、ぐるりとナカを掻き回す。それだけで快感を拾い上げた肉壁は熱くうねり、貪欲に長義の指を咥え込んだ。
「あ……ちが……っ、やだ、」
「そら、何が欲しいのか言ってごらん」
二本、三本、と指を増やし、ある程度解れたところで前立腺を探り当てる。ごりごり、とそこを強く押し潰すと、国広は声にならない悲鳴を上げて、空で達した。前を縛っていないのに、ドライで達するとは。まったく調教し甲斐のある身体である。
「足りない……ちょうぎのがいい……」
「ん?」
「ちょうぎのじゃないと、や……」
ゆらゆらと腰を揺らして、国広が先を促す。その様を何も手を出さずにじっと見つめていれば、我慢の限界に達した国広が、自らの手で尻たぶを押し広げて、くぱぁっと入り口を見せつけてきた。今までどれだけいじめても、そんなあからさまなお強請りをしたことがなかっただけに、流石の長義も目を見開いて驚く。
「いれて。ちょうぎのまらじゃないと、おれ……!」
ごくり。喉が鳴る。ゾクゾクと腰が震えた。こんな誘惑に勝てる男がいるのか? いたら不能だろ。
「……本当、お前は憎たらしくて仕方ないよっ」
ずちゅんっ!
一息に貫いて、最奥を叩く。挿れた時の衝撃で国広もまた絶頂を迎え、ほぼ透明な精液をシーツへぶち撒けた。
「あ、んっ! ぁ、アッ」
ぐちゅぐちゅと律動を繰り返し、甘く絡みついてくる内側を掻き回す。正直、死ぬほど気持ちよかった。食い千切らんばかりの締め付けも堪らないし、何よりあのプライドが高くて滅多に自ら求めてこない国広が、あんないやらしい誘い方を……。あの時点でよく暴発しなくて済んだなと、自分を褒め称えたくなるくらいには、下半身にキた。
「は、なぁ、くにひろのっ」
「んぁ、そこ、ちょうぎ、ぃ……っ! そこ、あッ!」
「俺の恋刀だってこと、皆に公表しよう、な?」
後ろから覆い被さる形で国広を抱き締め、耳元へ直接言葉を吹き込む。こんな状況下で国広がまともな判断を下せないのは、百も承知であった。それでも何とか言質が欲しくて、わざと話を持ち掛けたのである。我ながら卑怯な手を使っているというのは自覚している。自覚してはいたが、どうしても認めて欲しくて、国広が俺のものなのだと周りに思い知らせたくて……。
だって、もう二度とあんな惨めな思いはしたくなかったのだ。
「たのむ、国広っ!」
「だ、だめっ! や、ダメだ、ッア!」
「なぜ……!」
なんでだ。どうしてダメなんだ。やっぱり、俺との関係を知られたくない奴がいるからか? 誰だ、そいつは。折ってやる。欠片一つとて残らないくらいに切り刻み、この霊剣・山姥切の刃の錆にしてくれる。
「俺が……弱いから! お前を守れない、から、ァッ!」
「は……、?」
国広が自分以外に心を砕く刀がいたら粉砕してやる、と鼻息荒く意気込んでいた長義はしかし、予想外の言葉に一瞬思考が凍結する。何と言われたのかわからなかった。弱い? 誰が。守れないとは? 誰のことを。
「つよくなったら、ちょうぎに言おうと、んん……っ! どうどうと、お前のとなりに、は、アッ、もう……――ッ!」
「ぐ……っ!」
聞き返そうとして、一際強い締め付けに襲われ、喉から出かかっていた言葉が奥に引っ込んでしまった。完全に不意打ちだ。どくどくと中へ精を吐き出した後、数度腰を揺すって最後の一滴まで奥に注ぎ込む。射精後特有のぼんやりした頭では、碌に考えも纏まらなかった。
はて、なんの話だったか……あぁ、そうだ。今の国広の言葉についてだ。この子は今、強くなってから堂々と俺の隣に立ちたかったのだと、そう言わなかったか?
(何だそれは……)
クソッ! クソッ! 何だそのいじましい理由は!
まさかそんな理由であんなに頑なに、俺の提案を断っていたというのか⁉
「……嘘だろ」
俺は馬鹿だ。それも大馬鹿だ。そしてこいつは馬鹿がつくほど可愛い。可愛いが過ぎる。そして、彼らしい。この本歌を守ろうだなどと、そんなふてぶてしいことを考えていたあたりが特に。刀としてのプライドが長義並みに高い彼のこと。本当ならば、己の弱さを認めるような発言は、口が裂けてもしたくなかったろうに。だが、その矜持を捻じ曲げてまで、彼は長義へ本音を吐露した。そこまで追い込んだのは、他でもない長義自身だ。
あぁ、このいじらしい恋刀の愛を疑ったばかりでなく、彼を縛って無理矢理事に及ぶだなどと。俺はなんてことを……。
「はぁ……はぁ、ちょうぎ」
名を呼ばれ、びくっと肩を跳ねさせて、気まずげに俯く。とはいえハチマキで目を覆い隠したままなので、そんな長義の様子は国広にはまったく見えていないのだが。それでも、彼に見えていないとわかっていても、とにかく罪悪感が半端なくて、顔が上げれなかった。
「……これ、外してくれないか」
「ダメだ」
「長義、」
きゅ、と咎めるようにナカを締め付けられる。眼下にある、しっとりと湿った白い肌が艶かしい。挿れたままの己が、心とは裏腹に反応してしまって、思わず頭を抱えた。情けない。これだから男という生き物は。俺の下半身は空気が読めないのか。一人自己嫌悪と屈辱に押し潰されそうになっていると、もう一度「外してくれ」と催促される。だが、それに黙って頷けるほど、今の長義に余裕はなかった。
「……見ないでくれ。お前に愛想を尽かされては冗談抜きで折れる」
「ふ、……お前が言うか、それを」
ばたり。
布擦れの音と共に、限界を迎えた国広の身体が左を向いて崩れ落ちる。その拍子にずるり、と長義の魔羅が抜けた。異物が内側から出ていった感覚にすら、感じでしまったのだろう。ん、と鼻にかかった甘ったるい声が、国広の口から漏れる。
「すまんな……これ以上は本気で無理だ」
「安心しなよ。もうしないから……」
「そうか、それはよかった」
空気が緩んだ。
怒っていないのか、と恐る恐る国広の顔を見て、戸惑う。彼の口元は、仕方がないなぁ、とでも言うかの如く緩んでいた。許すつもりなのか、俺を。まさか、怒る価値もないほど、どうでもいい存在だと切り捨てられたのでは。こいつは昔から開き直ると手がつけられないのだ。もし、恋仲を解消するなどと言われたら……。
さぁっと顔から血の気が失せていく。怒られないことがこんなにも辛いなんてことを初めて知った。いっそ怒鳴ってくれたなら、怒りをぶつけてくれたなら、安心出来たのに。
「お前が嫌というのなら、目隠しの方は外さなくていい。ただ、腕のは解いてくれ……お前に触れないのは寂しいから」
「……わかった」
しゅるり、と腕の自由を奪っていたネクタイを外し、拘束を解く。
きつく縛っていたせいで、彼の手首にはくっきりと痕が残ってしまっていた。晴れて自由の身となった国広は、ぐ、ぐ、と何度か手に力を入れて調子を確かめた後、今度は手探りに何かを探し始める。右へ、左へ、上へ、下へ。それが己を探している動きだと察した長義が、咄嗟に彼の手を掴むと、離してたまるかとばかりに指先を絡め取られた。
「長義、もっとこっちに寄ってくれ」
ずりずりと這い寄って、言われた通りにする。彼の腰のあたりまで来ると、上半身を起こした彼にそっと抱き着かれた。
とく、とく。
心臓の音が肌越しに伝わってくる。国広の体温がじわりと染み入ってきて、心が凪いでいった。愛しい、愛しい。陽だまりのような感情が溢れてきて、涙が出そうになる。俺は、どれだけこの子に拒まれようと、もうこの子を手放せそうもない。一体、どうしたらいいのか。内心途方に暮れた。
「何を勘違いしたかは知らんが、俺がお前に愛想を尽かすなんてあるわけないだろ。逆ならまだしも」
「逆の方こそありえないさ……」
「そうか……そうだと、嬉しい」
「うん……」
ぽす、と国広が長義の肩に顎を乗せ、拗ねたように唇を尖らせる。頬を掠める金髪が、少し擽ったい。
「それはそれとして、今日のは明らかにやり過ぎだぞ。病み上がりだというのに、まったく」
だが、と。一言だけ吐いて、国広が苦笑する。綺麗な笑みだった。目を覆い隠す朱色の布の存在が、惜しいと思うほどに。
「……長義が俺との関係を公にしたいと言ってくれたのは、嬉しかった」
――てっきりお前は、俺とのことを周りに知られたくないのだと思っていたから。
そう続けた彼の声は不安げで、そこでようやく、彼は彼なりにこの関係を不安に思っていたことを知った。
「思った以上に弱体化が酷くてな。こんなことでは、お前が俺との関係を恥じても当然だと」
「そんな馬鹿なこと、」
「……だといいんだが」
それから二振りは、足りなかった言葉を少しずつ交わし合い、今まで抱えてきたことを打ち明けた。長義が国広の恋刀であることを、周りに秘密にしていた理由(性格悪いな、と国広にまで言われて何も言い返せなかった)。南泉から聞いた、国広と歌仙の関係について(後にこれは長義の勘違いであることがわかった)。そして、国広が実はかなり前から関係を公にしたいと思っていたこと。しかし、今の己の実力で長義の隣に立つことは、自分で自分が許せなかったため、練度が上がったら長義に言おうと決めていたこと。ここまで話していてわかった。長義は国広のことを理解していたつもりでいて、何も理解出来ていなかった。結局付き合う前と同じだ。圧倒的に言葉が足りていなかった。
「国広、すまなかった……」
それまで国広の目を隠していたハチマキを取り去り、きつく彼の身体を抱き締める。
話をしようと決めたばかりだったのに、また同じことを繰り返してしまった。それでも去らずにこの腕の中にいてくれる存在が、こんなにも愛しくて、有り難くて……。彼と番ったことこそが奇跡だと、名も知らぬ神に感謝した。
すべての話が終わった時。眠気が限界に達した国広の身体から、がくりと力が抜ける。汚れてしまった彼の肢体を横たえて、長義は手入れ部屋の中に常備されていた清潔なタオルで、彼の身体を清めてやった。それから、自身もあれこれこびりついた体液を拭い、裸のまま国広の隣に寝転がる。今日はこのままここで寝よう。お生憎様、また同じように秘された関係に甘んじるとは、一言も言っていないものでね。このいじらしい恋刀の気持ちは、受け取ってやるけれど。それとこれとは事情は別なのだ。今回の一件でわかった。
この本丸には、警戒すべき刀が多過ぎる。
「……さて、第一発見者は誰になるかな?」
次の日、朝一番に見舞いに来た堀川と山伏が、手入れ部屋のドアを開けた瞬間、裸で寄り添い合いながら眠る長義たちの姿を発見し、卒倒するまであと数刻ほど。それから、正気に戻った彼らから鬼の追求を受けた国広が、洗いざらい今までの事情を話したことで、長義が頬に青あざをつくられることになるまでは、半日ほど。
その後、一件の全容を聞いた審神者から、「だから次の日に響くような性行為を……」と方向違いの居た堪れない説教を、長義が受けることになるまでは、あと……。
*
「やぁ、猫殺しくん」
「げっ!」
途端に全力で逃げようとした男のジャージを引っ掴んで、その場に縫い止める。顔を合わせるなり「げっ」とは失礼だな。この霊剣・山姥切が忙しい時間を割いてわざわざ構いに来てやってるというのに。まったくこの野良猫くんは、少し躾が必要なんじゃないかな。あ、俺が躾てやる義理はないので、俺はやらないけどね。何せあれの躾と世話だけで俺は手一杯だから。逆に俺の方が猫の手も借りたいくらいで……。
「登場早々うるせぇんだよ! にゃ!」
「君には色々と世話になったからね。俺の話を聞くくらいしても、バチは当たらないんじゃないかな?」
「だぁーっ! あの件はもう謝っただろうが! しっつけぇ男だにゃ!」
あの件とは当然、長義に吹き込んだ国広と歌仙の『噂』についてである。
当の本刃たちは知らなかったようだが。あの二振りは始めの頃こそその価値観の違いから、付き合う前の長義と国広なんて目じゃないほど、犬猿の仲っぷりを発揮していたらしく。まさに水と油。顔を合わせたら抜刀騒ぎになる確率ぶっちぎり一位の、取り扱い注意認定されていたとのことだった。そこで流れたのが、件の『噂』である。曰く、歌仙と国広を二人きりにするな。顔を合わせたら必ずどちらかが軽傷になるぞ、という、長義から言わせたらまったく方向違いもいいところの『噂』だった。
南泉からの話に散々振り回された自覚のある長義としては、その事実を聞くや否や、それはもう怒り狂った。それこそ、長義と南泉が取り扱い注意認定を受けかねないほどに、キレた長義が殴りかかるわ、それに南泉が応戦するやらで本丸中が大騒ぎになって……危うく本丸の壁に大穴が空くところだった。
だって、仕方ないだろう。
危うく恋刀を失いかねたんだ。本気であの時は国広を折って自分も折れてやろうかと思ったのだ。愛が重い自覚は多分にある。それだけのことをしでかしたのに、すいませんでした、の一言でことを済ませようとは。随分と虫のいい話じゃないか?
「ねぇ、猫殺しくん?」
「……」
しん、と二人の間の空気が静まり返る。風の音もなければ雨の音もない。完全なる無音。先に気まずげに目を逸らしたのは、南泉の方だった。忌々し気に「ちっ」と小さく舌打ちを漏らした彼は、ごろりと寝転がっていた身体を起こして、長義に隣に座るよう無言で促す。
「これはこれは、どうも」
空いたスペースに当然という顔をして座り込んで、長義は懐から今日の分の手土産を取り出した。
「八番屋の豆餅だ」
「へいへい、ありがとうございます、と」
それで、今日は何なんだよ。
と、うんざりした顔で聞いてきた男は、始めから長義との会話を放棄していた。ようやく無駄な抵抗だと理解したか。ふんっと鼻を鳴らし、長義はまたいつものように、恋刀の惚気を語り出す。国広の可愛さ自慢に始まって、彼の好ましいところ、まだまだ拙くて躾が必要なところ、言葉では言い尽くせない彼の魅力……などなど。
そして、一通りの話が終わり、南泉が陽だまりの温かさも相まってうとうとしてきた頃。長義はいつも通りの飄々とした顔で、とんでもない爆弾を落とした。
「……それでね、俺は思ったんだ。俺たちは言葉が足りないと。だから、もっと話す機会を増やすために、今度こそ国広と同居をしようと思ってね。主に俺たちのための離れを建ててくれないかって頼んでみたのさ。あぁ、これは国広には内緒だよ? また逃げられては敵わないからね。あれに全部話すのは、外堀を埋め終わってから……かな」
「へぇ〜……って、はぁ⁉ 離れ⁉ お前らのためだけにか、にゃ⁉」
「あぁ、俺たちだけの」
当たり前だろう?
と続ける長義へ、南泉が信じられないと言わんばかりの視線を送る。そんなに驚くこともなかろうに。国広とは昨晩話し合ったばかりで、この時長義はそれはもう浮かれきっていた。今なら大嫌いな内番仕事も、喜んで引き受けよう。何故なら、今日はめでたい日なのだ。瑣末なことでは長義の機嫌を損ねることなど不可能なくらいに、とんでもなく幸せな一日で――、
「だって、俺とあの子は」
その時、キラッと南泉の視界の端で何かが光った。
猫の習性から思わず彼がそれを目で追うと、どうやら光は、長義の手元から発せられているらしい。そういえば、今日の長義はいつもの黒い手袋をつけていなかった。常にないその行動に首を傾げつつ、南泉は剥き出しの手をじっと観察する。露わになった白い掌には、己の存在を煩いくらいに主張する銀色の何かが嵌められていて、それは見間違いでなければ、多分……。
「にゃっ⁉」
長義が手袋をしていない理由に思い至るや否や、南泉は目をひん剥いて驚愕する。
「今日から、夫婦になるのだから」
にゃおーうっ⁉
その日、嘗て聞いたことがないほどの大きな猫の鳴き声が、本丸中に響き渡った。
【後日談 数万分の一の物語 完】