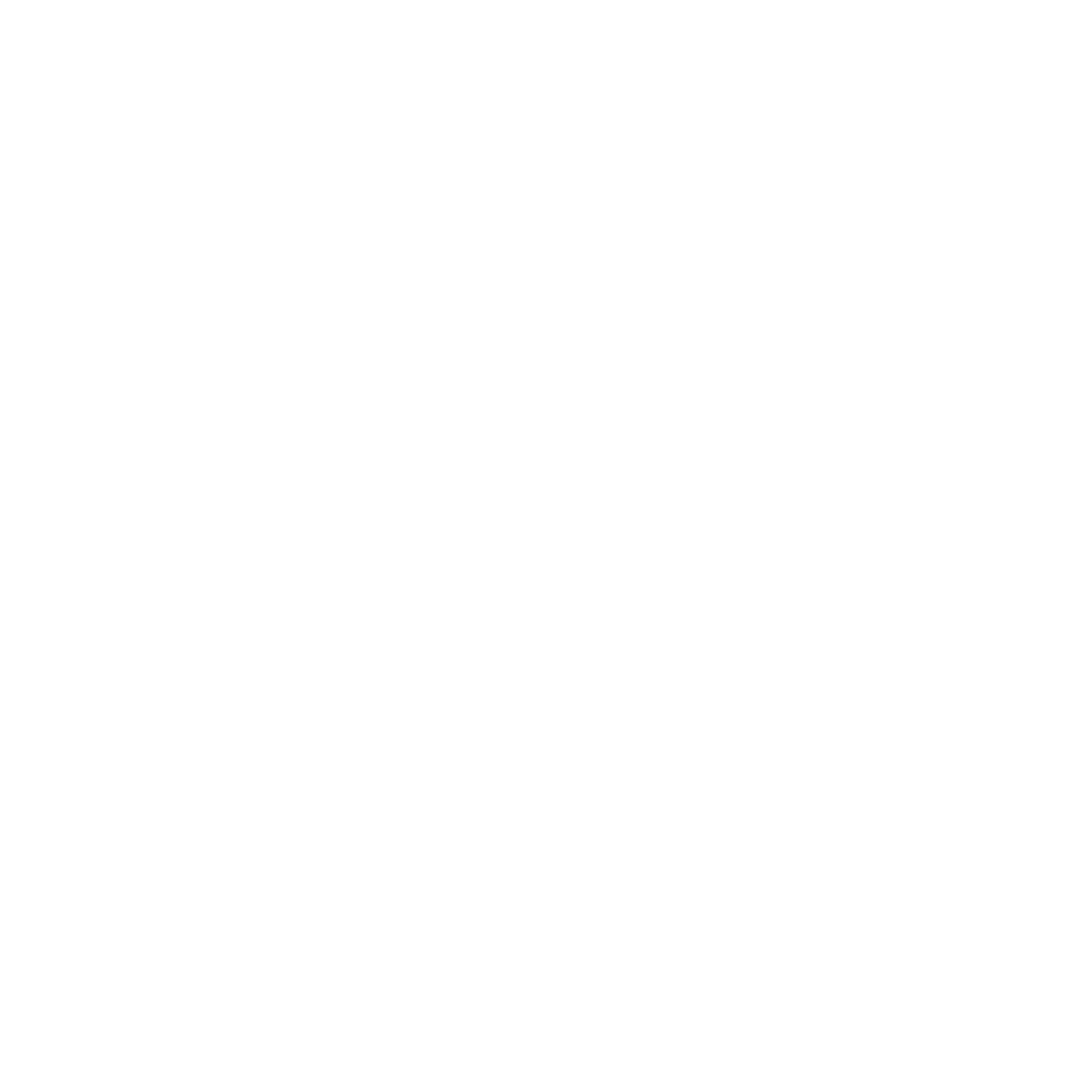第一話 監査官の来訪
今朝、丹精込めて育てていた朝顔が枯れた。
地面には色のくすんだ落ち葉と、鮮やかな青を残したまま永遠の眠りについた骸が散らばっている。潰えた夏の残滓が在る光景から一転。代わりに庭先には金木犀の香りが漂い始め、秋の気配がすぐそこまで迫っているのを嫌でも感じられた。山姥切国広は、熊手で枯葉を集めながら、ふ、と思い立ち顔を上げ、茜色に染まる空を見上げた。黄昏時だ。最近ではすっかり陽が落ちるのも早くなり、風は冷気を帯びた肌寒いものへと変貌を遂げている。刀の時分には気がつきもしなかった些細な変化を感じ取れるようになったのは、偏に、この奇怪な人の身のありとあらゆる感覚が、要らぬものまで鋭敏に拾い上げてしまうからに他ならなかった。
それは例えば、こうした季節の変化だったり。
またある時は、他刃からの好奇の眼差しであったり。
――己の心の奥に巣食う、劣等感や卑屈といった負の感情の蠢きであったり。
(……風が、)
風が、吹く。
予想以上に強いそれは国広の被っていた布を払い落とし、その下に隠していた金糸を露にした。悪戯好きな姿なき子どもは、動揺するこちらを嘲笑うように国広の周りをぐるりと旋回すると、せっかく集めた枯れ葉を散らし、跡形もなく消え失せる。文句を言う暇もない、あっという間の出来事であった。
「……どうしたものか」
また一からやり直すには時間が時間だった。あと半刻もしないうちに夕餉が始まるだろう。厨の方からは既に食欲をそそる匂いが漂っているし、腹の虫も今か今かと胃に詰め込める存在を待ち望んでいる。仕方がないので近場に固まっている落ち葉だけ集めることにして、散らばってしまった分はまた明日集めることにした。手近に置いてあったゴミ袋を手に取り、乱雑な手つきで枯れ葉を詰め込んでいく。
「……っ」
ぐらり。
その時、本丸の門に空間の揺らぎが生じたのを感知した。今日出陣した面々はとうに帰還しており、遠征中の者たちの帰りは明日の朝を予定している。今この時間帯に空間に歪みができる理由は何も思い当たらず、国広が疑念を覚えるまでにそう時間はかからなかった。
「妙だな……」
生じるはずのない時間帯に現れた、空間移転の痕跡。御神刀のような勘のいい刀ならば気づくであろうが、並の刀では察知出来るかどうか危ういほどのわずかな綻びは、何とも不気味で。ぞわぞわと背筋が粟立つような不快感を伴った。ちなみに、何故一介の写しである国広が感知できたのかと言うと、それは国広が主とこの本丸との結びつきが一際強い初期刀だからだ。今の国広は、この本丸の中に流れる主の霊力と、常に強固に繋がっている状態にある。
(侵入者か)
縁側に置いていた本体を手に取り、その場から駆け出す。もし敵襲だとすれば一分一秒の遅れが命取りだ。今は歴史修正主義者たちとの戦の最中。いつ何が起きるかわからない。政府の伝達によると、敵襲を受け攻め落とされた他本丸もあったという。そんな数々の物騒な話を思い出し、全力で走る国広のこめかみを嫌な汗が伝った。
(この本丸に立ち入ったこと、後悔させてやる……っ!)
この本丸は絶対に自分が守る。この命に代えても、敵の手に堕ちることなど許さない。ここに山姥切国広が在る限り。
息を切らして辿り着いた先、門の周りは静かだった。風は無く、あれほど濃く薫っていた金木犀の香りもすっかり消えている。朱に塗られた鳥居に夕焼けが差し込み、朱と黄金の間でゆらゆらと斜陽が揺れている。黄昏時ということもあり、彼岸と現の境目があやふやになっているような錯覚を抱いた。
「……あんた、何者だ」
紅く熟れた風景の中で、異端を放つ一点。鳥居の柱に凭れ掛かり、鋭い視線を送ってくる男へ、国広は問う。
男の姿は紅色の布に覆われていて、よく見えなかった。否、夕陽に染まってこそあれど、よくよく見てみるとあの布の元の色は白であることが伺える。国広よりも深く、すっぽりと布を頭から被った男に、敵意は見られず。付け加えると歴史修正主義者ならではの穢れも、禍々しい気配も纏っていなかった。気になるとしたら、一瞬だけ殺気に似た視線を浴びせられたことぐらいか。しかし、それでもあくまで殺気に《似たもの》だ。国広が抜刀を示唆する動作を見せても、男の手は胸元で組まれたままで、腰に携えた刀へ指先すら触れようとしない。そのことが、男が敵ではないことを示す唯一の証拠であった。
「やぁ、夕餉時に失礼するよ。審神者に急用があってね。政府からの使いで参った次第だ。書状もなく勝手に侵入したことを、まずは詫びさせてもらおうかな」
涼やかな声だ。思っているよりも歳は若そうで、人の子でいう十代から二十代の間といったくらいと見受けられる。身長もそれほど高くはなく、布越しに伝わるシルエットから、国広とほぼ同じくらいの体格をしていることがわかった。
「……審神者に?」
怪訝そうに繰り返した国広に、布の男は無防備に曝け出した口元を歪ませる。嫌な笑みだった。まるで、理解の悪い幼子を前にしたような、こちらを見下す笑みだ。
「あぁ、言伝がある」
「悪いが、得体の知れない者を通すわけにはいかない。主に会いたいというならば、まずはこの場で名乗ってもらおう」
「……ふぅん。随分と警戒心の強いことだ。まぁ、主を守る刀としての振舞いと見れば『良』ってところか」
男は少し苛立ったように頭の布を引っ張ると、さらに目深に被り直した。口元には先ほどまでの歪みは既になく、発せられた唸るような声には棘が含まれている。
「君は知らないのかな。我々政府側の者たちは神籍の末端といえど付喪神たちと相対している。故に、軽率に真名を名乗るなんて愚行は犯さないし、そもそも名乗りを許されていない」
「……」
「だが、そうだな。まったく名乗りもしないというのも怪しいから、少しだけ自己紹介をしてやろう……俺は政府に属し監査官を任されている者だ。今回は特命調査の任務を伝えにここへ来た。政府より与えられた俺の仕事は、君たちの任務に同行し、君たちの本丸の実力を監査すること……つまりは評価することにある。暫く君たちと共にいることが多くなるだろうが、よろしく頼むよ」
思わず呆気にとられた。国広の属する本丸は、十年以上もの間戦に塗れた毎日を過ごしてきた、中堅どころの本丸である。そのため、限定された期間の中で開かれる戦場や、政府が定期的に行なっている刀剣男士たちの鍛錬を目的とした仮想の戦場は、それなりの場数を踏んでいるけれど。政府直々に監査官を寄越すような特命調査など……ましてや本丸を試すような任務を与えたことなど、今まで一度も無かったと記憶している。
「特命調査とは、一体……」
「それは審神者本人に伝えることであって、君に話す道理はないよ」
動揺を隠し平静を装いつつ問うてみると、ぴしゃり、と言い切られてしまい閉口する。
「さて、理解してくれたなら、さっさと審神者の下まで案内してくれないかな。俺は意味の無い残業は嫌いでね。今日は伝達だけしたら直帰していいと言われている。早く所用を終わらせてしまいたいんだ」
審神者の元へ監査官を案内している間に、会話は無かった。
元より他刃と関わることを苦手としている国広が、積極的に会話を行おうとしないのは当然のこととして。監査官の方も何となく国広との会話を拒んでいるような、努めて心を閉ざしているような、そんな空気を放っていたため、ついに審神者の執務室へ辿り着くまで会話の機会を失ってしまったのだ。
「あそこが審神者の執務室だ。悪いがあんた一人で行かせるわけにはいかない。俺も同席させてもらう」
「それで構わない」
「理解のほど感謝する」
長々と続く大廊下を進むこと暫く。特殊な呪の施された札が数枚ほど貼り付けられた部屋に辿り着いた。周りに人の気配はなく、辺りはしんと静まり返っている。そんな、妙な緊張感の漂う執務室の前で、国広と監査官は立ち止まった。
「……主、政府からの来客だ。通しても構わないだろうか」
国広の声掛けの後、そう時を置かずしてドタドタと落ち着きのない音が響き始め、次いで押し入れを頻りに開閉する音が聞こえてきた。前もって訪問する旨を記した書状も何もなかったのだ。大方取っ散らかった書類だの何だのを押し入れに詰め込んで、少しでも部屋を綺麗に見せようと悪足掻きしているのだろう。だからあれほど普段から整理整頓をしろと言ってきたのに……なんて小言を言ったところで後の祭り。抜き打ち監査にどうか引っ掛かってくれるなよ、と。国広はこっそり名も無き神に神頼みする。
「待たせてすまないね。いいよ、お通ししてくれ」
「わかった……入ってくれ」
「失礼する」
金箔のあしらわれた襖絵が特徴的な入り口を開くと、一段高く作られている上段の間にて、審神者が座していた。それまで書き物の仕事をしていたのか。傍らには執務机と、座った彼の腰まである高さの書類の山が、無造作に積まれている。
「散らかったままですまないね。どうぞ、そちらに座ってください」
「では、お言葉に甘えて」
一礼した監査官が、下段の間に敷かれた二つの座布団のうち、部屋の奥側に位置する方へ腰を落とす。その隣に国広もまた座り、居住まいを正した。審神者は二人の前では動揺を一切見せず、毅然とした態度で上段の間からこちらを見下ろしている。ややあって、皆それぞれ話をする態勢が整ったと判断出来る頃合いで、監査官が口を開いた。
「まずは突然の訪問となってしまった無礼を、ここで詫びさせて頂く。俺は政府から監査官の役職を与えられている者だ。本日は政府よりの直々の命にてこの本丸へ参った」
「えぇ……とても驚きましたが、何か急ぎのようでもあったのでしょう。それで、一体何用で我が本丸へ……?」
「特命調査の依頼について伝達したく参った次第だ」
「……っ特命調査?」
驚いたとばかりに声を詰まらせ、審神者が問い返す。すると、当たり前だが先程国広が問うた時のような拒絶はせず、監査官は淡々と特命調査の内容について答え始めた。
「そうだ。放棄された世界。歴史改変された聚楽第への経路を一時的に開く……政府曰く『各本丸は部隊を編成し、一五九〇年の聚楽第、洛外より調査を開始。同時に敵を排除せよ』とのお達しだ」
「ほう……」
「聚楽第……安土桃山時代に、豊臣秀吉が政庁兼邸宅として建てた代物だな……僅か八年で廃城となったために、色々と謎の多いものだと聞いているが」
審神者は監査官の話を聞くや否や何事かを考え込み、国広は今しがた耳にした《聚楽第》について想いを馳せる。国広にとって聚楽第はまったくの無関係と言える存在ではなかった。一番目の主である長尾顕長が従属した北条氏。その北条氏を滅亡させた豊臣秀吉が住んでいたのが、京の都に建てられた聚楽第であった。
あの頃の国広はまだ生まれたてで、存在があやふやな付喪神だった。そのため当時の記憶が定かでなく、聚楽第が存在した時のことについて特別詳しいというわけではない。ただ、こうして何の因果か審神者に呼び出され、刀剣男士として歴史修正主義者と戦うようになり、自らが存在した時代とまったく関係のない時分まで詳しく正史を勉強していく中で。奇妙な縁で結ばれたその存在へ妙に惹かれるものがあったのを、よく覚えている。
(ましてや、特命調査の対象である天正十八年は、俺が打たれた時代だ。興味を持つなと言う方が難しい……)
そこまで思い至れば、俄然特命調査へのやる気が高まる。聚楽第は文禄四年には廃城されてしまい、僅か八年でその役目を終えたことから、現代においてもまだまだ不明な点が多いとされている。あの頃は見ることの叶わなかった嘗ての仇の様子が、この目で直接見れるかも知れない。主でさえも見ていない、北条氏滅亡の裏側を、この俺の目で。考えれば考えるほど興奮した。
「聚楽第……なるほど。そこが次の戦場となるわけですね。しかし一度閉ざされてしまっている以上、行ってみなければ何があるかわからない分、危険は多そうです」
人知れず国広が特命調査へのやる気に満ち満ちている一方、審神者はこの任務の難易度について考えていたようだった。彼は書類仕事は苦手だが、戦事になれば頭の切れる戦略家であり、こと軍術に長けていることで定評のある審神者である。しかし、流石に未踏の地とあっては判断がつきかねるらしく、戸惑いが大きいように感じられた。
そんな審神者の心情を察してか、監査官が続ける。
「本作戦への参加は任意である……が、政府は戦いの長期化に懸念を示している。実力を示す機会は、無駄にしないことだ」
「……」
「主、新たな戦場というのならば、俺が行く。いや、行かせてくれ。写しの俺が差し出がましい申し出だと理解してはいるが……」
顔を隠す紙のせいで、審神者の表情は見えない。しかし、彼がその下で今回の特命調査を行うかどうか迷っているのは明らかで。そんな主を安心させようと、国広は言い募った。
「俺は刀だ。刀は振るわれてこそ、その真価を発揮する。俺はどれだけ危険があろうとも戦いたい……果てるなら戦場で果てたい。それが刀の本能だ。主、迷うことはない。俺を使ってくれ」
暫しの間、審神者と国広の間に沈黙が流れる。先に折れたのは審神者の方であった。はぁ、と一つため息を吐いた審神者は、次の瞬間何かを振り切ったように顔を上げ、語気を強くして言う。
「……わかりました。あなたに任せるのが適任でしょう。では、最高練度の者たちで部隊を組み、戦支度が整い次第、聚楽第へ向かってください」
「拝命した」
「……話は纏まったかな。尚、本作戦においては監査官が同行し評定する……話は以上だ。俺は先に現地で待つ」
最後にそう言ったきり、監査官が立ち上がる。ふわりと布がはためいた拍子に、柑橘系の甘酸っぱい香りが鼻腔を掠めた。
(……?)
燭台切がつけている香水ともまた違う、自然なそれ。どうしてだろう。知っている匂いのような気がして、意識がはっとした。そして、無性に懐かしくて泣きたくなる。
「不満なら反乱を起こしてもいいが……」
国広が慌てて男の方へ視線を移した時、丁度襖の前に立った監査官がこちらを振り返るところだった。
「まぁ、無事では済まないな」
「あ……っ」
布の隙間から覗いた深い青瑠璃の瞳が、国広の持つ翡翠を射抜く。どうして。何故。猛烈に男を引き留めたい衝動に駆られ、絶句した。初めてだった。これほどまで誰かに対し、明確に《囚われた》と感じたのは。
「待て……っ」
再び意識が戻ってきた時には監査官の姿は忽然と消えてしまっていて。動揺する審神者の声にも碌に反応せず走り出せば、廊下は暗闇に包まれ誰の気配も無くなっていた。そのまま茫然とその場で突っ立っていると、不意に空間の揺らぎを感じ、そこでようやく監査官が門から帰還してしまったことを悟る。
逃してしまった。何を。追いかけなければ。誰を。次々脳内を巡る感情が溢れて、意識が混濁していく。
「誰だ……あいつは、何なんだ? どうして、俺は、」
怖い。
姿の見えない何かに呑み込まれていくような恐怖。足元から存在そのものを揺るがされているような、じわじわと侵食されていく悍ましさ。あの香りを嗅いだ時は、確かに懐かしいと思った。あれを好ましいと、叶うならずっと傍に在って欲しいとすら欲が芽生えたというのに。
わからない。わからないことが、怖い。恐ろしいのと同時に、惹かれてやまない。
(あいつともう一度会うには……)
現地で待つ、と。男は言った。そこに行けば、国広はあの布の男と再び顔を合わせることが叶うだろう。ならば、選択は一つ。
「聚楽第……か」
陽が落ちて床冷えする回廊に、独り言が落ちては消える。何処からか唸りを上げる風鳴が、荒れ狂う国広の胸中を表しているようで、そっと胸元に手をあてがっては逸る鼓動を慰めた。トク、トク、と脈打つ音を聞く限り、どうやら平静を取り戻すまでは時間が掛かりそうだ。挙句一人取り残された暗闇で、腹の底に僅かばかりの灯火が燈ったのを自覚する。
その後、夕餉の時間に遅れてやってきた国広が、同席していた最高練度の者たちと部隊を組むまでは半刻ほど。それから何かに追い立てられるように戦支度を整え始めた国広に急かされ、準備を整えた一行は、明朝には聚楽第へと進軍を果たすことになる。いつになく焦躁に駆られた様子の国広へ首を傾げた面々はしかし、彼の内に燻る影のようなものを、敢えて指摘する者はいなかった。
*
「来たか……。いい覚悟だ」
――時は一五九〇年一月。場所は京都洛外にある清水。
日の出前の早朝、まばらに雪がちらつく中で指定された場所へと向かえば、そこには既に監査官が待っていた。
「布……?」
国広の隣を歩いていた蛍丸が、あ、と声を上げる。
「あなや、まるで山姥切ではないか」
変わらず白い布で全身を覆った姿は、商人たちが忙しなく行き交う町中では、些か浮いて見えた。そんな監査官の姿を初めて目の当たりにした部隊の面々は、それぞれが驚きを露わにする。蛍丸と三日月は顕著に驚愕を表情に乗せ、青江は常らしい読めない笑顔で、監査官と国広を見比べ意味深に微笑む。その一方で、太鼓鐘と髭切に至っては始めこそ驚いていたものの、すぐに降り積もった白雪を踏み締めることに夢中になった。相変わらずマイペースな刀たちである。
「……」
刹那、それまで飄々と立っていた監査官が三日月の言葉に反応し、布の下から鋭い視線で国広を睨みつけてきた。写しと似ていると言われるのがそこまで嫌なのかと内心落ち込んでいると、すぐさま男は何事もなかったかの如く視線を逸らし、今回の特命調査の詳細について語り始める。
「現状、この聚楽第は敵に占領されている。その中心部にて北条氏政なる存在が確認された。が、これが正史でない以上、当人であるかどうかは瑣末なこと。歴史の修復の糸口を見つける。まずは、洛外を突破せよ」
機械的に言いたいことだけ言った監査官は、もう用はないと言わんばかりに肩に積もった雪を払い落し、一歩後退る。どうやら後は自由にしろ、という意味らしい。その隙のない口ぶりに何か口を挟む暇もなく。国広たちは監査官から説明された内容について議論を交わし出す。
「北条氏政、とな」
一番最初に口を開いたのは三日月だ。
「ふむ……おかしなこともあるものよ。この時分の北条氏は相模国におるのではなかったか」
「監査官の言うことが本当ならば、確かに北条氏政がここにいるのはおかしい。この頃は小田原征伐を控えている時期で、今頃あの男は戦に備え小田原に籠城している筈だからな」
比較的この時代について関わりのある国広が、北条氏政についての情報を付け加えた。
「それに、本来この場所にいるのは、秀吉公と北条氏の間で板挟みになっていた家康公の筈だったね。北条氏が聚楽第の中心部にいるというのなら、その理由は何なのか……秀吉公の暗殺か、それとも降参の申し入れか……まずはそこを探るところから始めた方が良さそうだ。一番イイところをピンポイントで狙うのが効果的、てね……あぁ、歴史の綻びのことだよ?」
青江の言葉に頷き、国広は髭切たちの方を見る。何か他に意見はあるか、と問うと残る二人はゆるりと首を横に振り、「特に無い」と答えた。ならば早速、と北条氏の動きを探るべく国広が先陣を切り歩き出せば、それに倣い一同は歩き始める。
尚、その間も監査官は国広たちの様子をじっと観察しており、三日月と青江は顔には出さないながらも、そのことを意識しているようだった。まぁ、髭切と太鼓鐘の二振りはのんびりとした口調で、緊張感の無いことに世間話に興じているようであったが。もう少し自分たちの行動次第で、本丸の評価が変わってくるのだと自覚してもらいたいものだ。そうは思えど、言っても聞かないだろうから諦める。
伊達に初期刀として彼らと長く付き合ってはいない。諦めの早さは機動と同じく早い国広であった。
「源氏以外のことについて、僕はからっきしでね。細かいことはわからないから山姥切たちに全部任せようかなぁ。あ、でも何を斬ったら良いのかだけ教えてくれよ」
にこにこと上機嫌な笑顔を見せ、髭切が右手をハサミの形にしてちょきちょき、と指先だけ動かす。その隣を歩いていた太鼓鐘は目をキラキラと輝かせ、大仰な身振り手振りで言った。
「聚楽第かぁ……資料で見た限りだと、派手な見てくれだったな、ありゃ。豊臣秀吉は良い趣味してやがるぜ!」
「兎に角北条氏政を探すぞ。そら、そこは地面が滑るから気をつけろ」
「おうよ。て、うあっ!」
案の定踏み固められた雪のせいで、つるっと綺麗に滑った太鼓鐘がバランスを崩す。
「おっと、危ない危ない。えーと……」
「太鼓鐘貞宗だ! 悪りぃな、ちょっち油断しちまった」
お決まりのすっ惚けた髭切とのやり取りに、太鼓鐘は慣れたように言い返した。第一部隊に所属する自分たちはかれこれ長い付き合いになる。よって、今更髭切に名前を忘れられたところで、彼はそういうモノなのだの一言で流されるのが常だった。血気盛んな和泉守や陸奥守などは、未だに彼に噛み付く姿がちらほら目撃されているけれど。
それでも、それもそのうち上手く受け流せるようになるだろう。国広は彼らの関係を楽観視している。時の流れというのはそういうものなのだ。尖っていた者も、皆いつか丸くなる。
(……なんだ)
唐突に背後から視線を感じ、国広は身を固くした。チクチクと突き刺さるそれを誰が送ってきているのかなど、容易に想像がつく。
ほぼすべての意識が背後に立つ存在へと向かった。じっとりと睨め付けるような視線は国広が勘づいてからも逸らされる気配はなく。いっそ愚直なまでに真っ直ぐ国広の奥深くまで射抜いてくる。腹の底まで見透かしてしまいかねない眼差しの強さは、相対していないとはいえ猛烈に感じられて、一度意識してしまえば気を逸らすなんてことは許されなかった。
こちらを見ろ、と視線が物語っている。
すべてを曝け出せ、と暴力的なまでの眼光が訴え、国広の意識を絡め取る。
「……っ」
耐えられなかった。思わず「もうやめてくれ」と叫びそうになり、衝動に突き動かされて男の方へ上半身を捻る。しかし、その瞬間深く積もった雪に足を取られ、身体が大きく傾いた。
「ぁ……、」
「……っと」
覚悟していた痛みが、一向にやってこない。不思議に思い国広が薄目を開くと、眼前で小綺麗な白布がひらひらとはためいた。次いで香ってくる、あの懐かしい香り。そこでようやく、自分が監査官に抱き留められたことを理解した。
「す、まない」
みっともない様を見せてしまったことにカッと頰が熱くなり、慌てて男から距離をとる。怪我はしてないだろうか。自分の粗相のせいで本丸の評価が減点されたりはしないか。ぐるぐると混乱した頭で考えていると、頭上からあからさまなため息が落とされ、雪より冷えた声が降ってきた。
「注意力散漫もいいところだ。今は特命調査中だろう。気を抜くな」
「あ、あぁ……」
「……がっかりさせてくれるなよ」
その場に突っ立ったままの国広を置いて、監査官が歩き出す。吹きすさぶ木枯らしに身震いし、冷風に晒されたことで火照った頬の熱さが浮き彫りになった。悔しさから歯噛みする。情けない。極めていないとはいえ、国広は長らく顕現し刀剣男士として戦場で刀を振るってきた。主に選んでもらった初期刀であるという自負もある。堀川国広第一の傑作であるという誇りも。そんな己が、少し注視されたからといって無様な姿を……よりによって本丸を評価する監査官の前で晒すなど。
「……言われなくとも」
ここからは、絶対に不甲斐ない姿なんて見せない。最後まで矜持を貫き、戦いきってみせる。
写しであるという引け目を忘れ、卑屈を置き去りにした国広は気づかない。何故、こんなにも監査官の前では緊張してしまうのか、彼の前では誇れる姿でありたいと強く願うのかを。
「ふぅん……そういうこと」
「また面妖な形の縁よの……」
そんな二振りの姿を微笑ましく見つめていた青江と三日月だけが、複雑に絡み合った彼らの縁の存在に気がついていた。
白の中に飛び散る赤。鮮血を浴びて穢された白雪は、されど新しく降り積もる白銀に埋もれ元の美しさを取り戻してゆく。
もう何体斬ってきたのか。数えるのも億劫になる程度には、洛外での戦闘数は多かった。手始めに監査官と落ち合った清水寺近辺で三連戦、鬼の目撃情報があったことから急遽東福寺方面へ移動し、道中と寺内でそれぞれ二連戦、そして逃げた残党を追い掛けて東大路通経由で八坂神社へ向かい、残党を狩り尽くすまでにまた三連戦。やっとこれで終わりかと思いきや、今度は洛中へと逃げ出した敵がいたため、四条大橋前で待ち構えていた敵陣を打ち破り、鴨川を渡って雪崩れ込むようにして洛中へ押し入った。
途中、身を隠しながら休むのに丁度いい、放置された無人家屋をいくつか見つけられたのは幸いだった。適度な回復を図りながら戦闘に挑めたため、まだ重傷状態の者は出ていない。ただ、斬っても斬ってもキリがない戦況に対して、全体の士気が低下しつつあるのが問題だった。
「もうそろそろ陽が落ちそうだ……これじゃあキリがないね」
――洛中・京都御所の屋根の上。
疲労感を滲ませたため息を吐き、青江がぼやく。
「物足りない敵ばかりだったからね。そろそろ骨のある鬼を斬りたいなぁ」
髭切が青江の言葉に頷きながら答え、他の面々もまた同意した。確かに、洛外の敵はそう強いわけでもなく、国広とて物足りなさを覚えていたところであった。洛中に入る際、四条大橋にて戦った敵はまだ少し手強かった気がするが、それでも楽しめたかと言われるとそうではない。今は人の器を得ているとはいえ、やはり刀の身。皆それぞれ戦闘本能を有している。自分より強い敵を追い求めるのもまた、刀の性と言えるのだろう。本能的な欲を言えば、もっと血肉湧き踊る戦がしたい。血を浴び、誉を掻っ攫いたい。所詮は玉鋼から作られた抜き身の刃だ。そう考えるのは当然と言えば当然だった。
「肩慣らしにもならぬのう」
「派手にやれば……って思う前に呆気なく倒しちまうんだもんなぁ。張り合いってもんがよ、こう……」
「洛中の敵は、もう少しマシになるだろう。聚楽第内部と比べるとまだ低レベルだがな」
そこで、ぐだぐだと文句垂れていた国広たちをフォローしたのは、予想外にも監査官だった。今まで積極的に関わろうとしてこなかった男からの初めての接触に、皆一様に面食らう。当の本人も今の口出しは無意識のうちに行っていたらしく。結果的に六人分の視線を一手に浴びることとなった彼は、布を深く被り直し、気まずげに顔を背けた。
「ふむ、そなた話せたのだな」
軽く目を見開いたまま、あっけらかんと三日月が言う。
「政府が送ってきた、えーと、ろぼっと? とかいう物かと思ってたよ」
髭切が追撃し、いよいよ居た堪れなくなったようだ。監査官はこちらに背を向けると、更なる追及を断ち切らんとその場を後にしようとした。
「……そら、先に進むぞ」
「あー! ちょっち待ってくれって、俺たちはあんたともっと話してみたくて、」
「生憎と、監査対象との過度な接触は政府から禁じられている。それに、ただでさえ時間遡行軍の侵略を許してるんだ。こんなところでもたもたしている暇はな――」
ボンッ!
完全な不意打ちだった。突然小さな破裂音と共に白煙が立ち昇り、視界が奪われる。
「なんだっ」
「敵襲か⁉」
素早く身構えた国広たちは一斉に抜刀し、白煙の向こう側へと刃先を向けた。しまった、油断した。ぐたぐたと文句を並べる前に、もう少し身辺に警戒を張り巡らせておくべきだった。知らぬ間にここまで接近を許していたなんて……。
「下には天皇、上には燃えるような茜空……なんとまぁ贅沢な戦さ場じゃないか」
「落ちるなよ。不敬罪で折られるなど、刀匠たる親父殿に顔向け出来んからな」
煙は徐々に薄れゆき、中に潜む者のシルエットが明らかになっていく。予想よりも大分小さな影であることに、国広は内心驚いた。今まで見てきた時間遡行軍のものと比べると、随分と小型である。新種の敵短刀か、それとももっと別の新勢力か……? 何せここは未踏の地、放棄された時代だ。何が出てくるかは誰にも予想がつかない。
(まぁいい。相手がなんだろうが知ったことか。斬ればいいんだろう?)
「特命調査、どうもご苦労様です。政府所属コード一五七番・こんのすけでございます」
なんて考えていたのも束の間、ひょいっと中から現れた予期せぬ存在に、一同は驚かされることになるのだった。
「な……っ」
「こんのすけ!」
もくもくと上がる白煙の中から出てきたのは、政府に所属するという黒毛の管狐。
目元をぐるりと一周する、筆で描いたような鮮やかな朱色の模様。切れ長の目元に野性味のある牙が覗く口元、尖った鼻先……顔つきや模様、色に至るまで、彼は国広の所属する本丸のこんのすけとはまったく異なっていた。加えて喋り方も少々独特で、京訛りがある。やけにしっとりとした喋り方はまさに京の住民然りとしたもので、いつものこんのすけに見慣れている国広たちには違和感しかなかった。
「わざわざ地方から京の都まで……ほんに長旅をご苦労様です。洛中のことについては私の方から案内させて頂きます故、安心して任せてくださいね」
未だ驚愕から覚めていない面々は、こんのすけの挨拶に上手く反応出来ず、唖然と立ち尽くしている。だが、宙に浮いた管狐はそんな面々の様子など御構い無しに、マイペースに話しだした。
「えらいボロボロですなぁ。勝栗はどうしはったんです?」
「まだ外だからな……油断出来ないと判断して、休める場所を探していたところだ」
一足先に我に帰った国広が答えると、こんのすけが大仰に反応してみせる。
「それはそれは……せやったらこのちょっと行った先に春興殿がありますので、そこまで案内しましょうか。そこやったら普段武具とかを置いてるだけで、人もあまりいてはらへんので」
「……助かる」
「いるなら洛外から案内してくれれば良かったじゃねぇか。俺たち結構苦労したんだぜ?」
「……」
ピタリ。
ようやく一息つけそうだと各々がほっと気を緩めた頃。それまで人好きのする笑みを浮かべていたこんのすけの様子が変わる。カッ! と、前を行く彼の目が限界までかっぴらかれたかと思うと、管狐は唾を飛ばす勢いで喚き出した。
「洛外は管轄外です! 私の担当はあくまで京都内だけなんで!」
「お、おう……?」
あまりの勢いに揶揄った太鼓鐘の方が押され気味になる。釣られて他の者たちも思わず仰け反ってしまい、その迫力に度肝を抜かれた。何だこいつは。強い。小さいのに強い。逆らってはいけない空気をひしひしと感じる。
「……あそこも京都は京都だろ?」
「一緒にせんといてもらえます? 京の都と言われるんは、この洛中! 境から一歩でも外に出れば、そこはもう京やありゃしまへん」
ふんっと最後に鼻を鳴らし、ふりふり尻尾を揺らしながら歩き出した管狐の後を、男たちがついて歩く。なんというか、強烈な狐だ。うちの本丸のこんのすけが恋しい。そう思ったのは、きっと国広だけではない筈だ。直接凄まれた太鼓鐘はまだ魂が抜けてしまっているし、心なしかしょんぼりと肩を落としている。
「ぁ……」
咄嗟に、慰めなければ、と思った。
けれど上手い言葉が見つからず、何と声をかけようかうんうん唸る。暫く語彙を持て余していると、最後尾を歩いていた監査官が静かに太鼓鐘の方へ近づいていくのが見えた。そして、何事かを太鼓鐘の耳元で囁いた彼は、そっと眼下で揺れる小さな頭に掌を置き、今まで聞いたことのない優しい声で慰める。
「彼は京都洛中の案内に特化した管狐でね……そのせいか一般の個体より些か縄張り意識が強いと言うか、選民意識が強いというか……まぁ、少し変わった個体なんだ。君のせいではなく、彼が偏屈なだけだから、あまり気にするな」
「監査官……すまねぇな。ありがとう」
きょとんと虚を突かれた顔をした太鼓鐘が、次の瞬間眉尻を下げて礼を言う。
「こちらこそすまないね。まさか洛中に入った途端出てくるとは思わなかったから……俺の方からも協調性を持つよう注意しておくよ。言っても無駄かも知れないけど」
(……悪い奴では、無さそうだな)
太鼓鐘に話しかける時の監査官の様子を見て、国広は思う。部隊の士気が落ちた時のさりげないフォローといい、的確な判断や指示といい、彼は何かと気遣い上手な性分のように見えた。
ただ、一つだけ引っかかることがあるすれば。彼が柔らかく接するのは、国広以外の者に対してだけということぐらいか。現に、監査官は国広と接する時だけ声が固くなるし、物言いも数倍キツくなる。珍しく声を掛けてきたかと思えば、飛び出す言葉も「がっかりさせるな」「油断するな」「それでも初期刀か」などと厳しいものばかり。これで好ましく思われていないことを気づかない方がおかしい。
(何かしてしまったのだろうか……)
考えるがわからない。そもそもそこまで関わりがなかったのだ。原因が思いつかない。
「おい、そこのに、……初期刀くん。何を突っ立っているんだい。さっさと回復して、隊員たちと次の戦闘について話し合うなりしたらどうだ」
思考の渦に飲み込まれて一人考え込んでいると、悩みの種である張本人が国広に話しかけてきた。くそ、こんな時ばかり積極的に関わろうとしてくるなんて。優しいのか冷たいのか、よくわからない男である。少なくとも、国広にとっての彼は性格が良いとは世辞でも言えない印象だが。
「あ、あぁ……すまない、ぼうっとしていた」
「はぁ……部隊長は君なのだから、無様な姿を隊員に見せるな」
「ぅっ……」
「皆は既に勝栗を食べている。後はお前だけだよ」
ほら、と差し出された掌の中にあったのは、一粒の勝栗。わざわざ持ってきてくれたのか。戸惑いがちに監査官と手の中の勝栗の間で視線を彷徨わせていると、苛立ちを露わにした彼に無理矢理胸元へ押し付けられる。
「い、たい」
「グズグズしてるからだよ。そら、さっさと受け取れ。それとも、俺の手ずからその役立たずの口に捻じ込んで欲しいのかな?」
そこまで言われてカチンと来ないほど、国広はできた男では無い。奪うようにして勝栗を受け取ると、すかさず男の目があるであろう布の部分を睨みつけてやった。写しとはいえ目つきの悪さでは定評のある国広だ。多少なりともダメージを与えられれば僥倖。だが、そんな国広の反抗的な態度の意味も無く、男はふっと鼻で笑っただけで軽く受け流してしまった。
「あんた……っ」
「山姥切や、こちらへ参らぬか。かような遠いところにおっては、おちおち話もままならぬ」
「もうすぐ夜になる。僕たち太刀は夜目が効かなくなるからね。進軍は明朝にして、今日のところはここらで野宿といこうじゃないか」
噛み付こうとした矢先に出鼻を挫かれ、気が削がれた。慌てて視線を戻すも監査官は既にこんのすけの方へ歩き出していて、その背中からは断固とした拒絶の意思が滲み出ている。
悲しかった。どうしようもなく。
あの背中に追い縋ることの叶わない今が、悲しくて……。
「何なんだ……」
どうして、あれほど執拗なまでに自分に突っかかるのか。何故、気まぐれに干渉してくるくせして最後には拒絶しようとするのか。本当のところ、あの男の正体は国広の中で明確になりつつある。しかし、それでも信じたくない自分がいて。それに、あんな背中を見てしまったからにはもう、認めるわけにはいかなくなってしまった。
認めてしまえば、自分が深く傷ついてしまうことがわかりきっていたから。
「……なぜ」
視界の端で、春興殿の周りに置かれた松明の灯りが揺れた。虫の音すら聞こえない、真冬の都。見渡す限りの銀世界に色は無く、四季折々に魅せられた生命の輝きは、今や冷たい白の下で深い眠りについている。
雪解けの時を、国広は想像することが出来なかった。
いつかは、と期待することが恐ろしく。かといって凄惨な現実も見ないふりをして。目を逸らしては、物寂しい白黒の景色ばかりを瞳に映す。刀匠の最高傑作の称号が、聞いて呆れる。自分はこんなにも臆病で、しかし矜持ばかり一人前なものだから、腹を括って彼と向き合うことすらままならない。なんて情けなく、ままならないことか。こんなことでは彼の前にこの写しの姿を晒すなど夢のまた夢。布という絶対的な防御壁が無ければ、国広もまたこの雪の下に埋もれ、雪解けの頃には自責の念で溶けて消えてしまっていただろう。
ずっとこの冷え切った世界に閉じ込められたまま、嘗て慕った親のようなあの刀の後ろ姿を、ただただ眺め続ける。心にぽっかり空いた虚は埋まることがなく、欲求ばかりが募っていく。そんな世界は、まさしく地獄だ。
「……、んか」
それでも彼は、か細い糸すら垂らしてはくれないだろう。あの背中は、期待を抱かせる隙もないほどに頑なであった。
期待は、しない。手を伸ばすことはしない。
彼に気にかけてもらいたいなんていう、浅ましい願いだって、もう……。