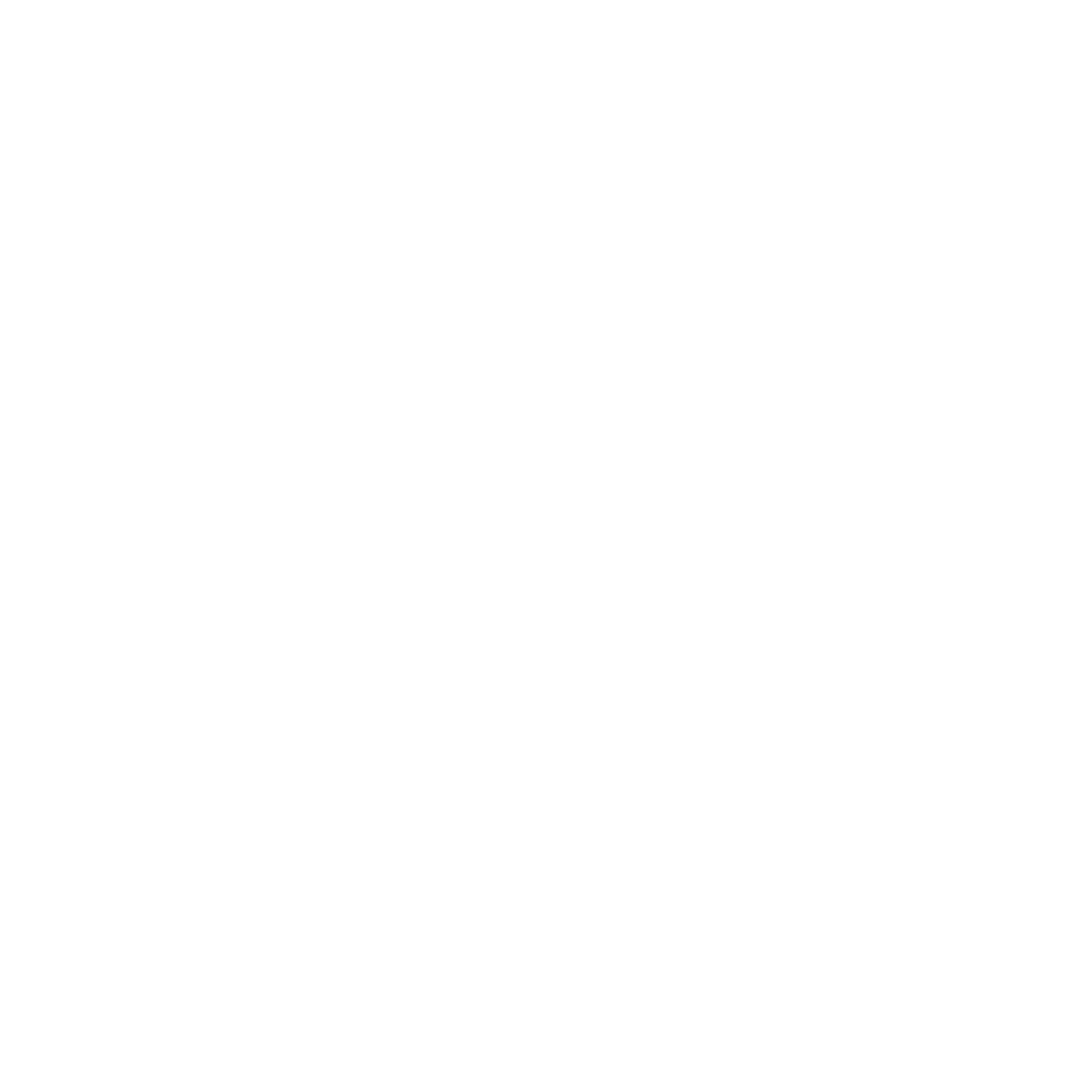第二話 洛中を突破せよ
甲高い金属音が聞こえる。カン、カン、という何かを打ちつけるような音だ。ぼんやりした意識のまま暫く聴き入っていても、音が途切れる気配はなく。それはただただ延々と、一定の間隔で繰り返されている。
「ん……」
眠りを妨げるその音はどうしてか耳障りが良く、不快になるどころかさらなる深い眠りを誘った。まるで耳元で優しい声が、眠れや、眠れ、と囁いてくるような、そんな安心させる音。意識は頻りに目を覚ましたいと訴えていたけれど、永続的に流れる心地の良い子守唄に抗う術もなく。トロトロと重くなった瞼を閉じたり、開いたりしながら、必死に眠気と戦った。そして、いよいよ陥落してしまおうかと諦めかけたその時、急に身体が熱くなり一気に目が冴える。
「ぅ、わっ」
「おや、もう形を成したのかい。おちびさん」
「……っ」
がばりと身体を起こすと、そこには見たこともない美しい男が座っていた。
地面につくほど長い、鋼を磨き上げたような冷たい銀色の髪。涼やかな目元に嵌め込まれているのは、海の色よりも深い青瑠璃色だ。暗い水底の色合いは光源によって濃淡を変え、不安定ながらも凛とした強い眼差しで前を見据えている。新雪の如き白い肌は目に眩しく、襟の隙間から覗くそれが禁欲的な印象を見るものに抱かせた。そして、男自身だけでなく彼の纏う紋付袴もまた、一目で仕立ての良い至高の逸品であることが伺えて。目覚めて早々視界に飛び込んできた、圧倒的な美の暴力は、即ち彼が只者ではないということを表していた。
「お前は特別のようだ。俺の写しは今まで何度か打たれてきたけれど、お前ほど早く形を成した付喪神はいなかった」
「うつし……?」
これは夢だ。何故だかそう思った。何を根拠に夢だと断定したのかはわからない。わからないが、今自分の見ている光景は現のものではありえないと、そう直感したのだ。
ぐるりと辺りを見渡す。開け放たれたままの立て付けの悪そうな引き戸に、部屋の中央に取り付けられた大きな火炉。この鍛冶場自体かなり使い込まれているのか。引っかいたような傷や、何かを落としたようなへこみが、至る所に見られた。火炉の前には、金床や向う鎚といった鍛冶の道具が無造作に置かれていて、それらを取り囲むようにして数人の男たちが立っている。そんな中、頭に手ぬぐいを巻いた一人の男が「今日は暑いなぁ」なんて汗を拭いながら、炉から高温に熱せられた鉄を取り出し、真剣な表情でそれを見定め始めた。
熱気に揺らぐ陽炎。
火炉の中でぱちぱちと弾ける火の粉。
懐かしさすら覚える光景に瞬きする。みるみるうちに形を成していく真っ赤に輝く玉鋼は、すらりと細身のシルエットを形作り、同時にその鉄が己の本体であると理解した。生まれながらにして備わっていた本能が、そう言っていたのだ。あの、鋭い眼差しで己を見つめる男が父であるということも。
隣にいる美しい男もまた、己と同じ存在であろうことも。
「……お前の完成も近い。出来上がれば、もっとその身は安定するだろう」
美しい男は打ち付けられる鉄を見つめながら、熱っぽい声で囁く。心から完成を待ち望んでいる声だった。炎に照らされ、白い顔を上気させつつ、恍惚とした笑みを浮かべる男を見ていると、得も言われぬ高揚感が沸き起こる。そうこうしているうちに、再びカン、カン、という音が響き始め、国広もまた視線を隣の男から玉鋼の方へと移した。
刀工たちが今まさに生み出さんとしているそれが誇らしくて堪らず。幼子は、にやける口元を耐えることが出来なくなる。
「うつし……おれは、あんたのうつし……」
「そうだ、国広の。お前は俺の写し。それも、いずれは伯仲の出来と称えられるほどの、特別な写しとなるだろうよ。あの刀工の腕、なかなか達つと見受けられる……」
「くに、ひろ……」
男が呼んだ名前を、口の中で転がしてみる。不思議としっくり馴染んだ。そこで、国広が名を繰り返し呟く度に、掌の透けが濃くなっていくことに気づく。名を与えられたことで存在が定着しつつあるのだと、そんな国広の身体を見て男が言った。
「それはお前の名だ。大切にするんだよ」
「くにひろ……おれのなまえは、くにひろ……」
「そうだ。そして、お前の本歌たる俺の名は……」
彼の名を聞こうと耳を澄ませたその時、場面は目紛しく移り変わった。
己が生まれた鍛冶場が急に遠ざかり、今度は拓けた場所に出る。妙にぼんやりした意識が覚醒した頃には既に、そこら中に石ころの転がる山道を、嘗て主と呼んだ男と歩いているところだった。
(山……?)
「国広の、初めての山下りは慣れない者にはキツい。そら、俺が抱えてやるから、こっちに来い」
「ことわる! ほんかのおてをわずらわせるわけにはいかない!」
一人で歩ける、と意地を張って首を横に振る国広に、本歌と呼ばれた男は困ったような顔をする。眉尻を下げ、目元をゆるりと細めたその顔。歪んだ様でも美しいとは、やはり本歌だからか。悔しくなり、ますます膨れっ面になった幼き国広に、彼は苦笑しながら言い募った。
「俺がお前を抱いていたいんだ。今は如月。本格的な冬を越えたとはいえ、まだ冷える……国広で暖を取りたい。なぁ、ダメか?」
「……ほんかが、そうのぞむのなら」
「ふふっ……ありがとう、国広の」
軽々と身体を抱き上げられ、男と目線が並ぶ。あの、吸い込まれてしまいそうな深い色合いを湛えた青瑠璃が、間近に迫った。思わずそのまま魅入っていると、本歌はくすくすと擽ったそうな笑いを漏らし、あちらをご覧、と国広の意識を逸らさせる。彼の示した先は山の麓側。何があるのかと思い目を向けると、そこには……。
「わぁ……」
城郭に取り囲まれた足利城の中からは、到底見ることの叶わなかった光景が、そこには広がっていた。
遠く向こうまで見渡すことの出来る頂上からの絶景。地に聳え立つ山々の間から朝陽が顔を覗かせ、現の輪郭を照らし出す。澄み切った青空を数羽の渡り鳥が横切り、生命の息吹が国広たちの真横を力強く通り過ぎていく。さざめく木々の真ん中で、どこからか運ばれてきた花の匂いが甘く鼻腔を擽った。霧のかかる麓の方には点々と何かが並んでおり、あれはなんだ、と問えば、あれは人の子の住む家なのだと、本歌が教えてくれた。
「俺たちは今からあの麓を行き、あの山を越え、遠く離れた小田原へと向かうことになる」
「おだわら……?」
「主がお仕えする北条家の城がある場所だ。此度の遠征で、主は正式に北条に付き従うことを誓うことになる。そうなれば、……」
「……ほんか?」
「いいかい、国広の」
柔らかい表情を見せていた彼の、恐ろしいくらいに美麗な顔から表情が失せた。ぐっとさらに距離を詰められて戸惑うも、彼は決して国広から目を逸らそうとはせず、言い聞かせるようにゆっくりと言の葉を紡ぐ。
「俺たちは、戦のために生まれた存在だ。如何に過酷な戦さ場へ赴くことになろうとも、怯んではいけない。主をお守りするのだという刀としての矜持を、断じて忘れてはならない。例えこの身が折れようとも……」
未だ戦場に出たことのない国広には、それがどれほど凄惨で、過酷で、恐ろしいものなのかわからなかった。わからないながらも、長義の口ぶりから生半可な覚悟で臨んではならない場所であることを理解した。ごくり、と無意識に唾を呑み込み、神妙に頷く。しかと長義の意志を受け取ったと伝えるべく、国広は頷くだけではなく敢えて「わかった」と震える声で言葉にした。
ここで交わされた誓いは、神同士の契約。例え生まれたばかりで幼い国広であろうと、誓約の離反は祟りに触れる。
「お前は賢い子だね……。だが、くれぐれも無駄死にだけはしてくれるなよ。お前は俺の、俺だけの、特別な写しなのだから」
ドロドロに煮詰めたような甘い声で、耳を犯される。呪詛のような囁きには、こちらを絡め取るような、目に見えぬ何かの存在を感じさせた。ゾッと背を這う悪寒に身震いすると、ふぅ、と耳の中に息を吹き込まれる。
「ひっ!」
「あはは、いい反応だ。本当にお前は揶揄い甲斐があるなぁ」
「な、う、うつしだからとあなどっているのか! からかうな!」
「はいはい」
さあ、と風が吹く。太陽に照らされた金髪と、男の腰まで伸ばされた銀の髪が舞う。絡み合い、一つになって、キラキラと眼前で輝く。屈託のない笑顔を見せるこの刀が愛おしいと、国広の心は叫んでいて、まさに神と呼ぶに相応しい美しい男の姿に、しばし見惚れた。
(あぁ……)
なんで、今まで忘れていられたのだろうか。あれ程まで慕っていた、あの刀の存在を。否、彼の存在を意識しない日はなかった。何せ、ずっと本歌と比べられてきた身だ。嫌というほどその存在感を意識せざるを得なかった。
ただ、彼と過ごした足利での日々を、国広は忘れてしまっていた。あの頃の国広は不安定で、鮮明な記憶はほぼ残っていない。あるのは、本歌と過ごした時期があったという己の来歴に関する、表面的な知識だけだ。そこに何か思い入れがあったかというと、そういうわけではない。寧ろ、ますます劣等感に苛まれてしまいそうだから、本歌の姿を覚えていなくてよかったとすら思ったくらいだ。
(忘れたままでいたかった)
現に置いてきた身体の覚醒の気配を感じる。目を覚ましたくない。ずっと、この幸せだった時間にいたい。だって、目が覚めたらまたあの冷たい視線に晒されることになる。一度彼の甘やかな笑みを知ってしまった今では、到底彼から向けられる悪意に耐えられそうもない。
小田原落城後、当時の足利城主であり、嘗ての主だった長尾顕長は秀吉に領地を没収され、流浪の民となってしまった。その際、国広は滅亡した北条家の遺臣であった石原甚五左衛門の元へ贈られ、そして本歌は顕長の兄である由良国繁の手へと渡った。一五九〇年七月。足利の春を共に過ごし、庭先の桜が散り、薄紅色の天蓋から深緑の空へと彩りの変わる頃。あれだけ満開であったのにあっさり散ってしまった花の如く、彼との思い出も儚く散って消えてしまった。
あれ以来、刀剣男士として現世に呼び出されるまでの間、二振りは顔を合わせることのないまま、それぞれの時を過ごした。厳密に言えば、過去山姥切本歌と写しとして二振り揃って展示されたことは、ある。しかし、隣り合わせに座していたにも関わらず、彼は頑なに国広の前に顔を出そうとはせず。完全な拒絶を突きつけられたのを最後に、また二振りは長きもの間離れ離れになってしまった。
つまりはそれが、一千年近く経った今になって返された答えだった。
――俺はお前を写しとは認めない。
あれほど立派であれと、俺の写しとして然るべき活躍をしろと言祝いでくれた彼が、残酷にも下した結論。それが、国広という写しの存在に対する拒絶、だった。
*
《一五九〇年一月二日午前六時 京都御所・春興殿》
今日も今日とて京の都は、地面から建物の屋根に至るまで真っ白に雪化粧を施されている。
まだ日の出前の真っ暗闇に包まれた中、第一部隊の面々は円になり、監査官から昨日の成果報告を聞いていた。ちなみに、情報の提供元はこんのすけ。洛外は自分の担当範囲ではないと突っ撥ねていた彼であったが、京の有名な店で取り扱っている油揚げで取引を持ちかけた結果、あっさり買収出来たらしい。迷うことなく買収を持ち掛けた監査官も監査官だが、掌返しの早い管狐も管狐である。単純過ぎて油揚げ一つで裏切らないか心配だ。
「洛外にて殲滅した敵数は三十体。以降、洛外での新たな情報はなし。これより、本格的に洛中へと入る。洛外とは違い、洛中は一本道ではない。戦いながら道を切り開き、聚楽第の入り口へ辿り着け」
監査官が話す度に、布の下から白い息が吐き出される。
敵が出没する大体の時間帯と場所は、こんのすけを通じて政府から報告が入るようだ。便利なのはいいことだが、それを思うと洛外で必死になって聞き込み調査をしたあの苦労はなんだったのか……。少しやるせない気持ちになるのは致し方のないことであろう。
「ふぁ……」
少しばかり遠い目になりながら戦支度を整えていると、小さく欠伸を漏らした国広へ早速監査官の嫌味が飛んできた。
「気が緩んでるんじゃないか。部隊長がそんなことでは、この本丸のレベルも知れたものだ」
「……すまない」
「何だい。隊長、昨日眠れなかったのかい?」
監査官と国広の会話を耳聡く聞いていた青江が、心配そうな声で話しかけてくる。そんな青江の声を聞きつけて、他の面々も一斉にこちらを振り向いた。太鼓鐘と話していた蛍丸がさっと駆け寄ってきて、布の下から国広の顔を覗き込んでくる。大丈夫? という無垢な問いかけに、うっ、と声が詰まった。寝たことは寝たのだ。ただ、その時見た夢が夢だっただけで。
「いや……大丈夫だ。ちゃんと寝たから」
「顔色が悪いように見えるが?」
すかさず鋭い指摘が飛んできて、誤魔化しが効かないことを悟る。国広が動揺から視線を彷徨わせていることは、角度的に布の下が見えてしまう蛍丸からは一目瞭然で。当然、長年の付き合いで気心が知れており、ズケズケと言いたいことは言ってくれる本丸仲間は、その一瞬の隙を見逃してくれるはずもなく。盛大に眉間に皺を寄せながら、無理をするなと叱られた。
「そんなことはない。大丈夫だ。俺は確かに写しの身であるが、国広の第一の傑作だ。戦働きに関しては自信がある。皆の足を引っ張らないようにはするから、」
「その前向きとみせかけて後ろ向きな発言も、部隊長らしからぬ言動だ。今の時点で評価をつけられたなら、俺は迷いなく君たちに『不可』を与えているところだよ」
本丸の評価が、自分の不注意のせいで台無しになる。冷え切った声で宣言されてしまえば、心臓が凍りつく思いになるというもの。ましてや、あんな夢を見た後では、この監査官の布の下にある存在を嫌でも意識させられてしまう。到底平静ではいられなかった。
「……っ」
あの夢のせいで、常より涙腺が緩んでいる。急に涙が出そうになって、咄嗟に布を引き下げた。すると、横から能天気な声が割り込んできて、緊迫した場の空気が壊される。
「はっはっは! 監査官殿は手厳しい。あいすまなんだ。こやつめ、昔から強がって弱ったところを見せたがらん。監査官殿は、隊長殿のことをよく見ておられるのだな」
「……そんなことは、」
「しかし、うちの隊長の不注意は、気づけなかった俺たちの不注意でもある。こやつだけが責められるのは、ちと道理が通っておらぬのではないか。責めるなら、俺たちのことも責めておくれ……。して、ここはこの爺の顔に免じて、どうか引いてはもらえんだろうか?」
瞬きするよりも短い時間、沈黙が訪れた。全員が口を閉ざし、監査官の言葉を待っている。彼をじっと見つめる目に、咎める色はどこにも無い。それどころか、その視線は何処か優しいもので、だからこそ戸惑ったのだろう。監査官はぴくりと小さく肩を揺らし、諦めたように深いため息を吐いた。
「……初期刀くん」
ひくっ。
布を掴んだままだった国広の指先が、震える。
「次はないぞ」
じゃり、じゃり、と音を立てて、監査官が歩き出した。向かう先にいるのはこんのすけだ。監査官に何かしら話しかけられた黒い管狐は、一度大きく頷くとドロンと消え、次の瞬間国広たちの前に現れる。もう驚くことはしなかった。元より神出鬼没であることに定評のある管狐。何度も不意打ちを食らっていれば、いい加減慣れる。
「えー、政府からの報告です。予定では七時半頃、この京都御所・南庭に時間遡行軍が四体出現するとのこと。日があるとはいえ薄暗いことが予想されるでしょう。加えて、一月の京の朝は霧も濃い……特に夜目の利かん太刀のお二人は、十分お気をつけくださいね」
「七時半頃か……ではそろそろだな。皆俺についてこい。南庭まで参ろうぞ」
三日月の後に続き、国広たちもまた南庭へと向かう。
「あぁ」
「んじゃ、派手に戦いますかっと」
しかし、二歩進んだところで監査官に呼び止められ、何事かと振り向いた。
「……南庭はそっちじゃない。こっちだ」
「あなや」
その後は碌に会話すらままならないほどに忙しない一日を送った。
京都御所内の南庭での一戦の後、皇后門前にて新たな時間遡行軍を発見、そのまま排除。この日は午前中だけで合計八体の撃破に成功した。また、午後に出没するとされているのは残り八体とのことで、一同は一条通を経由し、次なる出現場所とみられる聚楽第の城郭前まで移動しつつ。道中で出くわした敵も着々と排除していったのだった。
――そうして迎えた夜。
「結界は僕と三日月さんで張っておくから、皆はゆっくり休んでね」
案内された宿泊部屋から青江が出ていく。
「こういった小手先の術は得意なのだ。何せ平安の爺だからな」
それに続き、三日月もまた懐から取り出した札を手に部屋を後にした。室内に残された者たちはというと、皆それぞれマイペースに寛ぎ始める。国広は主への報告があったため、まだ暫くは気を抜けないが。気持ち的にはさっさと風呂に入って、寝室に敷かれているふかふかの布団に今すぐ飛び込んでしまいたい気持ちであった。
「ひゃ〜っ! ひっれぇーなー!」
「じゃーん、貸し切り露天風呂ってね」
「うおー! 湯けむり掻き分けド派手に登場ってか!」
一条通から北方向へ少し歩いたところに、偶然にも割と繁盛していそうな宿を見つけた。外観は小奇麗で、人の出入りもそこそこある。夜の間もずっと明かりが灯っているため、面倒なものたちも引き寄せられにくい。また、連日の疲労から昨日のような野宿ではなく、ちゃんとした宿に泊まった方がいいだろうという話になり……そういった理由から、あれよあれよという間にこの宿に泊まることが決まっていたのであった。
「この宿で一番良い部屋らしいね。確かに、置いてある壺やら掛軸やらも、それなりに上等そうだ。源氏にあったものとは比べものにならないけど」
「髭切、あまり部屋を物色するな。壊したら主に迷惑が掛かるんだぞ」
つんつん、と壺を突いたり、掛軸の裏を捲ってみたりする髭切を、国広が窘める。
「大丈夫、大丈夫。うっかり壺を割ったりなんてしな……ありゃ?」
しかし、忠告したのも束の間、髭切が手に持った壺が滑り落ちた。
「だぁー! あっぶねぇー! 言わんこっちゃねぇ!」
床に衝突する寸前で太鼓鐘がキャッチし、何とか事なきを得る。しかし当の本刃がまったく反省の色を見せておらず、太鼓鐘と国広の焦りようをみて笑い始めたものだから、救いようが無かった。余談だが、蛍丸はとっくに服を脱ぎ散らかして露天風呂に行っている。あのマイペース刀その一め。
「あはは、危機一髪だったねぇ」
「笑いごとじゃねぇ!」
そこで、国広は部屋の中に監査官の姿が無いことに気づいた。
費用はすべて主持ちということで奮発してもらい、予め大きめの部屋を取ってもらっている。何かあった時のため、流石にそれぞれ個室に泊まるわけにはいかないので、勿論大部屋の雑魚寝になるわけだが、それはあの監査官も同じ条件なわけで。にもかかわらず彼一人だけ忽然と姿が消えていることに、胸騒ぎを覚えてならなかった。
「……」
「監査官なら外に出て行ったみたいだぞ。こんのすけも一緒だったし、政府に連絡でもしてるんじゃねぇか?」
「そうなのか」
「君は監査官殿のことが気になって仕方ないみたいだね」
「別に、そういうわけでは……」
ない、と続けようとした時、髭切の凪いだ瞳と目が合う。途端に気まずく思ってしまい、国広はそっと彼の真っ直ぐな目から顔を背けた。
気にならないと言えば、嘘になる。だって、こちらがいくら避けようとも、ひしひしと感じるのだ。あの布の下から、嘗て慣れ親しんだあの気配を。思えば彼に近づいた時に顔ってくる柑橘系の香りだって、足利にいた頃に嗅いだ匂いと同じだった。
「……大丈夫、すぐに帰ってくるよ」
「だから、俺は監査官のことなんてまったく気にしてない」
「ふぅん? まぁ、僕はどっちでもいいんだけどね」
結局その日の晩、国広が睡魔に負けて眠りにつくまでに、監査官が部屋に戻ってくることはなかった。
気にはなったが、好ましく思われていない手前、下手にこちらから話しかけることも出来ず。かといってあの深く布を被った状態では、顔色や表情など確かめようもなくて、彼が昨晩ちゃんと眠ったのかそうでないのかも判断がつかなかった。なまじ淡々とした口調で話す彼の声が、いつも通りに聞こえるのが質が悪い。異様に隠すことが上手いのだ。口も達つのでいいように誘導されている感が否めない。
(気にしないのが、一番楽……なんだろうけどな)
諦めたように目を伏せ、刀を握る。今の自分に出来るのは、少しでも敵を倒し、実力を知らしめ本丸の評価を得ること。任務遂行という目的を前に、余計な雑念は断ち切らなければならない。今の自分は、主の初期刀なのだから。
――くれぐれも無駄死にだけはしてくれるなよ。お前は俺の、俺だけの、特別な写しなのだから。
夢で見たあの言葉が、ぐるぐると巡る。
人の器の内側を揺蕩い、残響が波紋となって全身に広がってゆく。狂ったように繰り返される甘い呪詛が、国広を雁字搦めにしてしまう。逃れたいのに、断ち切りたいのに、もうすべて忘れてしまいたいのに。あの熱っぽい眼差しや恍惚とした笑みが、脳裏に焼き付いて離れない。
囚われている。あの日からずっと、自分の背後には必ず本歌の影が付き纏っていて、国広の気が触れるその瞬間を、今か今かと手ぐすね引いて待っている。あの冷たい青瑠璃色の瞳で見つめながら。嘲笑うような表情で、口元を歪ませて。
あの日から、そして恐らくこれからもずっと、国広は彼に囚われ続けるのだろう。
磨き上げられた玉鋼のような銀色の、冷涼な空気を纏った刀の付喪神。その掌の上で、玩具のように弄ばれるのであろう。
彼が本当の意味で国広を、その意識の範疇から消し去るその日まで。
*
聚楽第特命調査任務三日目は、激しい戦闘が続いた一日だった。
宿から出た面々は、まず昨晩通った一条通りへと戻り、そこで出くわした時間遡行軍と朝一番に一戦。後、日が落ちた時には調べようがなかった聚楽第の入り口部分を探った。太鼓鐘と青江で偵察を行ったところ、一番目立たないで侵入出来るとされた北外門は、既に時間遡行軍により門ごと潰されており、罠のことも考慮すると安全に通れるとは言い難かったため、北外門からの侵入は断念。その他、人の出入りが多く目立ちそうな南外門、西外門も選択肢から除くと、必然的に第一候補となったのは東外門であった。
「嫌な空気だ……」
さて、それでは早速東外門を目指して北へ下ろうか、と第一部隊が移動を始めた時。なんとこんのすけによる時間遡行軍の出現予測が頻発する。
「一条通沿いに敵四体の出現予測、その半刻後、油小路通より北に時間遡行軍八体の動きが観測されたとのことです」
「……やけに連続しているな」
「ふむ、あやつらも我らの動きを察したのやも知れんな。どのみち迎え撃つのみだ。返り討ちにしてくれるわ」
こうして、急遽国広たちは聚楽第城郭前から西へ戻り、油小路通へ差し掛かったあたりで敵と交戦しつつ、北へ下っていくこととなった。
後手に回る形となったことで序盤までは押され気味であったものの、何とか態勢を立て直し、聚楽第東外門のある下長者町通へと出る。それから暫くは時間遡行軍の猛攻に遭う彼らであったが、陽が落ちかけた黄昏時にして、ようやっと本日出現するとされていた最後の敵陣営と相まみえるところとなり、疲労困憊の身体を引き摺って抜き身の刀を手に取った。
「大太刀、太刀、打刀に短刀が、それぞれ一体ずつか」
偵察を終えた青江が、敵の数や陣形を報告する。
「……斬ればいいんだろ」
「大太刀は僕が相手をしよう。骨のある敵を斬りたかったんだ」
「フォローは俺に任せときな!」
時間遡行軍側は未だ国広たちの存在には気づいていない。先手必勝。敵が油断しているのをいいことに、国広と太鼓鐘、青江の三人が投石兵の刀装を展開させ、先制攻撃を仕掛ける。
「やあやあ我こそは……源氏の重宝、髭切なり!」
一番手こずるであろう大太刀は、髭切が力押しで完全に動きを封じてくれた。その後ろを取り、すかさず太鼓鐘が大太刀の頸目掛けて短刀を振りかぶる。太鼓鐘の不意を突いた攻撃こそ交わされてしまったが、あの分なら大太刀は彼らに任せておけば問題はないだろう。冷静に戦況を見定めながら逃げ果せようとしていた打刀に斬りかかった国広は、躊躇うことなくその心の臓へ切っ先を突き立てた。
しゅう……と黒い靄となり消える敵の最期を見届け、さて次の敵は、と周りを見渡す。
「山姥切!」
しかし、不意にドシュッと鋭く風を切る音が耳元で聞こえて、反射的に仰け反った。
「……ちっ」
腕が斬られていた。幸いにも胴から切り離されてはいない。繋がっている。ただ、思ったよりも深い傷のようで、指先に力が入らなくなってしまったのが厄介だった。加えて、やられたのが利き腕であるというのもまずい。
「まだだ……っ!」
敵短刀が再び襲いかかってくる。ガラガラと骨がぶつかり合う音を鳴らしながら、鈍く光を湛えた切っ先が眼前へ迫り来る。
(ここは一度腕をくれてやって……左手で斬りかかれば何とか……)
「山姥切、避けろ!」
腕一本を犠牲にする覚悟を決め、身構えたその瞬間、視界いっぱいにひらりと白布がはためいた。
「……っ」
キィン!
鋭い金属音が辺りに響き、血が沸騰する。ぐわっと込み上げる高揚感は、戦場独特の血の匂いのせいか、それとも刀のぶつかり合う悲鳴を耳にしたせいか。されど国広が突如得た高揚感は、そのどれのせいでもないのだと、本能が告げた。
ひらり。
また、布が揺れる。布が翻る度に裏地の鮮やかな青がちらつき、一閃を放てば美しい銀色が夜空に君臨する月光の如く輝いた。見間違えることなどありえない。あれは、堂々たる本歌の太刀筋だ。空気を断ち切る鋭利さと、舞を踊っているかのような優雅さ。実際に彼が戦っているところを、国広は数える程度にしか見たことがない。それでも、わかった。わかってしまった。理解すると同時に、もう居ても立っても居られなくなった。
「ぼうっとするな! お前は鈍か!」
「っ!」
「この俺の前で無駄死には許さない! さっさと片付けろ!」
ハッと目を覚まさせる一喝に、身体が動く。息が乱れた。こんなに興奮した状態で戦に挑んだのは、現世に呼び出されてから初めてだ。
「がっかりさせるな……!」
「……っ言われなくても!」
痛む右手を耐え、左手を支えにしながら全力で振り抜く。すぱん、と小気味が良い音を立てて、山姥切国広の刃が敵短刀を真っ二つに両断した。カラカラ、と軽い音を立てて転がり落ちた残骸が、どす黒い瘴気を放ちながら消えてゆく。これで今日の殲滅対象は最後。日はまだ昇っている。しかし、落陽は時間の問題だろう。
完全に日が沈み、太刀たちが弱体化する前に、傷ついた身体を癒さねばなるまい。
「山姥切……っ」
色々とやらねばならないことは残っている。だが、それよりも兎に角、彼と話したかった。
(なんで俺を庇った?)
監査官という立場を放り出して、何故戦いに手を出した。俺を鼓舞した。あれほど拒絶しておいて、どうして今更……。
「やま、」
「さて、一体誰と間違えているのかな、初期刀くんは」
次々と溢れてくる感情を制御出来ず、はくはくと口を開閉させる。きっと、傍から見れば地に投げ出された魚みたいで、今の国広の姿は酷く無様であったことだろう。そんな己を自覚しつつも、形振り構わず関わりたいと思ってしまうのは、写しとしての性か。あんなに、もう期待なんてしないと散々絶望したはずなのに。
「あんた、山姥切なんだろ。俺にはわかる……!」
頑なに距離を置こうとする監査官を追い、離れた分だけ一歩、また一歩と国広は距離を縮めてゆく。
「だから、君が何を勘違いしているのかは知らないが。俺は政府の監査官だ。いい加減にしてくれないかな」
「何故俺の前に姿を見せてくれない……あの時だってそうだった! 俺が、俺が不出来な写しだからか……?」
「意味がわからない。話にならないな」
「……っ待ってくれ!」
国広の制止も虚しく、監査官の男は足早にその場から立ち去ってしまう。尚も追い縋ろうとした国広を止めたのは、ドロン、と白煙を上げて登場したこんのすけだった。
「監査官の顔や名前を教えるんは、政府の規定に違反しとります。山姥切国広様、お収めくださいませ」
「退け」
暫しの睨み合いが続き、不穏な空気が漂い始める。今の国広は、戦の後ということもあり、冷静さを欠いていた。気が高ぶり、衝動のままにカチッと鯉口を切ると、それまで大人しく国広たちの様子を見守っていた三日月が、素早く国広の右手を掴む。
「これこれ山姥切や、乱暴するでない。あちらにも色々と都合があるのやも知れぬ。あまり詮索してやるな」
元より怪我をしていた利き手だ。少し力を込められるだけで、簡単に動きは封じられた。
「……」
「本丸の評価が下げられてもよいのか? 主が悲しむぞ」
「……悪かった」
そこまで言われてしまえば、引き下がるしかない。
「少し頭を冷やしてくる」
ぐっと唇を噛み締め、柄から手を離した。布を深く引き下ろしてから、国広は三日月たちに背を向け歩き出す。
本来ならば過去の時間軸で単独行動は取るべきではないが……今の国広は一人にしてやった方がいいだろう。それに、それぞれの居場所は、霊力を辿れば大体見当がつくし、問題はない。そう判断した面々は、とりあえずここらで泊まれそうな宿を探すことに決めた。何せ今日は昨日よりも連戦続きだったのだ。国広を含め、怪我を負っている者もいる。夜も近いし、早く安全な場所で身体を休めたい。
「あやつも難儀なことよの……」
「慰めてあげれば良かったのに」
あっけらかんと言う蛍丸に、三日月が苦笑する。
「そうさなぁ……だが、こればかりは自分でどうにかせねば意味がないからな。それに、本当に慰めが必要なのは……」
――所変わって、聚楽第東外門前。
「正体を教えてあげなくていいのかい」
「……君は、」
本当なら無視してしまいたいだろうに、律儀に反応を寄越してくれる監査官に、青江はにっかりと笑む。
「ああ、僕はにっかり青江。これでも女の霊を斬ったと言われる霊刀でね。だから色々と見えるのさ。例えば、その歪な『縁』の糸とか……」
布の下から覗く、血で染め上げられたかのような赤黒い糸。男側に向けて黒ずんでいっているあたり、彼が抱く想いの深さや複雑さは尋常じゃないことが伺える。また、糸の伸びる先の方を目で追えば、それは徐々にか細くなっていっているようで。今までに切れてしまいそうになったことが多々あるのか。途中、無理矢理結び直したような硬い結び目が、いくつか確認出来た。
(うーん、拗らせてるねぇ)
先へ行くほど多くなる、数多の結び目。それらは、向こう側の者が糸を断ち切らんと足掻いた証でもある。それをわざわざ結び直すということは、つまり……まぁ、言葉にせずとも大体の想像がつくというものだ。
「なるほど。ならば、俺が誰なのかは君にはすべてお見通し、ということかな」
「うんうん、そういうこと。それでね、全部事情をわかった上で君たちを見ていると、どうにも不思議でならなくてね……彼は君の大切な子なんだろう。もう少し、彼の心労を汲み取ってやることは出来ないかい? とても心配していたよ、君のことを。ずっと眠れていないんじゃないかって」
「大切……? まぁ、俺の一部のようなものだからね。間違いではない、かな。ただ、勘違いしないで欲しい」
振り返り様、布の下から飢えた獣のようにギラついた青瑠璃が覗いた。すべてを見透かしてしまいそうな強い眼光は、成る程確かに絶対の自信が見て取れる。己が本歌たる自負を、伝説を持っていることへの誇りを、ひしひしと見る者に知らしめてきた。まるで「俺を写しと侮ったことを、後悔させてやる」なんて言いながら敵陣に突っ込む時の隊長のようだ、なんてことは口が裂けても言わない。言ったら最後、この場で叩き折られそうだからだ。
「俺とあいつはね、ただの本歌と写しの枠組みに甘んじることなど許されない……謂わば互いを喰らい合う存在だ。そんな相手を《大切な子》なんていう甘ったるい認識でいるほど、俺は愚鈍ではないよ」
「じゃあ、君は何故そんなにも必死になって、その糸を結び直してるんだい? おまけに断ち切られた分だけより太く……お熱いことだ。結構な執着じゃあないか」
青江の指摘をものともせず、男はハッと鼻で笑い飛ばしてみせる。それがどうした、そんなことで動揺を誘ったつもりか、と。どこまでもこちらを煽るその態度に、されど青江は苛立つこともなく。ただ純粋な好奇心から、男からの返答を待つ。
「……俺の誉を証明するが為に生み出された、俺の写しが。己の本分も忘れて薄情にも独り立ちしようとしたからだよ。確かにあれは、今や独立して在ることが出来るようになるほど力をつけた、正しく名刀だ。しかし、あれは俺と在ってこその存在。散々俺から号も、逸話も、何もかもを奪っておいて、今更この縁を断ち切り自由の身になるだと……? そんな勝手を、この本歌たる俺が許すわけないだろう?」
――写しとしての在り方も忘れたあんな刀、せいぜいが偽物くんってところかな。
あの卑屈の塊のような刀には到底聞かせられない暴言を吐き捨て、男の反論は締め括られる。
「なるほどねぇ」
予想以上に拗れているようだ。とはいえどうにも質が悪い。揺るがぬ矜持の上に成り立った絶対の自信は、自分が間違ったことは何一つ言っていないのだと、本気で思っている証拠。そして、そんな男の勝手に振り回されている彼のことを、この男は歯牙にもかけない。何故なら、写しとはそう《在るべき》だと信じているから。
(何とかならないものかなぁ)
青江が初めて彼――山姥切国広を見た時、それはそれは驚いた。
国広の首の周りにぐるりと巻き付いた赤黒い糸が、今にも彼を絞め殺してしまいそうで、あんまり窮屈そうなものだから勝手に断ち切ってやろうか、なんてことを思ったこともあった。しかし、本丸生活の中で彼と接するにつれ、青江はその糸の存在を《言霊による束縛》だと当たりをつけた。そのため、暫くの間様子見に徹することを決めたのだ。
つまり、彼自身がよく言葉にしている「俺が写しだからか」「写しの俺なんかが」という卑屈な言葉たちが、彼自身を締め付けているのだと、てっきりそう考えていたのである。
(それがねぇ……)
それが、まさか彼を雁字搦めにしている存在が彼の本歌だなど……誰が想像出来るだろうか。ましてやあの糸は国広だけではなく、目の前の男自身の首をも締め上げているときた。互いに締め付け合い、互いに苦しめ合う。それでも、糸を断ち切ることは許されない、この男が許さない。嘗て本歌と写しとして生み出されたものたちの中で、これほど歪で危うい縁を結んだものがいただろうか。
「わかったらさっさと宿に戻ってくれないかな。別の気配があるのでは、俺の気が休まらないんでね」
話はこれで終わりだ、とでも言うかの如く、男は青江に背を向ける。
「はいはい、夜分にすまなかったね。来たくなったらいつでも寝に来てくれていいからね。あぁ、夜のお誘いも大歓迎……添い寝のことだよ?」
「寝言は寝て言ってくれ」
これ以上は何を言っても無駄だと察し、青江はあっさり踵を返した。第一部隊の面々は既に休まる場所を見つけたようで、感じられる霊力は落ち着いたものに変わっている。しかし、霊力を辿れば容易に彼らの元には辿り着くとわかっていて、青江は敢えて宿の方向とは逆方向に向かって歩き始めた。彼らと合流する前に、一人別行動をしているらしい、あの不器用で繊細な刀を拾っていかねばならなかったので。
「……」
ふ、と気になって後ろを見る。すると、男がくるくると巻き付いた糸を、それはそれは大事そうに撫ぜていた。その表情は白絹に隔たれ見えないが、さぞ甘ったるい顔をしていることだろう。あの指先の動き一つで、そんなことは容易に想像出来る。
「……愚かな子だ」
見なかったことにしよう、全部。だって、馬に蹴られたくない。
だからこそ背中越しに聞こえた、甘い響きを有した声には、聞こえないふりをしてやった。