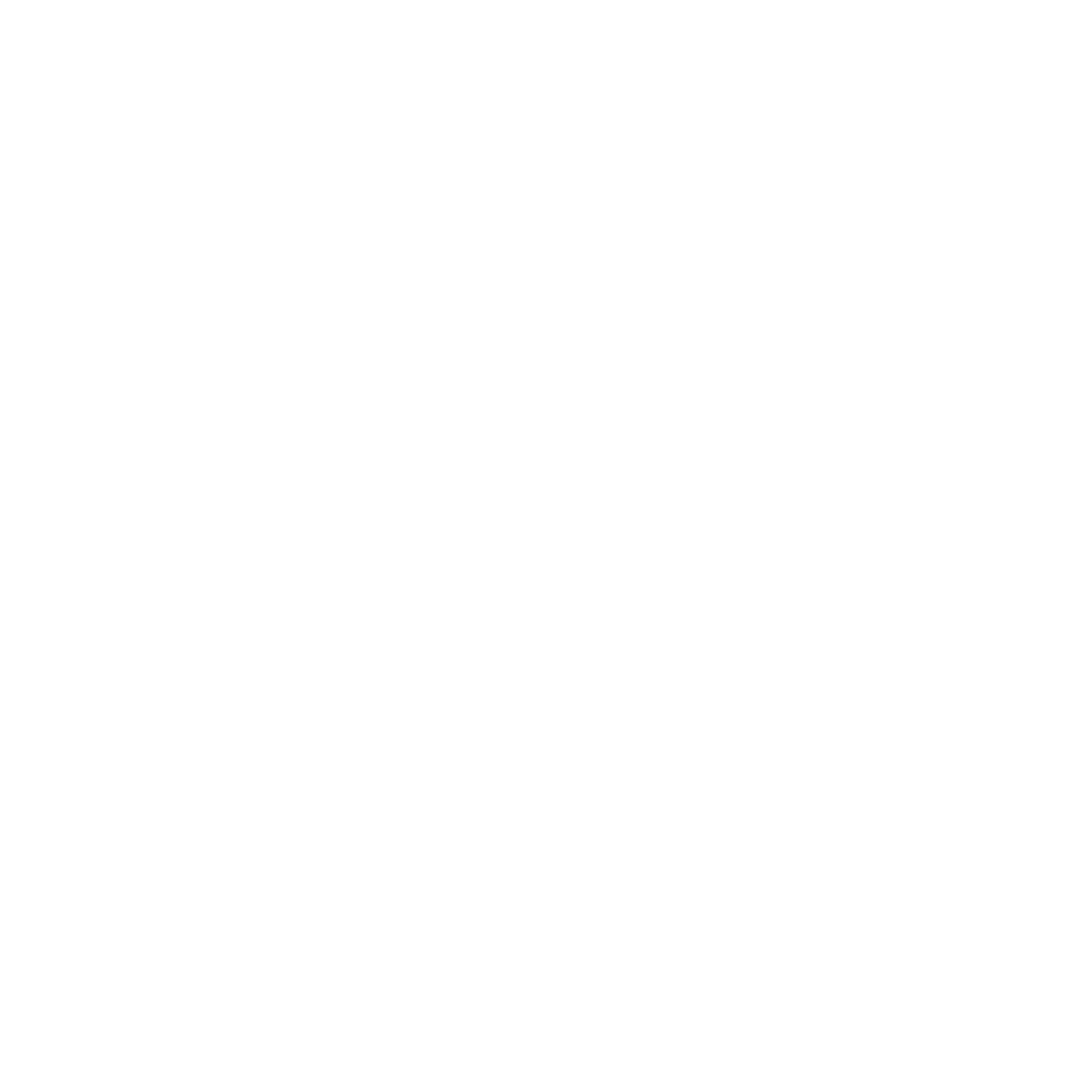第三話 聚楽第
三日目こそ激戦を極めた聚楽第特命調査であったが、四日目の洛中最終日はあっさりとした幕引きとなった。そう感じたのは偏に、交戦した時間遡行軍の数が八体と少なかったというのと、戦闘を終えた午後からの主な任務が北条氏政の捜索という、比較的穏やかなものであったが故だろう。加えて聚楽第東外門を守っている敵方の実力も、偵察によりそれほど強くないことが判明し、滞りなく聚楽第内部へと渡る準備は整えられた。よって、幾分か聚楽第内部への侵入まで余裕の出来た国広たちは、新たなる戦さ場に備え、洛中にて暫しの暇を与えられることとなったのだった。
「完全に占拠されておるのだなぁ」
聞き込み調査を兼ねて二手に分かれ、あちこちの店で茶を飲んでいた時のことだ。国広と同じ班となった三日月が、唐突にぼやいた。
「まさか三桁とはね。あの管狐くんから二四〇体と聞いた時は流石に驚いたなぁ」
「……一度は放棄された時間軸だからな」
茶屋で出された団子を食しつつ、大して驚いてもなさそうな声で言った髭切へ、国広は返す。
「どれだけ敵が多かろうと、斬ればいいんだろ。やることは変わらない」
「はっはっは、山姥切の言う通りだ。我ら刀のすることは、目の前の敵を斬り伏せるのみよ」
「そうだねぇ」
今は、監査官は国広たちと行動していない。国広たちに暇が与えられたと同時に、彼は政府への報告があるとだけ言い残し、こんのすけと共に何処かへ行ってしまったからだ。
監査官が国広たちに干渉したのは、後にも先にも国広が右腕に深手を負った、あの時だけであった。あれ以来、彼の戦うところは見ていない。夜になってもまたどこぞで一晩を過ごし、何食わぬ顔で朝になって現れた彼は、まるで自分は今後一切こちらと関わるつもりはないのだと告げるかのように、頑なに一定の距離を保つようになっていて、事務的な接し方を徹底するようになった。
心なしかこんのすけの監視が厳しくなったように思われたのは、きっと気のせいではないのだろう。あの管狐は確実に、国広たちだけでなくあの監査官すらも監視の対象としている節がある。おかしなことだ。自ら刀剣男士に監査官などを任せておきながら。政府が何を考えているのか、国広にはさっぱり理解出来ない。
(これも俺が写しだからか……)
嫌な予感がする。根拠はないが、読めない政府の動きといい、突如あてがわれた聚楽第特命調査といい、このままだと何か、取り返しの付かなくなる事態になるような……。
「お、これはなかなか」
ぐるぐると巡る思考が、唐突に割って入ってきた声に遮られ、何気なく目の前の皿を見下ろす。すると、いつの間にか三つの団子が乗った皿が空っぽになっていた。楽しみにとっておいたみたらしが無いことに気づき、まさか、と思い隣を見やると、丁度それを食べ終えたらしい三日月が、指先についたタレを舐めとっているところであった。
「……おい」
ひくひく、と頰が痙攣する。
「む?」
「……それは俺のだ」
「要らぬのかと聞いたぞ」
「聞いてない……っ!」
バンッ!
縁台を叩く。ざわっと周りの目がこちらに向いて、気まずさから布を引き下ろした。それもこれも全部このマイペース太刀のせいだ。
「……楽しみに取っておいたんだ」
地を這う声に、我ながら食べ物の恨みの深さを悟る。しかし、三日月とて悪気はなかったのだろう。彼は僅かに目を見開くと、眉尻を下げて申し訳なさそうな顔をした。美しい顔はこういう時に武器となる。怒りを削がれた国広は、今度は子どもっぽい理由で癇癪を起こした己を恥じた。
「あなや、難しい顔をしていたから腹でも痛いのかと思ってな。すまなんだ。どれ、それならもう一つ頼んでやろう」
「もういい……あんたに悪気は無かったんだろ……、」
――国広の、俺の分をお食べ。この本歌が、俺の写したるお前に施しを与えてやろう。
バツン、と頭の中で何かが弾けた。
懐かしい記憶だ。足利城の庭先に咲く桜を眺めながら、縁側で本歌と過ごした優しい思い出。主は信仰深く、敗戦の色が濃かった北条に最後まで従い続けたほど、何事にも義理を通す主義のお人であった。そして、一介の物であった国広たちにも、度々供え物をしては話し掛けてきてくれた。やれ、戦が近い。小田原は無事なのか。自分の名代として小田原に向かわせた兄弟は無事か、と。何度も、何度も。
やがて、桜が散り、夏の気配が近づいてきた七月頃。いよいよ俺がお前たちを振るうことになるやも知れん、と。顕長は度々刀掛台に置かれていた国広たちを撫でた。近づいてくる初めての戦の気配に武者震いし、血が騒いだのを覚えている。
「山姥切や、どうした……?」
「そうか……」
何となく、この聚楽第で何が起きているのか理解してきた。時間遡行軍の狙いも、政府が何をしたかったのかも、何故監査官として本歌が派遣されてきたのかも。
なんだ、簡単なことだったのだ。
「三日月、髭切」
「ん?」
「至急、青江たちと合流する。この聚楽第占拠で時間遡行軍が何を狙っていたのかわかった」
すく、と立ち上がり、言う。
もう国広の目に、迷いは無かった。翡翠の瞳のその奥で、戦を前に沸き立つ闘争心の炎が、ゆらゆらと揺らめいていた。
一方その頃。
青江と太鼓鐘、蛍丸の三振りはというと、城郭近くの下長者通に面したところで万屋を営んでいた老夫婦に、ここ最近不審な者がいなかったかどうか話を聞いていた。
「せやなぁ、洛外んとこで鬼が出たぁ言うから、興味本位で見に行こかって、そこの武家屋敷に住んではる若旦那と話しとったんです。まぁ、若旦那も忙しい人やから、結局そのまま流れてしもうたんですけどね……」
「なるほどねぇ」
にっこりと人好きの良い笑みを浮かべた店主だが、何となく腹に一物も二物も抱えていることは察せられた。京都特有の排他的な空気と言えばいいのか。話し言葉が異なる青江に対し、綺麗に一線引いてみせた男は、なかなかの食わせ者であることが伺える。
ここは明石あたりを連れてきた方が良かったかな、なんて後悔しつつ。青江は早々に撤退する方向で考え始めた。
「にしても、あんさんらええ刀持っとりますなぁ……」
不意に、店主の目が、腰に携えられた本体へと注がれる。
「ふふ、ありがとう。これは僕の自慢でね。命よりも大切なものなんだ……」
感心した声を上げる店主に、少し自慢げな声で青江は返した。命より大切なもの、と聞いた店主は一瞬面食らった顔をしたが、すぐに相好を崩すと満足げに頷く。
「青江ー、買い物終わったよ」
そこで丁度タイミング良く、万屋の奥方と話していた蛍丸と太鼓鐘が呼びに来た。彼らは何やら土産でも買ったのか。小さな買い物袋をそれぞれ手にしている。さて、特に得られるものも無かったことだし、ここが駄目なら他の場所で聞き込みを続けるか、と。頭を切り替え、青江は次の聞き込み場所について思いを馳せた。
「ん、じゃあ行こうか」
ぷらぷらと楽しげに買い物袋をぶら下げた彼らと合流し、そのまま店を後にしようと出口に向かい歩き始める。だが、そんな青江たちを突然店主が引き留めた。
「あ、お侍さん! ちょいとお待ちを……」
やけに焦った様子の彼に首を傾げていると、「お耳を」と促され、言われた通り耳を近づける。そして、店主は不審がっている奥方に目配せした後、そっと強張った声で耳打ちしてきた。
「……聚楽第の中には鬼が出る」
「……っ」
単純に驚いた。まさか、余所者と判断された自分たちに店主が事情を話すなんて夢にも思わず。つい、どうして、と呟きが漏れてしまう。
「若旦那が気ぃつけろって忠告してくれはったんや。他の武家屋敷に住んではるお侍さんたちも皆そう言うて、自分らが何とかするから、それまで何があっても聚楽第には入るなってな……あんさん、悪いことは言わん。そういうわけやから、ここらのもんは皆んな余所者を警戒してはる。面倒ごとに巻き込まれる前に、早う自分のお国に帰りなされ」
「……君、どうして僕にそんな話を?」
青江に問われた店主は、ニカッと白い歯を見せて豪快に笑った。きっと、こちらの方が本来の店主の笑みなのだろう。先ほどまで見せていた繕ったそれとは、受ける印象が雲泥の差であった。
「これでもなぁ、自分の目利きの腕に自信があるんですわ」
くい、と。顎で示されて言われる。その刀、見たことは無いが名刀なんやろ、と続けられ、何の忖度も無い心からの賛辞に柄にもなく照れた。
「えらい引き留めてしもうて、すんませんでしたな。またご贔屓に〜」
件の万屋を後にしてから、急遽国広たちと合流することに決めた青江たちは、彼らの霊力を辿り西に向かって歩き出した。
途中、何の話をしていたのかと蛍丸たちに問われ、青江は店主に言われたありのままの言葉を伝えた。そんな内容に対し、一番に返答を寄越したのは、聚楽第の内部の鬼とは十中八九時間遡行軍のことだろう、と素早くあたりをつけた太鼓鐘だった。
「しっかしまぁ、今回の時間遡行軍はちっとばかし派手にやり過ぎな気がしないでもねぇ」
確かに、と思う。今までの時間遡行軍は、大っぴらに過去の人の子たちの前に姿を現わすことはなかった。基本的には間接的に歴史へ関わり、当時生きていた人の子を使って、正史を歪ませる。それが、奴らの常套手段と言えた。それがこの時間軸だと完全に聚楽第を占拠していて、堂々とあの中を闊歩している。
「……」
この差は一体なんなのか。どうして、この時間軸だけこんなにも大規模に動いている? 特命調査を始めてから四日。その全容を、青江たちは一向に掴めていなかった。
「何が狙いなんだ?」
「さぁ……ただ、あちらも今まで以上に必死、ということだけはわかるかなぁ」
もしかすると自分たちは、うん十年と続けられてきた時間遡行軍との戦いにおいて、大きな変化の節目に立たされているのかも知れない。そんな予感をひしひしと感じながら、青江たちはあーだこーだと意見を出し合い、考察を続けるのだった。
*
明日からはいよいよ聚楽第内部へ入る。
その前準備のため、第一部隊の面々は城郭の傍にある宿へ泊まり、情報共有及び戦準備の再確認に努めていた。例に倣って監査官はいない。今日もまた、国広たちとは別の場所で一夜を明かすつもりらしい。しかし、相変わらずの徹底した避けっぷりに、国広が何かを思う暇もなく。怒涛のように毎日が過ぎていくものだから、正直気持ちの面では楽だった。
「聚楽第内部にいる時間遡行軍の数は二四〇。敵は中心部へ向かうにつれて強くなり、身体を休める場所も少ないため連戦が予想される。皆、勝栗は各々所持しておいてくれ。もしかすると戦闘時に分断される可能性もある」
「あいわかった」
「はーい」
勝栗を配りながら言う国広に、皆が返事をする。
こんのすけの報告によると、北条氏政は聚楽第の中心部にて時間遡行軍と共にいるようだった。彼が正気を保った状態なのかどうかは置いておいて、今あの男を殺されるわけにはいかない。何としても北条氏政を奪還し、彼の身に起こった仔細を聞き出さねばならなかった。それは例えば、時間遡行軍と接触した鮮明な時期だとか。もしくはここへ至った目的だとか。
「青江が万屋の店主から聞いた話も含めて考えると、聚楽第内の武家屋敷に住む武士たちは、既に何らかの方法で無効化されていると思っていいだろう。武士たちが店に来なくなって、それなりに時が経っているんだったな?」
「少なくとも二週間はね」
頷きながら、青江が答える。
「聚楽第内部は、正直言って未知数だ。僕もあの後式を飛ばしてみたり色々としてみたんだけど、何か強力な結界が施されているらしくてねぇ。全部は見えなかったんだ」
一同は一斉に押し黙る。戦は情報戦だ。前もって対策を取れないのは不利である。既に時間遡行軍の狙いに見当がついている国広としては、相手の目的が目的なため、どんな些細なことでも相手の動きを知っておきたいというのが本音だった。暫くどうしたものか、と皆で頭を突き合わせて考えていれば、本体を手入れしていた太鼓鐘が、不思議そうに言う。
「でもよぉ、こんなになるまで放棄されてたってのに、政府はなんでまた今になって取り戻そうとし出したんだろうな。ここまで侵略を許したんなら、封じておくのが一番だろ?」
降って湧いた疑問に、一部の者たちの顔が国広の方へ向く。一部の者、というのは先ほどまで行動を共にしていた、三日月と髭切だった。その、どこか真剣な彼らの眼差しに応えて、国広はそれまで考えていた己の考察を語り始める。
「恐らく、何処かの時空に存在する俺に影響が出たんだと思う」
ざわり。無音の中、空気が揺らぐ。
「山姥切の、それがそなたが先ほど申しておった、時間遡行軍の目的とやらか?」
「なんだって?」
三日月の言葉に青江たちが反応し、国広を注視する視線にますます怪訝な色が強まった。途端に居心地悪くなってきて身動きしつつ、国広は尚も言葉を続ける。
「あぁ……これは俺の推測だが、」
山姥切国広は、丁度この一五九〇年の二月に、本歌である山姥切長義の写しとして作刀された。それは、丁度今から一か月後にあたる。生まれた場所は長尾顕長が城主を務める足利城。国広の元主はこの頃北条家に従属する武将だった。だから例えば、北条氏政が今この場所で殺されたとする。本来七月に無条件降伏してから討たれる筈のあの男が、今討ち取られてしまえば、北条側だった顕長だって、無事では済まない。本来小田原征伐に向かう筈だった数多の軍勢が、虱潰しに同盟を結んでいた武将の拠点に……足利に向かう可能性もある。そうなったら顕長たちはひとたまりもなかったし、国広も……最悪苛烈を極める戦いの中で折れてしまったかも知れない。あの頃、共に城にいた本歌の山姥切共々。
「なるほどなぁ。その話が誠であったとすると、ちとまずいな」
「……?」
そこまで聞いていた三日月が、眉根を寄せて低く唸る。
「今まで時間遡行軍は間接的に歴史に関わり、正史を捻じ曲げるだけだった……それが、俺たちの本体に干渉することで、本格的にこちらの戦力を削ぐ作戦に出たわけだ。これはもしかすると……」
「何十年と続いてきた戦の形が、一気に変わる時が来た……ということだね」
「な、」
各々の間に緊張が走る。時間遡行軍がついに、刀剣男士たちの本体へ矛先を向けてきた。これは、こちらにとってはダメージが大きい上に、かなり急を要する事態だ。
「山姥切や、この聚楽第任務、最早お主たちを守るためだけの戦いではない。現代に顕現しておる刀剣男士たち……ひいては未来に顕現されることになる者たちすべてを守る戦いだ。まぁ、俺がいるからには好きにはさせんがな」
三日月が、強気に口端を吊り上げて笑う。
「何だかえらい話がでっかくなってきやがったなぁ。へへ、俄然やる気が湧いてきたぜ!」
手入れの終わった本体を掲げ、太鼓鐘が陽気に吠えた。
「よくわからないけど、鬼だろうが何だろうが、斬ればいいんだね?」
「ぜーんぶ、俺が薙ぎ払っちゃうよー」
「悪い子にはお仕置きが必要ってね」
髭切、蛍丸、青江と続き、国広はぐっと。掌を握り締める。
「あぁ……」
頼りになる仲間たちの未来。そして、積み上げてきた過去。俺は、そのすべてを守るためにここにいる。
「守ろう、歴史を」
――その夜、国広はなかなか寝つけなかった。
これまでなら疲労からすぐに夢の世界の住人となっていたのだが、今晩ばかりはそうもいかない。刀としての本能か。明日の戦のことを思うと血が騒ぐし、この特命調査任務に自分と本歌の命運……それどころか全刀剣男士たちの生死が掛かっていると思うと、昂ぶる気持ちを抑えることが出来ない。
気を紛らわせるために何度も寝返りを打ったり、瞼を瞑り無理矢理羊の数を数えたりとしてみたが、何の効果も得られず。ひたすらに続く静寂と暗闇に焦燥ばかりが募っていった。
(明日から大事な戦が続くというのに……)
眠らなければ。そう思えば思うほど、眠りから遠ざかってゆく。いよいよ限界に達し、外の空気でも吸いにいくか、と上半身を起こした時、
「山姥切や、起きておるか」
隣に敷かれた布団から、のんびりした声で急に話しかけられた。
「三日月……起こしたか」
声の主は三日月だった。いつもならさっさと寝落ちている彼にしては、こんな時間まで起きているのは珍しい。一体どうしたのだと暫く様子を伺っていると、クスクスと笑い出した彼が声を潜めて囁いた。
「いいや、何だか眠れなくてなぁ。お主もか?」
「あぁ……」
「どうだ、眠れぬ者同士、少しばかり話でも」
「……別に、構わない」
そこから二人は取り留めのない話をした。本丸に顕現された時のこと、出陣先で起こった面白い土産話。誰かと話して幾分か落ち着いたからだろうか。やがて自然と溢れ始めた欠伸に、ようやく眠気が訪れたことを悟る。
「……山姥切は本歌殿と足利で共に過ごしたことがあると言っておったな」
「ん……短い間だったが」
トロトロと回転の鈍くなった頭を動かして、三日月の質問に答える。
「本歌殿はどのような御仁であったのだ? なに、ただの爺の好奇心だ。少しばかり気になってな」
本歌、本歌か。
足利で共に在った頃の彼は、今とは似ても似つかないほど優しい神だった。何かと与えたがり、口を開けば己こそが本歌だからと、その写しである国広に教養を身につけさせようとしてきて。移り変わる季節を彩る花の名前、戦いの作法、刀としての心構え……色んなものを、彼から教わった。
彼のハッと目が覚めるような太刀筋を見るのが、国広は好きだった。彼は事あるごとに写したるもの、とあらゆることを強制してきたものだが、写し以前に自分は刀。優しくしてくれた本歌自身に、というよりは本能的にあの美しく堂々たる太刀筋の方に惹かれるものがあったのだろう。庭先でこっそり彼の真似をして刀を振るっていると、そんな国広をどこかから見ていた本歌がやって来て、手ずから構えを教えてくれた。それも、今では良い思い出だ。
「……俺はあの頃は生まれたばかりで不安定な存在だったから……詳しいことはあまり覚えていない」
「……」
「覚えていないが……あの頃が一番、楽しかったのだと……おもう」
そう、楽しかった。あの頃の彼と過ごす時間は、確かに楽しかったのだ。ただ、あれから長い年月が経ち、人の子たちの語る逸話に振り回され、本歌との比較の言葉を浴びせられ続けたことで、色々と彼へ向ける感情は変化してしまったけれど。
あの頃の思い出が温かかったことだけは、そっと胸の中に刻まれている。
「……長い刃生だ。一緒に展示されることはなかったのか?」
「確かに一度だけあるにはあったが……本歌は展示中はずっと刀のままで、会ってもらえなかった、から……」
「そうか……それは、寂しかったなぁ」
「さびしい?」
国広は問うた。寂しい、という言葉に、どうにも違和感を覚えたからだ。
「うむ。お主は会いたかったのだろう? だが、本歌殿が顔を見せてくれぬものだから、寂しかったのではないのか」
寂しい、とは違う気がする。だってあの時、国広は酷く納得したのだ。彼は己の写しに対して求めるものが、とても大きかった。生まれたばかりの国広へ、手ずから作法や刀の振るい方を教えてくれるくらいには、目を掛けられていた自覚はあるし、実際期待もされていたように思う。その反面、彼はどこまでも《物》であったから……期待にそぐわぬ働きを見せたが最後、冷酷に見放されるのだろうな、とは当時から覚悟していたことだった。
「俺は……当然だと思っていた。俺は、あいつの期待に答えることが出来なかったから……あいつが求める従順で美しいだけの《写し》になれなかったから……でも、当たり前なんだ。だって俺は、確かにあいつの写しだが、それ以前に国広第一の傑作なんだから……だから、俺は……」
行燈の明かりは、いつの間にか消えている。
沈黙が降りた。誰かの寝言が響き、すぅーっという穏やかな寝息が空気を揺らした。光も何もない暗がりの静けさは、耳に痛く。再び得も言われぬ不安が膨らみそうになり、目を瞑った。
「……色々と、あったのだなぁ」
そんな静寂を破ったのは三日月だった。
「だが、お主がどれほど本歌殿に想われていたのかはわかったぞ」
「は、……?」
話を聞いていたのか、と言いたげにジト目で睨め付けてやると、月の名を有しているくせに夜目の利かない太刀が、素知らぬ顔で言い募る。
「付喪神は形を成すだけでも九十九年掛かる。その定説を打ち消してしまえるほど、お主は本歌殿に想われて生まれたのだ。でなければ打たれて間もないお主が付喪神として形を得る道理が無い」
「それは……だが、本歌はあの時、俺の呼び掛けに応えてくれなかった……きっと不出来な写しだと失望して――」
「顔を見せてくれなかった、ねぇ。もしかすると、見せられなかった、のかも知れないよ」
びくっ!
布団の中で飛び上がった。急に三日月以外の声が割り込んできて、純粋に驚いたのだ。
「……え、」
「さ、明日は早いんだから。夜に二人してイチャイチャしてないで、もう眠りなよ……おやすみ」
「イチャイチャって……誤解を招く言い方を……、おいっ」
突然の乱入者は、言いたいことだけ言って自分だけ寝入ってしまった。一体何なんだと思いながら三日月の方を見ると、彼は最後に口だけで「おやすみ」と告げ、乱入者同様早々に目を瞑って寝る体勢に入ってしまう。必然、置いてけぼりにされた形となった国広は、今ひとつ腑に落ちないものを感じながらも、先ほどまで傍にいた睡魔を呼び寄せるべく、布団を頭まで被り直した。
――見せられなかった、のかも知れないよ。
青江の言葉が脳内を巡る。
見せられなかったとは、どういう意味なのだろう。考えたところでわからない。その後暫く眠気に抗ってうんうん唸ってみたが、結局半分眠りの縁に落ちた鈍間な思考回路では、納得のいく答えを見つけることは叶わなかった。
*
全三十五戦。
実に十日ほどかけて聚楽第内で交戦した数である。東外門の守りを破り、一気に突入した第一部隊はその後、聚楽第城郭内にて次々と時間遡行軍と応戦。途中、重傷者こそ出たものの勝栗による回復で持ち直し、何とか本丸手前・南二ノ丸まで駆け抜けた。
北条氏政は家臣たちの居住区とされていた一画の、浅野長政の武家屋敷にて発見された。混乱は大きいものの、五体満足、意識もしっかりしており、幸いにも無事であった。聞けば、彼は小田原城の寝所より寝ていたところを誘拐され、気がつけばこの武家屋敷の座敷牢に閉じ込められていたのだという。また、調べを進めていく中で、今回の事件の首謀者は浅野長政……ではなく、その家臣であった浅野氏重であったことも判明し、北条氏政の身柄は時期を見て出陣前の秀吉へ差し出される予定であったことも明らかになった。
「三月程前に時間遡行軍の一人と接触した氏重は、奴らに浅野家の手柄になる良い話があると仄めかされ、北条氏政誘拐の案に協力。人が滅多に訪れない座敷牢を提供し、時間遡行軍が連れてきた男が北条氏政本人であることを確信してから、当主である長政へ報告するつもりだったらしい」
毎夜恒例の国広による事情説明に、太鼓鐘がはぁ〜っと深いため息を吐く。
「危なかったなァ。あと一日でも見つけるのが遅けりゃ、秀吉公に打ち首にされてたぜ」
「何はともあれ、正確な歴史改変の起こった時期も聞き出せてよかったよ。じゃないと皆斬っちゃうところだった」
「いや、斬るなよ!」
北条氏政の一件については早急に政府へ報告するとして。明日は日が昇る前から聚楽第本丸へ太鼓鐘と青江、国広の三人で赴き、敵数や本丸の占拠状況などを確認することになっていた。偵察が終われば陣形などを打ち合わせて、本格的に突入となる。一山越えたとはいえ、まだまだやることは山積みだ。自分たちの本丸に帰るまで、休んでいる暇はない。
「山姥退治なんて、俺の仕事じゃないんだがな……っ」
ちくり。
胸の奥に棘が突き刺さったような痛みが走り、顔を歪める。次いで指先に痺れのようなものを感じて、掌をゆっくり開閉した。動かす分に支障はない。疲れか、それとも今まで気を張っていたことへの反動か。暫く様子を見ていれば痺れは収まったので、そこまで深くは考えず放置した。
「んじゃ、隊長。明日の偵察はよろしくー」
ざっと見回すと、全員の回復は済んでいるようだった。戦装束を解かぬまま眠るのも、これで最後。そう思えば幾分か気持ちが安らいだ気がする。
「あぁ……そら、明日は最終決戦だ。戦に備えて早く寝ろ」
「はいはーい。おやすみ」
「おやすみ」
あっさり訪れた睡魔に連れられて、意識はすぐさま沈められた。夢も見ないほどの深い眠りにつくと、身体が軽くなっていく。
何も見えない。
この時間軸に飛ばされてからうんざりするほど繰り返した足利時代の夢を、今日はまったく見なかった。ようやく心の整理がついたのかと嬉しく思う一方で、それを寂しく思っている自分がいる。ここへ来てから見るようになったあの夢のおかげで、国広は自分の出自について大分思い出してきた。それは、今まで自分が考えていたような苦しいものでは無く、幸せで、温かくて、真綿で包まれたような優しい思い出ばかりで……。このまま何も見なくなって、また記憶が薄れていくのは、些か惜しい、と。咄嗟にそう思ってしまった。
「ん……」
だというのに、夜は明ける。雄鶏より先に雀が鳴き、窓の外で可愛らしい歌を奏でている。何処か遠い場所でその歌を聴きながら、国広は覚醒の予感に打ち震えた。
今日は、聚楽第任務最終日。例の監査官と共にいられるのも、これで終わりだ。
(最後くらい、少し話がしたかった……かもな)
叶うなら、あの頃色んなことを教えてくれた礼でも。ただの自己満足ではあれど、ちゃんと伝えたい。伝えられたなら、前へ進める気がしたから。自分は写しだけれど、堀川国広第一の傑作。本歌との間の関係を清算出来たなら、堂々と己の価値を誇れる。そんな自分に、いつかは――。
「ぐっ、ぅ……っ」
がばり。
上半身を起こす。息苦しさを感じて、思わず噎せた。ゲホ、ゲホ、と何度か咳き込んで、無意識のうちに首元へ手をあてがう。ギリギリと何かに締め付けられているかのような痛みと、喉を塞がれている苦しさに何度も意識が飛びそうになった。
「ぁ、は……、はぁ……」
ひゅー、と喉が鳴り、次第に息苦しさは和らいでいく。昔からそうだった。国広が少しでも前向きになろうとすると、何故か首を絞められるような苦しさが襲うのだ。お前はあくまで写しでしかないのだと、調子に乗るなと、そう言われているのだろうか。
震える手で傍に置いていた布を掴み、そのまま自らを覆う。頭からすっぽり被ってしまえば、自分一人だけの閉鎖された空間であることに、この上ない安堵を覚えた。締め付けはもう無い。だが、心の臓はまだバクバクと鳴っている。一時的に死を垣間見たことへの恐怖から、身体は震え、冷や汗がこめかみを伝い、息も荒い。ぎゅうっと目を瞑ることでそれらが過ぎ去るまでやり過ごし、元に戻るまでひたすら苦痛の余韻に耐え続けた。
――なんだ写しか。偽物じゃねぇか。
嫌なことを思い出した。刀の価値もわからないぼんくらめ。
――写しとはいえ見事な出来よ。ところで本歌はここにはないのか?
珍しく審美眼を持つ主だと思ったのに。俺を認めてくれたのではなかったのか。結局、あんたも本歌を求めるんだな。
――なんと美しい。写しでこれなら本歌の美しさはさぞかし素晴らしいのであろうな。
あぁ、またか。どいつもこいつも。もう、いい。
(見るな。そんな目で、俺を見るな)
俺は本歌とは違う。写しだが、あの刀工国広の第一の傑作とまで称される刀なんだ。本歌と比較するな。俺は、独立した一つの刀として、正しく名刀と呼ばれるに相応しい出来栄えなんだ。俺の親父はすごいのだ。でも、結局俺は写しで、写しは人の子にとっては偽物も同然で、でも、俺は……俺は、おれは、おれはおれはおれは。
「偽物、なんかじゃ……」
「……り、山姥切!」
「っ!」
両肩を掴まれ激しく揺すられる。少々乱暴な接し方は、国広に触れる手の主にしては珍しく。ハッと我に返って顔を上げれば、そこには焦った顔をした青江がいた。
「……嫌な夢を見ていたようだね」
依然としてその表情は険しい。つ、と黄金色の瞳が国広の首元を映し、すぐに背後へと視線が逸らされた。
「あ、あぁ……すまない。うるさくしてしまったか」
「偵察組はもう起きる時間だから大丈夫だよ」
何があったか深くは聞いてこないあたり、青江は国広との距離感を弁えていると感じる。それは第一部隊の面々には共通して言えることでもあったが。気を遣われていることに思うことはあれど、本音のところではそんな彼らの付かず離れずの距離が有り難かった。
「身体が辛いなら無理をしない方がいい。酷い汗だよ」
「いや、大丈夫だ。深く眠っていたし、身体に支障はない」
「……そう。でも、辛くなってきたら言うこと。この聚楽第任務で君たちが危機にさらされている現状は変わらないんだ。違和感を感じたら絶対に教えて欲しい」
こくり、と頷く。その後、風呂に入っておいでと告げる青江の声は、いつもよりも優しかった。未だ恐怖に震える国広の心に気づいていたのかも知れない。彼は霊刀として妙に聡い部分があるから。
「さ、君が一風呂浴びてきたら続きをしようか……作戦会議のことだよ?」
「行ってくる!」
そして、ついに迎えた聚楽第特命調査最終日。
それから何事もなかったかのように行われた偵察の結果、本丸に潜む敵数は元々報告のあった十八体と同じであることを確認した。敵の強さは聚楽第・南二ノ丸に潜んでいたものたちと同じか、それより少し強いくらいで、今の国広たちの戦力ならばそこまで苦戦するほどの相手ではないだろう。また、本丸内に潜む時間遡行軍は、人の子に見えるよう術を施されているらしく、ある者は厨へ、またある者は門番として……といった具合に、上手く内部に忍び込んでいるようで。共に業務にあたっている人の子たちもまったく気づいていない様子であった。
「秀吉公、まさか自慢の居城に異形が紛れ込んでいるなんて、夢にも思っていないだろうね」
「知らぬが仏ってな」
「……」
宿で待つ待機組の元で報告を行いながら、国広はこっそり後ろに控える監査官の方を見やる。
手元のバインダーに何事かを書き入れている姿は、最早見慣れたものだ。しかし、今日は一段とピリピリしている様子で、あからさまに話しかけるなという空気を放っていた。
(……まぁいい。写しが本歌に声を掛けるなんて、元より烏滸がましかったんだ)
話してみたいと思っていた夜の勢いはどこへ。あの悪夢ですっかり卑屈さが助長した国広は、もう彼と話をしたいだなんてことは思えなくなっていた。名残惜しそうに壁に寄りかかる監査官を一瞥してから、国広は任務に集中するべく、敵の潜む場所が描かれている本丸の見取り図へと視線を戻す。
「……」
その一方で、そんな国広と監査官の様子を、青江は感情の読めない瞳で見つめていた。彼の目には変わらず首に繋がれた枷のような糸と、前に見た時よりも数の増えた結び目が鮮明に映し出されている。今朝の国広の様子がおかしかったことも、十中八九犯人はあの男だと見当もついていた。
全部事情を知る身としては、どうか最後まで無事に任務が終わることを、と。願わずにはいられない。
「突入はいつにしようか」
緊張感など微塵もない声色で、髭切が問う。
「夜は太刀以上の刀は弱体化する。やるなら日のある今からだな」
国広が淡々と返せば、三日月が揶揄いの色の濃い声で蛍丸へ話しかけた。
「蛍丸、室内戦だぞ。勢い余って壁に刀を突き刺さぬようにな」
「はいはーい」
「良い返事だ。石切丸は昔壁から抜けなくなって戦線離脱したことがあったからなぁ」
「え、何それ絶対面白いじゃん」
示し合わせたように全員が立ち上がった。
己の本体を携え、武具の具合を見る。全員の用意が整ったと判断した国広は、監査官へ一言「これより聚楽第本丸に潜伏中の、時間遡行軍の排除を実行する」とだけ告げて、そのまま宿を後にした。道中、こっそり横目で確認すれば、男は国広たちと距離を置きながらも、大人しくついてきていて。されど変わらず布で隠された男の心中は、何を考えてるのか読み取れなかった。
一歩踏みしめる度に、サクッという小気味の良い音が鳴る。深雪を歩いたその後に、七人分の軌跡が刻まれた。深々と沈んだその跡は、やがて数刻もしないうちに新たな雪に埋もれ、跡形も無く消え去ってしまう。
この、すぐに掻き消されてしまう一瞬の足跡を、確かに己がここに存在したという証明を、自分たちは今から守りにゆくのだ。
それは、絶対に一片の取りこぼしも許されぬ。
どれほど危うい均衡の上に成り立つ、儚い軌跡であろうとも。
*
桜の花弁が散るように、ひらひらと舞い落ちる儚げな粉雪。雪化粧を施された聚楽の城は粛々と佇んでいて、積もり積もった雪が剥がれ落ちた下からは、金箔のあしらわれた瓦屋根が姿を覗かせていた。
「……よくここまで来た。ここが聚楽第の中心部、本丸だ」
南二ノ丸と本丸を繋ぐ南御門。その門前に立った時、それまで沈黙を貫いていた監査官が徐に口を開いた。
「あの北西の方角に見える建物が、時間遡行軍の敵本陣がある天守だ。ここから天守の最上階までは、強力な敵部隊との三連戦となる。気を引き締めていけ」
男が言い終わると同時に、ドロン、と現れたこんのすけがその肩に飛び乗る。すると、男はそれまで何事かを書き込んでいた書面を管狐に渡し、せかせかと国広の方へ近づいてきた。
「実力を示せ」
「……っ」
「最後だからと気を抜くなよ」
「監査官はん」
「……わかっている」
こんのすけに言われ、あっさり引いているところを見る限り、彼が政府から何かしらの制限を受けているのは間違いない。それを証明するかのように、監査官は渋々という態度を前面に出しつつ引き下がると、再び後方へ控えた。勿論、布越しに国広のことを睨みつけることを忘れずに。
(……どうしたものか)
まったく、やりづらいことこの上ない。が、そうも言っていられない。
「……参る」
そこからの行動は早かった。
峰打ちにて素早く門番の意識を飛ばした国広たちは、まず南御門の屋根の上へと駆け上がり、天守を目指した。屋根伝いに遠侍、大広間、台所、と突っ切ると、ごろごろと石の積み上げられた天守台が眼前に現れ、その脇にそれた場所にある小さな門を潜る。
「ついて来な! 派手にキめてやるからよ!」
ぼんやりと行燈が照らし出す、うねうねと畝る小廊下。動きの素早い太鼓鐘を先頭に、全体的に薄暗いそこを走り抜ける。暫く続いた暗がりがようやく途切れたその先で、だだっ広い大広間が国広たちを歓迎し、そこで手始めに一戦交えた。その後は、三階部分にて二戦目、この時点で十二体の撃破に成功。追い風に乗った勢いで最上階にあたる五階部分に向かい、既に準備万端な敵の本陣と交戦へ。激しい戦闘へともつれ込んだ。
「魚鱗陣だ、一気に畳み掛けるぞ!」
「……っその目、気に入らないな!」
国広は先陣を切って敵陣へ乗り込み、目にも留まらぬ速さで敵短刀を一閃する。バラバラと砕け散った敵短刀が完全に消える前に、すぐ傍に潜んでいた敵脇差の気配に気づき、間髪入れずに斬りかかった。何だか身体が軽い。調子が良い。今なら何だって斬れそうだ。岩も、妖も、霊も、化け物だって。
「そら、来いよ。俺はここだ。かかってこい」
これなら相手を仕留められる、そう確信したその時だった。
『ヒヒッ……』
落ち窪んだ眼窩の中で不気味に光る赤が、弧を描いた。
「な、……っ!」
ガクッと足から力が抜ける。地面が大きく揺らぎ、世界が真っ逆さまに落ちていくような浮遊感に襲われた。身体からみるみるうちに力が抜けていき、本体を握ることすらままならない。なんで、どうして。こんなところで地に伏すわけにはいかない。立ち上がらなければ。焦る思考とは裏腹に、今度は激しい手足の痺れが国広の身体を苛む。
ガキンッ!
手から、刀が滑り落ちる。信じられないとばかりに目を見開き、床の上を転がる己の本体を見た。時が、一瞬止められる。その刹那に、敵脇差はゆっくりと頭上まで刀を振り被り、そして、
「ぐ、あ……ァア!」
右肩から左脇腹まで一文字に斬られた。鮮烈な赤が、目の前を飛び散る。
「山姥切⁉」
「隊長、なんで……っ!」
意識が点滅している。巡り、巡る、足利の思い出。本歌が笑い、桜が舞う。縁側で食べたみたらし団子。主と馬に乗り、野を駆けた日々。流れる走馬灯が遠ざかってゆく。
「ぁ……?」
焦点が合わない。ぼやけた視界の中、己の血に染まった掌を見た。指先がうっすらと透けていた。あぁ、正史が歪められてしまったのかと、その時やっと理解する。記憶がどんどん浮かんでは消えていき、空っぽになった胸の奥が虚しさで満たされていくのは、正史が歪められたことによる弊害か。どうやら俺は、守れなかった、らしい。
「国広の……っ!」
鋭い音が聞こえる。風を斬り、骨をも断つ、死の音が。近づいてくる。どうしようもなく孤独で真っ暗な虚空が。
「勝栗は無いのか!」
「もう使い切っちまった!」
「山姥切、身体が透けて……っ」
「こんのすけ! 政府の部隊はまだ対応していないのか!」
「氏重と接触した時間遡行軍を取り押さえたと只今報告が!」
「敵は排除した! 撤退だ! 本丸へ帰れ!」
――早くしろ!
あぁ、息苦しい。飛びそうな意識が無理矢理現世に縛り付けられている。いい加減解放されたい。何から? 俺を縛り付けているモノはなんだ? 俺は何のためにここにいる。此処はどこだ、俺は誰だ。俺の、生まれた意味は、名前は、
「国広の」
あぁ、そうだ。俺の名は国広。自慢の親父である刀工・堀川国広が打った刀で、彼が打った刀の中でも第一の傑作と称されていて、それから……。
「ほ、……んか……」
――俺は、本歌・山姥切長義の写し。
「ゲートが開いたぞ!」
「山姥切、あと少しだ。持ちこたえろよ!」
誰かに抱えられたらしい温もりと浮遊感を得た。もう目は見えていない。何が起きているのか状況を把握する暇もないまま、己が本歌の気配が遠ざかっていくことだけをありありと感じ取る。
「は、……ぅ……」
言葉を発する気力もなかった。
話せる状態であったとしても、なんと言葉をかけて良いのかわからなかったと思うけれど。それでも、最後に礼くらいはしたいと思った。存在が不明瞭になりかけた時に、名を刻んでくれた礼だけでも。きっとこれが、彼と会う最後になるのだから。
結局、そのまま意識を失った国広は、第一部隊の面々により手入れ部屋へ担ぎ込まれ、手伝い札を駆使しながら迅速な手入れが施された。手入れは傷一つ残さず無事成功。しかし、一度正史が歪められたことによるダメージが殊の外大きかったのか。その後一週間程は昏睡状態に陥り、目が覚めることはなかった。
だから、彼は知らなかった。
「俺こそが長義が打った本歌、山姥切。聚楽第での作戦において、この本丸の実力が高く評価された結果こうして配属されたわけだが、……さて」
彼が懇々と眠り続けている間に、本丸に嵐がやって来たことを。