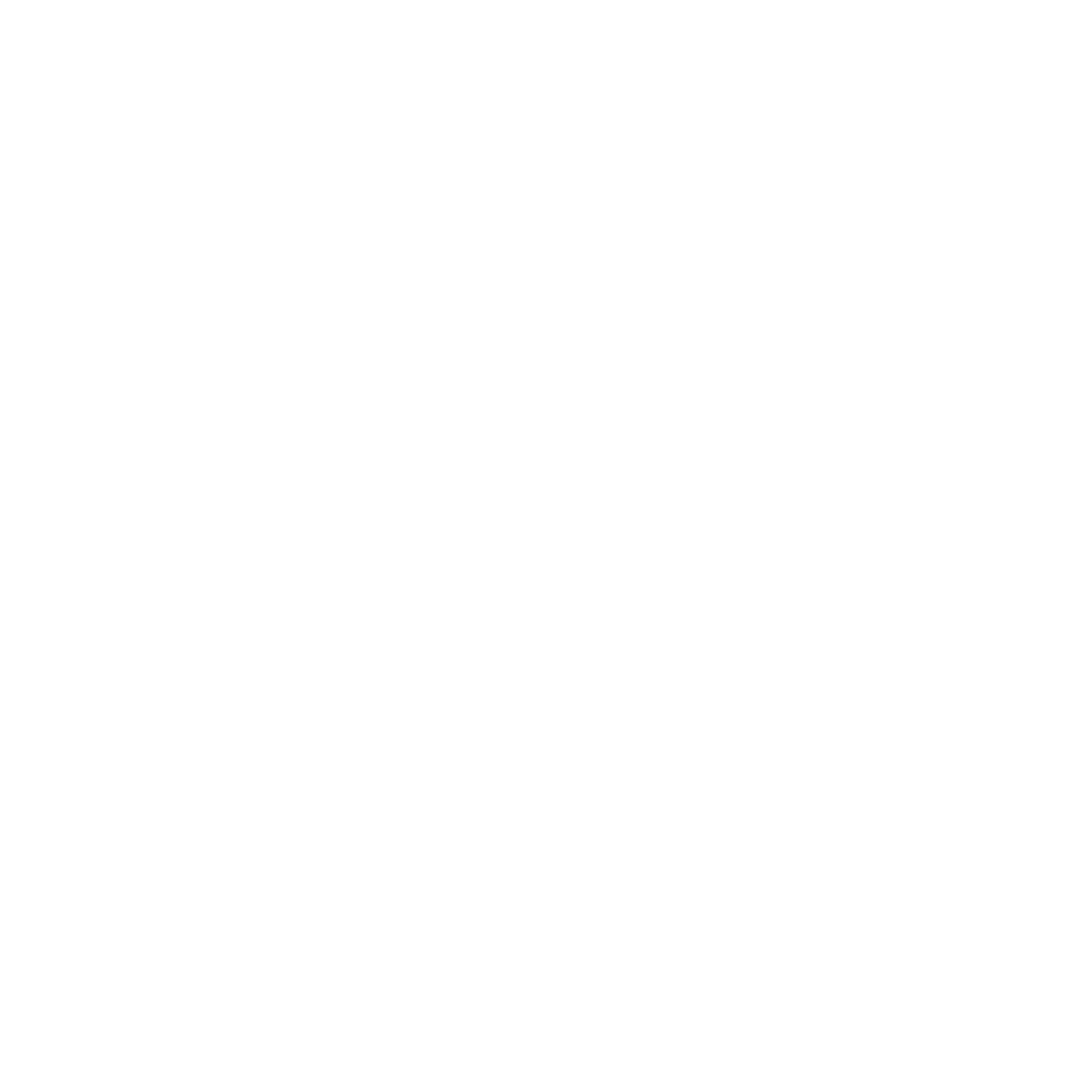第四話 二振りの『山姥切』
意識の浮上は唐突に訪れた。
ゆっくりと瞼瞼を開け、天井の木目を数える。ここは何処だ。そんな疑問はしかし、少し目線をずらしてみるとあっさり解決することとなる。部屋に備え付けられた棚にずらりと並べられた薬瓶たちと、鼻につく独特の臭い。傍らに置かれた果物や花は、見舞いの品々だろうか。花瓶に活けられ凛と咲く白い山茶花の姿からは、摘み取られてからそう時が経っていないことが伺える。間違いない。ここは己の過ごしてきた本丸だ。そこでようやく遅れてきた思考が追いついた。国広の寝かされていたこの場所は、練度が上限に達してからはすっかりご無沙汰となっていた医務室だった。
「お……れ、は」
開け放たれた窓の前で、白いカーテンが揺れる。ゆらゆらと陽の光が差し込み、そよ風が頬を撫でた。身体を起こそうと試みるも、上手く起き上がれず。喉奥に何かが突っかかっているような違和感を覚えて、声も碌に発せられない。現世に顕現して十数年。まるで初めて人の器を与えられた時のようだ、と他刃事のように感慨深く思っていると、徐に医務室のドアが開かれて何者かが入ってきた。
「邪魔するぜ」
声からして薬研のようだ。今が一体何月何日なのかはわからないが、自分がここで寝たきりの間、彼がずっと面倒を見てくれていたことは容易に想像出来る。
「やげ、……」
面倒をかけてすまない、と言おうとした。だが無理だった。口から出た音はヒューヒューという空気音ばかりで、言葉になる前に潰えて消える。何たる無様な。頭の中で燭台切が呟いた。
「……っ山姥切の旦那! 目が覚めたのか!」
国広が起きていることに気づいた薬研が、慌てて寝台の横まで駆けてくる。
「すま、な……め、ど……かけた……」
「気にすんな、俺っちたちは仲間だろ。器に馴染んでねぇみたいだな……まぁ仕方ねぇか。ずっと眠ってたんだからな」
それから国広は、薬研から聚楽第任務から重傷帰還した後、かれこれ二週間眠り続けていたのだと教えられた。思っていたよりも時が過ぎていたことに驚く反面、起き抜けに次々とこの身を襲った不具合に納得する。それだけの時を眠り続けていたのなら、身体が動けなくなるのも当たり前だ。今のこの身体は人の子に与えられた仮初めの器。只でさえ馴染ませるのにコツがいるのだ。意識を失ってから二週間ということは、霊力がこの器に馴染むまでは相応の時間が掛かるだろう。
仮に動けるようになったところで、すぐに戦果を上げるのは無理そうだ、と。そこまで思い至り、あまりの不甲斐なさから国広は深くため息を吐いた。
「聚楽第任務は無事に成功したぜ。政府からの褒美も……まぁ、色々とたんまりもらえた。博多の兄弟と長谷部の旦那が、帳簿片手にいつになく上機嫌に笑ってたのを、旦那にも見せてやりたかったなぁ」
「……そ、うか」
「んじゃ、旦那はここで絶対安静な。なに、今までずっと働き通しだったんだ。ちぃっとばかし休んだって、バチなんて当たりゃしねぇよ」
最後にそう告げてから、薬研は医務室から出て行く。一人きりになった部屋で、国広は手持ち無沙汰にまた天井の木目を数え始めた。
聚楽第任務は色々とあった。あの本歌とおぼしき監査官の男には最後まで悩まされていたし、自分の生まれにまつわる歴史の裏側を垣間見たことで、色々と思うことも出てきた。それに、親父の打った山姥切国広という刀に込められた想いを、任務中に見た夢の中で、確かに受け取った、ような気がする。今はまだ、受け取ったというだけで何がどう変わるというわけではないけれど。それでも大事な何かはこの手で掴んだように思うのだ。
「……ん、」
あぁ、まただ。息苦しさを感じる。顔の前に掲げていた掌を引き寄せ、首元へ触れた。
「……なん、なんだ」
今までのそれの比ではない、聚楽第任務が始まってから急に酷くなった窮屈さ。過去同じような経験はあれど、布に包まり、完全に一人の世界に入ってしまえば気にならなくなったというのに、今やそんな誤魔化しも通用しない。今も尚きりきりと爪をたてる苦痛の元凶は、どうやら国広を逃す気はないらしく。じっと抵抗することなく耐え忍んでいても、痛みと苦しさは酷くなるばかりであった。
「兄弟、僕だよ。入ってもいい?」
酸欠で意識が遠のいてきた頃だった。
薬研から話を聞いたらしい堀川と山伏の兄弟たちが見舞いにがやってきた。不思議なことに彼らがやって来た途端、あの圧迫感が波が引くように消え去っていき、幾分かの余裕を取り戻す。何とか声が出せるまでになった国広は「構わない」とだけ返事をして、兄弟たちを部屋へ通した。
「二週間も眠ったままなんて、兄弟は寝汚いにもほどがあるよ!」
開口一番に堀川からそんなことを言われて、苦笑が漏れる。
「カッカッカッ! 兄弟は早起きが苦手であるからなぁ」
山伏はそんな堀川の一喝を豪快に笑い飛ばして、がしがしと国広の頭を撫でた。その拍子に口元まで被っていた布団が捲れてしまい、慌てて傍に置かれている布に手を伸ばす。
「もうっ、久しぶりの再会なんだから、もうちょっと顔見せてよね」
しかし、国広の手が届く前に堀川によって布は取り上げられ、国広の目論見は敢え無く潰えた。
「それ、は……」
「兄弟、山姥切の兄弟が困っているのである。気持ちはわかるが病み上がりの兄弟を労ってやらねば」
「んー、しょうがないなぁ……」
「す、ま……ない」
山伏のフォローによって事無きを得た国広たちは、取り止めのない話をしながら、兄弟水入らずの時を楽しんだ。二人とも国広が目を覚ましたことを心から喜んでくれて、やれ国広がいない間の本丸は長谷部の独裁国家になっただとか、博多の算盤を弾く音が頭から離れないだとか、主が心配するあまり御神刀組に祈祷を頼んだだとか、なかなかに濃い二週間の様子を語ってくれた。また、ひょんな話から祝いに猪を一頭贈ると約束してくれたのは嬉しかったけれど。そんな話になれば最後、兄弟たちは思い立ったが吉日とばかりに早速本丸の裏山へ行ってしまって、正直なところ猪の肉……も勿論魅力的だが、それよりももう少しだけ彼らと一緒に居たかったので、兄弟たちが帰ってしまうのを寂しく思った。
そうして薬研も去り、嵐のような兄弟たちが帰った後は完全な独りだけの時間がやってきて、久しぶりに身体を使ったことへの疲労からうとうとと微睡みつつ、これからの己についてを考える。
(まずは誰かに手合せをしてもらって勘を取り戻して……いや、誰かに迷惑をかけるのはダメだ。きっと体の鈍った写しの相手なんて、相手に迷惑がかかるに決まってる。なら、裏山で山伏の兄弟と修行について行けば……それも足を引っ張ってしまうか)
身体は徐々に動くようになってきている。本丸に流れる主の霊力が、ゆっくりと肉の器を循環しているのだ。起き上がれたらまずは何をやろうか。そんなことばかり考えては、あれでもないこれでもないと斬って捨てる。誰が見ているわけでもないのに、無意識のうちに頭から被っていた布をさらに引き下げて、ほっと息を吐いた。やはり、布の中は落ち着く。
(聚楽第の報酬、か……)
己の働きが少しでも、この本丸のためになったのなら。そんなに嬉しいことはない。
結局、起きた時のことはまたその時考えればいいかという結論に至り、国広は意識を手放した。
その日から一週間ほど医務室で過ごした国広は、自力で歩く、走る、などの動作が出来るようになってから兄弟たちと住む堀川部屋へ移り、食事も粥やうどんといった消化に良いものから普通の食事へと切り替えられた。そして、兄弟たちの支えもあり、一通りの生活が一人で出来るようになった頃。聚楽第任務の成功を祝い宴が催されることになり、その日の晩大広間へ集まるよう伝えられた。なんと、戦果報告こそ主に済ませたけれど、任務完遂祝いは国広が動けるようになるのを待っていてくれたらしい。
《夕餉時に始めるから、調子が良ければおいで》
それだけ言って厨へ行ってしまった堀川の言葉が蘇る。
(そういえば、新刃歓迎会も兼ねていると言っていたな)
自分が眠っている間に誰か来たのだろうか。豊前江のことか、とぼんやりと予想する。彼とはこの前リハビリのために庭を散歩していたところで偶然会った。何というか、あれが燭台切の言う『かっこいい』ということなんだろうな、と思うくらい男前な刀だった。まぁ、国広と豊前江が顔を合わせていることは、他の刀たちは知らないので、新刃というのは十中八九彼のことだと思うが。
「余計な気を遣わせてしまったな……」
帰ってきてから迷惑をかけてばかりだ。
また、卑屈の殻に閉じ篭り己を苛む。慣れたものだ。長年ずっとこうして生きてきたのだから。
「兄弟ー、準備出来たよ。第一部隊の皆んなももう揃ってる!」
「……わかった、今行く」
襖の向こうから堀川に呼ばれる。支度は整った。後は、宴の前に皆に迷惑をかけたことを謝って、主にも改めて礼を……。
部屋を出る。一歩外に踏み出せば、底冷えする空気が足元から伝わってきた。聚楽第任務へ赴いた時には既に終秋を迎えていたが、今やすっかり真冬。丸裸の木々は哀愁を漂わせ、彩の失われた景趣はいつかの雪で覆われた京の都を彷彿とさせる。夕餉時ということもあり、人気のない静かな廊下を進むのは、何だか妙な緊張感を伴った。
「おお、隊長殿! やっと来たか。ほれ、こちらに参れ。この爺の隣だ」
大広間に到着すると、今回の祝いの席の主役でもある第一部隊の面々が上座側に座っていた。そこで、周りの者たちと談笑していた三日月がいち早く国広の存在に気づき、陽気に声を掛けてくる。
「三日月……あんたにも面倒をかけたな」
「なに、仲間の一大事よ。それに隠居生活で暇しておったのでな。また手合いに誘っておくれ」
主はまだ来ていない。豊前江は国広が座してから少しした後やって来た。大所帯の生活には既に慣れたようで。彼は騒がしい空気に戸惑うことなく、真っ直ぐ国広の左隣の席まで通される。やはり新刃歓迎会の主役は彼だったらしい。豊前江の席は主のすぐ隣だった。その場所は普段、何か特別な功績を建てた者や新刃以外には、近侍と初期刀しか座れない。
「よう、いつぞやの別嬪さんじゃねえか」
席に着き、一呼吸置いた豊前江が国広に声を掛ける。
「べ、……別嬪とか、言うな」
「おや、君たちいつの間に知り合ったんだい?」
向こう側の席で不思議そうな顔をした青江に、国広はこの前庭先で偶々彼とあったことを伝えた。すると、その話を聞いた青江たちは各々神妙な顔になり、何事かを呟く。
「……『彼』に会わなかったのは幸いというべきか、何というか」
「よかったんじゃねぇの? 病み上がりだったんだし、山姥切のメンタルがもたねぇって」
はて、何と言ってるのか。隣で嬉々として話を続ける豊前江の声に遮られて聞こえない。直接言ってこないということは自分には関係ない話か、と頭を切り替えたところで、国広はある違和感に気づいた。豊前江の向かいの席が、一つだけ空席だったのだ。
「……なぁ、そこの席には誰が座るんだ?」
すると、それまで談笑していた第一部隊の面々が固まる。豊前江と国広は揃って首を傾げ、彼らの突然の変化を訝しんだ。一体なんだと言うのか。
「新刃は二振りいるんだよ」
暫しの沈黙の後、凍りついた空気の中でも、唯一自然体であった蛍丸が言う。
「二振り?」
「あぁ、あいつか!」
思い当たる節があったらしい豊前江が、手を叩いて一人で納得した。しかし、かと思うと彼はすぐに眉根を寄せて訝しむ顔に戻ってしまう。国広だけがすっかり置いてけぼりだった。
「なんだ、俺より先に来てたのにまだ歓迎会してやってなかったのか?」
「おい、あいつって誰のことを……」
「俺が、歓迎会はそこの『偽物くん』が目覚めてからがいいと進言したんだよ」
脳天に雷が落ちた。
そう錯覚するほどの衝撃に目を見開く。割って入った声には痛いほど覚えがあり、俄かに信じ難い現実に直面したことで身体が竦み上がった。そんな、まさか。驚愕を露わに声の方を見上げれば、そこには白絹を取り去って美しい顔を惜しげもなく曝け出した男が立っていて。男が――見間違える筈もない己が本歌が、その冷涼な色の瞳で国広のことを睨みつけていた。
「……なん、で」
「お前、俺がこの本丸に配属されたことを聞かされていなかったのかい?」
「え、」
「はぁ……道理でね。動けるようになったのに挨拶の一つもしに来ないなんて、おかしいと思ったんだ……」
どうしてこの男が此処にいる。彼は政府に所属している刀剣だ。それが、何故本丸配属に。
――聚楽第任務は無事に成功したぜ。政府からの褒美も……まぁ、色々とたんまりもらえた。
(褒美……)
目覚めた直後に薬研からされた説明を思い出す。もしや、聚楽第任務の報酬の一つが、本歌だったのか? それが本当だとしたら、この男はこれから国広と共に過ごすことになるということで、となればまたあの冷え切った視線で睨まれて、嫌味を言われて……。
(冗談じゃない)
初期刀として顕現され、主に振るわれてきたこの身。練度も上限になり、ようやく主の満足する働きが出来るようになったと思えてきたところだったのに。こんなところで本歌が来てしまえば、自分はどうなる。今まで国広を所有してきた人の子は、その殆どが国広を通して本歌を見ていた。
――いくら伯仲の出来と言えど、その斬れ味は流石に本歌には叶うまいて。
また、奪われるのか。俺が、俺の親父が受ける筈だった賛辞を、本歌に奪われるのか。
(嫌だ……)
怖い。想像しただけで、それは途轍もなく恐ろしいことのように感じた。今の居場所をすべて奪われ、布の中で独り蹲る日々。誰も山姥切国広という刀を見ずに、眩いばかりの光の中にある美しい本歌・山姥切長義を見る。俺は、これからどうしたら……本歌の方が良いと言われてしまったら、俺は、俺でいられるのか。そもそも、俺は何だ。俺は、俺だ。堀川国広の第一の傑作で、でも本歌・山姥切長義の写しで、それで、
「いい様じゃあないか、偽物くん」
「……っ」
「お前はそうして苦悩しているのが一番似合いだ」
せせら笑う声が頭上から聞こえ、ますます顔を俯けた。布の中に顔を隠して縮こまる姿は、さぞかし滑稽に見えたことだろう。
「……写しは、偽物とは違う」
そう答えるのが精一杯で、もっと大事な言葉なんて出て来やしない。それもこれも、俺が写しだから。
「俺を差し置いて『山姥切』の名で顔を売っているんだろう?」
「……そんなことは」
「でもそれは、仕方がないか。だって、ここには俺が居なかったんだから」
「……それは」
「俺が居る以上、『山姥切』と認識されるべきは俺だ。そのことを教えてあげようと思っただけだよ」
言いたいことを言って満足そうに鼻を鳴らした後、長義は予め用意されていた豊前江の向かいの席に腰を下ろした。周りの刀たちは皆気を遣って、何とかこの殺伐とした空気を離散させようとしてくれているが、生憎国広は飲んで騒ぐ気分になれそうもない。それは長義も同じようだった。
「では、聚楽第特命調査の完遂と、新しく新刃を迎えたことを祝して……乾杯!」
微妙な空気の中でも、宴は始まる。暫く呑んで酒が入ってくると、はじめの席なんてあっという間にバラバラになって、皆それぞれ好きな者たちと盃を酌み交わすようになった。
「おおい、長義の! こっちに来て呑もうぜ!」
「長義くん、僕の作ったおつまみも是非食べて欲しいなぁ」
「祖の手製ですか。それは是非」
長義が遠縁にあたる長船の刀たちに呼び出されたところで、国広はそっと大広間を出る。右手には中身が少しだけ減った徳利と、左手には御猪口。元々酒は好きだった。今夜は部屋に帰って静かに呑み直そう。そんなことを考えながら、後ろ目でまだまだ呑み足りなさそうな様子の兄弟たちを見る。一瞬誘おうかとも思ったが、それぞれ仲の良い者たちと楽しそうに談笑していたので、早々に諦めた。
廊下に出れば大広間の熱気とは打って変わり、刺すような冷たさが肌を撫でる。ぶるり、と一度身震いし、吐息を零すと、それは真っ白な靄となり空気に溶けて消えた。まるで先ほどの国広が発した言葉たちのようだ。何を言ったところで無意味。碌な反論にもなりやしない。声に出しても出しただけ溶けて、消えて、あの男の胸には響かない。
「『偽物』だと……?」
この上ない侮辱。怒りのあまり、声が震える。
「俺は、偽物なんかじゃない……っ」
ダンッ!
自室に雪崩れ込むようにして入り、怒りに任せて畳を殴った。おざなりに机上へ置いた酒器たちがぶつかり、乾いた音を立てる。今まで抱いたことのないほどの激情が、臓腑を喰い千切って暴れ狂う。痛くて、熱い。血潮が昂り、無性に刀を振るいたくなった。
俺を捻じ曲げたあんたが、それを言うのか。
俺を俺であれと言祝いだ他でもないあんたが、俺を偽物と宣うのか。
御猪口に並々注いだ酒を煽る。次から次へと、酒を注ぐ手は止まらない。いっそ酒に溺れて折れてしまいたい。そんなことすら思った。このまま本歌に居場所を奪われ、偽物だと侮られながら在るくらいなら、戦さ場に刀装無しの単騎出陣して刀としての生を全うする方がマシだ。最後くらい盛大に華々しく戦果を挙げて散ってやる。
「……何をみっともないことをしてるんだよ」
徳利の中身が完全に空になってしまい、押入れから秘蔵の日本酒の酒瓶を出して、さらに呑み続けていた時だった。酒が回り、意識がふわふわとして怒りをも和らいだ頃、何者かに話し掛けられる。
常の時ならば他者の気配が近づいてきた時点で、警戒していたに違いない。だが、今の国広は如何せん酔っ払っていた。ましてや語らう相手もいなかったので、呂律が回らないほど呑んでいるという自覚もなく。文字通り際限なく呑みまくっていたのだ。
「……うるさい、じゃますりゅな」
酒瓶を取り上げようと横から伸びてきた手を叩く。誰だ、人がせっかく一人楽しく呑んでいるところを邪魔する奴は。斬ってやろうか。
「……酒臭い。呑み過ぎだ。これでは話も出来やしないじゃないか。話も出来ない偽物くんなんて、つくづく救いようのない」
だから、俺は偽物じゃないと言っている。何度言えば理解するんだ。
「何だよその目。やはり、お前は偽物くんで十分だな。なんて可愛げのない写しだ」
可愛げなんて求めてもいないくせに。よく言う。昔からそうだった。淡々と俺を見つめて、見定めるようなあの目が苦手だった。俺の写したるもの、と押し付けてくるあの考え方が嫌だった。俺は俺であって、あいつの写しというだけではないのに。
「……お前は俺の写しだという自覚が些か足りないようだね。そんなお前が、俺はずっと嫌いだった」
カタン。
酒瓶が奪われる。朦朧とした意識の端に、鈍く輝く銀色が見えた気がした。
抜き身の刃か。そうか、今から俺は斬られるのか。誰とも知れぬ何かに。言われたい放題言われたまま、なす術なく斬って捨てられる。写しの俺には似合いの最期だ。なんと呆気ない。
「俺は、お前が嫌いだ」
意識が遠のく。鋭利な言葉は国広の中の柔い部分を、的確に抉った。身体が熱くて、言葉も出なくて、悔しくて、悔しくて。それでも泣くことは己の矜持が許さなかった。
「躾し直してやる。覚悟しておけ」
嫌いだと言ったその口で、誰かが国広の持っていた御猪口の中の酒を煽る。空っぽになるまで飲み干したそれと酒瓶を持ち上げて、誰かは早々に国広の部屋から出て行った。隙間から入り込んだ冷気が、酒で火照った身体から温度を奪う。
静かに閉まる襖の音を、国広は遠く向こうで聞いていた。
次の朝目が覚めた時には、そんなやり取りがあったという記憶など、綺麗さっぱり消し飛んでいた。
*
新刃歓迎会から一週間の時が過ぎた。ここのところ時の流れが早い。流石は師走だ。主の言っていたクリスマスとやらのイベントも終わり、あっという間に年末がやって来て、新年を迎える用意をしている。そして大晦日を控えた十二月三十日。国広たち隠居組は、本丸の大掃除をさせられていた。
「主の部屋は相変わらず汚ねぇなー」
期限別に書類の山を分けていき、処理の終わってるものは保存ファイルへ。未処理のものは文机横の処理箱の中へと分別していく。去年の一月から何も手をつけられていない惨状を目の当たりにして、鶴丸が早々に根を上げた。
「貞坊が羨ましいぜ。俺も早く極修行が解放されねぇかな。そしたら毎日練度上げで出陣尽くしだってのによ」
「太刀の極修行はまだ先のようだぞ。しかし主も主よ。現世に帰省している間に片付けておいてくれ、なんて無茶なことを言う」
保存期間が五年を過ぎているものたちを処分箱へ移しながら、三日月がぼやく。
「ここが終わった後は書庫の方の手伝いだ。さっさと終わらせるぞ……長谷部が怒る」
本丸を運営して十数年。堅実に実績を積み重ねてきたこの本丸の刀たちの殆どは、練度が上限に達している。刀種も政府が新しく顕現に成功した刀たちは漏らすことなく迎えられており、現在の主だった出陣部隊の編成は、専ら最近新しくやってきた新刃たちで固めてあった。例えるなら長義と豊前江が最たるそれだ。練度の低い彼らは、岩融や蛍丸といった攻撃範囲が広く、練度も上限寸前である者たちを組み込んだ第三部隊に入り、日々出陣に明け暮れている。
「む……帰還か」
カランカラン、と鐘が鳴った。出陣部隊の帰還だ。今日は確か、祢々切丸獲得のための任務に第二部隊が、それから練度上げ目的で第三部隊が出払っていて、朝から慶長十九年の大阪冬の陣に出ていた第三部隊が、昼餉前に帰還予定だったはずだ。昼食を食べたら今度は慶長五年の関ヶ原へ向かうのだと聞いている。
「……手を止めるな。やるぞ」
「へいへーい」
「あいわかった」
鐘の音に気を取られ、すっかり集中力を切らしてしまった鶴丸と三日月を窘める。もたもたしていたら、長谷部が乗り込んでくるのは目に見えていた。また小言を言われては敵わない。面倒ごとはさっさと片付けるに限る、と気合を入れ直し、国広は目の前に積まれた資料の山に向き直る一方で、ここ最近のもう一つの《面倒ごと》について思いを馳せた。
三日ほど前から、長義の練度上げが本格的に始まった。彼が本丸にやって来た時期からすると、遅くないか? と訝しく思うかも知れない。だが、それにもちゃんと事情がある。彼が本丸に顕現されてから暫くは、里が解放されたこともあり、豊前江探索のために中堅どころの第二部隊が出突っ張りだったせいで、長義の練度上げの時期が遅れてしまっていたのだ。結果、新しく迎えた豊前江と同時に練度を上げていくこととなり、彼は先日から正式に部隊入りした、というわけである。
ただ、今までは手持ち無沙汰な長義に、肉の器を馴染ませる目的で内番や手合わせといった、本丸内だけで完結する諸々をあてがっていたから良かったものの。それが出陣という外へ自由に行き来出来る権利を得たことによって、国広にとっての面倒ごとを呼び寄せる結果になるなんて、この時国広は夢にも思っていなかった。
「おい、偽物くんはいるか!」
そして、そう思っていた矢先の、これである。
「山姥切……」
「お前、何故この俺が帰還したというのに出迎えに来ない。この前の宴の時にも思ったが、お前は酌もしないわ挨拶もおざなりだわで、俺への敬意が足りていないんじゃないか?」
顔を合わせて早々の文句の数々に真顔になる。だってそうだろう、どうして可能なら末代まで避けまくってやりたい存在に、やれ敬意が足りないだの写しとしての自覚がないなどと毒を吐かれなければならないのか。そんなに不満なら放っておいてくれればいいのに……とぼそりと言い返せば、これまた烈火の如く怒り狂って説教が倍になるときた。初めこそ国広のことを心配して周りもフォローをしてくれていたものだが、いつの頃からか他者が介入すればするほど長義の機嫌が悪化すると知られてから(一度兄弟と言い合って抜刀騒ぎにまで発展した)は、二振りのやり取りは静観されるようになった。
まさに文字通り触らぬ神に祟りなし、である。国広からすれば見捨てられたも同然だが。
「今日は歌仙殿から預かった書物だ。これを読んで励めよ」
そら、と手渡されたのは、《猿でもわかる五七五》と書かれた一冊の本。猿でもわかる、という部分に馬鹿にされている感は否めないが、それ以上に腑に落ちないのが、今のこの状況であった。
「……要らない」
歌だの華道だのを学ぶより、兵法を学びたい。練度こそ上限に達したとはいえ、自分にはまだまだ足りないものが多いのだ。だから、きっと本を贈られたところで読まないまま終わるに決まっている。率直に断って本を突き返すと、長義の片眉がひくりと跳ね上がった。
「何だと? お前のその上から下まで未熟ななりを、せめて見れるようにしてやろう、という本歌の好意を無碍にする気か?」
「俺がどんな格好をしていようと、何をしていようと関係ないだろ」
「だからお前は偽物くんなんだよ」
「……写しは偽物とは違う」
何がしたいのかわからなかった。
長義は出陣先で何かと気に入ったものを見繕ってきては、国広に押し付けてくるようになった。その理由は単純明快で、彼の慈愛や好意……なんてことからでは決してなく、山姥切の写したるもの云々という彼の超理論に則っての行動だ。
ある時は羽織だった。出陣先で見かけた城主の羽織っていた着物があまりに見事だったからという理由で、あの襤褸布を捨ててこちらを羽織れと押し付けてきた。当然押し付け合いになって、弁の立たない国広が思わず先に手を出した。その後は手入れ部屋送りになるまで拳で語らい合い、二人で厠掃除一週間の罰則を受けた。またある時は華道の教科書だった。これも歌仙の持ち物だ。終いには長義手ずから指南してやると言い出して、花瓶や花を大量に買い込んできたものだから逃げた。それはもう、徹底的に。結局花が枯れるまで逃亡劇は続き、三日三晩眠れぬ夜が続いた。ぶっ倒れて医務室で目が覚めた時には、また厠掃除の罰則を言いつけられて、お前のせいだと口論になった。口論と言っても、国広には反論するだけの機転も覇気もなかったので、ほぼ一方的に説教されるだけだったが。あれは今考えても納得がいかない。
「とりあえず、俺も忙しい身でね。これ以上無駄な時間を取らせないでくれるかな?」
「……ぁ、おいっ」
「俺が夜に帰ってくるまでには読んでおくように」
言いたいことだけ言って、長義が執務室から出て行く。勝手な奴だ。過去のあれこれを思い出して、手の中にある猿でもわかる何とやらを床に投げ捨ててやりたくなった。歌仙のものだというので、そういうわけにもいかないけれど。
「た、大変そうだな」
口元を引き攣らせながら、鶴丸が言う。同情するならアレをどうにかしてくれ。そう返せば、ただでさえ真っ白な顔をさらに青白くして、鶴丸は頭を横に振った。三日月もまた同じだ。やはり、俺は見捨てられているらしい。名刀たちに迷惑をかけてしまったとか考える余裕もないほど、国広は疲れていた。
「いやいや、本歌殿も難儀よのぅ」
「まったくだ」
「……斬るしかないのか……俺を」
折角迎えた本歌を折るわけにはいかない。もう国広はこの本丸に必要ないのではないか。所詮写しなのだから、代わりなんていくらでもいる。このまま皆に迷惑を掛けて過ごすぐらいなら、いっそ。
「待て、早まるな。早まるなよ山姥切!」
本体を呼び出そうとした右手をひっ掴み、鶴丸が叫ぶ。
「そなたがいなくなっては兄弟が悲しむぞ。あー……ほれ、鶯丸に茶を淹れてもらおうではないか。確か美味い茶菓子も買っておいたはずだ、な?」
幼子にするそれのように国広の頭を布越しに撫でながら、三日月が続けた。
「俺を山姥切と呼ぶな。慰めなんて要らない。写しの俺にそんな気遣いは無用だ」
「あちゃっ……まーた拗らせちまった!」
「よし、菓子を取ってくる」
鶴丸が国広を抑えている間に、三日月が慌てて菓子を取ってこようと入り口の方へ向かう。すると、運の悪いことに三人揃って騒いでいたタイミングで、ズドン! というけたたましい音を立てて開かれた襖から、主命の鬼が顔を覗かせた。
「お前たち! サボってないでさっさと掃除をしろ!」
抜刀しそうな勢いのある咆哮に、弾かれるように三人は離れて、それまで放置していた書類の山を崩しにかかった。ちなみに、国広が折れようとしていたと聞いた長谷部は、「お前が折れたら主のフォローをまともに出来る刀が少なくなるだろう!」と、国広のことを思ってくれてるのかそうでないのかわからない一喝をくれた。でも多分、あれは主のことしか考えてない……と思う。
*
何となく目が覚めてしまって起き上がった。
隣を見ると兄弟たちが穏やかな寝息と共に眠りについている。寝る前に灯されていた行燈は消されていて、部屋の光源は朧げな月明かりだけだった。
(……喉、乾いたな)
ふわふわと影が揺れる障子窓。窓外で揺れているのは、去年新しく植えられた枝垂れ桜か。春になれば艶やかに咲く薄紅色は今は散り、丸裸の枝が無防備に曝け出されている。
布団から抜け出て厨を目指した。当たり前だが廊下に人気はない。各部屋には刀剣男士たちのプライバシーとやらを守るために防音結界が施されており、廊下まで爆音のいびきが漏れ聞こえるなんてことにはならないので、非常に助かっているのだが。ここまで静かなのも落ち着かないものがあった。何だか世界に独りだけになったような気持ちになってくる。独りは好きだ。大俱利伽羅が常日頃「馴れ合うつもりはない」と言っているように、国広とて大勢に囲まれているのはあまり好きではない。それでも、この痛いくらいの沈黙は何か余計なことまで考えてしまいそうで、暗がりに一歩踏み出すのを躊躇してしまった。
(水……)
厨の明かりをつける。棚に収まっている湯呑みを取り出し、水道の水を入れた。それを一息に飲み干し、ほうっと息を吐く。
「……俺は、本当に必要なのか」
「なーに当たり前のこと言ってるの」
比喩でも何でもなく飛び上がるほど驚いた。
「な……っ」
がばりと勢い良く振り向くと、そこには国広と同じ堀川ジャージを着た兄弟が立っている。いつの間に、という声は出なかった。何か言おうと口を開いたところを、人差し指で塞がれたからだ。
「しー……大声出したら皆んな起きちゃうでしょ。ほら、僕があったかいお茶を淹れてあげるから、兄弟は食堂のストーブの電源を入れてきて」
言われるがままに厨に隣接された食堂へ向かえば、丁度部屋が温まった頃に堀川が盆に乗せた茶器たちを運んで来る。自身の前に湯呑みを置かれて礼を言うと、彼は目尻をくしゃりと歪ませて朗らかに笑った。
「……いつから?」
に、と悪戯っぽく笑った堀川が答える。
「そりゃ、近くでもぞもぞされたら気になるでしょ。闇討ち、暗殺はお手の物な僕だよ?」
そりゃそうか。とても納得した。流石は邪道を好むと自分で言っているだけはある。加えて堀川は修行に出て極めていた。ならば、自分が彼の尾行に気づかなくても致し方あるまい。ず、と出された茶を啜りながら、気まずさから顔を俯ける。先ほど無意識のうちに出てしまった言葉を聞かれてしまっていたとは。彼のことだ。怒られるに違いない。
しかし、そんな国広の予想は、良い意味で裏切られることとなった。
「で、今度は何に悩んでるの? いや、何となくわかるんだけどさ」
ぐしゃぐしゃと髪を撫でくり回され、うわ、とも、うお、とも何とも言い難い声が漏れる。堀川の声は優しかった。怒っているというのとは遠く離れている柔らかい声色に、国広は拍子抜けする。
「……長義さんのことだよね?」
びくり。
肩が揺れる。そんなわかりやすい動揺を見せた国広に苦笑して、堀川は続けた。
「兄弟が何を考えてるのかは大体わかるよ。伊達に長いこと一緒にいないし……何より兄弟だからね」
「兄弟……」
「ねぇ、兄弟。僕は兄弟のことを誇りに思ってるし、この本丸には兄弟が絶対に必要だと思ってる。それは何も僕だけじゃなくて、他の皆だってそうだと思うよ?」
戯れに布を引かれた。そのまま布を剥がされるのではないかと思い身を強張らせるが、国広より一回りほど小さな掌はそのまま離れていき、彼の口元へと引き寄せられる。はぁー、と吐息を指先へ吹きかけている様を見て、彼が寒がりであったことを思い出した。自分の我儘でこれ以上彼の身体を冷やすわけにはいかない。そう思った国広は、慌てて茶を飲み干そうと湯呑みを傾ける。
「兄弟が全部話してくれるまで、僕は帰らないから」
だから、ね? そこに座って。
有無を言わさぬ笑顔と共に急須を差し出され、無言で空になった湯呑みを差し出す。どうやら今日の彼は徹底的に国広の口を割らせようとしているようだ。これは堀川を動かすなら自分が話した方が早いな、と悟り、国広は大人しく浮かせかけていた尻を落ち着ける。先ほどまで温められていたそこは、じわりと肉の器に温度を与えた。
「何かあった?」
「……」
「最近、兄弟の顔が暗かったから。些細なことだっていいから、話してごらん」
時の止まった水面のような穏やかな声に、心が解けていく。本当に言ってもいいのだろうか。このまま兄弟に心配を掛けてしまっても、いいのだろうか。色々なことが脳裏を過ったが、何より鼻っ柱を赤くしたまま国広の言葉を待つ堀川を見て、話さないわけにはいかないと、いい加減腹を括った。
「……山姥切のこと、なんだが」
それから、国広はこの一週間のことを話し始めた。長義から贈られる羽織や髪飾りたちのこと。教養を身につけろと押し付けられた和歌や華道、茶道といった様々な娯楽の本たち。平行線を辿る山姥切の号についての話……自分で話しておいて、これほどのことがあったのかと驚いた。言葉にして初めて、上手く受け流せていたと思っていた自分の心に、暗い影が差していたことを自覚した。
「うーん……」
国広がすべて話し終わると、堀川が唸った。慎重に言葉を選んでいるような、何かを言うか迷っているような、優しげな見た目に反しバッサリと物を言う彼には珍しい反応だ。
「長義さんみたいな刀って、兄弟みたいな性格の刀とは圧倒的に相性が悪いんだよね。お互いが反発し合うというか、あまりにも反対過ぎて、理解出来ないからぶつかっちゃうというか……ほら、兄弟も変なところで意固地だし……その布とか」
「……布は絶対に取らないぞ」
指摘された途端に警戒を露にし、布を掴み引き下ろす国広を見て、堀川がまた唸る。なんだ、その目は。例え兄弟と言えど、その幼子の駄々に呆れかえったような目は気に入らなかった。
「そういうとこだよ……だからさ、一度長義さんの要求を受け入れてみればいいんじゃない?」
「は?」
彼は今、何と言ったのか。要求を受け入れる? ということは、あの次々贈られてくる身分不相応な煌びやかなあれこれを身に纏い、姫君が嗜むような教養を身につけて、長義の超理論にも反論せずに受け入れろと? 正気か。
「絶対に無理だ……っ!」
そんなことをするくらいなら折れた方がましだ。ほぼ反射的に叫んでいた。
「何も全部受け入れろってわけじゃないよ。ちょっとだけ許容範囲を広げてあげるのさ。例えば、着物とかだったら、皆んなの前で着るのはダメだけど、部屋の中だけだったら良いよ、とか。華道とか歌にしても、兵法や軍記を読む時間をくれるのなら、空いた時間で読んでみる、とか」
要は妥協出来るところを見つけて、それを条件にしてやれば良いのだと、堀川は言う。
「……そんなことであいつが納得するか?」
「多分許してくれると思うよ。……彼って策士なとこあるし」
「え……?」
「いや、こっちの話。まぁ、それで一度受け入れたと思わせておいて、上手いこと手綱を握っちゃえばいいんじゃない? そうすれば長義さんもある程度は納得するし、兄弟も絶対無理っていう一線は越えないわけだし」
大丈夫なのだろうか。堀川の言う通りに行動した自分を想像してみる。想像の中の長義は、部屋の中だけなら羽織を着てもいい、と言ったところで「周りに威厳を示さなければ意味がないだろう」と一蹴してきたし、空いた時間でなら稽古事に手を付けてもいいと言っても、「写し如きが本歌の命を片手間で済ませると?」と絶対零度の目で見降ろしてきた。挙句は写しが本歌に逆らうなんて云々と説教を垂れる始末。軽くホラーだ。想像しただけで気が滅入る。
「……やはり折れた方が、」
「あんまり言うと怒るよ」
その日はもう遅いからということで堀川と共に食器を洗い、そのまま部屋へと戻った。
暫くは冷え切った布団の中で考えを巡らせていたけれど、訪れた眠気には逆らえず。結果的に開き直った国広は、翌日長義が出陣から帰り、またいつものように国広の元へやってきたら、堀川の言っていた通りにしようとだけ心に決めて目を瞑った。
妥協点、というのはまだ決めていないが、それもまた明日考えればいいだろう。
なるようになる。夢現の思考回路でそれだけ呟いて、国広は夢の世界へと旅立った。