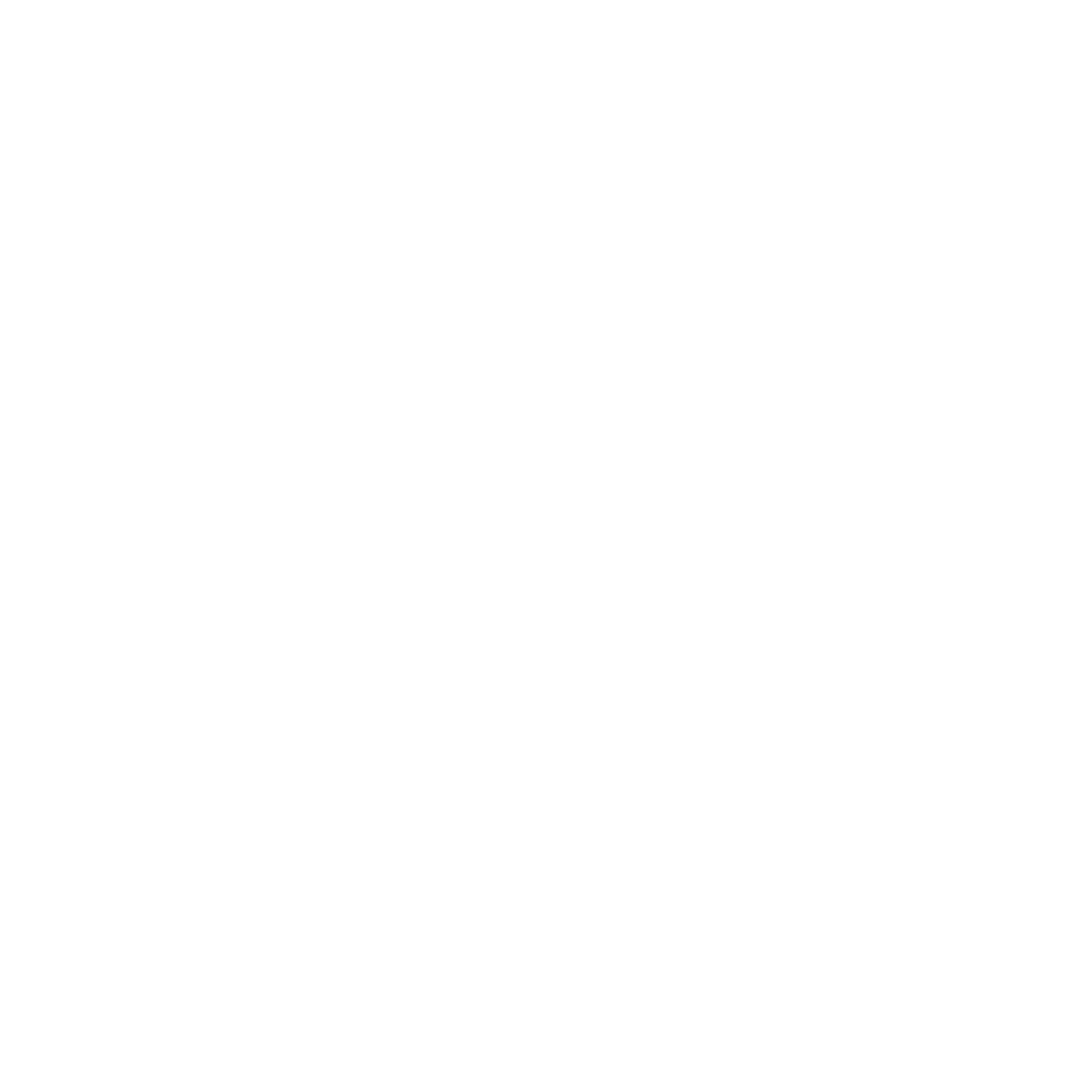第五話 本歌と写し
――慶長五年九月十四日。
歴史に残る大戦・関ヶ原の戦いが起こる前日。時間遡行軍の残党狩りに駆り出されていた山姥切長義は、深いため息を吐いた。毎日が出陣続きで疲労が溜まっているせいというのも勿論あるが、それ以上に頭の痛くなる事案が長義を苛んでいたからだ。
「なーんだよ、機嫌悪りぃな……」
うんざりとした声で、同じ第三部隊に所属する南泉一文字が話し掛けてくる。彼とは共に徳川美術館で所蔵されていたということもあり、それなりに長い付き合いだった。長義の機嫌の悪さをものともせず平然と接してくるのも、普段憎まれ口を叩き合っている関係ながらに、互いに気を許している証でもある。だからこそ長義は南泉の指摘にも噛み付くことなく、あっさり聞き流した。
「猫殺しくんは毎日が楽しそうで羨ましいよ。日向でゴロゴロしてれば悩みだって忘れそうだし」
「喧嘩売ってんのか、にゃ」
心なしかピンと張った猫の耳が見える。毛を逆立て、一直線に伸びた尻尾までもが見えたのは、きっと錯覚では無いはずだ。猫の呪いを受けているというこの男は、その本能に従って何処までも猫に近い行動をとる。長細い物を見れば蛇と間違えて飛び上がって驚くし、ちょろちょろ動く蹴鞠を見ればいの一番に駆け出して追いかける……その他にも様々な猫エピソードを披露してくれたこの男のこと。今更獣の耳やら尾の一つや二つ増えたところで、何らおかしな話ではないだろう。
さっさと呪いから解放されたい南泉からしたら、たまったもんじゃないことを考えながら、長義は言った。
「あの偽物くんのことだよ」
南泉がぱちりと瞬く。そして、すぐに咎めるような顔になった。
「お前、それやめてやれって」
君に指図される謂れはない、と何度言ったことか。最早同じことを繰り返すのも億劫で、ひと睨みするだけに留まる。しかし、南泉はそんな長義の苛立ちなど御構い無しに、さらに睨み返してくるものだから尚更腹に据え兼ねた。
「国広のやつ、あんま表に出さねぇからわかりにくいけど、結構キてんだぜ? 面倒なことになる前に、その呼び方を何とかしろ……にゃ」
さも自分の方が国広を理解してます、と言わんばかりの態度に、何となくイラッとする。
「だから、俺とアレのことについて、君にとやかく言われる筋合いはないと何度言わせるのかな?」
「関係大有りだ、にゃ。あの卑屈刀が思い余って……とかなってみろ。色んな意味でうちの本丸は終わんだろうが、にゃ!」
やけにあの偽物の肩を持つじゃないか。
言葉にはせず鼻白んだ。どうにもこの本丸の者たちは、アレに特別目を掛けているようで解せない。それらは本来自分に向けられるものだったのに。確かに写しは己の一部。写しへ向けられた賞賛の数々は最終的に本歌たる長義へ帰結するとはいえ、当の本刃がこの場にいるにも関わらず、あの写しばかりが目立っている現状は面白くなかった。
そもそも、アレは写しであるという自覚が圧倒的に足りない。己は本歌を引き立てる存在であるということを、本当の意味で理解しきれていないのだ。だから軽率に写しの領分を逸脱し、己の意にそぐわぬところで山姥切の号を喰いかける羽目になる。故意ではなかったにせよ、それはアレの不用意な行いが原因だ。もっと堂々と「俺は山姥を斬っていない」だの、「俺は山姥切の写しであって山姥切そのものではない」だのと主張し続ければ良かったものを。物であった時分は仕方がないが、自ら語る口を得た現在において、沈黙は悪と見做す。それは当然のことだった。
「……あんなものは偽物で十分だ」
「お前なぁ……」
呆れた目を向けられ、腹いせに足を踏んづける。「にゃっ!」と泣く子も黙る可愛らしい悲鳴が上がったが、それを揶揄うこともなく敢えて無視してやった。すると、顔を真っ赤にして怒った南泉が、仕返しをしようと長義の足がある場所目掛け思い切り踵を振り下ろしてくる。
「にゃおうっ!」
だが、南泉による渾身の一撃はあっさり長義に避けられ、その下にあった大きな石に衝突した。
「ふん、この俺が猫殺しの刀に遅れをとるわけがないだろう。斬ったものの格の差ってやつだよ」
乱れた前髪を指先で払いつつ、堂々と言ってみせる。
「お前マジで性格悪りぃ! にゃ!」
にゃーにゃー鳴かれたが響かない。お生憎様、長義は機嫌が悪いので。国広ではなく長義のことを、始めから『山姥切』と認識したことは褒めてやるが、気心が知れている分やかましいのが玉に瑕だった。特に今日のような日は、瑣末なことでも神経を逆撫でされて仕方ない。任務前にあの忌々しい写しと顔を合わせた時なんかは……。
(何故わからない)
関ヶ原出陣の前、国広と会った時のことを思い出す。
あの写し刀は練度が上限に達しているため、他の隠居組たちと共に本丸の大掃除を任されていた。どうせ暇だろうと思い、ならば時間を有効活用してやろうと……こんなにも完璧な本歌がやってきて肩身が狭くなってしまっただろう写しを哀れに思って、自分磨きの機会を与えてやったのに。あいつは感謝するどころか煩わしそうにするだけ。任務が終わり本丸へ帰る度、部屋の中に溜まっていく突っ返された着物も髪飾りも、歌仙経由で返された本たちも、嫌でも目に入る。何故長義の言う通りにしないのかと詰めっても、要らない、必要ない、無理だ、の一点張り。聞く耳などありやしない。それが本歌に対する態度かと説教すれば、反論はせずとも不満そうな顔をして黙り込む。最近はずっとそんなことの繰り返しだった。
(この俺が特別目を掛けてやっているというのに……)
親の心子知らずとはこのことか。
(確かにこんな素晴らしい名刀が本歌とあっては、気後れするのも頷けるが)
だが、あの態度はいただけない。本歌が名刀であることを誇りに思うどころか、あんな襤褸布に包まって現実逃避に明け暮れている惨めな写しなど、俺の写しというにはあまりに粗末だ。ましてや伯仲の出来と謳われた片割れがあれでは、この本歌の品格も疑われる。
「……偽物くんは何が不満なんだ」
理解出来ない。化け物をも斬ったとされる名刀中の名刀たる本歌・山姥切長義を基に作刀された写し・山姥切国広。自信を持つのに十分なバックボーンじゃないか。本歌たる刀がこの山姥切であることを自慢に思うこそすれ、あんなコソコソと人の目から逃げ回り、あまつさえ写しである身の上を恥じるような態度は、俺への侮辱にも等しい。
「これだから心が化け物になっちまった呪われ刀はよぉ。誰も彼もが皆、お前みたいな高慢ちきの強心臓じゃないってことだ、……にゃ」
一人ふつふつと湧き上がる怒りをやり過ごしていると、それまで黙っていた南泉が急に口を開く。
「何が言いたい」
「国広のみたいにぐちぐち考え込んじまう刀もいるってことだよ。呪いより厄介なもんを背負い込んじまった奴が、な」
呪いより厄介なもの?
何のことを言っているのかわからず、首を傾げた。訝しげな視線を南泉に送ると、当の本刃は意味深な言葉を投げつけてきたくせして、長義の無言の圧には素知らぬフリをし、一方的に話を切り上げた。その瞬間、モヤモヤとした黒い何かが再び心を覆っていく。
「……猫殺しくんのくせに、生意気な」
何を知った風な口を利いてるんだよ。そもそも何でお前の方が国広のことを理解してるような口ぶりなんだ。次から次へと溢れてくる不満が、ぷつ、ぷつ、と煮えては泡を弾けさせる。静かに背後へ忍び寄る粘着質な怒りは、長義の心も身体も縛り付け、果ては暫くその場から動けなくした。
「こんのすけから伝令だよー」
長義が怒りに侵食されつつあった時。こんのすけから指示を受けた蛍丸が、二振りの元まで伝言を伝えにやって来た。
「今から半刻後、松尾山付近で時間遡行軍の気配を察知。早急に排除にあたれってさ」
薙ぎ払っちゃうよ〜、と右肩をぶんぶん振り回す蛍丸の傍らで、岩融がガッハッハ! と豪快に笑う。本当に血の気が多い刀たちだ。こちらのことなどお構いなしのマイペースな二振りに面食い、長義は頭を切り替える。
「どぉれ、いっちょ狩りに出掛けるとしよう!」
「おー」
刀の本分は斬ること。それ以上でもそれ以下でもない。これから来たる戦場で如何に戦果を立てるのか。今はそれだけを考え、余計なことは切り捨てよう。
茂みに阻まれた道なき道を進む。落葉を踏みしめ、所々色づいた紅葉を前に秋の気配を悟った。ふ、と空を見上げれば、雲一つない澄んだ青空が青瑠璃の瞳に広がる。二振りの陽の気にでも吹き飛ばされたのか、長義の中で蜷局を巻いていた靄のような何かは、気がつけば綺麗に離散していた。
「待たせたな。お前たちの死が来たぞ!」
迷いを断ち切るかの如く蒼空の下で振るわれた太刀筋は、陽の光を反射して白銅色に輝いた。
長義と国広の関係に変化が起きたのは、二日に渡って続いた関ヶ原の残党狩りが終了した、大晦日の晩。国広から長義が押し付けた和歌の教本を突っ返された、その翌日のことだった。
「……手入れは、」
時空移転装置から降り立ち、過ごし易かった秋の戦場の空気とは打って変わった冬の寒さに、ぶるりと身震いする。べっとりと戦装束に染み込んだ返り血が冷たい夜風に煽られ、一層体温を奪っていくのが忌々しかった。傷は軽傷程度。手入れ部屋に入るか迷うくらいのそれに逡巡したのも束の間、長義は躊躇うことなく否の判断を下す。
「……それより風呂、かな」
手入れをするくらいならさっさと一風呂浴びたい。すん、と鼻を鳴らせば血の匂いがこびりつき、先ほどから一向に興奮が収まらないのだ。これは刀の本能だ。獲物を斬り、葬り、血を啜って生きている玉鋼としての本能。ままならない燻りを内に秘めつつ、第三部隊の面々と別れた長義は、その足で真っ直ぐ湯殿へと向かった。兎に角戦の残滓を流し落として身体を温めねばなるまい。その足取りに迷いはなかった。
「……っ」
「おっと……なんだ、偽物くんじゃないか」
湯殿へと続く廊下を曲がった時、丁度湯浴み帰りの国広と鉢合わせた。
時計の針は既に子三つ時を回っている。大方人目を避けて湯浴みに来たのだろう。まったく精の出ることだ。人気がないことで油断してか、いつもより無防備な様子の国広の身体には、申し訳程度に布が被さっているだけであった。よって、普段はあまり見えないその顔も、今は驚きに見開かれたその翡翠の輝きまではっきり見透せる。
「髪くらい乾かせ。この寒さだ、風邪を引くだろう」
体調管理がなってないんじゃないか。
そう鼻で笑いながら言ってやれば、自尊心が低い割りに負けん気の強い写しはキッとこちらを睨みつけてくる。あぁ、その目だ。その目が気に入らないのだ。思わず眉根を潜め国広を睨み返すと、彼はぐっと布を引き下ろしその鋭い眼光を隠してしまった。逃げを打つくらいならば始めから喧嘩を売らなければいいものを。戦で発散した筈のどす黒い何かが、再び長義の腹の底で首を擡げた気配を感じ、それを宥めるために深く息を吐き出す。
「ふん。まぁ、せいぜいそうやってコソコソ逃げ回っていればいいんじゃないか」
「……」
「俺は忙しい身だからね。お前の相手をしている暇はない。そら、さっさとそこを退け」
もう知るか。めんどくさい。
戦後の疲労と昂ぶりも相まって、何だか何もかもがどうでもよくなってくる。正直気が昂ぶっている時に会いたくなかった。ただでさえ彼には苛つかせられることが多いのだ。今の理性が磨り減った状態で国広と相対すれば、容易に長義の心は乱されてしまうに違いない。それは本意ではなかった。本来の長義は冷静で、己のペースを乱されることを酷く嫌う刀なのだ。
「……おい」
「何かな」
しかし、国広は長義の思惑とは裏腹にそこから去ろうとしなかった。いつもならこれ幸いとさっさと視界から消え去ろうとする彼が、珍しいこともあるものである。何か言いたげにその場に佇む彼はキョロキョロと周りを見回し、布の下から覗く桜色の唇を開いたり、閉じたりと落ち着かない様子を見せている。何をしたいのかわからなくて、不気味なことこの上なかった。
(何のつもりだ……?)
長義を引き留めたくせになかなか本題へ入ろうとしない国広へ、苛立ちが加速する。
「用が無いならそこを通してもらえないかな。見てわかるだろう。出陣帰りでね、疲れているんだ」
「ぁ……」
はぁ、やれやれ。愚鈍な写しと関わるとこれだからいけない。
もう構うことなく押し退けてしまおう。そう思い至り、長義が国広の肩に触れたその時だった。
「……あんたが贈ってくれた羽織、着てやってもいい」
「……は?」
すぐに肩から離されるはずだった掌の動きが止まる。
「あの花とか歌とかの本も、目を通してやる」
突然なんだ。こいつは何を言っている?
いや、わざわざ言わなくていい。ちゃんと意味はわかっている。俺は優秀だからね。だが、「着てやってもいい」とか「目を通してやる」とか上から目線なのが腹が立つとか、このタイミングで言うとか何考えてんだとか、突然の手のひら返しなんて何を企んでいるんだとか、言いたいことは山のようにあったのだけれど。一番に覚えたのは戸惑いだった。
「……はぁ?」
一度ならず二度までも、間の抜けた声を出した自分を折りたい。しかも、このクソ生意気な写しの前で、無様なところを見せるなんて。
「お前ね、」
「ただし、条件がある」
条件だって? 一丁前に何を偉そうに。
怒り狂うには動揺が大き過ぎた。あと、ここ連日続いた出陣の疲労が濃すぎた。何だろう。もう何も考えたくない。完全に頭が考えることを放棄している。
「他刃の目のないところなら、あんたの指定したものを着てもいい……外に着ていくのは……無理だ。すまない」
「……」
周りに威厳を示すために、そのみすぼらしい恰好をやめろと言っているのに、人目のないところで着るなら意味がないだろう。そう噛み付こうとした長義の言葉は、今にも掻き消えてしまいそうなほどに頼りない、国広の声によって遮られる。
「あんたの言う教養とやらは……戦事の知識を得る方を優先したいから、常にというのは難しいが、空いた時間で少しずつ学んでいく」
この本歌の命を片手間扱いか。失礼にも程があるな。こいつ、本当に本歌への尊敬だとか礼儀をこの数百年の間にどっかに捨ててきたんだな。
「いや……お前、ほんとさ……」
言葉にならない。頭を抱えた。他にどう反応しろというのだ。この意味不明な思考回路をしている写しの言葉を、誰か通訳してくれ。
「……ダメか?」
あれだけ数々の地雷を踏み抜いておいて、不安げに瞳を揺らしながらこちらを見る様は、酷く幼い。はぁー、と長いため息を吐いてしまったのは仕方ないことだった。内に溜まった澱みを吐き出さなければ、今にも叱りつけてしまいそうだったからだ。
尋常じゃなく腹が立つ。されど、何の心境の変化かはわからないが、少しでも長義の声に耳を傾けるつもりになったのなら、こんな機会は滅多にない。この本丸に配属になってから日の浅い長義だけれど、今までの国広がどれだけ頑なであったかは古参の連中から散々聞かされていたので知っていた。あのどんな時も己の姿を見せようとせず、布を手放さなかった男が、長義の前でだけならばその布を外してもいいと言っている。
(……まぁいい。急いているわけでもなし。今は無理でも、徐々に慣らしていけばいいだけのこと)
確かに本来の目的からは外れてしまうが、それでもそれは大きな前進であることには違いない。要は己の匙加減一つで、吉と出るか凶と出るかは変わるというだけの話。ならば、ここは妥協してやって、大変腹立たしいし不本意ではあるが、偽物の言う条件とやらを飲んでやろうではないか。
どのみち長義が手綱を握るのならば、最悪の方向へ転ぶことなどありはしないのだから。
「……いいだろう。俺は持てるものだからね。お前のように余裕のない奴に慈悲を見せるくらいのことはしてやろう」
ぽん、と。ほぼ無意識に国広の頭に手を置いた。
二度ほど軽く叩いてやれば、驚愕に見開かれた大きな目が、口元を緩ませた長義の顔を映し出す。
「励めよ」
今度こそ国広を押し退けて風呂へ向かった。身体は既に芯から冷え切ってしまっている。本丸の風呂は夜戦から帰還した部隊も自由に入れるように、基本的には昼間の清掃時以外はずっと解放されていた。まだ湯船の湯は温かいままだろう。
「ふぅ……」
明日は久々の非番だ。ゆっくり湯船に浸かって疲れを癒そう。あの困った写しをこれからどうしていくのかは、またその時考えればいい。欠伸混じりに明日の予定へ思い馳せていた長義は、不意に最後に見た国広の間抜け面を思い出した。
呆気に取られ口を半開きにしたままこちらを見ていたあの顔は、何度思い出しても傑作である。
(悪くない)
あの翳り一つない澄んだ翡翠の瞳は、純粋に好ましいと思った。
*
新年を迎えてからというもの、二振りの山姥切が、目立って喧嘩をしなくなった。
本丸内でそう囁かれるようになるのはすぐだった。顔を見ても長義が突っかからない。国広があからさまに長義を避けるようなことをしない。それどころか偶に、本当に偶にではあるが、二振りが普通に会話をしているところがちらほらと目撃されている。そんな彼らを見てほっと胸を撫で下ろした者もいれば、嵐の前の静けさなのではないかと訝しげにする者もいて。当の本刃たちを除いた周囲の刀たちは、戦々恐々と……否、興味津々とその状況を静観していた。
(いつ来てもすごい部屋だな……)
一方その頃、そんな皆の心労など知る由もなく、国広は非番だという長義の部屋に邪魔をしていた。
本丸内では稀に見る、ダークブラウンの木目調で統一されたフローリングの洋室。奥に置かれたシングルサイズのベッドの横には、寝台の高さに合わせられたベッドサイドテーブルが置かれていて、机上に閉じられたノートパソコンと、ステンドグラスのあしらわれた小型のランプが置かれている。また、全体的に深みのある真紅を基調としたインテリアは、決して派手ではなく寧ろ品よく空気を引き締めており、まるで西洋の城のような格式高さを思わせた。
(流石は長船と正宗の流れを汲む刀、といったところか)
長義の部屋を訪れる度にひしひしと痛感する。彼と自分の差異を。格の差というものを。やはり、国広の傑作ではあれど写しは本歌には勝ることは無いのだと、まるで責め立てるかのように己を囲う完璧な部屋に、思うのだ。
自分と彼は似て非なる存在であるのだと。
「……なあ、」
クローゼットの中をごそごそと漁る背中に声を掛ける。
「なんだ」
「……その……いくらなんでも買い過ぎじゃないか?」
ぽいぽいっと次々投げつけられる着物や装飾品やらを受け止めながら、国広は引き攣った顔で言った。すると、クローゼットの奥から顔だけ覗かせた長義が、部屋の真ん中で心許無さそうに突っ立ったままの国広へジト目を送る。
「お前が服を持たな過ぎるんだ。大体どうしてあのセンスの欠片もないジャージと、安っぽい着流ししか持ってないんだ。ありえないだろう」
「……いや、外に行くときは戦装束があるし、本丸内で過ごすだけならジャージで十分だろ」
「そういうところだよ、偽物くん」
「写しは偽物じゃない」
また、偽物と言ったな。
彼から呼ばれる蔑称に一々訂正を入れるのも億劫になってきた。しかし、ここで受け流してしまってはその呼び方を認めたみたいで癪であるし、無駄だとわかってはいても訂正させてもらう。
「はぁ……おい長義、」
「……長義だと?」
「……?」
ぴたり、と。それまで服を漁り続けていた長義の動きが止まる。
「……お前、いつからそんな風に呼ぶようになったんだ?」
ぐいっと金糸の刺繍を施された濃紺の羽織を、いつにない力で押し付けられ、たたらを踏んだ。ハッとして前を見ると、眦を吊り上げた長義が、憎々しげに国広のことを睨みつけている。国広が長義に対し柔軟に対応するようになってからというもの、こんな彼の表情を見るのは随分と久しい。
(しまった……)
今まではあんた、とか、おい、とか名前を呼ばないよう気をつけていたのだが。こう何日も顔を合わせていると、あれほど苦手意識を持っていた相手であろうと、気が緩んでしまうものらしい。
馴れ馴れしかっただろうか。けれど、長義と呼ぶのが不満だというのなら、他に彼のことを何と呼べばいいのか……。長義、と呼んだのは、写しとして不出来と思われている国広に、本歌や山姥切と呼ばれては不快に思うだろうと考えた末の結論だった。しかしその判断は、彼の反応を見る限りは完全な悪手となってしまったようだ。
「山姥切と呼べ。あるいは本歌と。お前がその名で呼ぶことは許さない」
ごくり。思わぬ言葉に息を呑む。まさか、その名で呼ぶことを許されるなんて、夢にも思っていなかった。
「しかし、」
「何か文句でも?」
「俺は……あんたの写しとしては不出来で、だから偽物なんて呼ばれていて……あの時だって、あんたは顔を見せてくれなかっただろう。だから、俺があんたを本歌と呼ぶのは烏滸がましいと……」
そこまで言って漸く、長義は合点がいったようだった。それまでのピリピリと張り詰めた空気を一変、呆れ混じりのそれへと軟化させた長義は深く息を吐き、布越しに国広の額を小突く。
「お前は馬鹿なのか?」
「は、」
馬鹿、と言われてムッとするも、目の前の整った顔は何処までも真剣で、怒りが削がれる。無言で発せられる圧に気圧されていれば、長義は再び国広の額を二度ほどノックし、言葉を紡いだ。
「お前に長義と呼ばれる方が虫唾が走る。お前は写しなんだから、俺を本歌と呼ぶ度に己の写しとしての立場というものをその身に刻み込め」
急に視界が開けた。長義が、国広の纏っていた布の留め紐を解き、あっという間に取り去ってしまったのだ。
「お前は自覚が足りないからね。それくらいで丁度いい」
それだけ言って満足そうに離れていった男を、じっと観察する。写しだということは、一応認めてくれてはいるのか。それがわかっただけでも幾分か気は楽になった。
ずっと疎まれていると思っていた。共に展示されたあの日。国広は数百年ぶりの再会ということもありすっかり浮かれていて、本体が移されるその日が来るのを今か今かと指折り数えていた。しかし、いざ対面してみると、刀本体の姿はあれど長義の姿は見当たらず。何日か待ってみても一向に姿を現さない。ならばと思って根気強く声を掛けてみても、返事はなくひたすらに無視され続けた。そこで自分は、彼にとっては顔を合わせる価値すらない刀なのだと思い知らされたのだった。
(そうか……てっきり失望されてしまったのかと……)
顔を見るのも、名を呼ばれるのも拒まれるほどに。
「なら、あんたは何で……」
――あの日、会ってくれなかったんだ。
そう続けられる筈の言葉は、吐き出されることは無かった。
「……むぐっ」
「うるさいよ」
乱雑に両頬を掴まれて手で口を塞がれる。意図せずひよこの嘴のような形となった唇は上手く言葉を紡げず、むぐむぐと不恰好な鳴き声を上げさせられる羽目となった。そんな間の抜けた国広の顔が面白かったのだろう。暫く国広の頬を掴んだまま、そのもがく様を楽しげに眺めていた長義は、ややあって国広が手に持っていた着物を掴み、それを着るよう促してくる。
「ぴーぴー鳴いてる暇があるなら、さっさとこれを着ろ」
「……こんな綺麗な物は俺には釣り合わない」
しかし、いざ長義から着物を渡されると、国広は固まった。
手触りはちりめんと西陣織の中間といったところだろうか。光沢のある滑らか且つ軽い生地感は、これがそれなりに値が張るものであることを示している。水のようにするすると流れる生地を指先で撫でて、思わず気後れしてしまった。素人目でもわかるほど、あまりに見事な逸品であったから。
「こんな……見るからに高そうな物を……俺が……?」
無理だ、無理。絶対に無理。
裾にかけての濃藍のグラデーションが美しく、ご丁寧に襟のすぐ下の部分に刀紋の刺繍まで施されたそれ。長義がオーダーメイドしたのだと思われる着物は、国広が纏うには些か上質が過ぎた。
「自分の言ったことを反故にするなんて、そんな情けない真似を俺の写しがする筈ないよな?」
「……っ」
「そら、早くしろ」
布は既に奪われてしまっている。加えて言質を取られてしまっている以上、国広に着ないという選択肢は残されていなかった。渋々下着以外の全ての服を脱ぎ去り、肌着を身に付ける。先に足袋を履いてから長襦袢に袖を通せば、そこで初めて衿元の差し色が深い青であることを知った。長義の瞳の色だ。思わずこの着物を押し付けてきた元凶へ振り返ると、彼はピクリとも表情を動かすことなく国広の動きをひたすら見つめている。その無機質な眼差しに射抜かれ、心臓が凍りつくような心地になった。
――見定められている。
直感でそう思った。足利で共に在った頃、よく向けられていた目だ。
「……何故ここまでするんだ」
気づけば口から滑り落ちていた。ずっと昔から疑問だった。何故、彼はここまでして好んでもいない写しを磨き上げようとするのだろう、と。彼にとって、何の得にもならないことを、どうしてわざわざ。
「あんたの時間や金を割いてまで、こんな……」
「そう思うならさっさと自覚してくれないかな」
「自覚?」
完全に手が止まってしまった国広を咎めるように、長義が目を細める。慌てて留守になっていた手を動かし、着付けを再開した。やっとの事で慣れないながらも長襦袢を着終えると、裾が若干広がっていたようで容赦無くダメ出しが飛んでくる。
「……お前が俺の写しであることの自覚だよ。俺たちは伯仲の出来とも呼ばれているんだ。お前がそんなにみすぼらしい恰好をしていては、本歌の品位まで疑われるだろうが」
長襦袢が合格ラインに達したところで、遂に着物の着付けに入った。角帯の色は藍に引き立つ空色鼠。これまた素材は正絹と手触りが良く、一目一目織り込まれた織柄が見事である。
「だが……俺がこうして汚くしていれば、誰も綺麗なあんたと比較する奴なんて……」
「言っておくが、それは逆効果だ」
「え……?」
右手に持っていた男締めが滑り落ちた。
逆効果。今まで国広がやってきた行動のすべてが無駄だったと、この男はそう言ったのか?
「なぁ、偽物くん」
床に落ちた男締めを手に取り、そのまま長義は国広の腰へ手を回す。慣れたような手つきで男締めを結ばれていく間、国広はいつものように「写しは偽物じゃない」と否定することも、淡々と着付けを進めていく長義の手を制止することも、何も出来ずにいた。
しゅるしゅる、という布擦れの音だけが、二人きりの部屋の中で響く。硬直した身体は指一本動かすことは許されず、こめかみを冷や汗が伝った。
「どうしたって人の子は、俺と写しを比較する。俺はね、比較され続けるのはもう懲り懲りなんだ。お前だってそうだろう?」
その長義の主張には同意しかなかった。徐々に取り戻しつつある思考を総動員させて、国広は従順に頷く。
「あぁ……俺も比較されるのは嫌だった。だから俺は、あんたとかけ離れた姿になろうとみすぼらしい格好をして、比較されないようにあんたから離れようと……」
「はぁ……呆れた。お前はこの数百年で何を学んだんだ」
きつく角帯を結ばれ、うぐっと苦しげな声が漏れる。部屋の温度がみるみるうちに下がっていった。何か嫌なことでも思い出したのか。目下の男の機嫌は急激に悪くなり、その美しい青瑠璃に翳りが帯び始める。
「俺たちが離れて過ごした結果、どうなった? お前を見た人の子はそこにあるはずのない本歌を思い浮かべ、期待と理想で塗り固められた虚像とお前を比較する。その逆も然りだ。俺だって、傍にはない写しの存在と散々比較されてきた」
「それは……」
「果ては、本当に山姥を斬ったのはお前の方だなどと戯言を……だから、俺は考えた。なに、簡単な話だったのさ。人の子の想像の中で膨らんでいった虚像と比較されるくらいならば、初めから隣にあればいいだけなのだと。そうしたら、人の子たちはありのままの俺たちを比較する。比較した上で評価する。比べる必要のないほど、『両者共に優れた名刀である』と」
「……っ」
最後の部分だけ、ぐっ、と顔を近づけ囁かれた。まるで愛の告白のようだ。実際はそんな甘いものではないけれど。それでも長義の声色には彼自身ですら気づいていない甘さが、一欠片分宿っていた。
「だが、俺の隣に並び立つお前がそんな様では、本歌たる俺の面目が丸潰れだ。だから、俺はお前を躾し直してやると言ったんだ」
「……そんなこと、言われていない」
半ば意地で反論する。声は震えていなかったろうか。それだけが気になった。耳に直接吹き込まれた甘い毒が、なかなか国広の身体から抜けない。
「俺は言った」
「覚えてない」
「それはお前の頭が空っぽだからだ」
「……写しだからと侮るな」
反射的に睨みつけると、さらにそれ以上の眼光でもってして睨み返される。
「侮ってなどいない。俺はお前をこの上なく評価している」
「……っあんたは、よくもそうやって恥ずかしげもなく、」
そんなの卑怯だ。今までの冷めた態度から打って変わって、そんなことを言われたら乱されるに決まっている。それを見越してやっているのだから、この男は尚更タチが悪かった。
「だから、弁えろ。お前は俺の写しであることを誇れ。そして俺の傍に在れ。それがお前の生まれた意味であり、義務だ」
はい、おわりおわり。
最後にバシバシと背中を叩かれ、着付けの完了を告げられる。姿見の前まで通されて己の姿を確認すれば、そこには普段ずっぽり被っている襤褸布を取り去った自分自身が、凛と背筋を伸ばして立っていた。触れることすら躊躇われた上質な着物は、長義の腕が良かったからなのか一糸乱れず着付けられている。小さめの貝口結びがまた小粋で、動いた拍子にちらりと覗く、羽織の裏地に描かれた大柄な花々が、良いアクセントになっていた。
「俺の写しならば当然のことだけど、お前はそうしていると美しいね」
和装になると自ずと背筋がしゃんとする。物珍しそうに鏡の中の自分を凝視していた国広へ、長義が言った。
「美しいとか、言うな……容姿に関する称賛は、本来あんたが受け取るべきものだ。俺のものじゃない」
途端に居た堪れなくなり、無い布を引き下げようとして掌が空を切る。そうだった。布は今長義の手の中だった。物言いたげに長義の方へ視線を送ると、彼はそんな国広の訴えには徹底的に無視を決め込んで、白々しく話を続ける。
「だから自覚をしろと何度言わせる。お前は俺の写しだろう。名刀・山姥切という存在を引き立たせる存在……つまりは俺の一部であるならば、俺への称賛はお前への称賛とと同義だ。余すことなく受け取ればいい」
それは違う、と心が否を唱えた。国広は長義の写しであるが、だからといって国広が長義の一部であるわけではない。それに、国広は長義に似せて作られたものではあるけれど、二振りは作刀した刀匠も違えば伝わっている逸話だって異なるのだ。まったく別の存在だ。
「……俺は、俺だ。あんたの写しであることは確かにそうだが、それと俺があんたの一部であるのとは……違う」
「……へぇ」
長義が徐に口を閉じた。その顔に表情はない。美人の真顔は怖いとよく言うが、まさに今の彼がそれだった。何の温度も感じられない長義の表情が、酷く恐ろしい。
「写しが生意気な口を利く。俺を基にして生まれたくせに、独立した存在として対等に並び立とうというのか?」
「……そ、そういうことではないっ」
ぶんぶんと勢いよく頭を横に振る。それだけは誤解して欲しくなかった。国広が彼の横に並び立つなど、そんな大それたことを考えたわけでは。
「違う、そうじゃない。そうじゃないんだ、本歌と対等なんて……そんな、」
「お前の言っていることはそういうことだ。……いいかい?」
隙のない動きで首へ手を掛けられる。初期刀として本丸を牽引してきた国広と、本丸へ来て間もない長義。二振りの間には紛れもなく大きな練度差があった。されど、そんなことは一切匂わせない動きで、長義は国広の急所に容易く指先で触れてみせる。
「ァ……、」
ひやりと冷たい温度が、長義の身に付けている黒い手袋越しに伝わる。ゾッと背筋が凍りついた。
「お前は俺の誉の証。俺の写しであり一部。身の程を弁えろ。二度とそんなことを考えるな。万一『また』写しとしての領分を越えてみろ――」
「……っ」
「ぶった斬るぞ」
喉仏を強めに親指で押され、ゴホゴホと噎せる。何か術でも掛けられたかのように身体が動かなかった。目の前でギラつくあの青瑠璃から、目を逸らせない。
(本歌……)
違う、違うのだ。何故、わかってくれない。国広は、長義の逸話を掠め取ろうだなどと考えてはいないし、彼の隣に並び立とうだなどとは思いつきもしなかった。そもそも自分は山姥切の号にそれほど強い執着を抱いていない。例え山姥を斬っていなくとも、俺は刀匠堀川国広の第一の傑作……それこそが揺らがぬ矜持であったのだ。
だというのに彼は、写しとして傍に在れという。
山姥切と名乗ることを許さぬくせに、山姥切の一部として在ることを望む。
そして今日も、無防備に背中を晒しておいて、いつ牙を剥かれるかと警戒しているのだ。矛盾極まりなかった。されど、彼はきっと、そう在ることでしか生きられない。わかってはいるが、国広とて譲れぬものがある限り、本当の意味でわかり合うことはない。
(俺は……俺、だ)
独立した一つの刀だ。それ以上でもそれ以下でもない。
閉じた瞼の裏側で、ぐちゃぐちゃに熟れた石榴が、地に落ちる様を見た。枯葉の上に落ちたそれはべしゃりと醜い音を立て、真っ赤な果汁を撒き散らして潰える。
あれはきっと、己の心の臓の行く末。どうしてかそう思った。
そう、あの穴だらけの果実は、きっと。
互いに喰らい合い、磨り減った先に待っている――二振りの成れの果て。
*
ぱちん、ぱちん。
命を絶つ音が響く。右手に持った花鋏で茎を断ち、水を入れた器の中で水切りをする。長さを整えた花々を剣山へ突き立てれば、美しい標本の完成へ一歩、また一歩と近づいていく。
「君も随分と手慣れてきたじゃないか。結構、結構」
竜胆色の髪を指先で払い、感心したように歌仙が言った。彼に空いた時間で稽古をつけてもらうようになってから、早くも一ヶ月が経つ。頻度こそそう多くはないまでも、はじめの頃と比べればマシなものを活けることが出来るようになった。
二月になった。まだまだ寒さの続く今日この頃。春の訪れを前にして景趣は徐々に彩りを取り戻しつつあり、丸裸の木々に新緑が芽吹き始めている。
「……そうか。だといいが」
猫柳、菜の花、レンギョウ。
歌仙自らが春をテーマに選んだ花材を活け、何も無かった空間に小さな箱庭を造ってゆく。ひたすらに無心で、心を空っぽに。
ぱちん、ぱちん。
しなやかな枝を強引に捻じ曲げ、美を形作る。悲鳴はない。何故なら植物だから。既に息絶えた骸を己の都合の良いように弄び、美しいと称される作品を作り上げる。なんという残酷無慈悲な。なんというエゴ。雅だの風流だのを愛する歌仙に言えば怒られるかも知れないが、国広はこの華道というものに本能的な嫌悪感を抱いていた。
まるで、長義によって歪められていく己の様を見ているようだから。
「君たちの関係が良好になったと、本丸内では宴をするかなんて話も出ていてね」
伸び伸びと枝を広げた猫柳を剣山に突き刺しながら、歌仙は続ける。
「僕としても君たちの仲が改善されたのは嬉しいんだが……本当のところはどうなんだい?」
「どう……とは?」
質問の意図がわからず、無粋とは理解しつつも問いに問いで返した。すると、歌仙は徐に手を止めて、花器から顔を上げる。真っ直ぐにこちらを見る胆礬色に、薄汚い布を被った男の姿が映った。これこそが俺であるのだと、強い光を湛えた瞳をその奥に隠した、男の姿が。
「君たち、ただ仲良くなったというわけではないんだろう?」
サー、と雨粒が地に叩きつけられる音が、部屋に木霊した。分厚い雲に覆われた空は濁りきった鼠色をしていて、陽の光が無いせいで部屋の中は薄暗い。
電気を点けようという国広の提案に、歌仙は頷かなかった。曰く、自然をそのまま感じて活けるのも、また風流なのだと。窓を開け放ち、晴れ渡った蒼空の下で活けるのならまだしも、こんなにも天候の荒れた日にすることなのか、なんていう言葉は飲み込んだ。最近はずっとそうだ。否と感じても言葉を表に出すことをしない。無理矢理己の中に飲み込んで、奥まった場所へ押し込んで、ぶすぶすと燻った何かが消化されるのを静かに待ちながら、ただ与えられたことを熟していく。
そう在るように、求められているから。己が抗えば抗うほど、息が苦しくなると知っているから。それは己だけではなくあの男も……どうしようもなく苦しくなることを、わかっていたから。
「仲が良いというわけではない」
雨音の響く部屋に、言葉が落ちる。
「本歌曰く、俺はあいつの物なんだそうだ。だから、俺を自由にする権利はあいつの方にあると……そう、言われた。元よりそんな関係だ。仲が良いとか悪いとか、そういう次元の話じゃない」
「……それで、いいのかい」
――励めよ。
幼子にするように頭へ掌を置き、優しげな目をするようになった男の姿を思い出す。
初めの殺伐とした空気が嘘のように、最近の彼は穏やかだった。長義の部屋の中だけで行われる着せ替え遊びでは、自身で着飾った国広を綺麗だと、美しいと手放しに褒めては満足げに口元を綻ばせる。歌仙のおかげで上手く花が活けれた時や、歌が詠めた時も、国広が生んだ作品のすべてに必ず目を通して、何故か長義の方が得意げな顔をした。
国広の存在を、少しは誇りに思ってくれている、らしい。
少しずつ積み重なった喜びが心に降り積もって、雪解けの下からじんわりと温かな何かが芽生え始めたのを感じる。長義の喜ぶ姿が見たい。最近ではそう思うようになってきていて、あれだけ億劫で仕方なかった着せ替え遊びも、稽古事も、それほど抵抗感が無くなった。
(これで、いい……のか?)
今までは考えないようにしていたこと。目先の小さな幸せを隠れ蓑に、目を逸らしていたもの。国広と長義の間にある、深い深い溝の存在。絶対に相容れない二振りの価値観と在り方について、考えることを放棄してしまっている自分は、果たして己が己であると胸を張って言えるのだろうか。
「……わからない」
それでいいのか、という歌仙の問いには、今はそうとしか答えられない。
自分で自分がわからなくなってきている。歪められている。それだけは確かなのに、それを恐ろしいとも、気味が悪いとも思わないのが重症だった。
「……あんたの目から見て、俺たちはどう映る」
「そうだねぇ」
うーん、と唸った歌仙はしかし、苦く笑うばかりでなかなか答えを言おうとしない。
「……僕の目には、どっちも苦しそうだなって思うよ。少なくとも雅ではないね」
彼らしい言い回しの返答に、国広は身体を縮こまらせた。このままではいけないということは、薄々理解していたのだ。
「あぁ、そうだ」
どことなく気まずくなってしまった空気の中、歌仙がぽんっと手を叩く。何を思い出したのだろう。そう不思議に思って彼の姿を眺めていれば、歌仙は国広を置いて部屋の奥へ引っ込んでしまい、間仕切りの襖越しにごそごそと何かを漁る音が聞こえ始めた。
「今君が山姥切殿から色々と着せ替えられていると聞いてね」
「……?」
「はい、これ」
ややあって戻って来た歌仙から手渡されたのは、一枚の白い羽織。裾部分に紅や金に色づいた紅葉の刺繍の施されたそれは、長義から与えられるそれと同じくらいに上質なもので、一瞬理解が追い付かなかった。
「これを君に着て欲しくて。本当は山姥切殿が本丸に来る前から誂えてあったんだけど、ほら、国広は頑なだったろう? 渡しても突っ返されそうだったから、タイミングを見計らっていたのさ」
山姥切殿には感謝しないとね。
無事に国広が受け取ったのを見て、歌仙が達成感に浸る。そんな彼を前に当の国広自身はというと、何故自分がこんなにも立派な物を贈られているのかわからず混乱した。
「どうして俺に……?」
戸惑いがちに問うと、ギラリと目を光らせた歌仙が、声高に理由を並び立てていく。
「君のその汚い布! 僕の美的感覚がどうしても許せなくてね。君はそんなに綺麗なのに勿体無いと常々思っていたのさ。だから、機を見計らって隙あらば雅なものを着せようと……いや、違う。うん、まぁ、古参組として、長年世話になってきた初期刀殿への礼みたいなもの……かな」
このごり押し文系刀め。絶対に前半が本音だろう。いい風に締めた気になっている歌仙を繁々と見つめても、半笑いでのらりくらりと躱されてしまい、大した威圧にはならなかった。それにしても、日頃の礼とまで言われてしまったからには受け取らないわけにもいかない。加えて長年の付き合いから簡単に筋を曲げる男ではないと知っていたので、手の中に押し付けられた羽織は有難く頂戴することにした。着るか着ないかはさておいて。
とりあえず、今言わなければならないことは……。
「……綺麗とか、言うな」
「ふふ、はいはい」
途中で放置してしまった花々と再び向き合う。
長時間空気にさらされていたせいで、花は少しだけ萎れてしまっていた。雨脚はどんどん強くなっていたけれど、何も気負わない言葉の応酬に紛れてしまえば、じめじめと湿った辛気臭い音なんて、何も気にならない。
やっとの思いで完成した標本は、些か形が歪んでしまっていたものの、暖かな陽だまりを思わせる、春の縮図のようだった。
晴れた空の下なら尚映えるだろうと言って笑った歌仙は、じきにここへやって来るであろう長義のために、二つの花器を文机の上に並べて飾った。