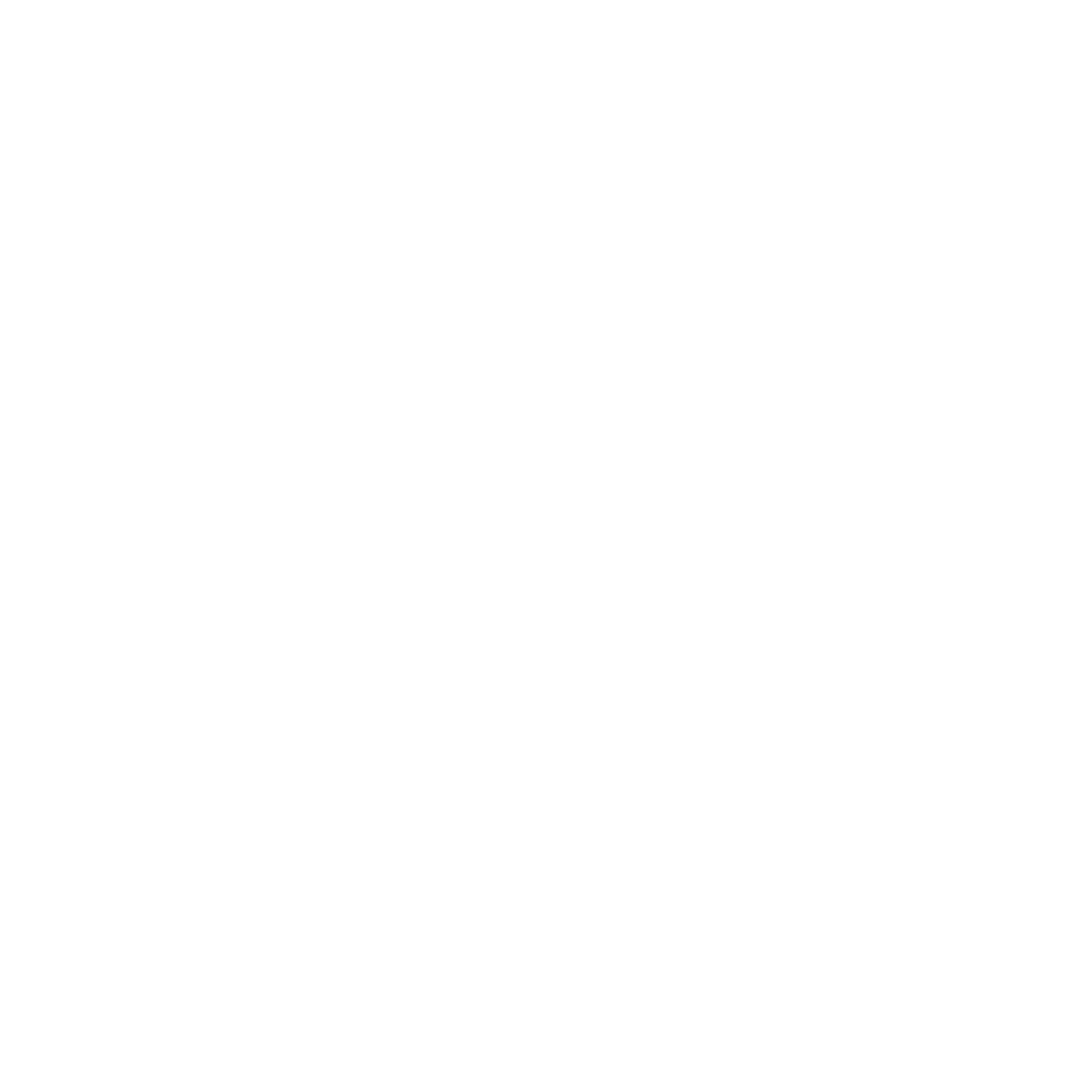第六話 奪い、奪われ
大切にしまい込んできた至極の珠を、箱から取り出しては光に照らす。陽の光を受けて輝くそれはこの世ならざる美しさで、こちらを魅力するくせ己を卑下して萎縮する。俺にそんなものは不釣り合いだと、美しいと言うなと拒んでは、男の無償の寵愛を受けておきながら、あの薄汚れた布で全てを隔てて拒絶するのだ。
男の好意も、慈悲も、憐憫も。すべてを拒んで斬り捨てる。しかしてその美しさはそのままに、それこそ男に言わせれば、不釣り合いな襤褸布に包まって、平然とした顔をして外界を転がる。
「……山姥切」
俺はおかしくなってしまったのだろうか。
「……なに」
「……着たぞ。そら、これで満足か」
己に釣り合うだけの装飾品とすべく磨き上げた筈のその珠を、このまましまい込んで誰にも見せたくないとすら思っている。
「またベストが皺になってるし、タイも歪んでるよ。偽物くんはまともに服も着れないのかな。直してやるから、こちらに来い」
いつの間にか手段が目的へ変わっていた。
そんな自分を自覚した瞬間、長義はそこまでショックを受けなかった。まぁ、そうなるだろうなと。心の何処かで考えていたのかも知れない。何せ、コレの本歌たる己自身が、人を狂わせるほどに美しく、気高い名刀であるのだから。そして、この本歌の写しであるこの刀も等しく名刀。ならば、自分がこれを気に入るのも仕方のない話。例え写しの領域を逸脱しようとする不届きものであろうとも。
(それに、過ぎた真似をするなら躾けてやればいいだけの話だ。何、減るものではなし。俺は持てる者だから、これに多少の慈悲を与えてやってもいい)
少し前の写しならば、最低限の用向き以外は顔を見るのも厭うほどに気に入らなかった。しかし、ここ最近は気味が悪いほど従順な態度を見せている。偶に不満げに唇を突き出すこともあるが、表立って反論はしてこない。これも、長義による日頃の躾の賜物だ。
(今の偽物くんなら、まぁ『良』をつけてやらないこともない)
「はい、出来たよ」
きゅっと純白のシルクのタイを締め付けて、手を離す。その際、国広には見えないであろう縁の糸を撫でつけ、長義は満足げに笑んだ。今日も、自分は彼と繋がっている。昔はよく糸を断ち切られそうになったものだけれど、こうして二人の時間が増えていく度に、糸は徐々に太くなり、幾多もの歪な形の結目もそれ以上数を増やすこともなくなった。
「本歌、どうした」
「いいや、最近のお前は素直でよろしいってね」
これが生まれた時からこれは俺のものだった。
写しが生まれることは本歌たる刀の誉れ。万一己が失われようとも、己があった証は代わりに写しが証明し続ける。これは最初から最期までこの本歌たる山姥切のために生まれた物だ。それなら、長義が国広をどうしようと誰にも何も言われる筋合いがない。国広本刃でさえ。
(これで俺の価値が証明される……)
美しい。己を写したとはいえ、長義の鋭く冴えたそれとはまた異なる、眩いばかりの美しさ。静と動。月と太陽。されど戦さ場で魅せる苛烈さは同じ。似て非なる存在。己の一部。これが俺の写し。
「お前を見せびらかしたい気持ちもあるんだけどね、こう美しいと逆に勿体無いな」
「美しいとか、言うな。外には絶対着ていかないぞ」
「はいはい、外に行くのは慣れてからでいいよ」
どれだけ時間が掛かろうと構わない。時間はまだまだあるのだから。
襤褸布を剥がされ、不安げな顔をした男が恐る恐るこちらを見ている。金髪の長い前髪の下から覗く翡翠が、自信なさげに揺れながら長義の瞳を捉えた。堪らない。この男を美しく飾り立てる権利も、男を正当に評価する権利も、所有する権利だって、この長義の掌に委ねられているのだ。
今日の国広の装いは、長義のよく使っている仕立て屋でオーダーした、上下揃いのスーツだった。暫く和装が続いたので、気分転換も兼ねて洋装を仕立ててみたのだ。色は長義と揃いの黒。リボンタイと迷ったが、ここは敢えて細身のダービータイを選んだ。細い腰回りを覆う布は一級品。身体の線にピタリと沿ったシルエットは、ひと針ひと針手縫いで縫製ひとつ取っても拘り抜いてある。着心地は軽く、ストレッチも効いており、有事の際にも刀を振り回すのに問題はない。大変満足のいく仕上がりだった。ただ、タイの色を白ではなく青にすればよかったと、少し惜しい気持ちになったけれど。
「……もういいか?」
「まだだ。今日はこのままお茶にしよう。歌仙殿から教わった腕前、この本歌に見せてみろ」
「はぁ……あんたも物好きだな」
窓を開け放った。春だ。開いた窓の隙間から、甘やかな香りを乗せて風が吹き込んでくる。窓外の枝垂れ桜が揺れ、薄紅色の花弁が舞った。
この本丸に長義が配属されてから、もう四ヶ月の月日が経とうとしている。体感としては一週間くらいだろうか。怒涛の練度上げで忙しない日々を送っていたが、それもじきに終わる。往時の力を取り戻し、さらに磨き上げられた長義の練度は、ついに上限に達しようとしていた。
「山姥切、茶器は何処にある」
「奥の部屋の戸棚に。右側の扉の中だよ」
「わかった」
国広が、とたとた、と足音を立てて部屋の奥へ消えていく。はしたないから静かに歩けと言っているのに、まったく。長義に似せられて作られたくせに、あれは無骨で大雑把なところがあるからいけない。これも刀派の違い故か、とまで考えて、徐に堀川を思い浮かべる。確かあの御仁は静かに歩く刀だった。何の気配も悟らせずに背後に忍び寄るような……否、あれは闇討ち・暗殺が得意という物騒な理由故の動作だろう。ぶるり、と悪寒のようなものを感じて、長義はそれ以上考えることをやめた。どうにもあの刀の品定めをするような目は、苦手でいけない。
「厨から水を貰ってくる」
「……ん」
完全に一人となった部屋の中で、果たしてこの部屋はこれほどまで広がっただろうかと首を傾げる。
長義が国広と過ごすようになってから、この部屋には物が増えた。国広が活けた花、週に三日ほど送られてくる和歌の札がしまわれた三つの桐箱、国広が着る服が詰め込まれた二つのクローゼット。長義のスケジュールの都合から、偶に夜遅くに呼び出すこともあるため、そのまま泊まれるよう布団も一組分増えた。ちなみに、こちらはまだ使われたことはない。国広を泊めようとすると、夜戦組の夜食を作っていたという堀川がタイミング良く迎えに来て、さっさと連れ帰ってしまうからだ。
「……あ、」
そこで、ぱちんと閃いた。そうだ、刀掛けを新調したい。己の本体だけでなく、国広の本体も掛けておけるような、二振り用の刀掛けが。
「うん。注文しておくか」
そうと決まれば話が早い。端末を持ち出して刀掛けを探す。この山姥切の本歌と写しを並べて飾るのだ。生半可な代物で済ませるわけにはいかない。それなりに値は張るが、漆塗りに箔が散りばめられた見目麗しい逸品を見つけた長義は、躊躇うことなくそれをタップした。金なら聚楽第の報酬から本丸に配属されてからの給金まで、たんまり持っている。使い道も国広のあれこれに使う以外は特にないのだ。惜しい気持ちは微塵もなかった。
「山姥切国広だ。入ってもいいか」
そうこうしているうちに、国広が帰ってくる。
「構わない」
「失礼する」
厨から戻った国広の手には、パック入りのミネラルウォーターがあった。水道水では不満な、水にうるさい刀たちのために主が取り寄せた物だ。長義もこの水は日頃愛飲している。
「それじゃ、茶室に移動するよ」
「それは俺が持つ……」
テーブルの上に置かれた茶器を抱えた長義に、国広が寄ってくる。
「いいよ、別に。大して重いわけでもなし。その代わり、その水はお前が持ってきな」
「……わかった」
長義の部屋は長船・正宗派の刀たちが住まう東の離れの中にある。一方、国広の住む堀川部屋は主に新撰組の刀たちが住む西の離れにあり、東の離れからは少々離れた場所に位置していた。そして、今から向かう茶室は、長義の部屋から見て西の渡り廊下を突っ切った先の、娯楽施設関係がまとめられた建物内にある。東の離れと西の離れの丁度中間地点だ。
「ねぇ、偽物くん」
半歩後ろを歩く国広へ、何気なく長義が話し掛ける。
「……写しは偽物ではないが、何だ」
まったく可愛げのない返答に眉根を寄せつつ、ふ、と思いついたことを言ってみた。
「お前、わざわざここまで来るのは面倒だろう。俺もいちいち呼びに行くのが手間だし、東の離れに越さないか?」
何の下心があったわけでもない、打算的な提案だった。
長義としても、いちいち堀川の許可を取って国広を連れ出す手間が省けるし、国広が部屋に来るまで待つ時間も短縮出来る。自分で言いながら、断る理由のない実に合理的な提案だと思った。しかし、長義に話を持ちかけられた国広はというと、初めは目を見開き驚いた様子を見せていたが、やがて不安げに俯いて無防備な顔から一変、ぐっと何かに耐えるような険しい顔つきになる。本歌の近くに在れることを喜ぶかと思っていた長義の思惑は外れ、予想外の反応に、二人の間には不穏な空気が漂い始めた。
「……いや、遠慮しておく」
国広の口から漏れた否定の言葉に、長義は内心ぎょっと目を剥く。
「遠慮など要らない。俺が楽だから越して来いと言ってるんだ」
「それでも……俺は兄弟たちと同じ部屋がいい」
長義の提案を足蹴にするばかりか、本歌を差し置いて兄弟刀たちの元に在りたいと宣う。
カッと臓腑の焼ける思いがした。湧き出てきたのは猛烈な怒りだ。何の前触れもなく噴火した火山の如く、それは突然長義の身を襲った。
「へぇ……」
ぎり、と茶器の乗った盆を握り締め、怒りを紛らわせる。余計なことを口走りそうな口は早々に閉じ、固く唇を噛むことで無理矢理言葉を飲み込んだ。熱い塊が喉奥を通り過ぎたのを確認すると、ふぅ、と小さく息を吐く。ぐらぐらと煮立った負の感情に煽られて、腹の底が熱くて仕方ない。それでも、この場で怒鳴り散らすようなみっともない真似をすることはしなかった。なけなしの理性が、長義の衝動に待ったをかけたのだ。
「あんたが俺を呼びに来るのが手間だと言うのなら、俺の方からあんたの元に行くようにする。俺は初期刀で部隊の出陣予定には必ず目を通しているし、あんたが何処で何をしているのかは、大体把握出来る」
いつになく饒舌だな。そんなに兄弟刀の方が大事か。
「本歌が求めるなら、何時になってもあんたの部屋に通ってもいい。俺は隠居組だ。あんたの都合に合わせる」
こういう時ばかり俺を本歌と呼ぶのか。忌々しい。
駄目だ、何を言われても神経を逆撫でされて仕方ない。元よりこの刀は長義の逆鱗に触れることに関して異様な才覚を発揮していた。有難くも何ともない天賦の才だ。さらには、長義がいくら感情を荒立てようとも、これはそれが何故なのか理由も察せられなければ、却って煽るようなことを言ってくる。愚鈍にもほどがある。
「……もう黙れ」
この恩知らずめ。
そう言ってしまえたらどれだけ良かったろう。されど、恩を恩とも思っていない相手に言ったところで、長義の嫌味は暖簾に腕押し、糠に釘。何の意味もないのだ。その現実を何度も目の当たりにしてきて、同じ愚行を犯すほど愚かではない。
「本歌……」
「黙れと言っている!」
かちゃん。
手に持っていた茶器がぶつかり、音を立てた。国広は何が何だかわからないといった顔をしていて、視線を彷徨わせながら戸惑っている。その反応一つ取っても苛立たしい。
「すまない……また俺は、あんたを怒らせた」
「……」
途端に萎縮し、殊勝な態度を見せた国広を前に、長義は舌打ちしそうになった。こんなに落ち込んでいるように見えても尚、彼には主張を譲る気はさらさらないのだ。気弱なフリをしてその実この男が頑固だということは、今までの経験から身に染みている。こうなっては絶対に折れない。
「……怒らせてばかりだな、俺は」
「興が冷めた」
その場で立ち止まる。
後ろからついてくるだけの国広もまた足を止め、手に持ったパックの中の水がたぷんと揺れた。長義が振り返ると国広はピクリと小さく身動ぎ、叱られる前の子どものように顔を強張らせる。その顔は、彼が普段から兄弟刀や古参の連中に見せている柔らかな表情とはあまりに似つかなくて、それもまた腹が立った。結局のところ長義は、国広が何を言おうと何をしようと、気に入らないのかも知れない。自分でも理不尽なことは自覚している。それでも、どうしてか許せなかった。他刃のことならまだしも、こと、彼のことに関しては特に。
「茶器は俺が片付けておく。お前はもう帰れ」
国広は動かない。それを押し退けて、長義は元来た道を引き返し始める。
「……っ山姥切、」
引き留められたが無視をした。誰がお前の言うことなんて聞くか。お前が俺の言うことを聞かないのに、何故俺が言われた通りにしてやる必要がある。それに、写しの指示に従うなんてまっぴら御免だった。
「……クソッ」
また、乱されてしまった。
乱暴な足取りで廊下を進む。普段あれだけ国広に注意していた歩き方を、今は気にする余裕なんてなかった。その余裕の無い自分にすら腹わたが煮えくり返って、苛立って仕方ない。それもこれも全部あの偽物のせいだ。あの刀が、長義の物のくせして他の刀なんぞ選ぶから。
(選ぶ? 違うな。そもそもあいつに選ぶ権利などない。あれは元から俺のものだ)
「……ふざけるな」
あれは、誰が何と言おうと俺のモノだ。あの刀が打たれる前から、打たれてからも、ずっと。
そうだろう?
*
長義に置いていかれたあの日から、三日経った。
あの時の国広は、長義から発せられる圧に呑まれ、何もすることが出来なくて……咄嗟にこのままではまずいと思い、何度か話し掛けに行ったのだけれど、綺麗に無視されてしまっていた。かといってそれ以上深追いも出来ず、気まずい状態が続き、それきり顔を合わせることのないまま気がつけば三日経っていた。
南泉と長義の練度が上限に達したと報告があったのは、そんな折だった。いつものように近侍である長谷部の書類仕事を手伝っていた時、帰還した第三部隊の隊長を務めていた蛍丸から報告があったのである。それを聞いた長谷部は静かに頷き、傍にいた国広へ指示を飛ばした。相変わらず頭の回転の速い男だ。
「早急に宴の準備に取り掛かる。国広、燭台切と歌仙にも連絡を」
「……わかった」
宴、か。
この本丸では、誰かの練度が上限に達しすると必ず酒宴が催される。しかし、正直呑んで騒ぐような気分ではなかった。しかも酒宴の主役が、現在冷戦中の長義ときた。気まずいことこの上ない。とりあえず彼の歓迎会の時のように距離を置いて様子を伺えばいいか、とだけ考えて、国広は厨の方へ向かった。今ならきっと、燭台切と歌仙が夕餉の準備に取り掛かっている筈だ。宴は明日になるので、取り寄せる材料だとか宴の時間だとかもさっさと決めてしまいたかった。
「燭台切、歌仙、いるか?」
暖簾をくぐると、厨に二振りはいた。それはいい。だが、そこにはあともう二振りの刀もいた。
「お、国広のじゃねぇか、にゃ」
「……」
親しげに右手を挙げた南泉と、無言でこちらを睨みつけてくる長義。しかし、長義のひと睨みはすぐに逸らされ、何事も無かったかのように無視さてしまう。まるで国広がこの場にいないかのように振舞われて心が痛み、キリキリと胃が握り潰されているような心地になった。
「もういいだろう、猫殺しくん」
親しげに南泉へ声を掛けてから、長義が燭台切と歌仙の方へ向き直る。
「では、燭台切殿、歌仙殿、お手数おかけしますが、よろしくお願いします」
「うん、任せておいて!」
「皆がため息を吐くくらいに雅なものを、明日の食卓に並べてみせるよ」
「それでは」
「……っ」
通り過ぎ様、柑橘系の香りが鼻腔を掠める。久しぶりに嗅ぐ、長義の匂い。
「ぁ……、」
引き留めようと伸ばした手は、空を切った。遠ざかる背中を見ていることしか出来ない。離れていく。行ってしまう。また、置いて行かれてしまう。
(また……?)
急に視界がブレた。雑木林の中の山道を歩く、国広と主たち。やがて分かれ道に立った二振りは袂を分かって、長義はあっさりこちらに背を向けた。死神のように全身真っ黒な袴を纏った、銀髪の付喪神。長かった髪は短くなり、背格好も一回り以上縮んだその姿が、遠ざかってゆく。
――本歌!
名を必死に呼んだところで、彼は振り返らない。その背中は既に先を見据え、国広の存在など眼中にも入っていなかった。気高く、誇り高く、高慢で、冷たい。進む道を決めたのなら後ろは振り返らない。凛と背筋を伸ばし、自らの刀一つで道を切り拓いてゆく。昔から彼は、己の背で道を指し示してくるような、そんな何処までも厳しく美しい『刀』であった。
「国広くん?」
「……」
「……大丈夫かい?」
布越しに頭を撫でられた。『これじゃない』と思ってしまった。
――励めよ。
また一つ、思い出す。あれは長義の、昔からの口癖。滅多に褒めることをせず、厳しい指南の間に挟まれる不器用な激励を、国広は確かに嬉しいと思っていた。
「……大丈夫だ。燭台切、歌仙、もう話は聞いているかも知れないが、」
宴の時には、せめて酌だけでも。
これが見放された己に出来る、唯一の誠意の示し方だ。
行燈に照らされた薄暗い廊下を進み、酒宴の会場へと向かう。娯楽施設の集う中央棟の中にある、刀剣男士たちが七十振り以上入ってもまだ余りある大広間にて、南泉と長義の練度上限祝いは催されることとなった。開宴は酉の刻から。丁度夕餉と同じくらいの時間帯である。国広は少し早めに来て準備を手伝うよう言われていたため、その一時間近く前から会場へ足を運んでいた。
まだ廊下に誰かの気配はない。当たり前だ、こんなに早い時間から来る者などいない。酒呑みの連中は早めに来て既に酒瓶片手にワイワイやっているが、酔っ払いに手伝いを任せるような危険な真似を厨担当が許す筈がないので、彼らが戦力としてカウントされる日は無いのだろう。現に、彼らは所謂盛り上げ要員というやつに分類されていた。
「来たぞ。何から手伝えばいい」
厨に入ると黒いエプロンをつけた燭台切と、白い割烹着姿の歌仙がちゃきちゃきと働いていた。彼らは国広が来たことに気づくと手を止め、こちらを振り返る。
「あ、国広くんお疲れ様」
「料理はほぼ出来てるから、君には皿や膳を用意して欲しいかな」
「わかった」
戸棚を漁って食器を出していく。慣れたものだ。もう何度も、もてなす側としての宴は経験している。ややあって書類仕事終わりの長谷部と博多もやってきて、さらには平野や前田という世話好きな短刀たちも合わせ、計七振りで宴の準備を進めていった。
「……集まりだしたな」
厨で盛り付けにやたらと拘ろうとする歌仙と口論しながら準備していれば、大広間の方から賑やかな声が聞こえ始めた。酒呑み連中のあの盛り上がりからしても、どうやらさらに数振りが加わって本格的な飲み会へ発展したらしい。主役が来てもいないうちから何をやってるんだ、と呆れる反面。ああして場を盛り上げてくれる者たちがいてくれることに、国広は心底安堵する。
長義と顔を合わせた時に、通夜みたいな空気で酒を飲むのは幾ら何でも耐えられなかったからだ。
「よし、膳を運んでもらおうか」
燭台切の声に反応して、それまでサラダの盛り付けをしていた前田と平野が立ち上がる。
「僕たちもお手伝いします」
「こちらは奥から運べば良いのですね?」
膳の盛り付けが完了したそばから、短刀二振りが大広間へ運んでいった。膳の数が多いので盛り付ける側の長谷部と国広は大忙しだったが、やがて火の始末と後片付けを終えた燭台切と歌仙が合流してくれたため、流れ作業は円滑に終了した。
(どうしたものか……)
初期刀と近侍の席は決まっている。
今夜の主役は南泉と長義なため、二人の席は主の両隣となることは決まっていた。だが、問題はその主役たちの隣となる初期刀・国広の席だ。長義の座る位置がわからなかったため、何処に座れば隣にならないのか判断がつかない。なるべくなら刺激しないよう、机を挟んだ斜め向かいの席に腰を落ち着けたいものだけれど、視界に入りにくいという面では隣も捨てがたかった。空席を前にしてうんうん唸っていれば、後ろに立っていた長谷部が、痺れを切らして一喝してくる。
「何をしている。さっさと座らんか」
「……あぁ」
ほぼやけになって部屋の奥側に座った。ここなら、入り口から入ってきた長義から目に付きやすい。ここまで来てしまえばもうあとは委ねるだけだ。向かい側にせよ、隣にせよ、長義の好きなようにすればいい。まるで丸裸で獅子のいる檻の中に投げ込まれたような心境で、本日の主役の登場を待ち続けた。
「お、主役の登場だ!」
暫く落ち着きなく席に着いていると、南泉、長義、主の順に会場内に入ってきた。
「今宵は俺たちのためにこのような場を設けて頂き、心より感謝する」
「ありがと……にゃ」
先頭を行く南泉は国広の隣に座り、長義は残る斜め向かい側の席に座る。少しホッとした。物理的に距離が離れていたから。これだけ離れていれば、俯いて布を引き下げてしまえば、彼を視界に入れずに済む。どうせ宴は後半になれば無礼講となり、席なんて関係なくなるのだ。兎に角、今この一時だけ凌げればそれで良かった。
「よう、相変わらず辛気臭い顔してんな」
人知れずホッと胸を撫で下ろしていると、乾杯の音頭が終わった直後、南泉から耳打ちされた。猫の耳のように横に大きくうねった金髪が、国広の頰に擦れて肌を擽る。
「……っ別に、そんなことは、」
内心の驚きを表に出さないようにしつつ、最低限の言葉だけを返す。しかし、南泉にはそんな誤魔化しなど通用せず、ぐいっと顔を近づけてきて国広の言葉を遮った。
「ない、とは言わせねーよ。どうせあいつのことなんだろ?」
チラッと長義の方を一瞥し、南泉が言う。長義は主と何事かを話していたため、二振りが話していることには気づいていない様子だった。まぁ、別に南泉と話しているところを見られたとて、何も咎められることなどないのだが。
「あいつはな、心が化け物になっちまったから、心っつーもんがわかっちゃいねぇんだ」
「……化け物?」
不穏な言葉が聞こえ、思わず聞き返す。国広の興味を引いたとわかった南泉は意地悪く口端を吊り上げ、やけに楽しそうな声色で続けた。
「俺は猫を斬って呪いを食らった……いつか解いてやっけどな。んで、あいつも山姥を斬って呪いを食らったってわけだ。一説によると、あいつが斬った山姥っつーのは、豊穣の神だったとも言われてるんだろ? そんなどでかい獲物を斬っておいて、何の影響もねぇってのがそもそもおかしな話なわけよ」
「……そういうものなのか?」
うんうん、と南泉が二度頷く。山姥を斬った記憶のない国広には、呪いなんてものが実在するのかどうなのかはわからない。わからないが、もしそれが本当の話ならば、それはとても恐ろしいことだと思った。少なくとも、こうして酒を呑みながら呑気に話すような内容ではない。
「ちなみにお前は呪いよりタチの悪いもんに取り憑かれてる」
ふに、と頰を人差し指で突かれ、ムッと顔を顰める。
「……前にも言っていたな。何のことだというんだ。俺は別に、」
何にも取り憑かれてなどいない。
そう国広が反論しかけた時だった。身を貫くような鋭い視線が、ひたりと国広を捉えた。
「……っ?」
ハッとして視線の方を見るも、そこには主と話が盛り上がっている長義の姿しかない。気のせいか……? と依然としてバクバク音を立てている胸元に手をあてつつ、キョロキョロと周りを見回していれば、徐に南泉が深く息を吐いた。そして、彼はそっと宥めるように国広の首筋に指を這わせてきて、ただでさえ小さかった声をさらに潜め、囁く。
「……気ぃつけろよ。お前は今、化け物の手の中だ。あんまり油断してると、そのままぺろっと丸呑みされちまうぞ」
悪寒が止まらない。
カリッと最後に国広の首へ爪を立てた南泉が、舌打ちをして素早く手を引っ込めた。その際、国広は見た。見て、しまった。離れていく彼の右手が赤くなり、何筋かの赤い線が浮き出て、みみず腫れのようになっているのを。彼の手が己の何かを剥がそうとしていた、と本能的に理解した時には、時既に遅く。あの身に覚えのある息苦しさが国広を襲い、身体が硬直した。
「……一体、何が、」
「やぁ、猫殺しくん、偽物くん。二振り揃って傷の舐め合いかい?」
いつの間にやってきたのか。
御猪口を手に持った長義がやってきた。今までの冷え切った態度が嘘のように柔らかな笑みを貼り付けた長義は、予想外にも南泉ではなく国広に声を掛けてくる。その顔は不気味なくらいいつも通りで、言葉とは裏腹に声に棘は感じられなかった。
「お前は酌の一つも出来ないのか。前にも言っただろう。俺の元へ一番に酌に来いと」
「……山姥切?」
どうしたというのだ。あれだけ避けていたくせに。何事もなかったかのように平然と話しかけてくる様が、不気味で仕方ない。
「そうだよ、俺がお前の本歌の山姥切だ。どうかしたかな、そんなにまじまじと見て」
嫌な予感がする。脳内で警鐘が鳴り響き、頻りに危険を訴えてくる。目の前の男に気をつけろ、気を許すな、この男は飄々とした顔をして国広に近づき……、
「いや、……何も」
丸呑みに、しようとしているぞ、と。
「俺と国広が話してたんだ、にゃ。邪魔すんじゃねぇよ」
凍りついた国広を庇うように、南泉が前に出る。そんな南泉を一瞥した長義は、ふん、と鼻を鳴らすと、嘲るように笑った。よく見る顔だ。南泉とやり取りしている時には割と頻繁に見る顔。しかし、何だろうか。今日の長義の様子は、嫌に胸を騒つかせる。ひたひたと迫る何かに、そっと急所を掴まれているかのような圧迫感。そんな息苦しさと違和感が、ずっと国広の傍を離れようとしない。
「おや、失敬。だが、これが俺のだということを忘れないでもらいたいね。俺は善意からこれを君に貸してやっていたんだ。そろそろ返してもらうよ」
そら、おいで。
口調は優しい。その表情も。なまじ元の造形が整っているばかりに、少し微笑めばその破壊力は抜群だった。
(怖い)
反射的に恐怖を覚えた。怖い。この男の底が見えないことが、恐ろしい。先ほどの南泉から聞かされた話を思い出す。この男が山姥を斬り、その心が化け物となってしまったという話を。化け物になったとは、どういうことなのだろうか。いや、それはただの作り話じゃないのか。だってこの男は国広に優しかった。辛くあたることもあったが、それは国広が彼に逆らった時だけで、従順に彼の言うことを聞いていれば優しく……。
(従順に……?)
ふ、と、引っかかる。
従順である必要が何処にある?
絶対に譲れないものがあった。国広第一の傑作であるという誇りが。それがある限り、俺は俺だと胸を張れた筈だった。それを揺るがす存在は、何人たりとも許さない。写しだからと己を侮る輩も、己を通して本歌しか見ていない者たちも、全部跳ね除け拒絶してきた。それはいくら己が本歌とて例外ではない。
その意地は、矜持は、何処へ行った。
「……俺は、あんたのモノじゃ、ない」
言葉が自然と滑り出た。突っかえながらも、ゆっくりと、己に言い聞かせるように。国広の言葉を耳にした長義の瞳孔が開かれていくその瞬間が、やけにゆっくりと見えた。
「……俺は、山姥切国広だ。堀川国広の、第一の傑作の」
ガシャンッ!
黒い手袋に覆われた指先から、御猪口が落ちた。運悪く善の上に転げ落ちたそれは、勢い余って床に落ち、割れる。周りが慌てた声を上げたのは聞こえていたけれど、反応出来なかった。無表情にこちらを見つめる長義の顔から、目が離せなかったのだ。
「山姥切……」
一瞬たりとも目を逸らすことが許されない。だって、彼が今にも折れてしまいそうな顔をしていたから。
「……あぁ、そう」
地獄の底から這い出てきたような低い声が、薄い唇の狭間から吐き出される。鼓膜を振動させ、肌を舐め上げるようなじっとりとした声が、暗に国広を責め立てた。
「おい、国広っ」
さっと顔色を変えた南泉が、国広に手を伸ばす。
「それに触るな。触れたら斬る」
だが、そんな彼の手は敢え無く長義に払い落され、寸前で空を掴んだ。同時に、長義の右手に光が集まり始める。
(この気配……)
本体か。
その様に長義が何をしようとしているのか早々に悟って、国広は立ち上がる。
「おいおい、抜刀はまずいんじゃねえの」
「あいつを止めろ!」
ついに静観していた周りの刀たちも騒つき始め、宴会場は一時混沌に陥った。流石に騒ぎ過ぎたか。しかも物騒な方向で。長義から放たれたほんの僅かな殺気をも感じ取れないような鈍は、生憎ここにはいない。場の空気に当てられて臨戦態勢となった大広間の刀たちは、それまでの楽しげな空気を一変し、いつ何が起きても対応出来るよう一斉に腰を浮かせた。長谷部は素早く主の前に立ち塞がり、既に本体をその手に呼び寄せて、いつでも抜刀出来るよう身構えている。
「本歌、どうかここは収めてくれ。俺が悪かった……だから、どうか」
このままでは本格的にまずい。せっかくの宴が主役のせいで台無しになるばかりか、乱闘騒ぎまで発展してしまっては目も当てられない。何より主に危険が及んでしまうのは避けたかった。だからこそ国広は、自分が悪いかどうかはこの際捨て置いて、長義に頭を垂れた。
「すまなかった。山姥切、だから本体は……」
第一優先は主の御身。自分の謝罪一つで事が収まるのなら、安いものだ。
「中身の無い謝罪は、見え透いた薄っぺらい社交辞令よりも礼儀を欠くことを知っているか?」
しかし、冷たく冴え渡った声が、国広の懇願を一蹴する。
「お前は何について謝っている。答えろ」
「……っ」
暫し沈黙が続く。口籠ってなかなか答えられない国広に、呆れたとばかりに長義がため息を吐いた。すると、若干張り詰めていた空気が綻ぶ。それに倣い、周りの刀たちも構えを解き、未だ警戒しつつも長義と国広の様子を伺う姿勢に甘んじた。
「……もういい。頭を上げろ」
ほっと気が緩んだからか。じとりとした脂汗が、身に纏うシャツを湿らせる。べたべたと肌に張り付く感触が、なんとも不快だった。
「騒いですまなかった。思ったより酒が回っていたようだ。少し頭を冷やしてくるよ。皆は気にせず楽しんでくれ」
やってられるか。吐き捨てられたような言葉が頭上から降ってきた。傍にいた国広と南泉しか聞き取れないほどの、小さな呟きだった。
くるりと国広に背を向け、その場を辞そうとする長義へ、もう大丈夫だと安心した刀たちが好き勝手に声を掛ける。やれ、一杯やるなら誘えだの、あの酒を持っていけだの、このつまみだけは食っていけ、だのと色んな声を。これも偏に、盛り下がってしまった空気を何とかしようという、年長者たちの気遣い故だった。
「井戸の水でもひっかぶって来い。目が覚めるぞ〜」
今にも出て行こうとしていた長義に言ったのは、同田貫だ。
「今夜は月が綺麗だからな。月見酒でもよいだろう」
「桜と共に眺めれば、風情もあろうよ。なに、俺にはまったく風流も雅も理解出来んがなァ!」
「それはそれは……僕の出番かな?」
それに三条派で呑んでいた三日月と岩融が続き、豪快な岩融の笑い声に、歌仙が頰を引き攣らせた。そんな刀たちの方を見て、長義は微かに口角を上げる。
「……そうさせてもらおう、かな」
(ぁ……、)
皆に押し付けられた酒瓶たちを抱え、大広間から出て行く彼の背に、吸い寄せられるようにして国広の足が追いかけ始める。気づけば早足になっていた。だだっ広い大広間の通路を、バタバタと忙しない足音を立てて、走る。
「兄弟!」
だが、襖を開こうとした国広の手は届かなかった。堀川と山伏が立ち上がり、国広の腕を掴んで引き留めたからだ。
「兄弟、今はそっとしておいてあげた方がいいと思う」
神妙な面持ちで、堀川が諌める。
「兄弟が行っては逆効果になるのである」
山伏がふるふると頭を横に振り、やめておけ、と制止した。常の国広ならここで諦めていた。兄弟たちが言うのなら、と。だが、何故かこの時は行かなければ、と何かに追い立てられるように感じていた。呼ばれているような気がしたのだ。
「……しかし、話さなければ何も進まない」
長義が本当に怒った時は無表情になる。それは、彼の真剣必殺を見たものならば誰でも知っていることだった。先ほど彼から感じた殺気と怒気は尋常ではない。あそこまで怒らせてしまったのは、紛れもなく国広が原因だ。今までもそうだった。無意識のうちにあの男を怒らせ、今日に至っては主の前で彼に恥をかかせてしまった。あのプライドの高い彼が、人前であるにも関わらずあそこまで激怒した理由は、本音を言うと今ひとつ理解出来ないが……。せめて悪気は無いのだという、自分の意思だけは伝えたい。その上で彼の考えを聞きたい。彼を理解したい。
拗れに拗れた関係を、そのすべてを紐解こうとまでは思っていない。だがせめて、顔を合わせて挨拶を普通に交わす程度にまでは、関係を回復したかった。だって、自分たちは切っても切れない縁で結ばれた、本歌と写しなのだから。
「……これは、あいつと俺の問題だ。悪いな、兄弟。迷惑をかけた」
「あ、兄弟……っ!」
兄弟たちの制止を振り切って、国広は長義が去った方へ走り始める。
廊下には既に彼の姿はなかった。されど、彼が何処にいるのかは、何となくわかった。霊力の残滓というのだろうか、残り香のようなものが国広に道を示していて、ここまで来いと呼んでいる。
(……山姥切っ)
鼓動が逸る。あの怒りようだ。顔を合わせた途端に斬りかかられるかも知れない。覚悟はしていた。勿論、本丸の初期刀としてタダでやられるつもりは毛頭無いが。
それでも万一、練度が上限に達した長義とまともにやり合うことになれば、国広とて無事では済まないだろう。良くて中傷、最悪重傷。折られることはない、と思いたい。あくまで自分たちは主の刀なのだ。主の所有物である自分たちが、同じ主の刀を……ましてや初期刀を折るなどということを、己の本歌が仕出かすなんて、あまり考えたくなかった。
(手入れ資材を無駄に使うことはしたくないんだがな……)
廊下を直走ること数分。東の離れに足を踏み入れ、慣れた道順を進んだ後、国広は唐突にその場で立ち止まった。
「山姥切……国広だ。入ってもいいか」
返事は無い。怒り立った獣が息を潜めているような物騒な気配が、国広の肌を刺す。生半可な気持ちで立ち入るなと、それは無言で告げていた。
だが言い換えると完全な拒絶ではない。指先一つの動きが命取りになるような、鋭い空気を放ってはいるものの、彼は「入るな」とは言わなかった。沈黙は肯定。緊張から喉を鳴らしながら扉を開けると、ぶわり、と生暖かな風が横を通り過ぎていく。
「山姥切……」
部屋に明かりは灯っていなかった。光源は窓から差し込む月明かりのみ。長義はその薄暗い部屋の奥、窓辺に置かれた寝台の上にいた。窓を開け放ち、寝台に座り込んでぼんやりと外を眺めていた彼は、入ってきた国広に一瞥も寄越すことなく、ひたすらに窓外の景色を見つめている。その手には先ほど刀たちから持たされたグラスが握られており、サイドテーブルに何本かの酒瓶が無造作に置かれていた。
「何の用だ」
毅然とした声で、長義が問う。
声の存在感とは裏腹に、月明かりに照らされた長義の気配は今にも消えてしまいそうなほど希薄だった。思わず目を疑った。弱っているのとは違う。悲しんでいるのとも、何かを嘆いているとか、そういったことではなく。彼の心の在り方など関係なく、その存在感自体があまりに儚く映ったのだ。
「……謝りに」
「中身のない謝罪は要らないと、さっき言ったはずだ」
きっぱりと切って捨てる彼の声に、覇気はない。
「……なら、何故あんたを怒らせてしまったのか知りたい」
静寂が場を支配した。風音に紛れて聞こえる葉擦れの音が、唯一現の断片を残していて。それが無ければ己の立つ場所を見失いそうだった。
「知りたい、ね」
あまりに、世界が朧げだったのだ。
波紋の広がる水面に映る月のように、輪郭がぼやけて、揺れて、実体が空にあるのだということすら、わからなくなっていく。
「来なよ、教えてやる」
目の前の男の瞳には、何が映っているのか。男が何を思い、何を考え、この痛いくらいに静かな光景を眺めていたのか。唐突に意識を乗っ取った好奇心が邪魔をして、理性を蝕んでいった。甘やかな香りに釣られ、気高く美しいその魂に惹かれて、直接心に訴えかける低い声に吸い寄せられて、可憐な花に集る虫のように、艶やかで美しいそれに触れたくなって近づいた。
その挙句が、このザマだ。
「……ぐ、ぅ……山姥切?」
それが罠だとも知らずに。押し倒され、縛り付けられ、抵抗も出来ぬままに籠絡される。上から覆い被さってきた男の顔は、一切の感情を押し殺した無表情。だが鈍く光を湛えた青瑠璃の瞳の奥に、隠しきれない熱がちらちらと覗いていた。
「……思い知らせてやるよ。お前が俺の物だということを。その身に直接刻んで、二度と忘れないようにしてやる。有り難く思え」
「何を……っ」
黒い手袋が取り去られた、剥き出しの掌があらぬところを弄り始める。は、と息を吐き、国広は驚愕の表情を晒したまま男を見た。
「せいぜい足掻け、偽物」
知らぬ間に絡め取られていた。後から知ったところで己の首には、死神の鎌があてがわれている。己の愚鈍さを後悔したところで、後の祭り。
――気づいた時には、腹の中。
*
弾力のあるマットレスに転がされ、されるがままに暴かれた。布を、服を、身に纏っていたものすべてを剥がされ、果ては己の服で手足を縛られる。完全に身動きを封じられたせいで碌な抵抗も出来ず、かといって大声を出して助けを求めるなんて無様な真似は、男としての矜持が許さなくて。生理的な涙と口から漏れる声を我慢するのに、全神経を費やした。
「う……ぐ、ぁ……っ」
くちゅ、くちゅ。
こんな快楽は知らない。先走りでぬるついた指先で、緩く立ち上がった肉棒を扱かれ、堪らず呻き声を上げる。括れの部分を強く握り込まれる度に強烈な射精感に苛まれ、ぎゅっと目を瞑って耐えた。そうして国広が悶絶している間にも腹や胸へ這う掌の動きは止まらず、着々と身体が拓かれていく。
「は、……ぁっ」
胸の飾りをカリッと爪で引っ掻かれた。最初は特に何も感じなかったが、次第にそこが感じる場所であることを知った。脇腹をするすると辿られれば、擽ったさから漏れる声の中に僅かな悦が混じる。今迄の自分がみるみるうちに変わっていくことに恐怖を覚え、されどそれを止められずにいることに屈辱を噛み締め……元凶を睨みつけては、されど次の瞬間込み上げてくる快感を耐えることで、頭が埋め尽くされてしまう。さっきからその繰り返しだ。ひっきりなしに訪れる快楽の波に呑まれながら、必死に海面へ顔を出して呼吸をしている。
「やめ、……ろ……」
「ふぅん。まだそんなこと言う余裕があるんだ」
ぎゅっと不意打ちに急所を握られ、腰が跳ね上がる。
「……ァッ!」
意地でも達してやるものか、と歯を食いしばって耐えた。が、少しだけ漏れてしまって、あまりの羞恥と屈辱で目の前が赤くなった。
「もういいだろう! わかった! わかったから!」
「薄っぺらい言葉だね」
ジタバタと暴れ出した国広の身体を力づくで押さえつけ、長義が面倒そうに言う。
「大人しくしろ。面倒は好かない性分なんだ」
「何でこんな……っやめろって、」
「うるさいな」
突然口に指を突っ込まれて気が動転した。何が起きたか理解が追いつかない国広に向かって、「噛むなよ」と一言だけ告げた彼は、口の中に突き入れた指先で上顎や舌をぐにぐにと愛撫していく。器用なことにその間も下半身への刺激は止められることなく、冷え切った心とは逆に身体の熱と興奮は高まるばかりで。ついに新しい快感を拾い始めた己の身体に絶望した。
「……お前も強情だね」
気持ちいい。あぁ、浅ましい。何だこの荒い呼吸は。発情した犬のようではないか。
最後の一線は越えてはならない。越えてしまっては、自分が自分で無くなるような気がしたから。今まで耐えていたものが溢れ出して、止まらなくなるような気がしたから。また下腹部にせり上がってきた熱の塊の気配を感じながら、理性は己の尊厳を守ろうと必死になる。
「はぅ、やまんば、ぎり……や、やだ、やだ……っ」
「怖くない、怖くない」
そら、気持ちいいだろう?
飛び切り甘い声を耳に直接吹き込まれてしまえば、脳髄が痺れる。
「あ……、ァアッ!」
びゅ、ぴるる、くちゃり。
同時に先端の割れ目に軽く爪を立てられてしまえば、ひとたまりもない。耳に入る音に粘着質な水音が混ざり始めて、遅れてきた思考が己が達したことを伝えてきた。腰が、衝撃からガクガクと小刻みに震えている。ありえない、屈辱だ。他刃の手で好きなように弄られ達するなんて。しかも本歌の目の前で。
「……、もういいだろう。離せ」
は、は、と短い呼吸をしながら息を整える。達した余韻に浸りながらも、芯から冷えた思考のままに拒絶した。これ以上はしたない己の姿を彼に見せることは耐え難かった。まともに顔を合わせることも出来ず、腕で己の顔を隠しながら言えば、長義が国広の手首を鷲掴みにする。
「おい、」
まだ何かあるのか、と言いかけたその時。ちらりと覗いた彼の顔を見て、国広はさらなる絶望に叩き落されることとなった。
「何を終わった気になってるんだよ。まだ本番が残ってるじゃないか」
「……本歌?」
唖然とした国広を他所に、長義が足にまとわりついていたジャージのズボンを抜き取る。この男は何をするつもりなんだ。何かがおかしい。自分は今からとんでもない事をされるのではないか。完全にキャパオーバーしてしまい、恐慌状態に陥っているうちに、長義の身体が立てられた両膝の間に滑り込んできた。その後、自由になった両足をぱかりと割り開かれて漸く、今から自分が何をされるのかを察する。
国広とて数百年以上生きた刀なのだ。それなりに人の子たちの営みも見てきた。だから、これから行われるであろう行為がどのようなものかは、大体想像がつく。
(そんな、まさか。嘘だ、やめろ。やめてくれ)
「や、……やめ……嘘だ、ろ」
「俺は本気だが?」
「山姥切……っ! 無理だ、むり!」
人差し指が、後孔に差し込まれた。ぐにっと柔らかい内側を押され、生々しい感触が内側を犯す。得体の知れない感覚に、「ひっ」と情けない声が漏れた。この際、矜持がどうのと言ってられる場合じゃない。明らかにこれはやり過ぎだ。
「だめだ、山姥切!」
「暴れるな。締め付けられたら入れにくいだろ」
ナカに入れられた指がくの字に曲げられ、何かを探るような動きになる。行為自体がどんなものかは薄っすらと覚えていても、具体的に何をするのかまでは知らない国広にとって、この先は未知の領域だ。内側から手酷く痛めつけられる可能性がある以上、無闇矢鱈と暴れるわけにもいかず。先ほどまでの抵抗が嘘のように、大人しくせざるを得なくなる。
「ひ、……ぅ、やめ……」
暫くの間国広のナカを掻き回していた指は、あっさり出ていった。
ずるり、と抜き出される時の感覚に肌が粟立ち、ぞくぞくと背筋が震える。だが、異物感が無くなったことにホッとしたのも束の間、長義は国広が自らの腹の上に吐き出した白濁を掬い取り、それを容赦なく後孔に塗りたくってきて。今度は指を二本に増やして、国広のナカに突き入れてきた。
「ぐ……っ」
「苦しい?」
「……ぬ、け」
「可愛げのない写しだ。せっかくグズグズに溶けるように優しく抱いてやろうとしているのに」
ぐに、ぐに。また、何かを探られる動きをされる。指が増えたせいで圧迫感がすごい。
真っ青な顔で眉根を潜め、長義が満足するのをひたすらに待つこと数分。体感的には数時間拷問されたような思いだったが、ある一点を長義の指先が掠めた時、脳天を貫くような激しい快感を拾った。
「アッ! ?︎」
「あぁ、ここかな?」
「あ、ん……っ、なに、やだ、やめ……っ!」
反射的に腰が跳ねる。萎えていた筈の自身が再び首を擡げ始め、怯えから震えていた身体が快楽に染め上げられていく。
「ほんか……っほんか!」
やめてくれ、いやだ。
「は、ふ……はぁ……っ!」
はくはくと口を動かすも、凄まじい快感を逃すための荒い呼吸音しか出てこない。拒絶の言葉は音にならず、結果的に国広が長義に縋っているような形になってしまって、心底居た堪れなかった。一方、そんな国広の葛藤なんてつゆ知らず、長義は国広の感じる場所を重点的に狙い続ける。ぐ、と気持ちいい場所を押される度に、いっそ忌々しく思うくらいにビクビクと身体が跳ねた。
「なぁ、ほんと……に、もう、やめ……」
震える掌で長義の固い腕を掴むも、押し退けるどころかもっともっととはしたなく縋っているようになってしまい、自分が情けない。
「たの、む……もう無理、むり、だから……ほんか……ァ、ほんかぁ!」
瞼の裏が白く染まった。また、達してしまったらしい。
とぷとぷと溢れる白濁は一度目よりも勢いを失い、腹ではなくすぐ下の下生えに溢れたようだ。濡れた感触が気持ち悪くて、雄を弄られてもいないのにナカだけで達したことが恥ずかしくて、猛烈に折れたくなった。
「才能があるんじゃないか? いいイきッぷりだったよ」
いい子だ、と頭を撫でられるも、その声色には明らかな嘲笑が混じっていて、悔しくて堪らない。
「……さいあくだ」
理不尽で一方的な行為に、怒りが湧いて仕方なかった。まさかこの男が、国広の尊厳を踏みにじる為だけにここまでするなんて。この部屋へ来るまでの歩み寄る気持ちなど粉々に砕け散って、今はもう、兎に角楽しげに自分を暴く男へ殺意しか芽生えない。精一杯の抵抗として、未だ覆い被さっている男を睨みつける。だが、そんな静かに殺気立つ国広を前に、長義は怯むどころか機嫌良さそうに目を細めてみせた。獲物を嬲ることを楽しむ獣の目だ。この余裕ぶっている顔がまた、国広の怒りを煽り立てる。
「知ってた? お前のココ、もう四本入るってこと」
ぐ、と再び穴を広げられ、いつの間にそれほど緩んでいたのかと驚愕する。すっかり解れたそこは己の意に反してパクパクと刺激を強請り、喜んで長義の指を咥え込んだ。
「そんな……」
「身体は素直で可愛いんだけどね。上の口とは似ても似つかぬ従順さだ。ここなら存分に愛でてあげてもいい、かな」
「や、」
それまできっちりと服を纏ったままだった長義が、自らも脱ぎ始める。勿体ぶるように上から順に、クロスタイ、ジャケット、シャツ、と脱いでいき、ついにその手はベルトへ掛かった。かちゃかちゃと鳴る金属音に恐怖が煽られる。この後の自分はどうなってしまうのか。頭は必死に思考を巡らせていたけれど、心が考えることを放棄した。これ以上先を思ってしまえば、精神が壊れてしまうとわかっていたからだ。
「待て、……っ」
長義がズラした下着の隙間から、ぶるん、と勢いよく怒号が顔を出す。既に天を仰ぎ、臨戦態勢のそれは見た目からして凶悪で、流石の国広も怯んだ。
「じゃあ、沢山愛でてやるから。良い声で啼けよ、俺の写し」
それは、死刑宣告だった。
「ひ、……ぐぁっ!」
じっくりと刻み付けるように挿入されるそれ。指とは比べ物にならない太さのものが、あらぬところに出入りしている。裂けてしまいそうだと涙目で抱いた懸念は幸いなことに杞憂に終わり、散々弄られ拡げられた甲斐あって、激痛を覚えることなく雄を呑み込んだ。
「は、……っ」
「呼吸、忘れてる」
ぺしぺしと頰を叩かれ、飛んでいた意識が戻る。内臓を突き上げる圧迫感で呼吸すら苦しく、酸素の足りない頭では何が起こっているのか理解が難しかった。
「ああ……っ、気持ちいいな? 偽物くん。やはりお前は俺のためだけに生まれたんだな。そら、誂えたようにぴったりじゃないか」
腰を使いぐるりと掻き回されれば堪らない。気持ちのいい場所に擦れるだけでも気をやりそうになるのに、奥の新たなイイ場所をこじ開けられてしまえば、それまでの強がりなどあっという間に吹き飛んだ。
「あっ、ぅ、ん、はぁ、」
律動に合わせて漏れる嬌声が、鼓膜を犯す。自分の声とは思えない甘やかな声に、己の敗北を悟った。
「ふふ、霊力に酔ってしまったかな?」
繋がったまま抱き起こされ、足の上に乗せられる。かわいい、かわいい、と乱れた金糸をなでつけられ、耳の奥に息を吹き込まれる度に、きゅん、とナカを締め付けてしまった。それに気を良くした長義がさらに睦言を囁いてくるものだから、一層タチが悪い。
「気持ちいいね、偽物くん。俺たちは二振りで一つなんじゃないかって、そう思えないか?」
「……うつし、は……にせものとは、ちがう」
「お前は本当に頑固だな。でもいいよ、今は気分がいいからね。特別に許してやる」
それから何度達せられたことだろう。
ついに身体に力が入らなくなり、全体重を掛けて長義にしなだれかかってしまった。それでも下から好きなように揺さぶられるせいで、度々バランスを崩して後ろに倒れそうになる。そんな国広を見かねた長義は、がっしりと細腰に腕を回してきて、ふー、ふー、と獣のように息をしながら、そっと言葉を囁いた。
「眠いのか? そら、あともう少しだよ。今お前の奥に注いでやるから」
何度も中に出されたせいで、結合部からは顔を背けたくなるほどの水音が漏れ聞こえていた。多分、見たら卒倒するくらいの量は出されているだろう。だと言うのにまだ中に出すのか、この変態が、なんて挑発する気力は、最早残っていなかった。
「やま、ば……ぎり……もう……おれ、」
そして、力強い腕に抱かれながら、何度目かの射精の後、やがて国広の意識は完全に落ちる。
「おやすみ、俺の写し。お前は俺のものだよ。お前が生まれた時から、ずっとね」
薄れる意識の中で何事かを言われた気がしたが、泥のように眠りについた国広に届くことはなかった。
開け放たれた窓から差し込む月光が、雪崩れ込むようにしてシーツの海に溺れた二人の影を、穏やかに照らし出す。事後特有の汗の匂いも、熱気も、淫靡な性の気配も、春の乾いた風がすべてを攫って、それらは現に溢れる甘い花の香りに掻き消され、やがて埋もれていった。