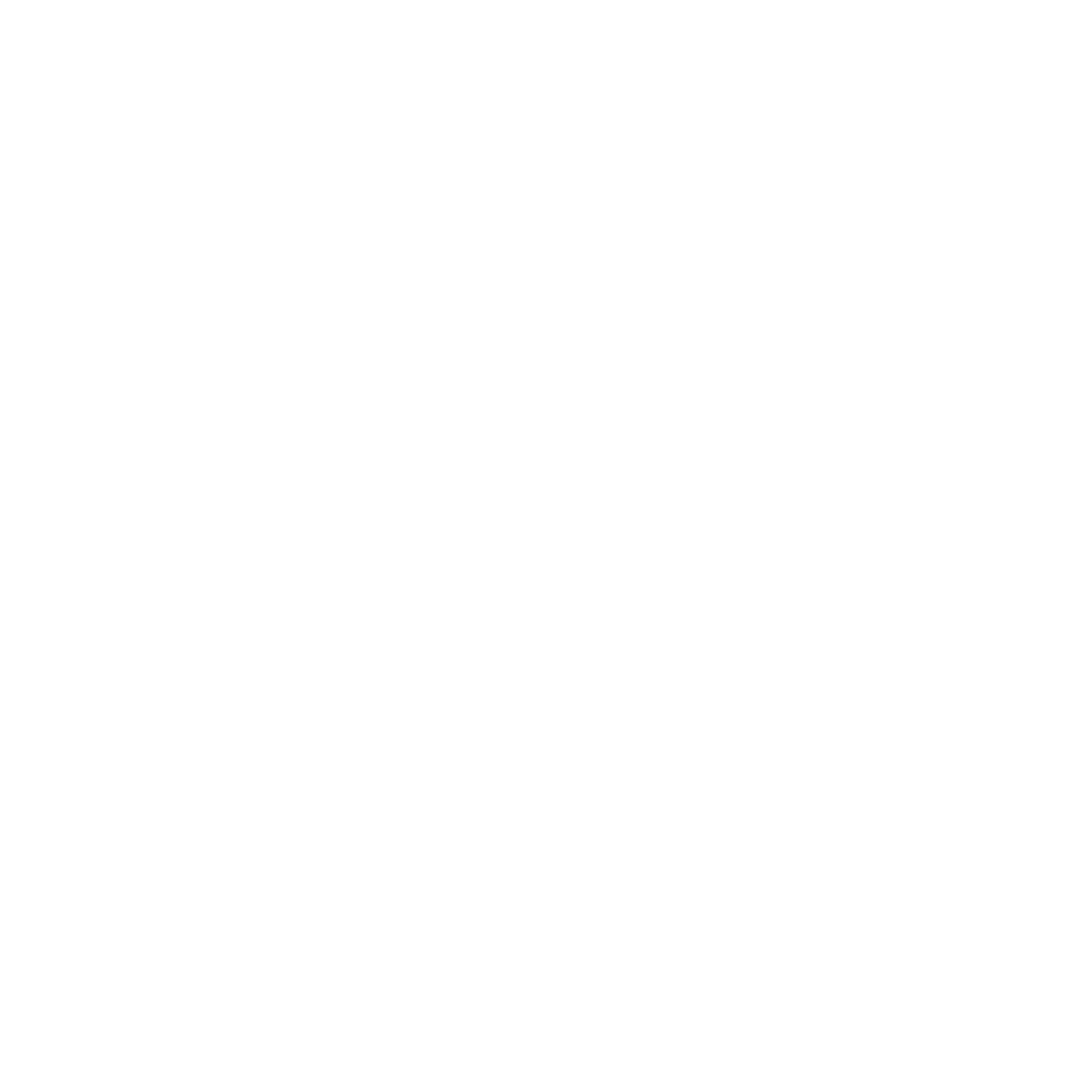第七話 縁に縋る
ずるり、と身体の芯から何かを引き摺り出されるような、そんな最悪な目覚めだった。
「……ぅ、」
少し身動ぎしただけで身体が痛む。特に酷いのは腰回りで、少しでも寝返りを打とうものならば、容赦無くあらぬところに激痛が走った。この時点で既に気分は最悪だ。さらには痛みのあまり思わず腹に力を入れた拍子に、どろりとしたものがナカから溢れてきて、しとどに下半身を濡らす。その生々しい感触に一瞬思考が止まり硬直していると、頭上から腹の立つほど冷静な声が降ってきた。
「あぁ、起きたのか」
「……やま、ば、ぎり」
声の主は長義だった。
湯殿から拝借してきたのだろう桶を持った彼が、傍らに立っている。もくもくと湯気の立ち込めるその中には、清潔な白い手拭いが浸されていて。動揺する国広を尻目に、彼は大して表情も変えぬまま、それを絞り始めた。
「血の気は戻ったようだね。あのまま折れてしまったら、どうしようかと思った」
華奢に見えて無骨な掌が手拭いを締め上げる度、びちゃびちゃ、と威勢のいい水音が響く。あの手が、昨晩国広の肌を暴いたのか。唐突に昨夜の情事を思い出してしまい、無意識のうちに目を逸らした。一方、そんな国広の変化になど微塵も興味がないらしい長義は、「ん、」と至って義務的に、適度に湿った手拭いを差し出してくる。
「顔でも拭くといい。身体は清めておいたから」
いや、身体の奥にぶちまけられた欲は、まったく処理されてないんだが。
未だシーツを汚し続けている下半身の惨状に、そんな口にするのも悍ましいことを考えた。大体、無理矢理犯しておいて、何でこんなにも淡々としているのだ、この男は。あまりに常通りの態度だったものだから、国広の心中は怒りよりも何よりも動揺が勝ってしまう。一発殴ってやろう、くらいは思っていたのだが、その勢いはすっかり削がれてしまっていた。それより早くこの場から去りたいのに、ままならぬ身体が忌々しい。
(何故、抱いたんだ)
寝台に横たわったままの状態で、手に握らされた手拭いを、暫く見つめる。国広の尊厳を傷つけるためか。それとも、自分の方が格上の存在なのだと知らしめるためか。どのみち碌な理由ではないに違いない。顔が上げられなかった。兎に角今は長義の顔を見たくなくて、目が合えばその瞬間殴り掛かってしまうだろう、と確信するくらいには、腹わたが煮えくり返っていたのだ。
そこで、ふ、と。何か身を隠すものを……と思い立ち周囲を見回す。しかし、己の布は部屋の中には見当たらず、長義が何処かにしまい込んでしまったのか、とあたりをつけた。
(……捨てられたか)
この男は何かとあの襤褸布の存在を厭うていたし、あの傍若無人ぶりだ。国広が意識を失っている間に、勝手に捨てられていたとしてもおかしくない。
「……そんなに憎いか」
自分でも初めて聞くほどの低い声。それを耳にして初めて、己が本気で怒りに打ち震えていることを知った。
「……ここまでするほど、俺が憎いのか」
「……」
長義は答えない。顔を上げればあの時と同じ無表情で、冷たい青瑠璃が国広を捉えていた。
「憎いよ」
鋭い声が、起き抜けの靄の掛かった思考を晴れ渡らせる。一気に冴えた感覚が、痛覚までもを鋭敏なものとして、身体ばかりでなく心の痛みまで拾い上げた。ふざけるな、と憤った。一時の激情に任せて好き勝手嬲っておいて、自分ばかり穢れを知らず、高潔ぶっているこの男が、憎くて憎くて堪まらない。
「はっ……そうか……。さぞ気分の良いことだったろうな。嫌いで仕方ない写しを組み敷いて……意のままに犯したのは……っ!」
これで満足だろう?
と、嫌味な笑みを浮かべてやる。布が無いことなど、この際二の次だ。それよりこの目の前の男の澄ました顔を、どうにかして崩してやりたい。今の国広を突き動かしていたものは、猛烈な怒りだけだった。
「写しの鞘はどうだった? 本歌のお眼鏡に叶ったか? そんなに気に入ったのなら、いくらでも抱かせてやるよ。そら、好きなだけ使え」
ただし、刀としての矜持は忘れない。いくら身体を穢されたとて、この心の在りようまでもを歪ませてたまるものか。国広第一の傑作という誇りは、何人たりとも屈服させることは叶わない、絶対に。
「……」
国広の安い挑発に、されど長義は何も返さなかった。聡いこの男のことだ。嫌味に含まれた言外の本意まで、しかと受け取っている筈。それでも彼は作り物めいたその美貌を崩すことはなく、こちらを見つめるばかりで。自ずと二振りは睨み合い、僅かな間に流れた沈黙をやり過ごした。
「……厨に湯を貰いに行った時、祖から手入れ札を持たされた」
突然の話の変わり様に、国広の表情が訝しげなものになる。
「宴の時の空気からして、どちらかが負傷するのは皆が予想していたらしい。資材も既に用意があるそうだから、手入れ部屋に行くぞ」
「話を逸らすな。話はまだ、」
「お前は何もわかっちゃいない」
傍らに置いていた桶を手に待ち、長義が振り返る。興奮状態にある国広を冷静な瞳が射抜いて、彼は静かに繰り返した。
「お前は、何もわかっちゃいないんだ。だから、……」
何かを言いかけて閉じられた口に、国広は目を見張る。あの、何事もはっきりきっぱりと斬れ味鋭く言葉にしてきた彼が、何かを言いあぐねた。咄嗟に聞き出さねばならないと思った。しかし、長義はそれきり硬く口を閉ざしてしまい、完全に無言になってしまう。
「本歌、何が言いたい。言ってくれなければわからない」
「……」
「……このままでは俺とて納得がいかない!」
「心配せずとも、お前がわかるまで教え込んでやるさ」
ひゅ、と喉が鳴る。長義が、胸倉に掴みかかってきた国広の首に手を掛け、軽く締めたのだ。これ以上言葉を発したなら躊躇うことなく斬ると、彼の纏う空気が告げている。殺気立った冷気が国広の首に刃を突き立て、一切の身動きを封じた。
「刻み込んでやるよ、偽物くん」
歪められたその表情には、底の知れぬ深い憎しみが剥き出しになっている。
結局、自分たちはこう在ることでしか生きられないのか。途端に頭が冷却されていった。切っても切れぬ縁で繋がれた、本歌と写し。すべてを理解したいとは思っていなかった。それでも、少しくらいは歩み寄れないものかと、頭を悩ませて……そして話をしようとした。その筈だった。だが、そんな国広の気持ちは悉く切って捨てられ、こうしてまた一方的な感情を押し付けられている。
何が彼をそこまで駆り立てているのか疑問を抱いた。
山姥切の号を奪いかけた国広への憎しみか、写しの領分を逸脱したことへの怒りか。そこまで根深いものを抱えているのならば、さっさと見放せばいいものを。彼はそれも許さず、果ては己の傍にいろと国広を縛り付ける。
「俺は、あんたがわからない」
「……」
「わからないんだ……」
だから教えてくれ、本歌。口で言われなければわからない。
俺を憎らしいと言い、憤怒を叩き付けてきた男。幼き頃から何かと厳しく接してきては、偶に気まぐれに甘やかす。昔から一向に内側を悟らせない男だった。そして、再会してからは嘗ての穏やかさなど欠片も失せていて。頑なに心を閉ざし、国広を突き放すような態度を取ってきた。お前を俺は認めない、と。国広を『偽物』呼ばわりしてまで。なのに、どうして。
「……何故なんだ」
(どうして、あんたが一番苦しそうな顔をしているんだ)
なぁ、教えてくれ。
銀色の付喪神は答えない。固く閉ざされた口が開かれることは、終ぞ無かった。
――あいつはな、心が化け物になっちまったから、心っつーもんがわかっちゃいねぇんだ。
不意に、南泉から言われた言葉を思い出す。あの酒宴にて告げられた不穏な呪詛が、じわじわと心を侵食していくのを、国広は他人事のように眺めていた。
手入れ部屋へと向かう道中、国広と長義はずっと無言だった。
噛み跡やら鬱血痕だらけの身体は、なかなか言うことを聞いてくれない。一歩踏み出す度に腰に電流が流れるような痛みが走り、足が鉛のように重たかった。途中、あんまり国広の歩みが遅いので、自分が運ぶなどと長義が言い出した時は、どうなることかと思ったが。しつこい彼の申し出を頑なに拒否した国広は、何とか自分の足で手入れ部屋まで辿り着いた。
「やぁ、待ってたよ。手入れの準備をしておいてよかった。さ、そこの診療台に服を脱いで横になってくれ」
手入れ部屋には、長義から話を聞いたと思われる主が、準備を整えて待っていた。
国広は手入れを受けるために主へ本体を差し出し、彼の指示通り服を脱いで横になる。一方、本体を受け取った主はというと、すかさず刀身を鞘から抜き出して、慎重な手つきでそれを刀掛け台に置いた。次いで、国広の肉の器の具合を確かめんと振り返り……殴り合いや刀傷といった、恐らく彼が予想していたものからかけ離れた痕跡の数々を目の当たりにして、ぎょっと目を剥く。
「……これは、」
明らかな情事の痕に、長義と国広の間に何が起こったのか漠然と察したのだろう。彼はすぐに険しい表情になると、長義の方へ向き直った。
「合意じゃないな?」
「あぁ」
こくり、と長義が頷く。何の悪びれてもない態度に、主はますます眉根を顰めた。しかし、基本的には刀同士のあれこれに干渉しない主義の彼である。険を露わにしたのはそれだけで、以降はそれ以上深く追求することはせず、淡々と国広の手入れを始めた。
(何考えてるんだ、あいつは……)
主の霊力を注がれていく国広の姿を、長義はじっと凪いだ目で見つめている。その瞳には心配や労りといった感情の色は皆無で、観察しているといった方がしっくりするほどの、無機質な光が湛えられていた。突き刺さるそれらの視線には一切無視を決め込んで、とりあえず国広は主に謝罪する。こんなことで資材を使い、手を煩わせてしまってすまない、と。すると、主は苦く笑い、毅然とした声で言った。
「いいや、これくらい構わんさ。ただ、次の日に響かないようにはして欲しいね。今は戦時中だ。いつ何が起こるかわからない。それに、彼に抵抗出来るだけの力はあるのだから、あなたも気をつけるべきだった。そこは深く反省するように」
まさにごもっともな話である。思い返してみれば、長義に逆らう隙はいくつかあった。それをわざと見逃して、快楽に流されたのは国広の落ち度だ。
「……わかった、すまない」
国広が項垂れると、すかさず主が壁に寄りかかり、こちらを見ている長義にも釘を刺す。
「山姥切長義、あなたもだ。あまり無茶はしないで頂きたい」
「……次からは善処しよう」
次なんてあってたまるか。
肩を竦めながらぬけぬけと言ってのけた男へ、国広は内心毒吐いた。流石に呆れた顔をした主が気を遣ったつもりなのか。「もう帰っていいよ」とやんわり退室を促すも、予想外にも長義はその場から動こうとはせず、主の申し出を丁重に断る。果ては手入れに半刻ほどの時間が必要とわかっても、彼が部屋から出ていく気配はなく。寧ろ長居する気満々に、近くにあった椅子に座り込む始末で。そこまできたら、主も長義を部屋から追い出すことは諦めたらしい。結局、国広の手入れが完全に終わるするまで、その微妙な空気は流れ続けた。
「終わったのか」
国広の身体の傷が癒えた頃。せっせと手入れ道具を片付け始めた主へ、長義が問う。
「ええ、傷一つなく無事に」
「そうか。手間を掛けたね。これの手入れをしてくれたこと、本歌の俺からも感謝する」
そもそも原因はあんたなんだけどな。
じとりとした目を国広が送ったところで、当の本刃はどこ吹く風。今度は椅子から立ち上がり、国広が着替え終わるのをじっと待っている。
(写しの意思など気にかける価値もない、ということか)
つくづく馬鹿にしてくれる。いくら本歌とて、写しだからと侮られるのは堀川国広の刀としての矜持が許さなかった。身体の痛みは無くなっても、勿論屈辱を与えられた怒りは持続している。正直、身体が動くようになった分、気を抜けば殴りかかってしまいそうだったため、先に帰って欲しかった。
「そら、さっさと着替えないか、偽物くん」
やはり彼が何を考えているのか、国広にはさっぱり理解出来ない。
「写しは、偽物とは違う」
お決まりのやり取りをして、国広は止めていた手を動かし始めた。いくら考えてみても、国広に無体を強いたこともそうだが、彼が何を理由に憤っているのかも、何故そこまで国広に拘るのかも、さっぱり見当もつかない。最後に刀紋の刻印された紋章を肩から下げ、入り口で待つ長義の下へ歩み寄る。長義の機嫌は悪そうだ。眉間に皺が寄っているし、口元なんてへの字に曲がっている。逆らったら逆らったで面倒なことになると学んでいた国広は、強引に手を引かれるままに長義の後をついて歩き、そのまま部屋を後にしようとした。
――しかし、
「あ、ついでに国広に話したいことがあるから、山姥切は先に戻っていてくれないか」
廊下にあと一歩で踏み出す、というタイミングで主に引き留められ、二振りは足を止める。
「……俺に?」
国広が繰り返すと、隣に立つ長義が不満げに目を細めた。
「……話、ねぇ」
「至急の用向きだ。山姥切」
「……承知した」
当然であるが、一介の刀である国広たちが、主に命じられたことに逆らうことは許されない。よって、やや渋っていた様子の長義は、されど最終的には名残惜しげにしながらも、大人しく手入れ部屋から出て行った。後ろ髪引かれる様子であったにも関わらず、こちらを振り返りもしない凛とした後ろ姿を見送った後、徐に主が呟く。
「……珍しいな。彼がああいった態度を私に取るのは」
「そうなのか?」
「珍しいどころか初めてさ」
国広は長義が本丸に来てからずっと冷たい態度を取られていたので、彼が主や他の刀たちに穏やかに接する方が、違和感を覚える。だが、どうやら主はそうではなかったらしい。ふむ、と何事か考え込んだ彼は、先ほどまで長義が立っていた空間と、国広のことを一瞥すると、やがて勝手に一人で納得して頷いた。その口元は何故か、楽し気に歪んでいる。
「難儀なものだね」
「……三日月と青江にも言われた。何なんだ一体」
クスクスと笑う主の言っていることがわからない。難儀だな、というのは、ここ最近他の刀たちにも言われるようになった。まったく、自分たちの何を見てそう言っているのやら。特に三日月や青江には聚楽第任務の最中から、ずっと壊れたラジオのように同じことを言われていて、正直反応に困る。
「言葉通りの意味だよ。あなたたちは何百年と生きてはいるが、人としては未熟だからね。非常に興味深い……。さて、時間は有限。時は金なり、てね。本題に入ろうか」
それから向き直った二人は、実に色々な話をした。
まずは改めて聚楽第任務での活躍について労われ、最近の本丸の活動状況、政府より報告のあった敵勢力の動向について、新たなる時代の合戦上が開放されるという新情報……そして、多岐にわたる話の中でも特に主が重点を置いたのは、国広の修行についてと、新しく政府から依頼された特殊任務の内容についてだった。
(修行か……)
ただ長義と国広を引き離すための口から出まかせではなく。ちゃんとした用向きがあったことに面食らう一方、少しでも主の行動を軽んじてしまった己を恥じ、深く反省する。
「短刀と打刀、大太刀で修行が許された者たちは、すべて修行して極めて帰ってきた。いよいよあなたの番だ。今まで待たせてすまなかったね」
「……いいや、打刀が極めた後に弱体化するというのは、敵に油断を見せることになる。本丸の守護のため、初期刀である俺の修行を遅らせたあんたの判断は、間違ってはいない」
「そう言ってくれると助かるよ」
極めた刀たちの練度は、それなりに上がってきている。初期からこの本丸に顕現し、弱体化を理由に極修行を遅らせていた刀たちの極後の練度も、各々安定してきていた。次は、国広の番だ。
「日取りはいつにしよう。私としては、明日でも構わない。あなたはきっと大仰な見送りは嫌がるだろうから、希望するなら内々だけの見送りにて、あなたを送り出そう」
修行の時を、国広はずっと待っていた。練度上限の中でも特攻役を担う第一部隊の部隊長を任され、極めた刀たちの練度上げにも尽力し、この本丸での戦果を着々と積み上げてきた。まだ実績を持たぬ頃の己なら、自分にはまだ早いと丁重に辞退したことであろう。しかし、今の国広は違う。本丸の仲間たちから初期刀として信を置かれ、今までの実績のおかげで、写しながらに戦働きなら右に出る者は居ないという自負もある。主の刀として振るわれてきたこの身を、さらに研ぎ澄ませることでより多くの敵を屠りたい。何より刀としての、付喪神としての本能が、もっと強くなることを望んでいる。
「修行の件、謹んで受け賜らせて頂く。そうだな、時期は……」
迷いは、無かった。
*
長義と国広の手入れ部屋事件から二週間。
あれから国広は、長義のことをひたすら避けて生活していた。四月に入り、丁度本丸の決算期を迎えたということもあって、目まぐるしく過ぎる日々の中、ぐだぐだ悩む暇すらなく。おかげさまで比較的平和な毎日を過ごさせてもらっている。長義の方から特に何を言われることもないのを見る限り、きっと先日の一件は、彼の中で終わったこととして処理されたのだろう。このまま国広のことなど忘れてくれればいいのだが……なんて思いつつ、国広は今日も今日とて書類仕事に精を出していた。残る書類はあと三枚。これが終われば自由時間になる。
「……よし」
気合を入れ直し、ペンを手に持つ。疲れてきた目を瞬かせてから、国広はみっちり文字の書かれた書面と向き合った。
――国広の修行は一ヶ月後に行われることとなった。
明日でもいい、と言われていたにも関わらず、なぜ一月も期間を開けたのかというと、そこには政府から新しく依頼された、とある特殊任務の事情が絡んでくる。
(聚楽第に比べれば危険は少ないとはいえ、確かに『特殊』な任務だな)
本日分の書類仕事を終え、自由時間中。
ペラペラと主から持たされた概要書を捲り、今回の依頼内容について思いを馳せる。敵勢力との戦であるとか、新たな時代への突入だとか、ブラック本丸の摘発だとか。そんな類の話ではないので、今回の案件に危険は無いというのは断言出来る。そう、危険ではないのだが……如何せんまた違った方向に特殊過ぎて、戸惑いが大きいというのが本音だった。
『あなたに護衛の任務を任せたいと思っている』
先日の主の言葉を反芻する。
国広の修行の話が一通り済んだ後に、その任務の話は始められた。
『此度の聚楽第任務にて、敵勢力が本格的に此方側の戦力……つまりは、あなたたち刀剣男士の本体を狙い、政府側の戦力の削ぎ落としにかかったことが判明したからね。本霊たちの守護を、さらに厳重にすることが決まったんだ。どうやら今彼らを保管している政府の中枢部から、少々特殊な環境へ移されることとなるらしい』
『特殊な環境?』
妙に引っかかる言い回しをした主へ、国広は尋ねる。そんな国広に対して神妙に頷いてみせた彼は、少し困ったような顔をして答えた。
『あぁ、絶対に人の手の及ばぬ、完全に隔離された空間……』
――《神域》だよ。
神域。神が管理する領域で、その領域を支配する神の許可無くしては、何人たりとも立ち入ることを許されぬ、究極の隔離空間だ。わかりやすい例で言うと、神隠しの時に連れ去られる場所がそこにあたる。あるいは、神が住まう常世とでも言うのが正しいか。神が絶対に誰にも奪われたくない愛し子を、連れ去り、囲い、ひたすらに愛でるために作られた場所。その話を聞いた時、国広はなるほどそれは良案だ、とその着眼点の良さに目から鱗が落ちた。あそこならば、余程のことがなければ敵勢力に攻め落とされる心配はない。
『そうか。それは良い案だと思う。敵勢力に格の高い神がつかない限りは、絶対安全だろうな』
まぁ、あそこまで穢れてしまっている時点で、奴らに味方する神なんてそういないと思うが。
感心したように国広が言うと、されど主は険しい顔付きのまま黙り込んでしまう。何がそんなに懸念されるというのだろうか。その主の表情の意味がわからず、国広は彼からもたらされる言葉を静かに待った。
『ただ、神域に本霊たちを移すとなると、どうしても今までのように、人間の手で管理することは不可能となる。ここは非常に議論されたところなんだが……結論から言うと、本霊専用の本丸を神域に作り、そこで本霊たちには自分たちの力だけで、本丸を自治してもらおうということになった』
それには国広も酷く驚いた。刀である自分たちが本丸を自治するなど、考えもしないことだったのだ。
また、その後続けられた主の話によると、既に本霊専用の本丸・通称《刀霊守本堂》は完成しており、本霊たちの移動も終わっていて、試運転中なのだという。自治に関しては、本霊たちの中でもより多くの分霊を顕現してきた、初期刀の五振りを中心に進めていってもらう事で、話は落ち着いたのだとか。今のところ、稼働当初に多少の設備の不具合こそあったものの、目立った不満の声は無いようで、本丸は順調に運営されているらしい。
『それで、政府の依頼とは……』
『政府の直接の管理下から外れた本霊たちと、定期的に接触し、彼らの無事を確認すること……だそうだ』
特殊任務の内容を聞き、国広の表情が僅かに曇る。
建前はそういうことにしてあるのだろう。しかし、その実不穏な動きがないか探れと言っているようなものだった。分霊たちとは比べ物にならない力を秘めた本霊が、管理下から外れるのだ。政府がそれを不安に思うのも無理はない。しかし、人の子と本霊の橋渡し役として主が選ばれた、という部分に納得がいかなかった。古参でもっと経験があり、力のある本丸はいくらでもある。果たして、わざわざ主が矢面に立つ必要はあるのか。
そんな国広の懸念は、しかし次の主の言葉で晴らされることとなった。
『まぁ、私はおまけだ。全国各地を代表する力のある審神者たちの補佐役、つまりは見習いといったところか。私は中堅どころだからね。年寄り連中が若い者も経験を積ませるために連れて行こう、と言い出したらしい。そこで選ばれたのが私と、あと二人だ』
『先日公表された戦績順位の、中堅どころ且つ上位の本丸か』
『如何にも。私の本丸は同年代の審神者たちに比べると、確かな戦果を挙げているからね』
あなたたちのおかげだ、と。誇らしげに、主が言う。
『そこで私はあなたに、刀霊守本堂へ赴く時の護衛を頼みたい』
主から名指しで命を受けて、断れる者などいるものか。修行の兼ね合いもあり、国広には他の者に護衛役を代わってもらい修行へ行くか、修行を遅らせ護衛任務を全うするか選択肢が与えられた。だがそんなもの、答えなど初めから決まりきっている。
『……その命、俺が拝命した。修行は一月後に遅らせる』
国広はその場に手をつき、頭を垂れる。主はそんな国広を前に満足気に頷き、予め用意していた機密情報が書かれた概要書を手渡してきた。思ったより文量のあるそれに一瞬怯むも、主が他でもない自分を頼ってくれたことに、じわじわと喜びが沸き上がり、すぐに概要書の分厚さなど気にならなくなる。
こうして、国広は西の審神者代表として《刀霊守本堂》へ赴くことになった主の、護衛役を務めることが決まった。そして同時に、修行の日取りを一月遅らせたのだった。
(本霊か)
概要書の注意文を、指先でなぞる。
自分と同じものであるが、違うもの。分霊として顕現されてこの方会ったことはなく、本霊の存在を仄めかされても、いまひとつピンとこなかった。
「ふぅ……」
分厚い概要書を閉じる。疲れきった目を瞑り、凝り固まった肩を回した。大方の任務の内容は頭に叩き込んだ。後は、《刀霊守本堂》までの道筋を確認し、襲撃の可能性がある場所を洗い出すだけ……。やるべきことを頭の中で羅列していきながら、文机の上に置かれた湯呑みを手に取る。先ほど堀川が淹れてくれた茶は、長い時間放置されていたせいで、すっかり冷め切ってしまっていた。
ぎしり。
その時、部屋の外から廊下の軋む音が聞こえ、部屋の入り口の方へ目をやる。午後の畑仕事を終えた山伏の兄弟が帰って来たのだろうか。ならば自分もここらで一服しよう、と。国広は空になった湯呑みを手に立ち上がった。
「山姥切国広はいるか」
胃がひっくり返るような思いとはこのことか。うっかり湯呑みを落としそうになり、慌てて滑り落ちそうになったそれを掴む。次いで叫び声を上げそうになった口を乱雑に塞いで、国広は固まった。部屋の外から聞こえてきた声が、予想外の男のものだったからだ。
「いるんだろう」
すると、部屋の中にいる国広の気配を察知したのだろう。さっさと開けないか、と急かされる。苛立っても尚、無断で襖を開けようとしないところが彼らしかった。
「……何の用だ」
いくら待っても立ち去る様子のない男に、いい加減諦めて襖を開ける。指三本分ほどの隙間から外を伺うと、やはりそこにいたのは冷戦中の長義で。むっつりと仏頂面をした彼は、あからさまに不機嫌そうに堀川部屋の前に立っていた。
「お前、自分の方から俺の下へ赴くと言っておいて、何故来ない。もう何日経ってると思ってるんだ」
「……は、」
間の抜けた声を出した国広は悪くない。一体いつの話をしているんだ。人を強姦しておいて、よくもそんなことが言えたものである。必然、国広の目が吊り上がり、纏う空気が何度か冷え込んだ。弁は立たぬが、かといって大人しく引き下がるタマではない。警戒する猫のように毛を逆立てて威嚇する国広に、されど長義は大して表情を変えることもなく。それどころか滑稽だとばかりに鼻で笑って、あっけらかんと宣った。
「東の離れに越さぬ代わりに、俺の下へ自ら足を運ぶと言い出したのは、どこの誰かな?」
「あぁ……あの話か」
「自分の言ったことも忘れたのか」
長義に無理矢理犯される前に、そんな話をした気がする。だが、普通に考えてあれは無効に決まってるだろう。
「……あれは無効だ」
誰が自分を犯した男相手に、自ら鴨がネギを背負って歩くような真似をするというのか。ふ、と。このまま襖を閉めてしまおう、なんて考えが頭を過る。だが、指先に力を入れた瞬間、長義の足が隙間に入り込んできて、彼を追い出す手段は呆気なく断たれてしまった。
「何が無効だ。一丁前に……まったく、本歌の手を煩わせるんじゃないよ。そら、俺の部屋に行くぞ」
布を掴まれ、部屋から無理矢理引っ張り出されて焦る。咄嗟に両足を踏ん張り何とかその場に留まろうとするも、思っていた以上に長義の力は強く。剥がされそうになった布を取り戻そうとして、一度体勢を崩されてしまった国広では、成す術がなかった。また、運の悪いことに廊下は人気がなく、明らかに不穏な空気を放っている二振りを見て、仲裁に入ってくれる存在にも期待出来ない。
どうしよう、と打開策を考えている間にも、国広は既に東の離れにまで連れて来られてしまっていて。完全に相手のテリトリーに入ってしまったことに、内に抱えた焦躁がますます煽られた。
「……何してるんだ。さっさと入りなよ」
長義の部屋のドアの前で、最後の抵抗を試みる。
「……いや、用ならここで、」
「いいから」
一縷の望みをかけた拒絶は、しかしあっさり一蹴されてしまった。そのまま強引に部屋の中へ引き込まれる。
(何なんだ本当に……屈辱を与えるというなら、この前ので十分じゃないか……)
あの日以来、足を踏み入れることのなかった長義の部屋。内装は変わらず几帳面なほどに整えられており、部屋に充満する彼の匂いが鼻腔に広がる。カッと身体が熱くなった。今でも鮮明に思い出せる、あの夜の記憶。もう二度と思い出すまいと怒りに打ち震えたというのに、その断片を少し拾い上げただけでこれとは。自分が情けなくて、無性に泣きたくなった。
「……それで、俺に何の用だ。まだ書類仕事の途中で、っ!」
布を掴んでいた右手に触れられ、肩が跳ねる。その瞬間、長義に両手を縛られた時の記憶が蘇り、反射的に手を振り払った。
パシンッ!
「……つ、」
僅かに走った痛みに秀麗な顔が歪み、直後頬を引き攣らせる。
「……また、細くなった」
「は?」
忌々しげに国広の首を睨み付けた長義が、何事かを呟いた。声が小さく、不意にもたらされた言葉を聞き取ることは叶わない。怪訝に思うも聞き返す間も無く、突然左手を掴まれ、その勢いのまま長義の方へ引き寄せられた。離れなければ、と。咄嗟に国広は身体を強張らせる。一方、そんな国広の思考を読んだらしい彼は、すぐさま先手を打ち、胸の中に飛び込んだ国広の身体をすっぽりと抱き締めてしまった。
「な、……おいっ」
細身に見えてしっかり筋肉のついた身体は、乱暴な態度とは裏腹に優しくしなやかな肢体を抱き留める。腰に回された腕にも、それほど力は籠められておらず、本気を出せば逃れられそうなくらいの緩い拘束に、国広の方が戸惑ってしまった。
「……そんなに離れていきたいか」
耳の真横で囁かれて肩が震えた。吐息を直接耳に吹き込まれてしまえば、それだけで一度快楽を知った身体には甘い痺れが走る。ゾクゾクと腰に重く響くそれに、つい舌打ちが漏れた。こんなにも簡単に隙を見せるなど、刀工国広の刀の名折れ。自分で自分が許せなかった。
「お前は昔からそうだね。何もわかっちゃいない」
「またそれか……だから、俺はあんたに何度も聞いてるだろう」
「お前は俺の写しなんだから、それくらい言葉にせずとも察しろ」
そんな無茶な。
という言葉は呑み込んだ。言えば余計面倒なことになりそうだと、本能が察知していたからだ。
「この前のあれで理解してくれたかと思ったけど、やっぱりお前はお前のままだった……」
「……」
「俺の写しであることは、光栄だろう? それでいいじゃないか。この山姥切の写しだぞ? 何を不満に思うことがある」
何一つ疑うことを知らない、澄んだ青瑠璃と目が合う。己が写しであること。昔から国広の矜持の在り方を歪めてきた元凶。山姥切の写しだからどうということではなく、己が只の《堀川国広・第一の最高傑作》とだけで在れなかったこと……己だけで個として存在することが許されなかったことが、ずっと悩ましかった。
この己よりも何百年と生きた男は、その葛藤がわからない。わからないから、こんなことが出来る。そう思うと、何だか可笑しい。
「……俺は、あんたの写しであることを不満に思っているわけじゃない……俺はただ、」
「嘘だ。お前は写しである自分を厭うている。その証拠に、お前はその襤褸布を皆の前で剥ごうとしないじゃないか。その言動もそうだ。何かと写しであることを引き合いに出して……お前は俺の写しであるということを疎み、その責務を放棄しようとしている。本歌を引き立て、本歌が失われてからも後世に渡り俺の存在を伝えていくという、写しの生存理由たる責務を」
血を吐くような声だった。
まさしく、これを慟哭と呼ぶのだろう。大きな声で叫ばれたわけではない。しかしそれは紛れもなく叫びだった。
「……っ」
息を呑んだ。彼の言う通り、国広は己が写しであることにずっと思い悩んできた。人の子たちが何気なく発した、「写しであることが残念だ」「これが本歌であれば」という言葉の刃たちが、国広の《刀工国広の最高傑作》としての自信と矜持を、徐々に擦り減らしてしまったのだ。そのことを、長義はすべてわかっていた。わかった上で、尚も国広を写しとして扱おうとしている。
なんて、残酷な男だろう。
いっそ国広への興味が一切なく、だからこそ身勝手に振り回しているようなら、まだ許せたものを。国広の地雷を軽々と踏み抜いておいて、さらには性懲りもなく己の定めた枠組みの中に押し込めようというのか。
「俺があんたを知らないように、あんたも、俺を知らないじゃないか……っ」
否、知っているふりをして、その根本の部分を理解しようとしないのだ。都合の悪いことに、見ないふりをしている。それは悪だろう。国広もまた叫んだ。そうでなければ、この内で燻る怒りのせいで、気が触れてしまいそうだったから。
「……お前は俺の一部だと、刻みつけたつもりだったんだけどね。やはり一度では足りなかったらしい」
しゅるり。
布の留め紐を外される。抵抗するつもりはなかった。これは戦だ。互いに譲れぬものをぶつけ合い、斬るか斬られるかの大勝負。
「いくらこの身を穢そうと……」
いいだろう。その勝負、受けてやろう。どさり、と押し倒された拍子に、長義の胸倉を掴み引き寄せる。
「俺は、決して屈しない」
――やれるものならやってみろ。
着乱れた衣服をそのままに、真正面から向き合えば、冷たい色をした瞳が心底可笑しそうに弧を描いた。目の前の薄い唇が、勿体ぶるようにゆっくりと開閉する。己の言葉を国広の奥に刻み付けるように、ぱっくりと開いた傷口に塩を塗り込むように。
「……いい覚悟だ。だがその強がりも、何処まで続けられるかな?」
どちらからともなく、噛み付くように唇を重ねた。長義の熱い舌が国広の唇をノックし、それに応えるようにして僅かに口を開く。すかさず口内へと割り入ってきたそれに自ら舌を絡ませ、時折甘噛みしては擦り合わせる、ということを繰り返していると、互いの息が荒くなり始めたのがわかった。呼吸を奪うような行為が続けられている間、二振りは一瞬たりとも相手から目を逸らさず、性急に口吸いを深めていく。
吹っ切れた国広の心には、兎に角このまま好きなようにさせて堪るかという、明確な怒りが燻っていて。捌け口のないそれを一気にぶちまけるかのように、行為に没頭していった。
「は……なぁ、」
暴かれ、溶かされ、揺さぶられ、それでも折れぬ国広の意志に舌打ちをして、長義が囁く。
「……傍に在れと思うことの、何がそんなに嫌なんだ……? お前は、俺の写しなのに」
傍に、か。
投げかけられた言葉は睦言そのものであるのに、その言葉の裏側に忍ばされた、本当の意味の惨さよ。本歌の傍でひたすら自分たちを比較する視線に晒されていろと? 冗談じゃない。
「はは、」
乾いた笑いが漏れる。己に覆い被さる男の方へ、国広は手を伸ばした。すり、と愛おしむように上気した頬を撫で、荒い息を吐く赤く熟れた唇を指先で辿り、汗で湿った銀糸を絡め取る。まるで心が通じ合った相手にするような愛撫は、やはり格好だけで心は伴っていない。最後に反抗心を示してキュウッと下を締め付けてやると、腹の奥に咥え込んだ男の熱がビクビクと震え、より一層圧迫感が増した。
「……、ぐっ」
「……確かにこれは、難儀だな」
何となく彼らが言いたかったことが、わかった気がする。
「……あんたが俺を、わかってくれたら……その時はあんたの傍にいても、いいかも知れない」
多分一生、そんな日は来ないだろうけれど。
「……生意気」
「ぁ、」
ズン、と最奥を突かれ、声が出た。一つになった場所から流れ込んでくる霊力が、途轍もなく気持ちいい。溶けてしまいそうだ。でも、この男は国広の芯の部分まで溶かすことは出来ない。勝った、と思った。俺は、まだ俺としての自我が確立されている。だが、写しとしての性か。長義を受け入れている今この瞬間が、とても満たされているようにも感じられて、ぴたりと隙間無く肌を重ね合わせて抱き合えば、意に反して本能が喜びの声を上げた。
「ん、……は、ぁ」
粘着質な水音を立て、ナカのしこりを重点的に突き上げられる。喉奥からせり上がってきた悩ましげな嬌声が溢れて、甘く囀る度に長義の口元が歪んだ。戦場で見たあの笑みだ。敵を前に、返り血を浴びながら浮かべる、獰猛で美しい笑み。
(綺麗だな)
快楽に溺れた頭で、ぼんやりと考える。明かりも点けず事に及んだおかげで、部屋は薄暗い。だというのに暗がりの中で揺れる銀髪が、きらきらと輝いて見えた。純粋にそれを、綺麗だと思った。例えるならそう、夜空に煌めく星のよう。暫く己の上で夢中になって腰を振る男を見つめていれば、男がギラついた眼差しを国広に向けてくる。その余裕の無さに笑いが込み上げ、ざまぁみろ、と心の中で嘲った。すると、国広の吐き捨てた言葉を拾ったわけでもないのに、長義の眉間に皺が寄り、唐突に鼻先を近づけられる。
「考え事なんて余裕だな?」
ちゅ。
唇を重ねるだけの軽い口吸いを仕掛け、言葉を塞ぐ。ほぼ無意識のうちにやっていた。
「あんたの、ことを……っ、考えてた……」
「……っ! クソッ」
大きく見開かれた目が、憎々し気に歪められる。突然ぐるり、と景色が回って混乱した。一体何が起きたというのか。身体をひっくり返される時に一度昂ぶりを抜き出され、今度は何をされるのかと身構える。その次の瞬間、ずぶりと再び勢いよく魔羅を捻じ込まれ、あまりの衝撃に悶絶した。
「ぐぅ……ッ!」
足先から脳髄までをビリビリとした快感が駆け巡る。縋るように己の下に広げられた襤褸布を掴んだ。そうしなければ頭がおかしくなりそうだったのだ。そして、快感を逃がそうと深く息を吐いている間に、うつ伏せに寝かされた身体を後ろから抑えつけられ、腰を高く掲げられる。やめろ、無理だ。そんな国広の蕩けきった声は、長義の興奮を煽る材料にしかならず。碌な抵抗も出来ないでいるうちに、自ら長義の熱を欲しているような体勢にされてしまう。
「いい眺めだな」
尻を後ろへ大きく突き出した格好に、あまりの羞恥から赤面した。
「な、」
己の状態を察した国広が、慌てて体勢を戻そうと腕に力を籠める。
「させないよ」
だが、起き上がろうとした国広を長義は力づくで押さえ込み、また好き勝手揺さぶり始めた。
「ふ、ぅ! やまんば、ぎり……! あ、この体勢は、やめ、やァ、……っ」
「……っ浅ましく啼いていろ。それがお前には似合いだ」
背に長義の汗が滴り落ちたのを感じる。そんな僅かな刺激にすら反応し、ビクビクと内腿が痙攣し始めた。絶頂は近い。恐怖から冷え切っていく心とは逆に、どんどん身体が火照っていく。怖い。自分が自分で無くなっていくような恐ろしさが、国広を覆い尽くしていく。
「は、おい、国広の、……っ」
生理的に溢れてきた涙を布で拭いつつ。決して泣き顔を見られてなるものかと顔を伏せていれば、後ろから伸びてきた長義の手によって、彼の方へ顔を向かされてしまう。
「ん、んぅ……っ」
「は、ぁ……くにひろ、」
貪るように口づけられ、恍惚と彼から与えられる快感に感じ入った。長義の霊力は、国広にとって毒にも等しい。相性が良すぎるのだ。無理な体勢を強いられているせいで、呼吸が苦しい。されどそれ以上に、気持ちいい。もう無理だ、限界だ。
「ほん、か……」
ぴちゃぴちゃと弄ぶように国広の口内を蹂躙した長義の舌は、やがて名残惜し気に糸を引きながら離れていく。
「……ぅ」
眩しいほどの白い肌を、湿り気を帯びた舌が這い回った。背骨に沿うよう下から上へ、その次は無防備に晒された肩へ、そして最後に後れ毛の隙間から覗く項へ。目的の場所に辿り着いた唇が、軽くそこに吸い付く。ちゅ、ちゅ、と何度も啄むようなもどかしい触れ方に、自ずと物欲し気に尻が揺らぎ、それを見た長義が「ふ、」と小さく笑んだ。
僅かな空気の揺らぎにハッと我に返り、己のはしたなさを恥じる。今すぐ布に包まりたくなり頭を抱えると、不意を突いて容赦ない力で項に咬みつかれた。
「は、ぅう⁉」
同時に激しく腰を打ち付けられ、眼前に星が飛ぶ。混乱のあまり何事かわめいてしまった気がするが、頭が理解を放棄した。わけがわからない。気持ちが良過ぎて。結果、本日何度目かの絶頂に達してしまい、その猛烈な国広の締め付けに耐えかねたのか。ナカに埋もれた長義の魔羅が、小刻みに震え出す。
「……〰〰ッ!」
言葉にならない悲鳴を上げながら、国広と長義は二振り共に達した。生温い長義の精が己の中に広がっていくのを、国広は朦朧とした意識の中、どこか遠くで感じていた。
「ぁ……うあ……」
「……く、」
崩れ落ちるようにして国広に凭れ掛かってきた長義が、耳元でフー、フー、と荒く息をしている。横目で彼の顔を盗み見ると、硬く目を瞑り、眉根を潜めた美しい顔が、快楽の波に呑まれぬよう歯を食いしばって耐えていた。
熱い吐息が肌を擽る感触にすら感じてしまう自分が、浅ましいと思った。
それでも屈することのない己の心の在り様に安堵して、男の体温を感じながら目を瞑る。もう、疲れた。限界まで貪られた身体が、酷く怠い。さらには全身に行き渡る長義の霊力が眠りへ誘ってきて、半ば気絶するようにしてそのまま意識を失った。
「……くに、ひろ……あぁ、」
――太くなった。
完全に力の抜けた肢体を、ぎゅうっときつく抱き締めた長義が、恍惚とした声で呟く。愛おしむような手つきで国広の首筋をなぞった彼は、やがて満足そうに微笑むと、国広に続き穏やかな眠りの縁に落ちていった。