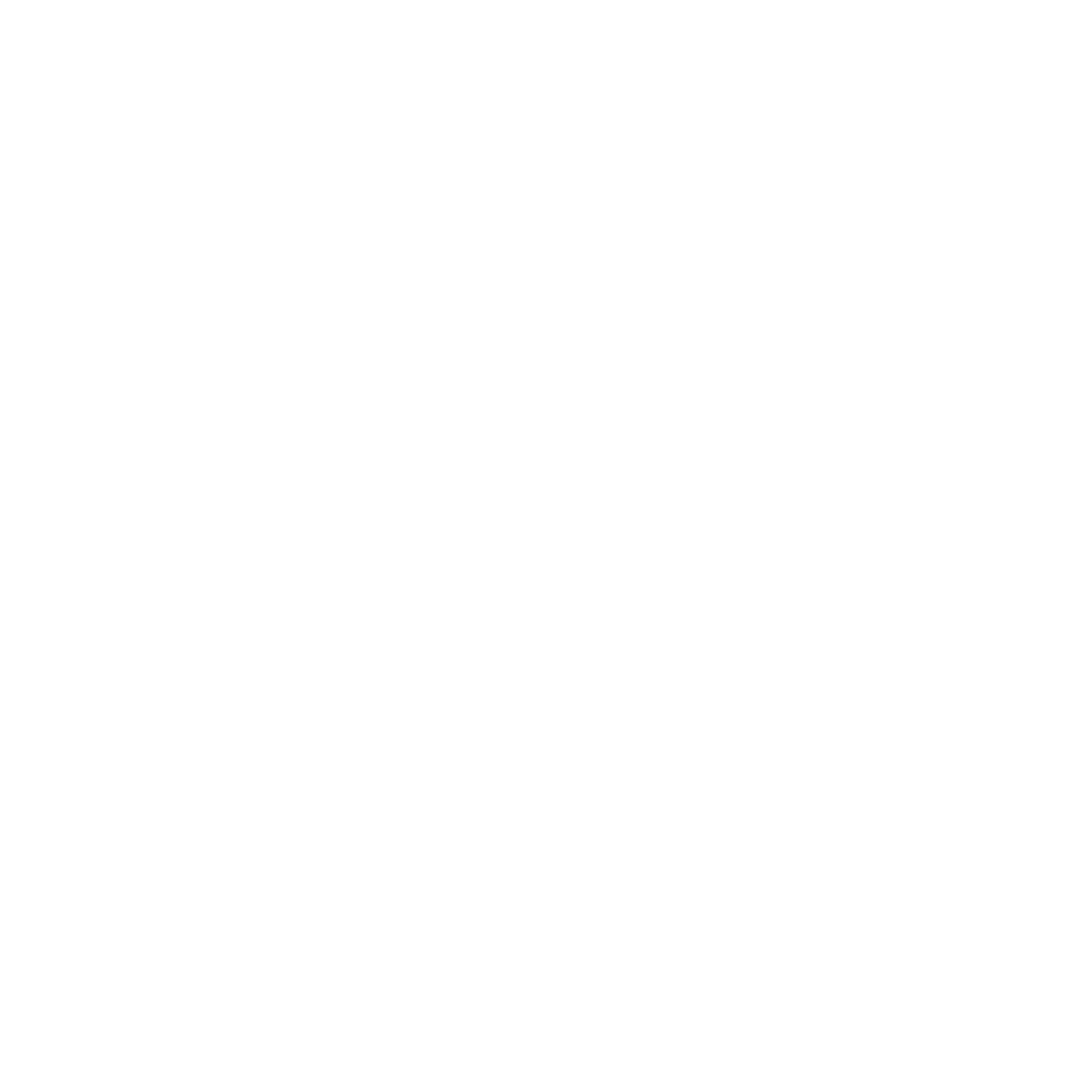第八話 刀霊守本堂
ふ、と眩しさを感じて、瞼を開けた。眩しさの元凶たる窓外に視線をやると、既に日が昇りかけている。明るさからして、今は卯の刻といったところか。確か、今日の任務は午後からだった。この分ならもう少し眠れるな、と再び眠りの縁に意識が沈みかけた時。開け放たれた窓から風が舞い込み、剥き出しの肌を擽られる。全開になったそこは、情事の名残を逃すべく換気をした時のままの状態で。それを見てようやく、戸締りもせずに力尽きてしまったことを悟った。
ちゅん、ちゅん。
枝の上で囀る雀が、眼前を飛び去っていく。揺れた枝先から桜の花びらが舞い落ち、甘い香りが辺りに広がった。早いものでもう四月上旬だ。すっかり暖かくなった気候は過ごしやすく、日の無い時分でも薄着のまま過ごすことが出来るようになった。今の国広の夜着に至っては、借り物の薄手の着流し一枚という無防備さである。しかも下着はつけておらず、ほぼ全裸に等しい。寝汗で湿った肌には春の風も冷たく感じ、ぶるりと小さく身震いしながら、国広は乱れた着流しの合わせ目を直した。
「ふぁ……」
欠伸が漏れた。当然だ。昨晩もまた根競べのような激しいまぐわいをして、気絶するように意識を失ったのだから。
(今回も俺の負けか……)
不毛な行為を始めてから此の方、国広の敗北が続いている。苦い表情を浮かべ隣で眠る男に視線を移すと、すぅすぅと規則的な寝息を立てる布の塊が、呼吸に合わせて僅かに上下していた。布団から覗く銀髪は、セットしていないというのに寝癖一つない完璧さで、無性にぐしゃぐしゃと鳥の巣になるまで搔き乱してやりたくなる。
ここ最近行為の頻度は徐々に増えつつあり、週に三度ほどは国広と長義は身体を重ねていた。今や身体がすっかり行為に慣らされたおかげで、初夜の時のような無様を晒すことはないが。それでも行為自体が、受け入れる側である国広の負担になっているのは事実だった。とはいえこちらから頻度を落とせだなどとは、口が裂けても言えない。貧弱だな、とか、口ほどでも無い、だとか嫌味を言われるのが目に見えているからだ。それに、こちらが先に根を上げたと思われるのは癪である。付け入られる隙を見せて侮られるくらいならば、精根尽き果てるまでこの男から搾り取ってやる……なんて闘志を燃やしている国広は気づいていなかった。まったくの見当違いな場所で一人相撲をしていることを。
「……ん、なんだ、起きたのか?」
落ち着きなくごそごそと布団の中で身動いていたら、繭になって眠っていた長義が目を覚ました。ぱちぱちと目を瞬かせた彼は、眩しそうに眉根を寄せつつ薄目を開き、冷たい色の瞳に国広を映し出す。
「おはよう」
起き抜けだというのに毅然とした声で、長義が挨拶してくる。
「……おはよう」
昨晩のこともあり不貞腐れながら応えれば、聡い男はすぐに国広の心中に燻る不満を見透かしたようで、見慣れた高慢な笑みを貼り付けた。
「お前が気絶したから身体を清めてやったんだ。感謝しろよ」
「……清めたという割に、いつも中がそのままなのはどうなんだ」
これは清めたと言っていいのか。今日も今日とて中に出された白濁に内腿を汚され、国広は不快感から視線で男を責め立てる。しかし、長義に反省の色は一切見られず。寧ろ楽し気に口角を吊り上げたので、怒りを通り越して呆れてしまった。
「なに、人の子でもないのだから、腹を下すわけでもなし。それに俺の霊力がたっぷり籠められているものだ。そのまま有難く受け取ればいい」
「要らん。掻き出す」
「お前はほんとに可愛くないね」
「……」
可愛さなど微塵も求めていないくせして何を言っているんだか。
ぬくぬくと温まっていた掛布を剥ぎ、起き上がる。乱れた着流しをおざなりに整え、緩んだ角帯を締め直すと、布団の傍に置かれている塵紙を数枚手に取った。そして、膝立ちになった途端、ドロドロと生温かい体液が溢れ出した後孔を乱雑に拭っていく。だが、次から次へと男の欲は止まることなく零れ続け、拭いたそばから流れ出すものだから、すべて無駄な抵抗に終わってしまった。というか、出し過ぎじゃないか、これ。これはあれだ、気をやってからも何度か出しやがったな。
長義の遠慮のなさに呆れ果て、本日二度目の大きなため息を吐いた。
「はぁ……」
おざなりに纏った着流しの下半身を寛げる。外側から拭うだけでは無意味だと早々に悟ったので、本格的に掻き出すことにした。隣に長義がいるが、今更恥じらうこともない。彼には自分でも見ないような場所まで曝け出しているし、何より掻き出すところを見て少しは反省しろ、という当てつけの気持ちの方が強かった。自分がどれだけ国広のナカに注いだのか、改めて目で確認して、せいぜい自身の行いにドン引きすればいい。
(少しは遠慮しろ……まったく)
寛げられた着流しから、すらりとした白い足が露わになる。
肩幅ほどに両足を開き、窄まりへと手を伸ばした。布団を汚さぬよう僅かに前のめりになれば、必然長義の方へ尻を突き出すような格好になる。しかし、掻き出すことに意識を集中させている国広が、今の己の姿が如何に男の欲を煽るものなのか、自覚することはなく。また、己に注がれるねっとりとした長義の視線に、情欲の炎が灯ったことにも、気づくことはなかった。
「ん……、」
そうっと閉じた蕾に指を挿し入れていく。
一晩中長義のものを受け入れていたそこは、思っていた以上に呆気なく解れてくれて、容易に二本の指を飲み込んだ。慣れた手つきでズブズブと奥まで進めていき、奥まったところで第一関節を曲げる。すると、腹いっぱいに出された欲の残滓が、勢いよく流れ出てきた。コポコポ、と空気の抜ける音が部屋に響いた時は、流石に少々気恥ずかしいものがあったけれど。ここで照れたら負けなので、構わずそのまま処理を続ける。
ぐるり、と内側を掻き回せば、粘着質な音を立てて体液が泡立つ。
「ふ、……」
何度か指を抜き差ししているうちに、イイところを掠め、時折小さく喘ぎ声が漏れた。ビリビリとした甘い痺れが、断続的に頭のてっぺんから爪先までを駆け抜ける。柔らかく綻んだ肉壁が、内側からの刺激できゅっと引き締まり、己の指を嬉々として咥え込んだ。はくはくと物欲しげに開閉する穴を、長義は瞬きもせずに焼き付けるように見つめている。ごくり、と喉を鳴らす獣の息遣いを嗅ぎ取る余裕は、この時の国広には無かった。
(……まだ出てくるのか)
よくもここまで出せたものだ。こんもり積もった塵紙の小山を見て、呆れると共に感心すら覚える。一体何回出したらこんな量になるのか。思わず遠い目になりながら、国広はずっと無言のままでいる長義の方へ振り返った。
「おい、山姥ぎ……り……?」
だが、一言二言文句を言ってやろうと意気込んでいた国広の言葉は、そこで不自然に途絶える。
柔い内腿を伝い落ちる白濁を、長義が食い入るように見つめていた。その眼差しは今にも獲物に襲い掛からんと、ギラギラと物騒な輝きを放っていて。その涼やかな瞳の色と内に秘める苛烈さのアンバランスさに、国広は言葉を失う。
「……っ」
何か選択を間違えたかも知れない。それまでの煩悩など瞬く間に吹っ飛び、戦々恐々と男の様子を窺う。すると、突然動きを止めた国広を訝しみ長義が顔を上げた。どうした、と端的に問う声は、常よりも低い。正直に言おう。腰にキた。特に事後の名残が色濃い身体には、その声は毒だった。
暴れ狂うものを押し殺したその声を聞くだけで、情けないことに腰が砕けそうになる。
「いや……」
「……手伝ってやろうか」
「え、」
挿入したままの右手を掴まれて身構える。そんな目をして手伝うなどと言われても、碌なことにならないのはわかりきっていた。しかし、国広が拒否する暇もなく長義が背後に迫り、それまでナカを弄っていた指を一息に抜き出してしまう。
「……ん、ちょ、」
「俺がやってあげる」
ぞわり。
熱い吐息を多分に含んだ声が耳を犯し、身震いする。手伝いなど要らない、という言葉は形になる前に彼の口内へ呑み込まれた。荒い口吸いの直後、あれよあれよという間に四つん這いにされた国広の後孔に、許可なく勝手に男の骨ばった指が侵入してくる。性急に三本の指をバラバラに動かされれば堪らない気持ちになり、自ずと快楽を逃すべく腰が逃げを打った。
「んぁ、……っ」
「気持ちいい? いけないね。俺はお前の処理を手伝ってやっているのに、一人だけで気持ちよくなるなんて」
「あんたが……っ、そんな触り方、する……から」
ナカのしこりをゴリッと押され、ひ、と小さく悲鳴が上がる。
「へぇ……? どんな触り方かな?」
「あ、おい……!」
国広の反応に気を良くした長義が、さらに感じるところを攻め立て、鎮まった筈の身体が再び火照り始めた。くそ、油断した。抵抗しようにも完全に背中を取られてしまっている。こうなっては自分にはどうすることも出来ない。また俺は好き勝手されるのか。熱い息を吐き、為す術なく目を瞑り感じ入る国広の姿は、長義からすればさぞ滑稽なことだろう。それをわかっていても、快楽に呑まれ完全に拒むことが出来ずにいる己が、心底情けなかった。
「は、ぅ……」
ぬちゃぬちゃと派手な水音を立てながら、長義の指が国広のナカを掻き回す。尻穴から精液が伝い落ちる感触にすら感じてしまい、内腿が痙攣し始めた。隠さなければ。咄嗟に平静を取り繕おうとするも、この数日幾度となく国広の絶頂する様を見てきた男が、不意に訪れた限界の兆しを見逃すわけもなく。まずい、と国広が腰を引いたその瞬間、容赦無く前立腺を押し潰された。
ごりっ。
「ァアッ!」
――ぱたぱた。
我慢出来ず白濁を零してしまい、ぼーっとする意識の中、射精後の余韻に浸る。はぁ、はぁ、と目の前の布団に顔を埋め、屈辱に耐えながら息を整えていると、真っ赤に熟れた耳朶をかぷっと甘噛みされた。
「ナカだけで気をやったのか。ふふ、恥ずかしいね?」
「……っこの、」
一々煽ってくる男をジロリと睨みつければ、怖や怖や、なんて白々しく宣いつつ、男の手が離れていく。やっと満足したか。昨晩に続き、またもやしてやられてしまったことに軽く絶望していたら、今度は意味深に下半身を擦り付けられ、大仰に肩が跳ねた。恐らく、勘違いでなければきっと、いや、間違いない。この、尻に当たる感触は……。
「勃った」
「な……っ! やらないぞ、やらないからな!」
「慰めろ」
ぐるん、と世界が回る。物凄い既視感だ。じたばたと足掻いてみせるが、上から押さえつけられマウントを取られた状態では、何の意味も為さず。結局その日の朝は長義が満足するまで貪られ、あまりの身勝手さに激昂した国広が本体を呼び出すまで、その責め苦は続けられたのだった。
*
ずらりと並んだ千本鳥居。
京都・伏見稲荷神社を彷彿とさせる幾多もの鳥居の下を、国広は例の特殊任務のため、審神者の護衛を務めながら歩いていた。
「主、身体に障りはないか」
「平気だ。少しばかり息苦しいけどね」
四季折々の花々が狂い咲く、時の止まった神域。政府に協力する数多の神々の力で生まれた常世は、息苦しいくらいの神気で満ち満ちている。清く鋭い気の在り方はまるで、この先に待つものへ敵意を持つ者が入り込めば最後、そいつは容赦無く首を掻き斬られ、この場で息絶えるのだという圧を、無言で掛けているように感じて。こちらの忠誠を試されているような、首元にひたりと刃をあてがわれているような、妙な緊張感があった。
「……あと少しで門の前に出る。本丸内部へ入ってしまえば、ここまでの干渉は受けないだろう」
じわりと冷や汗の滲んだ審神者の顔を、険しい顔をした国広が覗き込む。
「……そう願っておこうか」
「俺も人の身となり初めて神域に入ったが……この神気は肉の器にはキツい。無理はするなよ」
「すまない、ありがとう」
気丈に振る舞ってみせた男は、そんな国広の心配を片手で制して、苦く笑った。
三つ指の落葉が積もる道中は、秋らしく朱と黄金に染まっている。しかし天を仰げば春めかしい薄紅色が空を埋め尽くし、傍を流れる川のほとりには夥しい数の曼珠沙華が咲き乱れていた。何となくゾッとするものを感じて、国広はそっと鳥居の外側から目を逸らす。あれは多分、誘われている。鳥居の外側に踏み出せば、この不変の檻へ永遠に閉じ込められ、あの川を渡ったならあっという間にあの世逝きだ。あれらは全部、現世に生きる者たちを惹き寄せ、あの世に攫おうとする幻。あまりじろじろと見ていても良いことはない。
(……もうそろそろか)
沈黙が降りてきて、淡々と足を動かす。半刻ほど経ちそっと横目で審神者を確認すれば、幾分か顔色は良くなっていた。これも目的地が近いという証か。終わりの見えない道をひたすらに突き進む不安から解き放たれ、人知れずホッと胸を撫で下ろす。
「なぁ、主」
手持ち無沙汰に話し掛けた。前々から聞きたかったことがあったのだ。だが、こうして二人になる機会がなかなか無く、ずっと後回しになっていた。
「なんだい」
「何故、人の子はまぐわうんだ?」
ぴたり。
審神者の足が止まる。顔の大半を覆い隠す目隠し布の下から、唖然と半開きになった口元が露わになった。何をそんなに驚くことがある、と国広が首を傾げていると、ややあって石化していた審神者が正気に戻り、ごほんごほんっと態とらしく咳き込む。一体あの間はなんだというのだ。もしや自分は、それほどおかしなことを口走ってしまったのだろうか。一抹の不安が胸中を過る。
「あなたには恥じらいというものはないのか」
「……まぐわいは人の子にとって、口に出すことを厭うほどに恥ずべき行為なのか?」
「そうではない。いや、そうでもある……んだが……そうではないんだ」
あー、だの、うー、だのと暫く唸っていた審神者を他所に、国広は表情には出さず内心焦り始める。しかし、己の周りで己が求める解を持つであろう、身近な人の子というのが、主しかいなかったのだから仕方なかった。それに、今更口から飛び出た言葉を、無かったことに出来るわけでもなし。そこまで思い至れば、自ずと開き直れるというもので。一人勝手に心の整理をつけた国広は、じっと審神者から答えが返されるのを待った。
(人の子にとってのまぐわいとは何だ)
ずっと、不思議だった。
長義が、何を意図して己を抱くのかを。始めは、国広の矜持を木っ端微塵に打ち砕き、完全に屈服させるためだけに抱いたのだと思っていた。否、きっと初めの頃はそうだった。初めての夜も、それから迎えた幾度かの夜も。長義の中でのまぐわいとは、己の方が格上であるということを知らしめるだけの、唯の自己顕示行為であった。だが最近の長義は、少々様子がおかしい。手酷く強引に快楽を引き摺り出そうとしたり、こちらの都合を丸無視で、精根尽き果てるまで抱き潰したりすることもなくなり、それまでから一変して優しい手つきで触れてくるようになった。さらには聞いている方が気恥ずかしくなるような、甘やかな睦言を並べ立て、こちらの反応を楽しむ始末。これを異常と言わずして何と言う。
――国広の。
偶にそう呼ばれるようになったのは、いつからか。
共に果てるその瞬間を見計らったように、耳元で国広の名を呼ぶ長義に、心が喜びから打ち震えたのを思い出す。本歌がようやく、己を国広の刀として見てくれたのではないか。俺を独立した一振りの刀として、写しとして認めてくれたのではないか。そう期待しては、朝一番に浴びせられる『偽物』呼びに落胆し、肩を落とす日々が続いた。
そして、期待と落胆を繰り返すうちに、いつしかあれほど内に渦巻いていた怒りは鎮まっていた。勿論、元来の負けず嫌いな性分が顔を出し、意固地になっている部分は多々ある。一方的に体を暴かれるのは癪だし、一泡吹かせてやりたいとも思っている。だがそれ以上に、触れられたい、触れたい、という気持ちの方が強くなっていった。足利で与えられたあの温もりを、無意識に探している自分がいる。むず痒くなるこの気持ちがなんなのか、今はまだわからない。わからないけれど、存外悪い気はしない。
「……まぐわいねぇ」
審神者の困りきったと言わんばかりの呟きを耳にし、ふわふわと浮き上がった意識が一気に戻ってくる。
「確認行為、かな」
「確認行為?」
「あぁ。不安だから、確かめる為にまぐわう。稀に行為で得られる快楽に溺れた愚か者が、中毒のようにまぐわいを求める、なんてこともあるけれど……大抵は前者であることの方が多いと思うよ」
なるほど、確認行為か。
もたらされた解は、ひどく国広を納得させた。後者はまず間違いなくありえない。あの気高く高潔な男のことだ。色欲に溺れるなどという無様な姿を、周りに見せることをよしとする筈がない。だとすると圧倒的に前者だった。
ただ、あれが長義にとっての確認行為であるならば、彼は一体何を確かめたいのか。ぐるぐると思考を巡らせてみるも、まったく見当もつかない。そもそも長義の思考回路は、国広には意味不明であることの方が多いのだ。例え千年経ったとしても、あの超理論を展開する刀を理解出来る気がしない。自信がない。
「……何を確認するんだ?」
きょとり、と幼子のような純粋さで、国広が再び問う。それを見た審神者は、可笑しそうにころころと笑い声を上げた。あなたは私よりもうんと年上なのに、随分と可愛らしい、なんて言いながら。
「愛を……もしくは相手が己を拒むことがないかを。人は臆病な生き物だからね。相手を想えば思うほど、わからないことを恐ろしいと思ってしまうのさ」
――人は常に、《未知》におびえている。
そう、審神者は続けた。わからないことが恐ろしい。その気持ちは、国広にも理解出来る。長義が何を思い、何を考え、何を国広に求めているのか。察することの出来ない状況がもどかしく、彼を理解出来ないことが悔しくて……ふとした瞬間に、わけのわからない彼のことを恐ろしいと感じる。
「ほら、昔の人は予想もつかないことがあると、すぐに霊だの化け物の仕業だのと騒ぎ立てていただろう? 要はそういうことなのさ。自分の理解の及ばぬ存在に恐れを抱き、だからこそその正体を知ろうとする。そうして我々は今まで歩んできた。まぐわいは、その延長線上にあるのではないかな」
あなたの恐ろしいものは何だい? と、今度は問われた。答えられなかった。確かに長義のことはわからないし、そんな彼を怖いと思う。だが、だからといって彼を理解したいがために、彼を組み敷いて抱きたいなんてことは、絶対に思わない。逆を言えば長義にそこまでさせている何かが、己にある。彼が欲する答えを国広が持っているからこそ、抱かれている。そうか、そういうことだったのか。
「……要は、俺が何たるかを示せばいいのか」
俺が俺たる所以を。国広が何を重んじ、何を考え、何に葛藤してきたのか。それを伝えることが出来れば、彼の憂いも晴れ、こんな不毛な行為を続ける必要はなくなるのではないか。ぱぁっと視界が開けるような感覚だった。
「……何か変に解釈してないかい?」
「いや、主の言いたいことは伝わっている、と思う。すまない、変なことを聞いたな」
「まぁ、少しでもあなたのためになったのなら、私はそれでいいんだけどね。それと国広、あまりこんなすっ飛んだことを他所で聞くんじゃないよ。聞かれた方が堪ったもんじゃないからね」
堪ったものではない、とは?
やはり、人の子の感覚はよくわからない。これでも顕現されてそれなりの月日が経っているので、大分暗黙の了解とやらを学んだものだと思っていたのだが。自分はまだどこか、人の感覚とはズレているらしい。
「……? あぁ、わかった。今後はあんたにだけ聞くようにする」
「いやそれは……知りたくないというか……あー、うん、もうそれでいいよ」
そうこうしているうちに、ついに目的地へ辿り着いた。
堅牢な門が構えているわけでも、嘗て慣れ親しんだ城郭が取り囲んでいるわけでもなく。ただポツンと朱に染められた巨大な鳥居があるだけのそこに、こんなに無防備でいいのか、と不安を抱く。だが、そんな不安は一歩境界線を踏み越えた瞬間、杞憂に終わった。
「な、」
ゲートとなる鳥居を潜ると、一番に目に飛び込んできたのは広大な日本庭園だ。来客を出迎える顔となる南ノ庭は、春に咲く花々を中心に華やかな色合いで彩られている。中でも庭の中心に植えられた、樹齢千年は超えているであろう満開の桜の木が見事で。そのあまりに神々しい立ち姿に、あれがただの桜の木ではなく、この場所の守護を務める神の御神体そのものなのだということを、痛いほど思い知らされた。
国広はぽかんと口を半開きにしたまま、頭上を見上げる。
「これが……《刀霊守本堂》……」
見渡す限りの花、花、花。歌仙あたりが見たら「実に風流だ!」と喜んだことだろう。もしかしたらこの場で一句、小粋な和歌でも詠んだかも知れない。雅だの風流だのとはまったく無縁な感性を持つ国広でさえも、こんなにも圧倒されたのだ。この壮絶な美しい光景は、まさしく神のために造られた、常世然るべき威厳と風格を有していると、頷かざるを得なかった。
「よくぞ参られた、審神者よ」
国広たちがきょろきょろと物珍しげに周りを見回していると、不意に聞き慣れた声に呼び止められた。
「三日月……」
声の方を向いて軽く目を見張る。国広たちに声を掛けてきたのは、花々に負けず劣らず美しい天下五剣・三日月宗近だった。その刀の正体を目の当たりにした時、国広は無意識のうちに身構える。自本丸の三日月は長年同じ部隊に所属したことで、ようやくあの存在感に慣れたのだ。それが他本丸とあっては、唯の信頼関係がゼロに等しい苦手な名刀筆頭格。国広が警戒してしまうのも無理はない。
「その菊の紋に付き添いの山姥切国広……貴殿は西の代表・野路菊殿とお見受けするが、如何であろう」
「違いありません」
三日月からの問いに、審神者が何処か緊張した声で答える。
「蘇芳殿から話は聞いておる。若いが才気溢れた武人であるとな。なに、俺は分霊だ。そう固くなることはない」
「御心遣い感謝致します」
「早速案内しよう。今から向かう大広間はな、俺たち平安刀が暮らす本殿でもあるのだ。造りは立派だぞ?」
カチンコチンに固まった審神者と国広を見て、三日月が朗らかに笑う。「分霊相手にこれでは、軍議の最中で倒れるのではないか?」などと揶揄われ、国広が睨みつければ、それを見てまた三日月が笑った。写しだからと侮っていると痛い目を見るぞ。内心そう毒吐き、黙って彼の後ろをついて歩く。
広大な庭を突っ切って、蓮の浮かんだ池をぐるりと周り、煌びやかな装飾の施された回廊を進む。やがて目的の大広間に辿り着いたところで、国広は別に用意されている待機場所へ通され、一時の暇を与えられた。待機室には他に刀や人はいない。完全に独りきりの控えの間から覗く外の景色は、変わらず美しい春の色で溢れていた。
「おや、こんなところに偽物くんの偽物くんがいる」
――一体いつまで待てばいいんだろう。
いい加減暇になってきた国広が、無防備に欠伸を漏らしたその時、丸窓の外から嫌というほど聞き覚えのある声が降ってきた。
「……山姥切?」
「如何にも、お前の本歌だよ」
あの長義と同じ個体とは思えないくらい、にこやかに話し掛けられ、国広は思わず固まる。これが個体差というやつか。いや、しかしそれにしては彼の隣の南泉の反応がおかしい。恐ろしいものでも見たかのように顔を強張らせた南泉に、国広はいつもの彼がそんな質ではないのだということを早々に悟った。
「ケッ……山姥切が猫撫で声とか気持ち悪いったらありゃしねぇ……にゃ」
「猫殺しくんを撫でたつもりは無いんだけどね。とりあえず、その小煩い口を閉じてくれないかな?」
まるで今の様子が異常だとでも言うような、あの南泉の口ぶり。ということはやはり、この長義は何か企んでいるのでは……。どんどん警戒心を積もらせていく国広に、されどしれっと何食わぬ顔をして長義が話し掛けてくる。
「そんなところで置物やってないで、此方へおいで。そら、折角来たんだ。俺がこの本丸を案内してやろう」
窓の外から手招きする長義に、国広は首を横に振った。
「いや、今は任務中で……」
「心配しなくとも、お前の主は暫く戻って来やしないよ。それとも、この本歌で本霊の俺の言うことが聞けないというのかな?」
本霊、という言葉に目を剥いた。先程の三日月宗近の分霊のこともあり、てっきりこの目の前の男も分霊だと思っていたのだ。だが、まさか本霊だったなんて、夢にも思わなかった。
「本霊……?」
見た目は殆ど己の知る彼の姿と同じだ。ただ彼の浮かべている表情が、いつも見ているものと比べると幾分か柔らかくて、同じ顔でも表情が変われば、これほど印象が変わるのかと感心する。また、腰に携えられた本体は厳重に封がしてあり、にも関わらず鞘の部分に貼り付けられた札の下からは、ピリピリと肌を刺すような神気が漏れていた。流石は本霊と言うべきか。その研ぎ澄まされた霊気は、確かに分霊のものとは比べ物にならないほど洗練されている。
「し、失礼した……まさか本霊だとは、」
「仕方あるまい。分霊は本霊よりも霊力を嗅ぎとる力が弱いからね。なに、不敬を働いたわけでもなし。咎めやしないさ」
「明日は槍でも振るんじゃねぇか、にゃ」
咄嗟に頭を垂れた国広と、それを軽くあしらった長義のやり取りを聞いて、すかさず南泉が茶々を入れる。
「せいぜい尻尾を踏まれないよう気をつけないとねぇ。天下三名槍の御三方は重いから」
「尻尾なんざねぇよ! あとあの三本のことを言ってんじゃねぇ! にゃ!」
南泉が物凄い剣幕で長義に怒鳴った。ともすれば取っ組み合いの喧嘩になるのでは、と思うくらいの勢いである。しかし、これがこの二振りにとって、いつもと変わらぬ戯れ合いなのだということは知っていたため、国広が焦ることはない。寧ろ、本霊同士も仲が良いのだな、と微笑ましく思えてきて、小さく笑ってしまった。咄嗟に布を引き下ろしたので、長義には見えはしなかったと思うが。
(危なかった……)
見られたら嫌味の一つも飛んできていたところだった……とまで考えて、はたりと思考が止まる。目の前の男はどうしてか、そんなことはしなさそうだと思ったのだ。存外自分は、この目の前の本霊とやらを、早くも信頼しかけているらしい。
「さて、偽物くん。この本霊の好意、無碍にするなんてことはなかろうね?」
「……俺は偽物なんかじゃない。今からそちらへ行く。少し待ってくれ」
長義と南泉の本霊には色々な場所を案内された。
春を思わせる南ノ庭と同様、本丸を守護する神の御神体たる銀杏の木が祀られた東ノ庭。ここは秋を司っている庭らしく、辺り一面紅と黄金の紅葉に囲まれていた。そして夏を司り、向日葵の咲き乱れた西ノ庭に、今までの鮮やかな景観を白で塗り潰したかのような、雪に閉ざされた冬の北ノ庭。次から次へと連れて行かれた場所は、どれも絶句するほど美しく、国広が無言で驚く度に、前を行く長義がクスクスと愉快そうに笑い声を上げた。
「最後に、とっておきの場所を」
そう言って通された場所は、立派な門構えの離れだった。否、離れと呼ぶのは似つかわしくないか。独立した一つの本丸のような堂々たる存在感は、最早城と呼ぶ方が相応しい。
「ただいま」
ガラガラと我が物顔で門を開けた長義を見て、国広はこの建物が長義の家であることを悟る。流石は本霊だ。長船派全員で住んでもあまりあるほどの大きさに、思わず慄いた。
「随分と……大きな家だな」
「まあね。足利の城に似せてみたんだ。どうだい、懐かしいだろう」
「あぁ……俺はあの頃の記憶はそれほど持っていないが……何となく懐かしいとは思う」
ギシギシと軋む廊下を歩き、客間へ通される。
二十畳ほどある広々とした客間は物が少なく、生活感は皆無だった。かぽん、というししおどしの音を聞きながら、南泉と国広が隣り合い、座布団の上に腰を下ろす。長義はというと床板の上に置かれた、二振り用の刀掛け台に本体を置き、パン、パン、と二度ほど手を鳴らした。すると、部屋の外から足音がして、ややあって襖が開かれる。
「どうかしたかな、本霊殿」
「やぁ、分霊。客刃がいらしていてね。茶を三つ用意して欲しい」
「へぇ、客刃ねぇ」
ちらり、と分霊の長義が国広を一瞥し、ふんっと鼻を鳴らす。いい気分にはならなかったが、国広は特に睨んだり不満げな顔をしたりといったこともせず、布を引き下ろすだけに留まった。こんなところまで来て喧嘩なんて目も当てられない。主の顔に泥を塗るのだけは御免だった。
「あぁ、そうだ。芋羊羹も用意しよう。先日政府の者から頂いてね。確か偽物くんも好きだったろ?」
こくり、と無言で頷く。あまり強請ってもはしたないかと思ったが、好物を前に我慢するなんてことは難しかった。それに、丁度腹も空いている。純粋に長義の好意は有り難い。
「お前さ、それをこっちの国広にもやってやれよ。なーんで本命には出来ねぇかな……」
「俺は本霊だよ? 本霊で本歌の俺が、分霊の写しにまで当たるなんてみっともない真似をすると思うかい? 俺は持てる者だからね、与えなければ」
「クッソめんどくせぇなこいつ……にゃ」
確かに面倒臭い奴だ。ついつい南泉の言葉に頷いてしまい、ハッとして前を見ると、頰を痙攣らせた長義が国広の方を見ていた。笑顔だというのに背筋が凍るような空気を放っていて怖い。彼の本霊としてのプライドのおかげで怒られるということはなかったが、これが分霊の彼相手だったら、今頃懇々と説教されているところだろう。相手が本霊でよかった……。
「お前、よくこんなめんどくせぇ本歌の相手なんてしてられるな、にゃ」
出された茶を啜りながら、唐突に南泉が言う。
「……もう慣れたからな」
遠い目をした国広が答えれば、南泉はしたり顔で長義の方を見た。
「はは、言われてやんの」
「……猫殺しくんはそれを食べたらとっとと帰ってくれるかな?」
「やーだね。俺がいなくなったら国広が可哀想だろ。……にゃ」
ぎゃーぎゃーと口喧嘩を始めた二振りを他所に、国広は先ほど出された芋羊羹に舌鼓を打つ。滑らかに口の上で蕩ける羊羹は甘さが控え目で、口の中に入れた瞬間ふわりと広がる鳴門金時の香りが、ホクホクとした芋の風味を引き立てた。
「……美味い」
「おや、それは良かった。まだあるから、おかわりしたければ言うんだよ。茶は熱いから気をつけて飲むこと」
ここは天国か。
目の前の美しい顔が、花が綻ぶように微笑を浮かべたのを目の当たりにして、くらりと目眩がする。優しい本歌に美味い菓子。のんびりと流れる時間に、清浄な神気で満ちたこの本丸は、まさに極楽浄土だった。しかし、だからといってここにずっといたいとは思わないのが不思議である。殺伐とした戦場の最前線に立ち、生きるか死ぬかといった日々を送っている国広であるけれど、だからといってあの場所が嫌ということはない。寧ろ、あそここそが己の場所だと断言出来る。
――国広の。
気紛れにもたらされる長義の言葉が、脳内に反芻する。帰りたい、と思った。あの、わけがわからなくて底意地悪い、優しさとは無縁の男の下に。
「お前の本丸の俺は、随分とお前を可愛がってやってるみたいだね?」
ぼーっと口を動かしていると、机に肘をついてこちらを見つめていた長義が、揶揄いの色を含んだ声で言った。可愛がられているだなどと、まったく心当たりのないことを言われ、国広は訝しげに眉根を顰める。
「……それはない。俺は、あいつに嫌われてるから」
「へぇ? 何故そう思うんだい」
「あいつは、俺を写しとしては不十分だと……偽物扱いしてくる。それに、」
「……それに?」
無理矢理抱かれた、などと言うのは何となく憚られた。抵抗出来なかった己の力不足だと言われてしまえばそれまでだし、何より目の前の本歌を落胆させるようなことはしたくなかったから。いや、あいつは元を辿ればこの男の分霊なわけだけれど。ただ、この目の前で優雅に茶を飲みながら、己の言葉を静かに待っていてくれる男の表情を、曇らせるようなことはしたくなかった。
「おいおい、勘弁してやれよ山姥切。そりゃあないぜ、にゃ」
暫しの沈黙が降りた後、南泉が苦虫を噛み潰したような顔で長義を責める。
「俺じゃない。俺の分霊がやったことだよ」
「こいつの首見ても同じことが言えるか? 明らかにやり過ぎ。お前の管理不行き届きだろうが、にゃ」
「まぁ流石にこれは……少々行き過ぎている、かな」
遠回しにぼかされて交わされる言葉たちに首を傾げ、二振りの様子を伺う。俺の首に何かあるのだろうか。そういえば、自本丸の南泉も首に興味を示していた気がする。以前引っ掻かれた首元へ何となく手をあてがって、同じようにそこを引っ掻いてみた。
カリッ。
「……?」
だが、予想に反して何も起こらず。ますます疑問ばかりが募っていく。
「あまり刺激しない方がいい。首を絞め落とされたくなければね」
やんわりとした制止の声は、嫌に真剣なものだった。
表情こそ穏やかであるが、国広に向けられる眼差しは険しい。南泉の方へ視線をやると、彼もまた神妙な顔をしてこちらを見ていて、何処か心配そうな、同情するような目を向けていた。
「……何だその目は。写しだからと哀れんでるのか」
ギッと睨みを利かせながら威嚇すると、呆れたようにため息を吐いて、南泉が問うてくる。
「んなわけねぇだろ……。ていうか、おい、国広。お前んとこの本歌、なんかヤバい感じはないか?」
「……? ヤバいとは?」
「こう……とって食われそうな感じとか、折る気満々って感じの殺気とか、兎に角『怖っ』て思うことは無いのか、にゃ」
とって食われる、ということなら、もうとっくに食われている。全身隈無く貪られたし、あの男に見られていないところを探す方が難し……っ。
(何考えてるんだ、俺は)
あらぬことを思い出し、思わず赤面した。よりによって本霊たちに囲まれている場で、何を思い出そうとしてるのだ。
「……、え……? まじ? もう手遅れ? しかもそっちの方向で?」
「いや、……っぅ、」
引き攣った声で南泉に指摘され、居た堪れなくなり布饅頭になる。
「俺はこう見えて手が早いからね。まぁ、想定の範囲内、かな」
「お前は鬼か! いや、化け物だったな……」
顔を上げれない。耳まで熱く火照ったこの顔を、二振りに見られたくない。
暫くずっと布の中で蹲っていると、ぽん、ぽん、と軽く肩を叩かれて上を向かせられる。労わるような手の正体は、その元凶とも言える本霊の長義だった。
「お前は俺が恐ろしいか? お前も俺を……化け物だと思うか?」
恐ろしいか、と問われ、考える。
あの男を怖いと思ったことはある。だが、だからといって長義のことを、南泉と同じように化け物などと思ったことはない。そのことを正直に伝えると、眼前に迫った顔が、僅かに緩められる。綻んだ顔は嬉しそうとも、悲しそうともとれて、複雑な感情を露わにしていた。
「……そう。では、俺に触れられるのは、嫌か?」
「嫌じゃない」
即答した。彼に触れられるのを厭うたことはない。勿論、初めは屈辱的で耐え難かった。一度は己を組み伏せる男を恨みすらした。だが、最近の長義の触れ方は優しく、彼が意識してのことなのか無意識のことなのかはわからないが、そこにはちゃんと優しさが感じられた。その手を国広は心地良いと感じていて、何より国広自身が、彼に触れたいと思うようになった。だから、彼に触れられたくないというのは、違う。
「嫌ではないんだ……。ただ、あいつのことがわからなくて……それが、偶に酷く恐ろしく思う」
「……なるほど」
「なぁ、何であいつは、俺をその、抱く……のだろう。あいつは俺をどう思って、」
「その答えを、俺は持ち合わせていない」
ぴしゃり、と言われて閉口する。
穏やかな物腰の彼だ。そこまできっぱりと切り捨てられるとは思わなかったので、一瞬面食らった。
「お前の本歌は俺であって、俺ではない。……お前が俺の『偽物くん』でないのと同じようにね。それに、お前は俺から答えを示されて、それで納得出来るのか?」
「いや……」
「そうだろう。つまりはそういうことなんだよ」
そっと頭を撫でられて、改めて自覚した。そうか、あの男の手でなければダメなのだ、と。
主は相手を知りたいから、人の子はまぐわうのだと言っていた。身体を重ね、相手が己を拒まぬか、己を愛しているのかを確かめ合っているのだと。国広たちは愛し合ってはいないし、恋仲というわけでもない。それでもまぐわうのは、無意識のうちに相手の中に答えを探しているからで――、
(俺は、あいつを知りたい。そして同じくらい、俺のことも知って欲しい。あいつも、俺と同じなのだろうか……)
俺のことを知りたいと、思ってくれているのだろうか。触れたいと、触れられたいと、思ってくれているのだろうか。
「答えは出たかい」
「……あぁ、感謝する」
もう一度、ぐしゃぐしゃと頭を撫でられる。今度は布を払い落とされ、金糸に直接指を絡めませながら。布を被り直したくてうずうずしていると、ふ、と。疑問を抱いた。何故この本霊は、己をあの場所から連れ出したのだろうか。先ほど言われたように、この男にとっての『俺』ではない国広を、どうして。
「お前は可愛いね。あいつもお前くらい素直だといいのだけれど。すっかり図太く育ってしまって……俺の話なんて聞きもしない」
「あんたは、俺の本霊と仲が悪いのか?」
「仲が良い、悪いとか以前の問題かな。あれはすっかり『偽物』になってしまった。俺の怒りは当分解けないだろう。でもね、それと同じくらいお前のことを、俺は憎らしくも愛おしく思っているんだよ。あれは、そんな俺の気持ちすら理解しようとすらとしない。酷い写し刀だろう?」
「こちらの俺も、きっとあんたのことを憎からず想っていると思うぞ。あんたたちは、多分言葉が足りないだけだ。少なくとも俺は、あんたと話していてあんたをいい奴だと思った。……写しで分霊の俺なんかがこんなことを言うのは、烏滸がましいとは思うが」
国広の言葉を受けた長義の本霊は大きく目を見開き、間の抜けた顔を晒した。会ってから此の方隙のない仮面を貼り付けていた彼にしては珍しい。それとも本霊の方が表情豊かなのか。暫しの間沈黙が続いた後、ややあってくしゃりと表情を歪めた彼が、苦く笑って言った。
「……やっぱりお前もお前だね」
「当たり前だ。分霊だからな」
「そんなところがすごく憎たらしいよ」
帰り際、長義たちに連れられてあの待機場所へ向かっていた時、あの長義の住む離れに彼以外誰も住んでいないことを知って、国広はひどく驚いた。だが、妙に納得もした。足利の城に似せられた懐かしい造り。床板に飾られた二振り用の刀掛け台。示し合わせたように出てきた、国広の好物である菓子。彼はあそこで一振りで過ごしていると言っていたけれど、本当は国広の本霊と住むつもりで、あのような場所を作ったのではないか。そう思うと、色々と込み上げるものがあった。
(……帰ったら、少しはあいつの言うことに聞く耳を持ってみるか)
彼に東の離れへ越せと言われた時には突っ撥ねた。贈られた物たちも、彼の前で一度着てみせてからは、使われることなく箪笥の肥やしになっている。加えて国広は、何かと長義の言葉には反発しがちで、素直に首を縦に振ったことはない。ただ、あの本霊と接しているうちに、少しだけ、ほんの少しぐらいは彼の命令を聞き入れてみても良いかと思った。
……少しでいい。彼があんな風に笑う顔が、見たいと。
「ねぇ、偽物くん」
待機室の前に到着し、前を歩いていた本霊の長義がこちらを振り返る。
「俺はかの名刀工堀川国広が作刀した『山姥切国広』が俺の写しであることを、とても誇りに思っているよ」
「……あぁ」
同じ顔、同じ声、されど違う表情。
「本霊の俺にも言ってやれ。絶対に喜ぶから」
「……ぶはっ!」
それが出来たら苦労しねぇんだわ! と噴き出した南泉を、長義が睨みつけて、また騒がしい喧騒の中に時が埋もれていく。本霊の長義からの言葉は嬉しかった。だが、国広が本当に言って欲しいのは、彼であって彼じゃない。
(……帰りたいな)
閉じた瞼の裏側で、底意地の悪い笑顔でこちらをみるあの男に、何だか無性に会いたくなった。