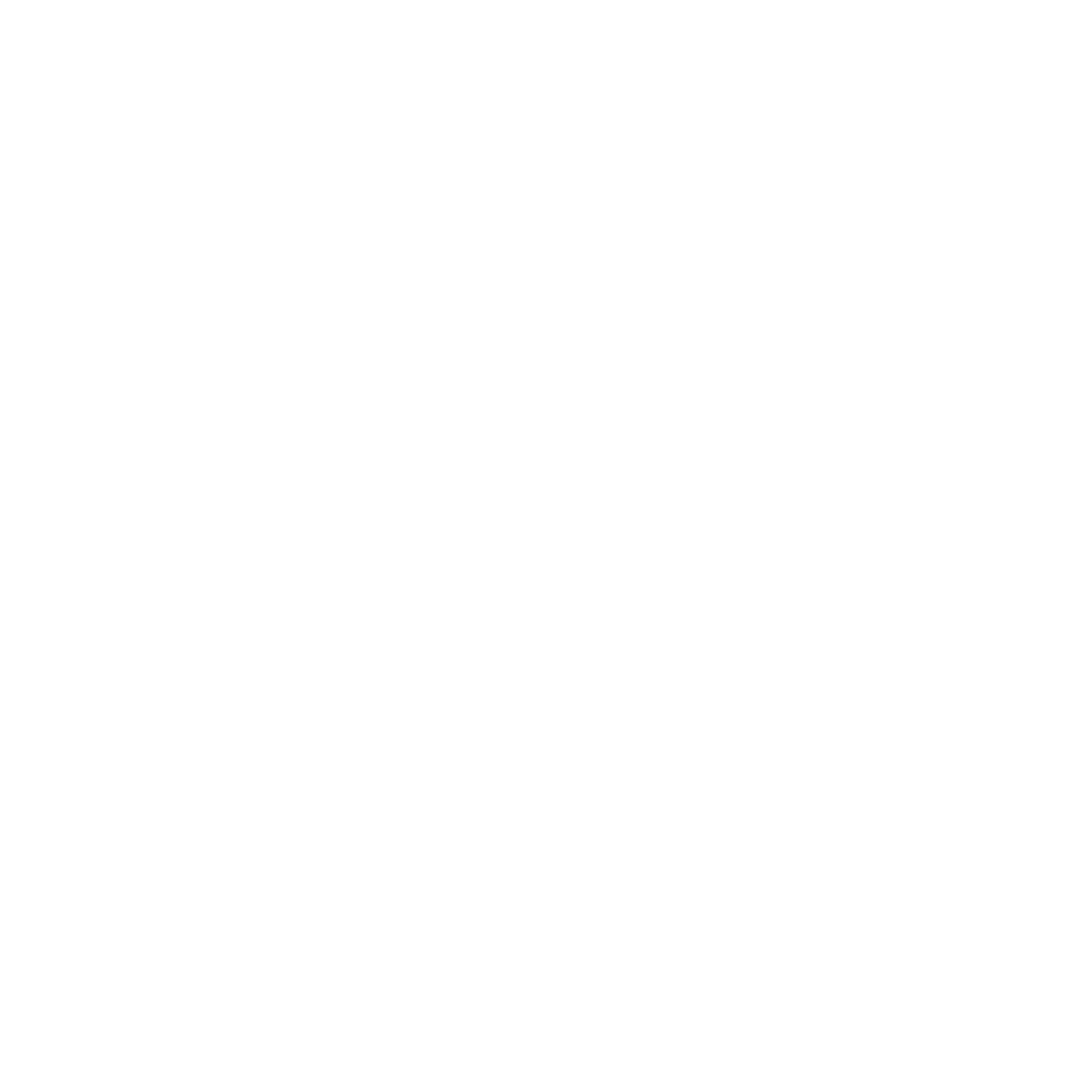序章 漣
流した涙は水の中に溶けて消えて、自分が泣いていたことすらわからなくなる。
斬っても斬っても何も感じない。敵を屠ることも、犠牲が出ることにも、仲間の死にも大きく感情を揺さぶられることがなくなった、と。己の感覚が麻痺していることに気がついたのは、この戦いが始まってから半世紀ほど過ぎた頃だった。昔は陸地にしか存在しなかった本丸は、いつしか技術の進歩により吹雪く雪山の頂、荒れ狂う海の水底、水源無き灼熱の砂漠のど真ん中といった、一昔前までならば考えられない場所に拠点を置くことが可能になり、おかげで時間遡行軍からの襲撃を受ける確率は段違いに下がった。
(……息苦しい)
頭上を見上げればそこに満ち満ちているのは一面の蒼。空のそれとは違う。空よりもさらに深く、暗く、澱んでいて、月の光を反射して漣が小刻みに揺らいでいる。
山姥切国広が所属する本丸は、特定不可能な座標に在るとある大海の底にあった。潜水艦すら介入不可能なほどの水圧に、十分耐えうるだけの強度を誇る限界結界が、本丸をすっぽりと覆い隠している。また、結界内には高濃度に圧縮・濾過された酸素や霊力が常時循環していて、当本丸の刀たちはこれ以上ないくらいに清らかな霊力を存分に供給されていた。そんな恵まれた環境の維持を可能にしているのは、近年政府が開発した新システムによる徹底した管理方法と、この本丸の審神者が持つ規格外の神力だ。神力、という言葉からも察せられる通り、審神者は人ではない。政府が助力を求め、それに応えた神々の中の一柱――海に生まれ、海を守り、海と共に生きる白蛇の海神――それが、国広が仕える審神者の正体であった。
「……神に仕える神……滑稽だな」
ちゃぷん、と。魚の泳ぐ音が聞こえてくる。空気中よりも水中の方が音の伝わる速度が速いのだと言ったのは、どこの誰だったか。音のした方へ何気なく目を向けると、海底に差し込んだ月光に照らされて、ギラギラと輝きを放つ銀の鱗が、視界の端を横切っていった。
何処までも青い。底が見えぬほど深くて、際限なく沈み、溺れてしまいそうなほどの青。息が詰まった。この本丸の中には確かに酸素があるはずなのに、偶に酷く息苦しさを覚える。
「青い……」
アレの目と同じ色だ。不意にそう思った。異なるのは苛烈さを露わにする輝きの強さのみ。影が差し、内側を晒すことを良しとせず、気味悪く水面を揺らすあの複雑な色彩は、国広の天敵とも言える男の目の色ととても良く似ていた。
そんなことを考えたその時だった。タイミングを見計らったように、ゲートの前に桜の花弁が散った。風などないはずなのに渦を巻き、薄紅色の花びらが勢いよく吹き荒れる様は、いつ見ても美しく怪しい。眩しいほどの光が国広の視界を襲った後、光は徐々に人の形を成していった。噂をすれば何とやら。お出ましか、なんて思わず眉根を寄せてしまいそうになるのを耐える。そんな顔を見られようものなら、アレはまた変に突っかかってくると思ったからだ。
「おや、こんなところでぼうっと間抜け面をしている奴がいると思えば……偽物くんじゃないか」
「……俺は偽物なんかじゃない」
庭先に突っ立つ国広を見た瞬間、思い切り顔を歪めながら、突如現れた銀髪の男が吐き捨てる。
「練度が上限に達した初期刀殿は暇人なのかい? こんなところで海を眺めているなんて……その刀もついに海水で錆びたのかな?」
(……口の減らない奴め)
国広は無視をした。この男は本丸にやってきてからずっと、国広にやたらと突っかかってくる。応戦すれば毒舌がエスカレートするのは知っていた。エスカレートした果てに手が出ることも。そして、割と沸点が低い己が懇切丁寧に売られた喧嘩を買ってしまい、最終的には二振り共医務室送りになることも。だからこそ、ここで下手に口答えするのは得策ではないと判断した。しかし、己が本科たる男はその反応がお気に召さなかったらしい。先程よりもさらに顔を険しくして続けた。
「言葉すら忘れたか。ついに老耄したようだ。俺より若いのに嘆かわしいことよ」
流石にここまで言われるとカチンとくる。元々ここで思い耽っている間から苛立っていたこともあり、湿り切っていたはずの導火線に火が点いて、つい言い返してしまった。
「……相変わらずよく吠えるな。そんなに極めた写しが気に入らないか? 俺に構っている暇があるなら、さっさと主の下へ報告に行くといい。今頃御社で御神刀たちと酒盛りでもしているだろうさ」
「……生意気な」
「先に噛み付いてきたのはあんただろ」
ギロリ、と苛烈な怒りを露わにして睨みつけられる。こういう時の色は、穏やかな暗い海の色とは似ても似つかなかった。例えるならば南国の海を照らす太陽の如き激しさ。直視すれば目が焼け、触れれば火傷を負う。関わると碌でもない部類のものだ。
「……本当にお前は気に入らない」
チッ。
荒々しい足音を立てて、舌打ちした男が近づいてくる。
「その澄ました顔を見るとね、偶に問答無用で斬りつけてやりたくなる」
ガツンッという鈍い音を立てて額同士が打ち付けられた。間近に迫った二つの瑠璃玉が眼前に広がる。頭突きされた額が痛んだ。目を逸らした瞬間に、首を刎ねられる。そんな野生の獣じみた危機感を抱いて、国広は男の目を見つめ返す。
「俺こそが、『山姥切』長義。お前の本歌であり、化け物を……一説には豊穣の神ですら切り捨てたとされる霊剣だ」
吐き出された言葉は最早呪詛だ。瞳の奥で修羅の炎が燃えている。涼しげな色彩の底で獰猛な何かが頻りに叫んでいた。山姥切は俺だ、お前は写しであり偽物、奪われたその名を返せ。何度その声を聞こうとも、国広には彼の叫びの意味が理解出来ない。大切なのは名ばかりではない。逸話なんて人々の曖昧な記憶に基づいた記録の一つでしかなく、それだけに固執し依存するにはあまりに不安定なものだ。彼の主張を投げつけられる度に、国広なりの言い分を返してはいるものの、やはり彼と国広が分かり合うことはない。
血が垂れてきた。長義に額をぶつけられた時に切れたのだろう。拭おうと僅かに身動ぎしたと同時に、長義の顔が右に傾いた。
「……んぅ、」
唇が熱くて柔らかいものに塞がれた、と気づいたのは我が物顔で長義の舌が入り込んできてからだった。接吻とはいえ、それは愛だとか情だとかを交わすような甘ったるいものなんかじゃない。
――これは存在証明だ。
「俺が山姥切だ」
「ぐっ……ぅ」
口の端を切ったのか。唾液に混じって、血と煮え滾った長義の霊力が流れ込んでくる。本科と写し。双方の関係性は近しくも遠く、霊力の質は見事に正反対といえる。毒にも等しいそれが一方的に体内に流し込まれ、カッと熱くなった腹の底がもんどり打って苦しみを訴え始めた。
「ぁ……ッやめ、ろ……っ!」
「いつか、お前を塗り替えてやる。絶対に」
震える両手で突き飛ばせば、長義の身体はあっさり離れた。酩酊した状態で覚束ない足元が崩れ落ち、激しく噎せる。唇も、喉も、腹も、男の霊力に触れた場所が熱くてたまらない。生理的に浮かんだ涙をそのままに己を見下ろす瞳を睨むと、唐突に二人の上に影がかかった。
鯨だ。
三十メートルはあろうかという巨体な鯨が、頭上を泳いでいったのだ。暗がりの中で爛々と輝く瑠璃玉は、未だ国広のことをギラついた眼差しで捉えている。弱った瞬間を狙う獣のように。狙っている。国広の喉笛に噛み付いて、骨まで食らわんとするその時を、手ぐすね引いて待っている。そんな気がして、ゾワァッと背筋が粟立った。
「……っ」
「俺は社へ行く。お前も早く部屋へ戻れ」
踵を返して歩き出した男は、ついに視線を逸らした。それでも悪寒は止まらない。心臓がバクバクと脈打ち、鳥肌が立った肌の上を無意識のうちに掌で撫で摩る。冷や汗がこめかみを伝って乱雑に布で拭うと、極める前から愛用している襤褸布が赤く染まった。そうだった。額の何処かを切っていたのだった。少量こびりついた鮮血を見て、そこでようやく己が怪我をしていたことを思い出す。
(……偽物、か)
偶に長義から向けられる激情に、どう返したらいいのかわからないままここまできてしまった。日に日に男から投げつけられるそれは熱を帯び、不穏な気配を濃くしている。完全に持て余していた。長義のことを。以前一度だけ、アレとの接点を徹底的に失くして関わりを絶ってしまえば……と考え実行したこともあったが、かえって彼の怒りを買ってしまい抜刀騒ぎにまで発展してしまった。それからは彼のしたいようにさせており、気まぐれに突っかかってきては喧嘩を売ってくる長義に、その都度ネチネチと嫌味を返すといった妙な生活が続いている。
長義からすれば、国広と顔を合わせる度にストレス発散が出来るので、良い息抜きになっているのかも知れないが。国広からすればいい迷惑だった。元来言葉にするのが苦手な質のため、思うように言い返せず着実にストレスが蓄積されていっているのが自分でもわかる。彼がこの本丸に来てからもう二年。流石に堪忍袋の緒が切れそうだった。
「……はぁ」
ぐるりと周りを見渡して、深くため息を吐く。月の光は雲に隠れたのかもう見えない。あるのは結界の外を泳ぐ生き物たちの気配と、本丸の宴会場から漏れる明かりだけ。きっと酒飲みたちがまた馬鹿騒ぎでもやっているに違いない。
己を取り囲む青に居心地の悪さを感じて、そそくさと自室に向け歩き出した。何となく、今日の海は荒れる。そんな予感めいたことを思いながら。